|
ここには、童話や物語(らしきもの)を掲載します。ぜひ、忌憚のない、忖度なしのご意見を待つことにしたいと思います。育ててやろうというつもりで、感想をお寄せください。お待ちします。 |
FANTASY 53 年末・年始企画 デザイン事務所の副業と生活 新たな出発・7
生活編・3
「だから、アルバイトをさ」
Aが答えた。自分に言い聞かせるようでもあった。
「はい。でも大丈夫ですから」
Cは、ごく自然に応じたようだったが、本気とは思わなかったのかもしれなかった。
「何が?打ち込みたくなったものがあるんだろ?」
Aは、Cの方を見ながら確かめるように言った。
「ええ」
「だったら、それに打ち込むのが一番だよ。そうするのがいい。ま、そうしてごらんよ」
「はあ」
「俺もね、実は少し考えるところがあってね」
Aがしばらく上の方に目をやった後、真面目な顔になって切り出した。
「はい?」
Cも、今度は真剣な面持ちになったようだった。
「ここに出る時間を減らそうかと思っているんだよ」
「えっ、きついんですか?」
Cは、半ば驚きつつ心配したようだったし、半ば安心したようでもあった。
「まあ、きつくないとは言わないが、そういうことでもない」
「じゃあ、どうして?」
「俺は知っての通り、怠け者だろ?」
「うーん……」
「遠慮しなくてもいいよ。俺は怠け者で、そのせいで何事も中途半端に過ごしてきた」
「そうなんですか?」
「ああ。残念ながらそうだね。人並み、いやそれ以上に幸運に恵まれたけれど、いい人生を送ってきたというわけじゃなかった。こないだの新聞には、こんな記事が載っていた」
「はい」
「この為だけに行く価値のある店と評される気鋭の菓子職人が問われて、『あんまり人に言うことではないですけど、圧倒的に努力した自負はあります』」と答えたんだよ。まあ何かを成し遂げた人はこうしたものだろうけど、俺はこれができなかった。何か目標を持って、これを実現するためにやり通すということがなかった。だからね、それが心残りに思えてきたんだよ。今更だけどね」
そう言うと、Aは下を向き、すぐに顔を上げると、また遠くを見つめた。そして、楽器が弾けたら良かったのにということを思った。一人で楽器を弾くということは自己との対話でもあるような気がしたのだ。文章を書くことも似たようなところがあるはずだけれど、それとは違って自己を見つめ直すという面がより強いう気がしたのだ。だから、憧れはよりいっそう募った。
「そうなんですか?」
予想外の言葉に、Cは呆然としたようだった。その言葉に、Aは我に返った。
「ああ。もう手遅れかもしれないけどね」
Aが言うと、
「そんなことはありませんよう」
Cが、間髪を入れずに応じた。すると、Aは確かめるように呟いた。
「そうかな?」
「そうですよう」
「例えば、楽器はどうだい?遅く始めたら、なかなか上達しないだろ?」
「たしかに。そうかもしれませんけど、自分で楽しむくらいにはなれるんじゃないかな。だから、手遅れなんて、ありませんってば、絶対に」
「絶対に?」
「はい。絶対に。それに、楽器が上手に弾けなくても、そのことを嘆く人ばかりじゃないんだし。楽しく暮らしている人はいっぱいいますよ」
Cがいっそう力を込めて繰り返した。Aは、楽器を上手に弾けないこと自体が問題ではなく、上手に弾けるようになりたいと思っていながらそれができないことと、そもそもその気がないと言うのではまるで違うことだという気がしていたけれど、そのことは言わないでおくことにした。Cの言うように、楽器が弾けないことよりも自分がそのことに真剣に取り組もうとしてこなかったこと、さらにそうした持続的な努力ができないことを恥じていたのだ。だからその代わりに、Aは、
「ありがとよ。まあ、お前さんは、若いからね。でもありがとよ。だからね、店に出る時間を減らそうと思ったってわけさ」
言ったのだったが、自身の気持ちを懐かしむようで、それは独り言のようでもあった。
「そうなんですね。でも、困る人がいっぱいますよ」
Cはいくらかは納得したようだったが、すっかり得心したというわけでもないようだった。それで、Aがふたたび疑問を挟んだ。
「そうかな?」
すると、Cは間髪入れずに言ったのだ。
「そうですよ」
「たとえば?」
Aが訊くと、
「いつも来てくれる人たち」
Cが、またもや間髪を入れず応じた。
「ああ、定連客も増えたよな。こんな風になるとはね、正直、想像していなかったけど、それに
……」
人はたいてい楽しい人のところに集まる、という。Aは、自分がそういう質じゃないことを自覚していた。大建築家のミースを真似て、面白い人間であるよりも良き人間になりたいのだと強がったりしたくらいだったが、それは自身を正当化するとも思えないでいたのだ。それで、常連客がこんなにいるとは思いもしなかった。だから、それは自分のせいではなくCの存在が大きかったのかもしれなかった。
「それにって?なんですか?」
「これからは、やりたかったことややりたいと思うことを、やってみようと思うんだよ。と言うか、やらなくちゃと思ったんだよ。できるかどうかは別にして。今、やれることをね。それに、人は幾つになっても夢というのか、あるいは幻想と言う方がいいのかもしれないけれど、それはいつまでもくすぶっているものだろ?そうしたものがないと、たぶん、人は生きていけないという気もする……」
Aは、意を固めるようにポツリとつぶやくように言った。すると、
「ふーん、そうなんですね。でも、私だって、困りますよ。おしゃべりしたり、相談したりするところがなくなるし……」
Cが、ちょっと拗ねるような、甘えるような仕草をした。
「そうなのか。でもそんなことなら、心配することもないさ。来たい時に来ればいいじゃないか?」
「いいんですか?」
「いいに決まってるだろ。なんと言っても、お前さんはこの店の創業メンバーなんだからね。しかも、二人しかいない」
「ああ、はい。よかった」
Cはようやく安心したようだった。そこで、Aが続けた。
「それに、デザインのことなら、いつかここにも来たBさんのこと、覚えているだろ?」
「ええ。はい」
「彼と話せばいいんじゃないか。話せるんだろ?」
「はい。でも、B先生は授業が詰まっていて、受講生以外と話す時間がないようなんです」
「ふーん。そうなのか?」
「はい。なかなか会えないんです」
そうなのか、これもまたなかなか思い通りにはいかないものだ(人はそれぞれに事情を抱えているのだ)。それで、Aは話の続きに戻ることにした。
「それにね、ここのオーナー、Dさんのことを覚えているだろ?」
「はい。どうされているんでしょうね?」
Cは、心配そうに言った。なにしろ、DのことはAより先に知っていたくらいなのだ。
「彼とは、時たま、連絡を取り合っているんだけれどね、彼がね、田舎に引っ込んでからすっかり体調が良くなったらしいんだけど、ちょっと退屈しているって言うんだよ」
「へえ。でもよかったですね」
Cも安堵したようだった。何しろ、Dとの付き合いは、Cの方がAよりも長いのだ。
「まあ、そうなんだけどね、ちょっと暇つぶしに何かないかなって言うんだ。まあ、あの独立独歩ぶりは変わらないのかもね?」
「ええ」
「だからね、彼に2、3日任せることにしたらどうだろうと思ったんだけどね。どうだろうね?」
「そうなんですね」
「それに、残りの日は、流行りのシェア・キッチンとして貸し出すというか使ってもらうのはどうだろうということもね。これについてはどうだい?」
「へえ」
Cの顔には、驚きとも感心ともつかない表情を浮かだ。
「どうだろうね?」
「いいんじゃないですかね。お店の使用率も上がるし、ランチを食べることのできる日は変わらないわけですから。あ、もしかしたら増えるんですかね?だったら余計、近所の人も助かるんじゃないですかね?」
Cが言うと、Aもすっかり安堵したように、
「そうか?そうだろ?いいよね?」
と念押ししたのだ。
「ええ」
Cが言うと、
「それに、お前さんが来たい時に来れる場所もこれまでと同様、いやそれ以上に確保されるし、ね?いいはずだよね?それに、俺も1日くらいは出たくなるかもしれないし……」
Aはほっとした様子で訊いたのだったが、自分自身を安心させるためだったのかもしれない。
「ええ。はい」
Cもにっこり笑った。
「ところで、話したら、なんだか気分も晴れてきたみたいだ。そのせいで、ちょっと小腹がすいたな。お前さんは?」
Aが珍しく、唐突に言い出した。
「いいえ。それほどでもないです」
Cが少し考えた後でそう言うと、Aはやや残念そうだった。
「そうか、じゃあ、自分の分だけ何かこしらえることにするよ。なんだか、いつものお前さんじゃないみたいだよ」
「えーっ、それってどういうことですか?」
「ただ、いつもならすぐに、食べますって言うと思ったんだけどね」
「それって、私がいつもお腹をすかしているってことですか?」
「いや、そういうことじゃなくてさ……、付き合いがいいってことさ」
なんとかしのぐことができたようだった。
「そうですか。軽いものって、おやつみたいなものでいいんですか?」
Cは、Aの気持ちを察したように言った。
「ああ。ほんのちょっとでいいからね。もうすぐ昼飯だしね」
「そうですね。じゃあ、今回は私が作ることにします。いつもとは立場を変えてみるのも、あんがいいいかも……」
「えっ、そうなのか?じゃあ、任せてもいいのかい、ほんとうに?」
Aが、Cの方を見た。
「はい、もちろん」
「それじゃあ、お任せします」
今度はAが、笑顔で、かしこまったふりをした。
「はい。わかりました」
そう言うと、Cはカウンターの向こう側に歩いて行った。
Cはあっという間に戻ってくると、器の載ったトレイをAの前に置いた。白いものの上に、緑や黄色の果物、そして金色をしたものがかかっているようだった。
「さあ、どうぞ。召し上がれ」
「お、なんだい?アイスクリーム?」
目の前に置かれた器の中を見たAが、Cの方を見上げた。
「いいえ。冷蔵庫にあったものなんです」
「アイスクリームも冷凍庫にあったと思ったんだけどね」
「ああそうか、冷凍庫は見ませんでした。それより、どうぞ」
「おっ、うまいね。すごく滑らかだね?」
ひと匙掬って口に入れたAが、Cの方を向いてにっこりした。Cも満足そうだった。
「ええ。よかった。実は、ヨーグルトと果物の残りにオレンジマーマレードを足したんです」
「へえ。でもそれだけ?」
「ええ」
「ヨーグルトはずいぶん滑らかだけれど、どうしたんだい?」
「ぐるぐるかき混ぜたんです。そうすると、
滑らかでとろりとした食感になるんです。それに、疲れた時には甘いものが必要ですから、マーマレードを少し。彩りも良くなりますしね。ま、ジャムでも蜂蜜でも、なんでもいいんですけどね」
「へえ、そうなんだな。でも、いいね、これ」
「よかった。気に入らなかったらどうしようと、ちょっと心配していました。デザート系は、ケーキ以外は苦手なもので」
Cが、片目をつぶった。
「なかなかいいよ、これ」
「よかったです」
「うん。おいしい」
「はい」
そんなことがあって、店の営業形態やAの生活も変わることになったのだった。AとCのカフェの新たな始まりだった。
その夜、Aはレコードプレイヤーに一枚の盤を載せた。もちろん、ていねいに磨いた後でだ。うんと昔には、よく聴いていたものだった。いろいろなことが頭の中をよぎったが、しばらくするとほんの少しの違和感を覚えた。当時とは違って、なんだか貧しく響くような気がしたのだ。たぶん、かつての気持は今よりも幼いものだったに違いないけれど、それほど違わない気もした。それでも、同時に何かが決定的に違っているようだった。
すべてを初めからやり直したいと思った。そうしなければならないような気がしたのだ。果たして人はそういうことができるものかという気もしたけれど、そうするしかないようだった。だから、レコードを聴いた後には、レコード盤を取り出し、叩きつけて壊すべきだったのかもしれなかったけれど(ザ・フーのギタリストのピート・タウンゼントのように)、それはできなかった。それが、Aの弱みでもあったかもしれなかった。
ひとまず、了。
2026.01.25
FANTASY 52 年末・年始企画 デザイン事務所の副業と生活 新たな出発・6
生活編・2
「ま、たいしたことじゃない。だけどだな……」
Aが切りだしたが、まだ単刀直入に、というわけではなかった。
「だったら、なんで言うんです?それに、だけどだなって、いったいなんなんです?」
「おっと、一本取られたね。でも、まあそんなに身構えられたらちょっと言いにくいね。そんなに真剣な顔をしてもらっちゃ、何も言えなくなりそうだ」
「だったら、なんで言うんです?じれったいなあ」
Cは、もはや我慢の限界に近づいているようだった。それを感じ取ったAが、なだめるように言った。
「まあ、そんなにカリカリするなよ」
「してません」
「してるよ」
「してませんってば」
「してるよ」
話そうとするのになかなか切り出せないまま、Aの気持ちは堂々巡りするばかりだった。
「だったら、話してくださいよ。さっきからずっと同じですよ。私には話せないってことですか?それって、ずいぶんじゃないですか。こないだの学生たちにはずいぶんやさしくして、積極的に話していたのに」
「ああ、お前さんと話をしていたら、つい俺の内気な面がつい出てしまうようなんだよ」
「へえ、そうなんですかあ。それって、どうなんですか?なんだか、嫌だなあ」
「そう嫌がるなよ。俺も気をつけるよ。そうなりかけても、グッと我慢することにするよ」
「はい。そうしてください。さあ、今度こそ話してください」
Cが、きっぱりと言った。
「さて、じゃあ話すことにしよう。いざ、話せと言われたら、なんだかやりにくいね」
「じれったいなあ、もう」
Cの呆れ果てたような顔を見たAが、ようやく話し始めた。
「すまん。最近の子は、電車の中でもスマホを見るだろ?それに食事中だって、中には歩きながら見てる輩もいる」
「そのようですね。でも、またスマホの話ですかあ?」
「ああ。やっぱり、なんだか冷たい気がするけどね」
「Aさんと話をしていると、私の意地悪な面がついでちゃう時があるのかも」
「参ったな。それでね、ある日なんかは電車のホームで、若い女性がベビーカーを片手でつかんで、ずっとスマホを見つめていたことがあったよ」
Aはなぜか、簡潔に話すことが苦手だった。簡潔に言おうとすればするほど、肝心なことを忘れるような気がしたのかもしれない。それは昔から変わらない癖のようなものだった。
「はあ」
「そんなに膨れないで」
「もう、いったいなんだっていうんです?」
Cは、いよいよ堪忍袋の緒が切れそうだった。
「あれがよくわからないんだよ」
「えっ?」
「何を見ているんだよ、と思うんだよ。スマホのことだよ。あ、いつの間にか、縮めて言っている。やれやれ、こりゃちょっとまずいなあ」
Aが最後につぶやくように付け加えてが、Cは聞き逃さなかった。
「何がですか?」
「えっ?何がって?」
「そのまずいことって、いったい何なんです?」
「ああ、それね。なんでも縮めて言うことが嫌いな俺が、自分で縮めて言ったことだよ」
「それなら、さっきからずっと言ってますけど」
「あ、そう?参ったな」
「それで、などうしたんですか?」
「でね、俺がある店のカウンターで昼飯を食べていたときのことなんだけどね、若い親子らしき2人組が乗り込んできたんだよ。それが、座ったと思ったらすぐに母親もまだ小学生のような息子もスマホとにらめっこ。一言も話さないんだよ。なんだろうね?そんなに面白いものがあるのかね?家族や友人と話しをする以上に大事なことって?せっかく一緒にいるのに」
「なぜなんでしょうね。でも、そうしないといられない気もするんです。私は親じゃありませんけど」
「へえ。そういうものなのか?でも、もったいないよねえ?」
それは独り言のようでもあったが、Cがすぐに反応した。のんびりしているようだけれど、あんがい耳聡いのだ。
「何がですか?」
「だから、スマホとにらめっこすること。それが親子や友達との会話よりも大事らしいってことさ」
「ああ、そうなんですね」
「そうさ」
「たとえば、目立ちたくない?とか、話していて意見が違うのが怖い?とか、苦手な話題になるのが嫌だ?とか?」
「えっ?なんに対してだよ?」
「さあ。でも、なんとなくそんな気がしたんです」
「でも、きみたちはたいていのことに対しては恐れないよね。そうだろ?それは傲慢で不遜に見えるくらいだ」
「ええ。まあそうかもしれません。そうありたいとは思っていますけど、もちろん傲慢は嫌ですけど」
「でも一方で、何に対しても自信がないようでもある。惜しくはないのかね?」
「なにが?」
「話もしない、景色も見ない、本を読むわけじゃない。話をしても、相手に合わせて自分を表に出すことをしない。そんなことさ。おまけに、他者との比較をとても重視するように見える時もあるね。自分のあり要素のものよりも、他者に対して優位性があるかどうかが大事なように見える時もある」
「どうなんでしょうね。でも、スマホを見ることが強要されているような気もしますけどね」
「確かに、スマホから離れられないというのは、事実のようだな」
「ええ。そうですね」
AとCはたいていそんな話、しかもなかなか噛み合わないままのような話をすることが多かった。
それに、実は少し前にはAの心にちょっとした変化があったのだ……。それは、以前に流行った言葉で言うなら、ミドル・エイジクライシスというものだが、実際のところAにとっては、オールドエイジ・クライシスというのが正しいかもしれない。そもそもAは、その年になるまで、自分の年のことを考えることがなかった。その年の頃にやるべきことというものをきちんと自覚することがないまま、過ごしてきたのだ。
ある休日のことだった。その日はよく晴れていたので、シーツやタオルケットの洗濯もしたし、散歩にも出かけた。気分もよかった。しかし、夜になるとAは、なんとなく重く、すっきりしない気分だった。いつものように、お酒の入ったグラスを手にしていたら、不意に、これから俺はどうなるんだろう?どうすればいいんだろう?という思いが湧き上がってきたのだった。そうしたことは今までもないわけじゃなかったし、それなりの自己療法ともいうのか、やり過ごし方を見つけていたのだが、今回は結構しぶとかった。いつものようにシャワーを浴びて、寝しなに文庫本を手にした。ベッドで本を読むとすぐに眠くなるのが常だったのだが。
その夜はミステリーじゃなくていわゆる純文学作品だったが、読み始めると、壁に映る樹の影を偏愛する老作家が登場した。Aは、えっと思った。Aも同じように壁に映る影を見るのが好きだったのだ。しかも、その小説はたぶん初めて読むものだったので、奇妙な感じがした。彼の場合は、ロバート・ロンゴの絵に通じるような面白さを感じていたのだったから、その本の影響というわけではなかったはずなのに、Aは、ああここでも二番煎じなのかという思いがしたのだった。しかも、その老作家は超一級とは言えないかもしれないが、ともかくも作品がいくつもあり、社会に受け入れられていた。それで、ますます気分が沈んだのだった。
本を閉じ、ようやく寝入って、翌日遅く起きた時にも気分は変わらなかった。
朝早く一旦目が覚めて枕元のラジオをつけると、半世紀ほども前の歌が聞こえてきた。いっとき懐かしく甘やかな気分になった。何しろうんと若かったのだ。まだ未来がたっぷりとあった。しかし、すぐに苦くて重いものに変わったのだ。
何も理解することなく表層だけを見て過ごしてきた気がしたのだった。何であれうわべだけを見て、何一つ深く理解することができなかった。深く関わろうともしなかった(というよりも、むしろ避けてきたのかもしれなかった)。そして、そのことを今になって罰せられているに違いないという気がした。
Aがそんな気分を抱えたまま何かを見るでもなく、店の外に目をやりながら所在無げにぼんやりと立っているところへ、Cが入ってきた。元気よくドアを開けると、大きな声をかけた。相変わらず元気がいいことだ。それが若いということなのかもしれない。
「おはようございまーす」
「やあ。おはよう」
Aもいつものように朝の挨拶を返したものの、なんだか力がなかった。
「どうかしたんですか?何かあったんですか?」
Cがちょっと心配そうに訊いた。
「そんなことはないよ。あるわけないだろ?」
Aは、どうしてわかったんだろうと訝りながら、慌てて言った。
「ええ。まあ、そうですけど」
「まあって、どういうことだよ?」
「でも……」
「でも、なんだい?」
「えーっと、ちょっと変な気がしたから……」
「変?そんなことはないさ。あるわけがない……」
Aが、少しむきになったようだった。
「だったらいんですけど。でも……」
Cは、すっかり納得したようではなかった。
「なんでもないよ。でも、心配してくれてありがとな」
AがCが手にしていた本を見やりながら、声をかけた。
「……」
Cは、それでも変な感じがして、黙ったままだった。
そんな気配を感じたAは、話題を変えようとして、訊いた。
「ところで、学校の方はどうだい?」
「はい。けっこう忙しくなってきました」
Cが少し安心して答えると、ややそっけない調子でAが応じた。
「ふーん。そうなんだな」
「演習やら現場に出ての学習なんかが増えたんです」
いかにも充実していることが知れた。
「楽しいんだな?」
Aは、羨ましい気分を隠すように訊いた。
「はい」
Cは申し訳ないような気がしなくもなかったけれど、当然だというように答えた。
「それは何よりだ。よかったよ」
「ええ。ありがとうございます」
「なんと言っても、学生は学校が楽しいっていうのが一番だ」
「そういうもんですかね」
Cが言った。この店にすっかり慣れ親しんで、安心しきっているという言い方だった。
「ああ、きっとそうだよ。1日のうちで一番長く過ごして、一番人と接する場所だろ?」
「ええ、わたし、ようやくわかってきたかもしれません」
Cがにっこり笑った。
「ん?」
「学ぶ楽しさって言うのかな、そんなものを、です」
今度は、ちょっと照れくさそうだった。
「へえ。それは何よりだ。いいね」
「はい。けっこう忙しくなってきたんですけど。でも、楽しいです」
「ふーん。そりゃあ、ますますいいな。なんと言っても、楽しくなくっちゃあな」
Aがようやく機会がやって来たと思いながらも、秘めた思惑をうまく話せるものか不安なまま、終いの方はつぶやくように言った。
「じゃあ、こっちの時間を減らさくちゃあいけないか?」
すると、Cは驚いて、素っ頓狂な声を出した。
「えっ?」
次週に続く。
2026.01.18
FANTASY 51 年末・年始企画 デザイン事務所の副業と生活 新たな出発・5
生活編・1
また時が過ぎ、いつものカフェの日常が、いつものように過ぎていった。
お客がいなくなりぽっかりと空いた時間にカウンターの椅子に腰掛けてスマホを見ていたCに、Aが声をかけた。
「ねえ、どう思う?」
反応がなかった。Cは気づいていないようだった。スマホをいじりながら、耳にはイヤフォンを挿していたのだ。で、Aはもう一度大きな声で訊いた。
「なんですかあ、どうかしたんですかあ?」
Cが上の空で答えた。音楽か何かを聞いているのに違いない。ふだんなら気にしないのだが、その日は違った。Aは少し苛立地ながら近づくと、つい冷たい口調になった。
「まず、イヤフォンを外してくれよ。俺が話しかけているんだからさ」
「どうかしましたかあ?」
Cはようやく片方のイヤフォンをはずし始めたのだったが、相変わらずのんびりした様子のままだった。それで、Aの声はさらに大きくなった。
「いいから、こっちを向きなさい」
「えっ」
Cも、さすがにその声には驚いたようで、急いで顔をAの方に向けた。これを見たAは、呆れたように呟いたのだった。
「えっじゃないよ、まったく。お前さんは能天気でいいねえ」
「どうしたんですか、そんなにカリカリして。なんかあったんですか?」
Cは、もう一方のイヤフォンを外した。
「カリカリなんかしてないよ」
「してますよお、絶対」
「ああ、してるよたしかに。カリカリしたくもなるってもんだよ、まったく」
Aは、いつのまにか攻守逆転しているような気がしたが、Cはまったく意に介していないようだった。
「いったいどうしたっていうんです?」
「お前さんたちはスマホを持っていると、他のことが目に入らないようだな」
「そりゃあそうですよ。だってスマホを見てるんですから」
「まあ、確かに。そういうことは機転が利くんだよなあ」
Aは怒る気も失せて、苦笑いするしかなかった。一方、Cの方は、逆にすっかり余裕を取り戻したようだった。
「はいはい。で、なんなんです?」
「忘れちまったよ、今の騒ぎで」
「忘れるくらいなら、たいしたことじゃなかったってことですね」
「なんだと。やれやれ、そんなふうに言うかね」
そののんびりとしたCのペースに、Aの先ほどから消えかかっていた怒りはもはや完全に失せてしまったようだった。
「だって、私が前に言われたんですから」
「誰に?」
「私の目の前にいる人に」
「そうだったか?まあ、確かに。そういうことはあるかもな」
もはやAは、すっかり力が抜けてしまったようだった。しばらく天を見つめていたが、すぐに大きな声を出した。
「あ、思い出した。いや、違うか……?」
「何をですか?」
「話そうとしていたことかどうかわからないけど、思い出したことがある。そのスマホのことで」
Aが言うと、Cが素っ気なく応じた。
「はい、じゃあどうぞ」
「そう冷たくするなよ」
「してません」
「そうかな。してるよ。でも、別にお前さんのことを咎めだてしようというわけじゃないんだからさ」
「だから、してませんてば。はい、どうぞ。いったい、なんなんですか?」
「そう?ならいいけど、ほらね、先日……」
Aが話し始めた。少し前のことだった。そのことは、Cもよく覚えていた。
目の前のカウンター席に陣取った大学生らしい男女の二人連れを見ていたAが、珍しく自分の方から声をかけのだった。店ももう終わりかけの頃だったので、ほかには客はいなかった。
「なあ、お前さんたち、ちょっといいか?」
「はい。何ですか、改まって?」
男の学生が答えた。女子学生はちらっと顔をあげたが、すぐにスマホに戻った。
「そのスマートフォン、縮めて言うのがお前さんたちの流儀のようだから、スマホと言うのか、そのことだけどさ」
Aが言うと、
「ええ、それがどうかしましたか?こないだ買ったんですよ、思い切って新型。高かったけど、いいですよお。カメラは超広角で高画質なんですよ。まあちょっと大きくて重いですけど、それほどでもないし、待機状態でもすぐにロック解除ができるんです、それに……」
男子学生の方は警戒が解けると、ここぞとばかりに説明し始めた。
「ま、いいものだということはよくわかった。でも俺が言いたいのはね、そのスマホをいったん脇に置けばってことなんだよ」
「えっ、どうしてですか、やっと入れたスマホですよ。これを触っているのが楽しいのに?」
Aとスマホを交互に見ながら言った。
「余計なお世話だろうけど、せっかく二人できてるんだから話でもしたらどうなんだい」
「どうしてですか、なぜそんなことを?」
「どうしても何も、スマホは一人の時にでもできるだろ?それともよほど急ぐことがあるのかい?」
「いやあ別に急いでいるわけじゃないんですけど、面白いし」
「それだったら、別の面白いことをやればいいじゃないか。せっかく二人いっしょにいるんだから、二人でできることをね?」
「はあ」
「俺が淹れたコーヒーだって、味わって飲んでいるわけでもなそうだしな。出来合いのもんをコーヒーカップに入れて出されてもわからないんじゃないかね?せっかくここに居るのにな」
「すいません。じゃあどうしろと?」
最近の若者は何でもすぐに聞きたがる。あるいは、無視するかのどっちかだ。自分の頭で考えることはしないのだろうか。きっと、これも少なからずスマホのせいがあるに違いない(おまけに、最近ではAIがなんでも教えてくれるらしいのだ)。
「どうしろと言うわけにもいかないが、まず話でもしたらどうなんだい」
Aが言うと、男子学生がまた訊いた。
「何の話をですか?」
「やれやれ、どうしようもないね。うーん、たとえばだな……、お前さんは映画や小説が好きだと言っていたよな?」
「そうですけど、よく覚えていましたねえ。なんだか嬉しいなあ」
「音楽の話だっていいよ」
「音楽はですね、俺の好きなものが他のやつとだいぶ違うんです」
「あ、そう?なんだっていいんだよ。でもな、違っているから面白いんじゃないか」
そんなやりとりを側で聞いていた女子学生がスマホを見るのをやめて顔を上げると、Aの方をちらりと見たあと、隣の男子学生に話しかけたのだった。
「あなた、映画が好きなのかあ。それに、小説も読むのね?知らなかったなあ」
「ああ。映画は時々だね。映画館は高いから。だから、たいていはパソコンだね。その点、小説はいいんだよ。図書館でも借りれるし」
「そうか。私も読まなくちゃと思うんだけど、長い文章が苦手で、無理みたいなの」
女子学生が言うと、男子学生はスマホを置いて彼女の方を見た。
「そうなんだ?実はね、俺も最初から好きだったわけじゃないんだ。短いものを勧められて読んだら面白くて、だんだん読むようになったんだよ」
「そうなのね。だったら、私も読めるようになるかもしれないってことよね?」
女子学生が言うと、男子学生が間髪を入れずに応じたのだった。
「ああ。そうだね。初めから長いものじゃなくていいし、絵本みたいなものからでもいいと思うよ。読みはじめて、面白くなったらね、終わってしまうのが惜しくなる時があるよ」
「へえ、そうなんだ。じゃあ、今度何か読みやすいものを教えてくれる?」
「いいよ」
「よかった。よろしくお願いします」
「ああ、いつでも」
「ところで、他の人と合わないという音楽ってどんなもの?」
「実はね……」
「えっ?ほんとに?、私……」
こうしてようやく二人の話しが始まった。それからは、ずいぶん盛り上がっていたようだった。しばらくして、ようやく話に一区切りがつくと、
「ありがとうございました」
二人は礼を言って、席を立った。
「な、話せば、色々と見つかるもんだろ?」
Aは少し嬉しそうに声をかけたのだったが、二人にはもう聞こえていないようだった。
これを見ていたCが近づいてきて、言った。
「ずいぶん優しんですね。いつも以上に辛抱強く話していた」
「まあね、そうかも。あんまり小言ばかり言うのが寂しいような気になる時があってね、言うにしてもやさしくしなけりゃと思う時があるのさ。歳のせいかね?」
「へえ。そういうもんですかねえ」
「ま、お前さんには、まだ当分わからないだろうけどね。それにね、あんまり時間を浪費して欲しくないんだよ」
「えっ。でも若い時の経験は無駄にならないと言いますよね」
「まあ、そうかもしれないけどね。人によってはね。でも、浪費ばかりしてるだけじゃまずいだろう?」
「うーん。そういうものですかねえ?」
「ま、お前さんにはわからないかもしれないけどね。失ってはじめてわかることもある……」
Aは遠くの方を見やった。
「それは、私がバカだってことですかあ?」
「そうじゃないよ。お前さんはまだ若いからってことさ。ただね、若さに甘えすぎて、俺のような思いをして欲しくないっていうか、あとで後悔して欲しくないんだよ。ま、余計なお世話だと言われれば、その通りだけどね」
「はあ。そうなんですか?後悔してるんですかあ?そうは見えないけどなあ。ずいぶん楽しそうだし、まあこう言っちゃなんですけど、悩み事なんかなさそうなのに……」
「ああ、恥ずかしながらね。よし、恥ずかしいついでに、話すとするか」
Aはようやく踏ん切りがついたようだった。
次週に続く。
2026.01.11
FANTASY 50 年末・年始企画 デザイン事務所の副業と生活 新たな出発・4
デザイン編・2
「で、どうする?見られてもいものは見せて、見られたくないものは見せない、そして自分の方は見たいものを見ることができる、そのための方法は?」
「そうですねえ。家の中の生活を見せてもいいものと見られたくないものを分けて、間に仕切りをつくるというのは?」
Cが、少しずつアイデアを思いつき始めたようだった。
「うん、なるほど。いいね。ただ、問題はそれをどう実現するかってことだよね?」
「うーん。そうですよねえ」
Cは大きく息をつくと、天を仰いだ。
「ああ、この問題に限らず、ある考えを実現するために具体的にどうするかということこそが大事、だと思うんだけどね」
「ええ」
「それが考えられていないなら、いくら立派なコンセプトでも、絵に描いた餅だ」
「そうですよねえ」
「だから、なんであれ、そのための仕掛け、問題を解決するための方法、仕掛けや仕組みを具体的にどう作り出すというのがデザイン、じゃないのか、と俺は思うんだけどね?」
「そうか。そうですよねえ」
「住宅で言うなら、そこで実現したい暮らし方のイメージを描くだけじゃなくて、それを実際に可能にするための具体的な住宅の形として示すのが住宅のデザインなんだと思う。インテリアデザインだって同じことだよね」
「はい。そうですね」
お客がいないせいで、AとCの話はさらに続いた。
「でも、解決する必要のあるものは、形のあるものだけじゃない。たとえば、同じ部署のスタッフ同士の情報共有をどうするか、さらに異なる複数の部署ではどうするのがいいのか、そのための仕掛けや仕組みを考えて、それらを作り出すのもデザインなんだよね。住宅のことでいうなら、そこでの過ごし方、1日あるいは季節ごとの住まい方をどうするのかイメージを描くのもデザイン。ちょっと飛躍するようだけれど、人の一生の過ごし方だって一緒じゃないかな。だから多くの人が言うように、デザインというのは、何も形のことだけじゃないんだね」
「ええ」
「とは言っても、一般的な使い方としては形のことを指すことがまだまだ多いような気がするけどね」
「ええ。私の学科の学生はもともとそういうふうに思って入ってきた人が多いんですけど、入学するとすぐにほとんどの先生たちから『デザインは形のことじゃない』と叩き込まれるんですよね。なんことかさっぱりわからないまま。で、形のことを言うのが悪いような気がしてくるんです。だから、今では、形はどうでもよくて、そのもとになるコンセプトの方が大事だと考えている人が多いみたい」
「ああ。で、お前さんはどう思う?」
「うーん。でも、形のことを考えないならつまらない気がします。私の個人的な意見ですが」
「その個人的な意見をまず大事にしなくちゃね」
Aは、だいたい個人の意見というものは全てまずは個人的なものであるはずと思っていたが、そのことは言わないでおいた。
「はあ」
Cは、半信半疑のままのようだった。
「だから、さっきの同じ部署のスタッフ同士の情報共有するための仕掛けや仕組みも、それらを考えて作り出すのもデザインなんだね。お前さんたちが入学して間もなく洗礼を受けたように、デザインという言葉が色々な場面で使われるようになって、デザインが形だけのことを指すものじゃないということは知られてきたとは思うけど。それでも、お前さんと同じように、まあ、形だけしか考えないというのもどうかと思うけど、形はどうでもいいというのはどうかと思うけどね」
Aがいつの間にか問いを発することをやめて、自分の考えを口にし始めるようになっていた。いい教師の資質は相手の言うことをよく聞くことだとわかってはいたものの、時にむづかしくなる時があったのだ。頭でわかっているということと実際にそうするということは、異なる2つのことなのだ。おまけに、喋りたがりという性格は簡単には治らない。
「ええ。でも、エスキースチェックや講評の時には必ずと言っていいほど最初にコンセプトは?って聞かれるんですよね」
「ああ。でも君たちもコンセプトが好きなんじゃないの?何かにつけてコンセプトという言葉を使いたがるような気がするけどね」
Aがそう言うと、Cはいかにも残念そうな顔をした。
「ええ。でも、私の場合、そんなに立派なコンセプトなんかないんです」
「それがふつうじゃないの」
「えっ?」
「コンセプトと言ったからといって、立派なことっていうわけじゃない。たいていは、最初に考えたこととか、最終的には設計趣旨や目的と言っていいくらいのものだろう?」
「ええ」
「だから、初めから立派なコンセプトなんかなくてもいいと思うよ」
「いいんですかねえ」
「いいさ。設計案と無関係な言葉をひねくり回すよりも、問題をどう捉えるか、どう解決しようとするかなんかについて頭をひねる方が断然いい、と思うよ」
「そうなんですかねえ。いいんですかねえ。でもそうします。その方が私に合っていそうだし」
「そうそう。さらに言うなら、提出する際につけるいわゆるコンセプトは、できた案を最もよく説明するものにすればいいんだから。極端にいうと、出来上がった後からでいい。たいてい、はじめに思いついたことと最終的に出来上がったものは違うのがふつうだろ?」
「そうですよね。わかりました。それでいいんですね。なんだか気が楽になりました」
「よかった。だから、形から出発して、これをもとに目的なりお前さんたちのいうコンセプト、最初のね、これに適合させるやり方だってあるんじゃないか。ついで言うなら、もうひとつオリジナル信仰という病がありそうだけどね。これについての話はまたにしよう」
「はい」
Aが立ち上がるとカウンターの中へ入って行き、コーヒーを淹れ始めた。しばらくして、2つのコーヒーカップを持って戻ってきた。
「さあ、どうぞ」
「ありがとうございます」
それから、Aがまた話し始めた。
「それにね、たとえばね、こういう話がある。恩義ある人に勧められた建築家が住人はいやだと言うのに大きな天窓をつくったせいで、住み手は夏は麦わら帽子を壁って暮らしているって。断りきれなかったんだね、何しろ恩義ある人の推薦だったから」
Aの説明の仕方が、だんだんちょっと説教めいてきたようだった。長年勤めた職場での習い性なのだ。これを聞いたCがふっと笑った後、言った。
「へえ。でも、独りよがりはダメだけど、形も大事な気がします。形だけじゃダメだということはわかったように思いますけど」
だんだん、自分の意見をはっきりと言うようになってきたようだった。
「それにね、逆に、お下がりの服でも暑さや寒さは凌げるからといって、たいして気に入ってもいない服を着てずっと過ごすというのもつまらないじゃないか?だから、お前さんの言うとおり、デザインというのは、見た目も大事、すごく大事だと俺も思うね。結局、使う人、住宅なら住む人が嬉しいと思うものじゃなくちゃね、つまらない。街だって同じだと思うよ。形に、特にその美しさに気を配らないというのは、ものの魅力の半しか見ていない、味わっていないということじゃないかな。いや半分じゃ済まないかもしれない。よく見かけじゃない、本質が大事だというだろ。確かにそのとおりだろうけどね。でも、きちんとした身なりをした人のことは誰も疑わないのに、だらしない格好の人はつい遠ざけたくなるのが常だよね。もちろん、見かけだけに騙されちゃまずいけどね」
「そうですよね。きっとそうだと思います」
「ああ。だけど、その魅力も様々なことも忘れないようにね」
「はい。華やかでスタイリッシュなだけが魅力じゃないということですよね?」
「そうだと思うよ。前にも言ったことがあると思うけれど、簡素で素朴なものだって十分魅力的なものがたくさんあるからね」
「はい。シブイっていうやつですよね?」
「うん、まあそうかもな。他にもね」
AはCの言い方に違和感を覚えたが、言葉の使い方はともかく、それよりも一面的でなく多面的に見るということの大事さに気づいて、自分で考えるようになったのなら、今のところは呼び方はどうでもいいという気がした。
「ええ」
「ところで、コンセプトと形の両立、そのためにはどうすればいいんでしょうね?」
「むづかしいよね?」
「ええ。だからあ、どうすればいいんですか?」
Cはいつまでも自分の質問に答えようとしないAに対して、少し苛立ち始めたようだった。Aはそのことを知ってか知らずか、あっさり言ったのだった。
「自分で考えなくちゃあね」
「えっ?」
「さっきも言ったろ、まずは自分で考えてみる、それが大事だと思うよ」
「はい。でも具体的には?どんな風に進めるのがいいんでしょう?」
「簡単じゃないけどね。でも、結局は人それぞれなんじゃないかね」
と、Aが言う。やっぱり、昔の癖が抜けないらしかった。すると、すかさずCが訊いた。
「はい。でセンセイは?」
今度はなかなか上手いやり方だった。一般論としての解答ではなく、個人的な方法を問われたのなら言わないでおくこともない。
「おい、またセンセイかよ。まいるね」
「あ、ごめんなさい。でも、センセイの場合はどうするんですか?」
Cが尋ねると、Aはすぐさま答えた。
「俺の場合はね、短い言葉でもスケッチでも、まずは思いついたことをとりあえず書きつけることから始める。頭の出来のせいか、目に見えるようにしないと理解できないんだ。でもね、梅棹忠夫先生も、人間の頭はそんなに立派にはできていない、初めから論理的に考えるわけじゃないと言っているよ」
結局のところ、喋りたがり教えたがりなのかもしれない。
「へえ。そうなんですね。書くと何かいいことがあるんですか?」
Cが、やや小さな声で訊いた。
「いろいろあるよ。でも、これも人それぞれかもね」
「そうなんですか」
「ああ」
「でも、センセイの場合は?」
「で、書いたものを見ながら、気づいたことがあれば足す。逆に不要だと思ったものは消す。また、見ていたら連想が働くことがあるから、それをまた書きつける。まあ、そうやって小さな種を育てていくんだね。これを繰り返しながら少しずつ、自分がいいと思うもの、求めるものに近づくようにする。だから、時間がかかるし、効率的じゃないんだけど、俺の場合はそうしないとできないから仕方がないんだ」
「なるほど……。あ、ミステリードラマの捜査室と同じだ!」
Cが突然、分かったと言わんばかりに、小さく声をあげた。その様子に驚いたAは、
「えっ?」
思わず問い返したのだったが、するとCが続けて言った。
「犯人を突き止めるために、ボードに写真やら日付やら、手がかりになりそうなものを貼り付けるんです」
「ああ、それと一緒のようだな」
Aも、Cの方を向いて言う。
「時々、並べ替えたりもします」
Cは、さらに続けた。
「そう。同じだね。まあ中には、アイデアが固まるまで書かずにいて、頭の中で考え続けるという人もいるようだけれど、それはある種、天才にしかできない気がする……」
「そうなんですね。そうですよね。でも、わたしも、おんなじように、捜査の方法と同じやり方をやってみることにします。小さなアイデアの種を大きく育てることができるよう頑張ります」
「ああ、そうだ。そうするのがいい。あ、それに、こないだここにもきたBとも話すといいよ」
「はい。わかりました。そうします」
「ところで、この先の2つほど先のブロックを左へ入ると、空き地になったところがあるだろう?あそこに何が建っていたか覚えているかい?」
Aが何か思い出したのか、唐突に言った。
「そういえば、いつの間にか空き地になっていましたね。もう2ヶ月くらいになるのかしら?」
Cも思い出したようだった。
「そんなものかね。もう少し経つという気がするけどね。で、覚えてる?」
「さあて、なんでしたっけねえ?よく見ていたのに思い出せない」
「やっぱりね。俺も考えてみるんだけど、覚えてないんだよ」
「考えてみると、こういうことってけっこう多くないですか?」
「そうだよなあ」
「どうしてでしょうね?」
「なぜだと思う?」
「記憶力のせい?そんなはずはないですねえ、私だって覚えていないんだから」
Cがふっと笑った。Aは拗ねるように呟いた。
「そういうものかね、じゃあ、なんのせいだよ?」
「でも忘れたということは、一度は覚えていたってことですよね?」
「ああ、少なくとも覚えているつもりでいたってことだな」
「思い出せないんだから、よく見てなかった?」
「たぶん、そうなんだろうね。きっと、ちゃんと見ているつもりが、実はぼんやり眺めていただけってことなんだね?」
「ちょっと怖くなりますね」
「何が?」
「見ていたつもりが、実はちゃんと見ていなかったということですよ」
「そうだよなあ。だいたい、大きなもの、華やかなもの、変わったものなんかは目につきやすいけどね。小さなものや地味なものは気をつけてしっかり見ないと気づかないことがたくさんあるよね?」
「はい。建物以外では、他にどういうものがありますかね?」
「ひっそりと咲く小さな花とかね。その気で見ないとなかなかね。お前さんも紅葉しか目に入っていなかったようだし。もっとも、柿の木だって切られてしまえば、気づかないこともありそうだけど」
「でも、町のことをちゃんと理解しようとすれば、それじゃいけませんね?」
Cが珍しく真剣な顔つきになった。
「そうだね。特に若いうちはね、忙しいし、他に面白いことがたくさんあるし、おまけに派手で大きなものに目が行きがちだからね。もっとも、俺だって偉そうには言えないけどね」
「そうなんですか?」
「ああ。年取ってようやく少しずつ気づき始めたんだ」
「へえ。そうなんですかあ?ちょっと安心しました」
Cがまた元の言い方に戻った。Aは慌てて付け加えた。
「おいおい、俺を見て安心しちゃいけないよ。そりゃ甘いってもんだよ。こんなに能天気にやってきた輩はそうはいないんじゃないかという気がするよ。だから、これでも反省しているし、後悔してるんだよ」
冗談めかして言ったのだったが、一瞬顔を曇らせたようだった。
「えっ。そうなんですか?」
「ああ」
そうして、ふたりの住宅をめぐる論議は、とりとめのないままで、必ずしも結論を得たというわけではなかったけれど、一先ず終わったのだった。Aは、Cが自分なりに理解して、自分で考えようとしはじめたことで十分だという気がした。まだ不思議だと思うこともたくさんあったのだけれど。
「あっ。あの大昔の映画って何ですか?」
Cが不意に思い出したようだった。Aは、大昔?と思いながら返した。
「おや、興味があるのかい?」
「ええ。ちょっと気になったんです。観てみようかなあって」
「ふん。「あれはね『ビフォア・サンライズ』。『ビフォア』3部作と言ってね、9年おきに作られたシリーズの最初のやつだ」
「へえ。そうなんですね。面白そう」
「ああ」
それに伴って、AとCの関係にも微妙な変化が生じたようだった。
ここまでのあとがき
今年の分はこれでおしまいです。
相変わらず、詰め切れないまま時間切れのようだし、手を替え品を替えようとしてはみるものの代わり映えがしないし、なかなか上達しませんが、も少し続きます。
皆さま、良い年をお迎えください。
2025.12.28
FANTASY 49 年末・年始企画第2弾 あるクリスマスの日
ようやく暑かった夏が去ったと思っていたら、秋はあっという間に過ぎてしまった。その年の夏は異常に長かったのだ。あたりの木々の葉がいつの間にかすっかり色づいて、鮮やかな黄金色や紅色に染まると間なく散ってしまった。それでも、近所の庭先では、紫の朝顔の花と黄色の柚子の実が同居しているのを見ることができた。もはや昔の気候と同じではないことが知れた。
すぐにでも本格的な冬がやってきそうだったが、時折り季節が逆戻りしたような暖かい日が不意に混じることがあって、そんなある日ぼくはいつものちいさな公園のベンチに座っていた。隣りでは仔犬のひまわりが手をぼくの膝に乗せていたし、さらにその隣りのベンチの左端にはちいさな女の子が時折り足をぶらつかせながら座っていた。
「もうすぐ、クリスマスだね」
ぼくがいった。こんなことを口にしたのは久しぶりのことだ。長い間ずっと、クリスマスは自分の生活とは無縁のままだった。ちいさいころのことはほとんど覚えていないけれど、当時のクリスマスの思い出はといえば、父がいちごとヒイラギの葉の飾りがが載ったいわゆるクリスマスケーキを買ってきて、家族で食べたことくらいだ(それだって、いつのことだったかたしかじゃない)。たぶん、ようやく経済が復興しはじめて、庶民のささやかな楽しみとなったころのことだ。
「ええ。もう、お店ではジングルベルが聞こえているわ」
女の子が応じた。クリスマスがこの国にすっかり定着しただけでなく、いつのころからか、一と月以上も前から期待や購買欲を掻き立てるような行事になった。同じようなもので、少し前にはハロウィーンがあったばかりだ。こちらもすっかり定着したようだけれど、最近では若者が大騒ぎをするということでニュースになるばかりで、子どもたちにとってはどうなのは知らない。ぼくにはまったく縁がなく、わからないのだ。
「楽しみにしている?」
ぼくが、さらに訊いた。するとどうしたことか、女の子は、
「ええ、でも……」
と口ごもったのだった。予想もしなかった反応に、思わず訊き返した。
「えっ、でもって?」
この国のちいさな子どもたちのほとんどが、クリスマスを楽しみにしているはずなのに。そう思っていると、
「サンタクロースがいないの」
女の子がポツリと、つぶやくようにいったのだった。
「えっ、クリスマスのプレゼントがないのかい?」
ぼくは、意表をつかれたような気がして、思わず訊いた。
「プレゼントはあるわ、もちろん。おばあさんが用意してくれているの」
女の子が、ごく当然なことだというふうに答えた(ということは、まだちいさいのにもかかわらず、もうサンタクロースを信じてはいないのだろうか)。女の子の家の事情については、彼女が大好きなおばあさんといっしょに暮らしていること以外はほとんど知らないぼくは、間抜けな質問をしたようだった。
「ああ、そうか。そうだよね」
「でもね、サンタクロースじゃないの。サンタさんの代わりなの」
もう一度、ちいさな女の子がそういった。それもまた思いもかけないことだった。それで、また訊いた。
「どうしてさ?」
すると、女の子はそれが不思議でもなんでもないことのようにいったのだった。
「だって、サンタクロースは白い髭のはえた人でしょ?赤い服を着て、赤い帽子をかぶった」
「ああ、そうだね、たしかにね」
ぼくは、少しほっとしていった。ちいさいころから現実的なことばかりを教えられたり、そのことだけを信じたりするのはさびしい気がするのだ。
「サンタクロースのいないクリスマスは、クリスマスじゃない。そうじゃない?」
女の子がそういったので、ぼくは、
「そうだね」
と相槌を打つしかなかった。すると、女の子は、
「家にはおばあさんとわたししかいないし、パパももういない……」
と、ちいさな声で続けたのだ。
「そうなんだね」
ぼくはうなづきながらいった、できるだけさりげなく聞こえるように気をつけながら(でも、うまくいったかどうかはわからない)。でもそれは、これまで聞いていた話からすると、容易に想像がつくことでもあったのだ。
女の子は、
「ええ」
とこたえたのだけれど、ぼくは相変わらずなんというべきかわからないまま、
「うん」
とうなづくしかなかった。
「パパは、ママが亡くなるより前に死んじゃったの」
ちいさな女の子が、続けた。この女の子は、サンタクロースを身近に感じながらクリスマスを楽しむことがあったのだろうか。そして、そのことを覚えているのだろうか。あったとしても、うんとちいさい時のことのはずだから、もう覚えていないのかもしれなかった。
「……」
ぼくがなにもいえないままでいると、女の子が思い出すようにしていった。
「そして、そのあとすぐにママも死んでしまったの」
「そうなのか」
「ええ」
「辛かったね」
ぼくは、そういうしかなかった。
「ええ」
女の子は、感情を挟まずにいった。そのちいさな顔にはほとんどなんの表情も浮かんでいないように見えたが、不思議に冷たいという印象はなかった。彼女は、まだ幼いにもかかわらず、とくにかなしさを表に出すことがなかった(少なくとも、ぼくが目にしたのは、たぶん1度か2度くらいだ。それも自分のことについてじゃなかった)。うんとちいさいときからつらい経験を続けてしたせいで、知らず知らずのうちに感情を心の奥底に閉じ込めてしまうことを覚えてしまったのかもしれない。それでも、やっぱり気になって、訊かないではいられなかった(その日は、どうやらぼくが質問する日のようだった)。
「それで、きみは大丈夫?」
「ええ。大丈夫よ」
ちいさな女の子も、それまでと変わることのない様子で、そう答えた。
「よかった」
ぼくが少し安堵すると、
「だって、おばあさんがいるし……。このひまわりだって」
女の子が、その隣ですっかりくつろいだ様子でちいさな体を横たえている仔犬に目をやった。それで、ぼくも今度はすっかり安心したのだった。
「うん。そうだね」
「ええ。それに、あなただっているもの」
女の子はそういうと、はにかむようにちいさくにっこりわらった(ように見えた)。
「ああ。たしかに」
ぼくもうなづいた。心の底からほっとした。それに、なんだかからだの中をあたたかなものが巡るようなような気がした。
*
ちいさな女の子とクリスマスについてのやりとりをしてしばらく経ったころ、ぼくは誰もいない公園のベンチに座って、すっかり葉を落としてしまった枝の間からのぞく真っ青な青空、もはや秋ではなく冬の空、を見ながら、考えていた。1年を振り返るのはまだ少し早い気がしたけれど、ぼくのこの1年はどうだったのだろう。なんだか、今年も何もしないまま、なにも起こらないまますぎてゆくばかりのようだった。
歳を取ったら、若い時以上にはじめて経験することが増える。何しろ老人になり、それからさらに歳を重ねるということは、誰にとってもはじめてのことなのだ。それは、若い時以上にあたらしく思い知る感覚のような気がしていた。しかし、同時にそれは、たしかにあたらしい経験であるかもしれないが、決して喜ばしいと言えるようなものばかりではなかった。むしろ、いわばなにもしないでも次々にやってくる、毎日のささやかでちょっとさびしいようなお知らせのひとつに過ぎないのだ。
で、もう一度考えてみたのだ。今年は、いつもと違って、何かいいことがあっただろうか。まあ、改めて考えなければわからないというのが、もうすでに答えを示しているようなものだけれど、歳をとると忘れるということも多い。もしあったとしたら、それはなんだったのだろう。忘れているのかもしれないので、もう一度よく考えてみようとしたら、今度はすぐに思い出した。
なんといっても、第1はあたらしい友だちができたということだ(このことは、忘れるわけにはいかないことだったが、歳をとるとなかなかそうはいかないのだ)。しかも若い、うんと年の離れた女性。ひまわりと、ちいさな女の子だ。退職してからは人と会う機会もほとんどなくなって、したがって誰かと親しく話すということもなかったのが、時々おしゃべりを楽しむようになった。
たとえ、それがちいさな子ども相手だとしても、まっすぐな好奇心とやさしい気持ちを持った子どもなら、十分に楽しい話し相手になることができる。そればかりか、時には教えられることさえあって、しかもそうしたことはけっして少なくなかったのだ。
ただ、残念ながら二つ目以降はなかなか思い浮かばなかったけれど。それでも、あとから思いついたことがあった。
*
クリスマスの日の朝は、赤い上着と帽子と白い髭をつけることにしよう。サンタクロースになるのだ。そして、あのちいさな女の子にプレゼントを渡すことにしよう。といっても、さすがに家からその格好で出るのは恥ずかしいから、公園で着ることにすればいい。どうせ、そのころは公園にはまだ誰もいないし、それにぼくの最新の友人となった女の子は、仔犬のひまわりの都合もあって、大雨や大雪が降らない限りはほぼ決まった時刻にやってくるのだから。
*
計画の大筋は、そんなふうにすぐに決まった。しかし、肝心のプレゼントをなんにすればいいのか、まったく見当がつかなかったのだ。だいたいぼくは昔から、年齢にかかわらず女性が何を好むのかはわからなかったのだ。それに、時々おばあさんのことは聞いてはいたものの会ったことはなかったので、彼女を不安にさせたり、不審に思われるようなものであっては困る……。そんなことを考えていたら、プレゼント選びはますますむづかしくなった。
それで結局、何かを買うことはあきらめて、絵本を自作することにした。はじめは、それまでに書き溜めていた子どもでも読めるようなファンタジーめいた話をいくつかまとめようとおもったのだけれど、それは自己流で、助言してくれる人もいなかったので、出来栄えに自信があるというわけではなかった。もしかしたら、女の子をがっかりさせてしまうことになるかもしれない。
それで、どうせなら新しく書いてみようとおもった。ちいさな女の子を主人公にした話にするのがいい。まあ、出来栄えは変わらないかもしれないが、しかしそのことはともかくとして、その絵本は世界に1冊しかないものだから、世界にひとつだけの贈り物になるということは、まちがいなかった。おまけに、女の子が最初の読者になるのだ。それは素敵なことのように思えた。それに、少なくとも害になることはないだろう(たぶん)。
*
そう思うと、さっそく制作に取りかかった。まずは物語をつくり、苦手な絵も少しだけ入れた。さらに、装丁のためのスケッチをした。幸い時間はたっぷりとあったし、まあやさしい作業ではなかったが、気分もまぎれたし、何より楽しい仕事だった。それに、誰かのために何かをするというのは、なかなか気分のいいことでもあった。
新しくつくった物語は、だいたいこんなふうだ。
*
あるちいさな女の子のクリスマス(あらすじ)
その年のクリスマス、ちいさな女の子はなんだか嬉しそうじゃありませんでした。家の中には、豪華ではなかったれどきれいにかざりつけられたクリスマスツリーが置いてありましたし、テーブルの上にはわずかに揺れながらやわらかく灯るローソクと、何やらふたがかぶせられたものが載っていたのでしたが。
「さあ、いらっしゃい。用意ができたよ」
おばあさんが、女の子に声をかけました。
「ええ」
女の子は返事をしましたが、そのまま動こうとはしませんでした。
「どうしたんだい。早くおいでよ」
おばあさんが、もういちどやさしく声をかけました。
「ええ」
返事をしたものの、気分がのらないようすのまま、女の子はテーブルにつきました。すると、おばあさんがいいました。
「さあ、いいかい?あけるよ」
「ええ」
「じゃじゃーん」
かけ声とともにおばあさんがふたを開けました。
「わあ、これはなに?」
女の子ははじめてみるものにおどろいて、声をあげました。

「クリスマスケーキさ、もちろん」
「ええ。それはわかっているわ」
「これはね、フランスのクリスマスケーキなんだよ。ブッシュ・ド・ノエルというらしいよ」
「へえ。どうしたの」
「もちろん、わたしがつくったに決まっているさ」
「ええ。そうね」
女の子がこの家へきて以来、クリスマスケーキは、毎日のおやつのクッキーやビスケットなどと同じく、おばあさんが手作りしたものでした。一緒に暮らすようになって初めてのクリスマスにケーキを見た時こそ嬉しそうだったのでしたが、すぐにその表情は消えていってしまったのでした。おばあさんは、それも無理もないことだとわかっていましたから、女の子をただやさしく見まもるだけでした。なんと言っても、幼いうちに母と父をふたりとも続けて亡くしてしまったのでしたから。それで、一緒に暮らすようになったのでしたから、おばさんは、自分にできることはなんでもしようと決めていたのでした。
「でも、木のかたちをしているのね?」
はじめてみるかたちのケーキを前にして女の子がいいました。それというのも、女の子が打ち解けた様子で話すことはめったになかったのでしたから。
「そうだね」
おばあさんもうれしそうでした。
「どうしてなのかしら?」
女の子がまた聞くと、おばあさんは、
「わたしもよく知らないけどね、なんでもイエスさまが生まれた時に寒くないように温めようとして、暖炉で夜どおし薪を燃やしたということらしいよ」
というのでした。
「へえ。そうなのね」
「さ、食べてごらんよ」
おばあさんはケーキを切り分けると、女の子の皿に乗せて、いいました。
「さ、どうぞ召し上がれ」
「わ、おいしい」
一口食べた女の子は、おおきな声でいったのでした。
「そうかい。それはよかった」
おばあさんもうれしそうです。
「うん、とってもおいしいわ」
女の子はそう言いながら、おばあさんをじっと見ていました。それから、今までおばあさんがしてくれたことを思い出して、なんだかあたたかな気持ちでいっぱいになり、この時がいつまでも続くといい、と願ったのでした。
*
当日の朝は、よく晴れていた。雪に包まれたホワイトクリスマスというわけにはいかなかったことは残念な気もしたけれど、冬の冷たい朝の空気の中で、日差しがあるのは嬉しかったし、足を滑らせる心配がないのも助かった。
公園に着くと、ひまわりと女の子がやってくるのを見つけやすいように、いつものベンチの反対側の道路に近い方に座った。それからコートを脱ぎ、袋から年出した赤い服と帽子を着て、もう一度上からコートを羽織った。そして、公園と隣接する住宅地を分ける低い塀のスチールワイヤー越しに、その向こうの道路を見ていた。機会を逃すわけにはいかないので早く家を出たため、日差しはあったとはいうもののやっぱり真冬の空気は冷たく、だんだん体が冷えてくるのがわかった。もうそろそろ現れてもいい頃だった。
やがて、毛糸の帽子をかぶった女の子の頭が見えたようだった。そのことを確かめると、ぼくは羽織ったコートを取り、赤い帽子をかぶってサンタクロースの格好になると同時に席を立った。ベンチの上に、赤と緑のリボンを結んだ袋を一つだけ置いて。もちろん、「ひまわりをつれたおんなのこへ。あかいふくとしろひげのサンタクロースより」と書いたカードを添えることは忘れなかった。それから、道路の方へ歩き出した。
ぼく、いやサンタクロースの姿に気づいた女の子はおどろいて、すぐに声をあげた。
「あ、サンタさん!」
それにつられて、ひまわりも軽く吠えた。
その声が背中の後ろに聞こえたときには、ぼくはすでにもう公園を出て角を曲がっていた。計画は、うまく行ったようだった(少なくとも、ここまでのところは)。そして、すぐに帽子と服を脱ぎ、髭を外した。もう女の子の声も聞こえなかったし、ひまわりも吠えてはいなかった。
*
その夜、ぼくは朝の出来事を思い出して、思わず独り笑いをした。それから、果たしてちいさな女の子はサンタクロースからの贈り物を気に入ってくれただろうかと考えた。
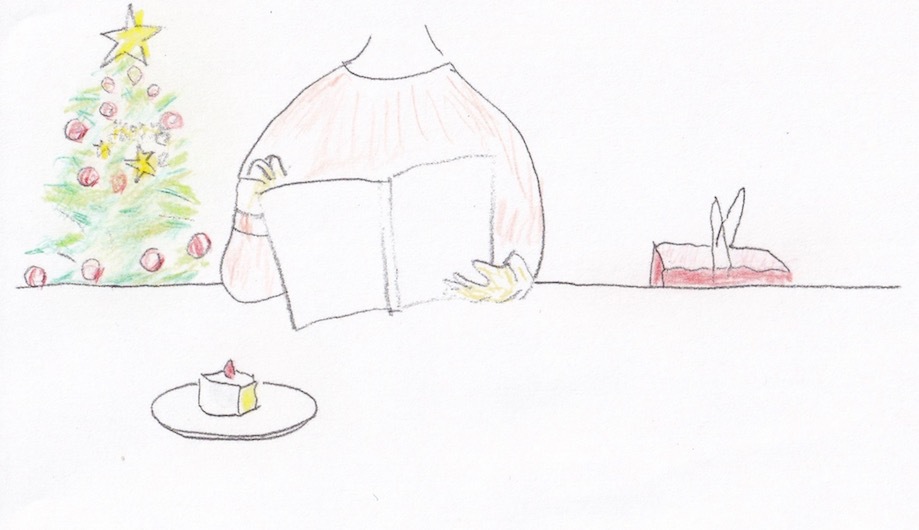
そして、クリスマスのためにおばあさんが焼いたケーキの残りと温かな紅茶の載ったテーブルについた女の子が、手にした絵本をおばあさんとひまわりに読んで聞かせるところを想像して、ぼくはもう一度、独り笑いをしたのだった。
短いあとがき
ずいぶん前に書き始めていたのに、しばらくのあいだ寝かせようと思っていたら、ずっと眠りっぱなしのまま。あっという間にクリスマスになってしまった。で、またしてもいつものように急ごしらえの見切り発車とあいなりました(やれやれ)。
2025.12.24
FANTASY 48 年末・年始企画 デザイン事務所の副業と生活 新たな出発・3
デザイン編・1
「おはようございます」
いつもの大きな声の挨拶とともにCがドアを勢いよく開けて、店に入ってきた。のんびりした喋り方とは違って、元気いっぱい、というか豪快なところがあるようなのだ。彼女はまっすぐAの前にやってくると手にしていた小さな袋ごと差し出した。
「はいどうぞ」
「えっ、どうしたんだい?」
驚いたAが、小さく声をあげた。
「忘れたんですか、先週末は旅行に行くと言っていたでしょ。その時のお土産です」
Cは呆れたように言った。それで、Aも思い出したのだった。
「ああそうだった。で、どうだった?」
Aは、お土産も嬉しかったが、Cがなんと言うかが楽しみだった。Cは旅行のことを聞かれて勢い込んだ。
「すごく良かったです。あちこち行って、楽しかったなあ。何しろ女五人ですから、どこへ行っても賑やかで日頃のうさをすっかり忘れて楽しみましたよ。特に、川下りの船の上から見た紅葉が素晴らしかったんです。最初は皆はしゃいでいたんですが、そのうちに、みんな黙り込んで見入ったくらいなんです」
「へえ、そりゃよかった。お前さんたちも静かになることがあるんだねえ」
Aは半ば皮肉っぽく、半ば感心したようだった。
「もちろんですって言いたいんですけど、ほとんど初めてだったかも。息を飲むっていうか、言葉を失うっていうのか……、実際に、あんな景色があるんですねえ」
Cはよほど感心したのだろう、もう一度思い出すように天を仰いだ。
するとAは、
「まあね、いろいろなところにあるだろうさ」
と、こともなげに言ったのだ。Cはなんのことかわからずに、黙ったままだった。
「……」
それで、AがCの方に向きなおった。
「ところで、途中はどうだった?」
これもまた、Cにとっては予想外のことのようだった。
「えっ?途中ですか、途中って?」
「目的地に行くまでのことだよ?歩いたり、バスだったり、電車だったり。文字通り、目的地までの途中では、いろんなものが見えただろ?」
「うーん。電車の中ではスマホで調べ物をしていたし、バスや歩くときはみんなでおしゃべりしていました。だって、初めてのところだったから皆気持ちが高ぶって楽しかったんです」
「もったいないねえ」
AがCの方を向きながら言っても、Cはぽかんとしたままだった。
「えっ、どうしてですか?素晴らしい名所はバッチリ見たんですよ。しっかり目に焼き付けました」
「歩いている時にはもちろん、電車やバスの車窓からも、その気で見ていたのならたくさんのものが目に止まったはずじゃないかな。昔観た映画の中でね、列車の中で同席した若い女性に若者がユーレイルパスでの旅行のどこが良かったかと訊かれて『何週間も車窓を眺められて良かった』と答え、さらに問われると『思いも考えが浮かぶんだ』という場面があったよ。もはや30年前の映画だし、当時の携帯事情はわからないけれど、これは今も変わらないだろうと思うよ」
Aがさらに付け加えても、Cはにわかには承服できないものの、先ほどまでの自信はなさそうだった。
「へえ。そうなんですか。でも、一番綺麗なところはどこかとちゃんと調べて行ったし……」
「一番ね。一番と言うけどね、いろいろあるんじゃないか?じゃあ、一つ訊いてもいいかい?その五人のうちで一番はだれだい?」
「一番はですねえ……、あれ?私が一番気の合う子ってことでもいいですか、それとも一番背が高い子?一番おしゃれな子?それなだったら言えますけど」
「ということは、一番は一つだけじゃない、他にもあるってことだよね?」
「ええ。確かに」
「だからね、自分にとっての一番は、世間が言う立派なもの、一番だけじゃないってことだよな?」
Aは改めて確認するように言った。
「ああ、そうか。そうかもしれないです」
Cは、Aの言うことをいくらか理解したようだったが、すぐにまた羨ましそうに言うのだった。
「でも、他にも近くに色々あったしなあ……。あの辺りに住む人たちはいいですねえ」
「えっ、どうして?」
「だって、あんな素晴らしいものをいつでも見れるんですよ」
Cは、当たり前のことでしょという表情になったのだったが、Aはすぐに返した。
「ああ、確かにね。でも、それならお前さんだって同じことだろ?」
「えーっ。何言ってんですか?そんなわけないでしょ。比べものになりませんよ」
Cは半ば呆れたように大きな声を出した。それでも、Aは意に介さないようだった。
「そうかね?」
「そうですよ」
「ほんとに?」
「当たり前ですよ」
「そうでもないさ」
「えーっ」
Cは今度こそ心底呆れたようだった
「例えば、近所の山という丘というか、そこの木々の紅葉も美しいよ。小さな公園のものだって、なかなか侮れない」
「まさか……」
Cはからかわれているんじゃないかと思ったようだった。
「嘘だと思うなら、まあ先入観を捨てて見てごらんよ。虚心坦懐な気持ちでね」
Aが言っても、Cは信じられないまま気の無い返事をした。
「はあ」
「虚心坦懐にね」
Aはもう一度繰り返した。
翌日、Cはドアを開けると開口一番、
「きれいでしたよ」
と大きな声で言うと、にっこり笑った。
「何が?」
「だから紅葉ですよ。いろんなものがあるんですねえ」
「えっ、紅葉?紅葉がどうしたんだい?」
「昨日の話ですよ。あれから注意深く見てみたんです。今日の朝も」
「ああ、で、どうだったって?」
Aがようやく思い出すと、
「最初に言った通り、きれいでした。とっても。規模や華やかさはね、当然負けていましたが、とってもよかったです」
Cは初めて気がついたことにすっかり感心したようだった。
これを見て、Aが訊いた。
「そうだろ。で、途中はどうだった?」
昨日の会話と同じだ。
「え、途中ですか?紅葉のことばかり考えていたので、他にはちょっと気づきませんでした」
「そうか。でもね、近くにある美しいものは紅葉だけじゃないよ。他にもいろいろあるはずだから、自分の目でたしかめてごらんよ。旅行の時と同じことだね」
「ああ、そうでした」
「お前さんの好きなあのソール・ライターも、年取ってからは自分の住むアパート周辺の限られた場所だけを歩いて、写真を撮っていたらしいよ。きっと、彼にとっての美しいものを日々発見していたんじゃないかと思うね」
「はい。わたしもそうします」
「そういう気持ち、そんな目で歩いたら、いろいろと気づくんじゃないかのかな。街と住宅の関係だとか、住宅のありようだとかね」
「ええ。頑張ります」
Cが力を込めると、Aはすかさず釘をさすことを忘れなかった。
「ま、あんまり張り切りすぎないようにしてね」
意気込みすぎると案外長続きしないことを、経験上知っていたのだ。
*
別のある日、店を開けてしばらくした頃、まだ客がいない時に、Aが切り出した。
「お前さんは、以前に俺が店に出る回数を減らそうかと思っていると言った時に、不思議そうな顔をしたよな?」
Aが、にやりとしたと思ったら、今度は少し顔を曇らせた。
「ええ。確かに、そうだったかも」
Cはそう答えたものの、よくわからないような面持ちだった。確かにそれらしき話があったことは覚えていたが、途中でお客が入ってきたためにそのまま立ち消えになったのではなかったかしらと思った。Cの様子を見たAが、さらに続けた。
「でもね、今日はそのことじゃない。そのことは、いずれゆっくり話すよ。不思議なのは他にもある」
「はい」
Cが、神妙な顔をAの方に向けた。
「お前さんも知ってのとおり、俺は毎日散歩するだろ?」
「ええ。たしか、近所だけなんですよね?」
「ああ」
「ソール・ライターのように?」
「ソール・ライターのように?いや、俺の場合は決められた歩数を確保しなくちゃいけないからね。それに育ちのせいか、方向音痴気味ってこともある」
「へえ、そうなんですか?」
「まあね。大事にされすぎたんだね、きっと。それはともかく、古い住宅街だから、ほとんど1戸建だよね。それらを見るたびに思うんだよ」
「はあ」
Cはまた、わからなくなったようだった。
Aが急いで付け加えた。
「もちろん、住宅についてのことだよ」
「ええ」
「歩いていると、いろいろなデザインの住宅がある。和風、洋風、切妻、陸屋根、木造、鉄骨造、RC造、大きいの小さいの、派手な色のもの地味なのもの、まあ実に様々だよ。統一感なんてものは皆無だね。まあ、これも日本の街の風景の特徴の一つだよね。このこともいつか話せたらいいけどね」
「ええ」
「しかも、たいていの家で、リビングルームと思しき部屋が見える。でも問題はね、その窓が開いているのを見たことがないんだよ。しかも、いつでもカーテンが閉まっている。ああ、まあレースのものがほとんどだけどね」
Aが続けると、
「はい。でも、それは暑かったからじゃないんですか?今年はいつも以上に暑かったし、長かったですからね」
Cは、それなら当たり前のことだと思ったようだった。
「うん。夏だけだったらね、そうかもしれない。ところが春もそうだった。秋も同じ。冬だってもちろん変わらない。つまり、1年中閉まっているんだよな。大小はあるものの、庭もあるのにね。でも、あれじゃ、リビングルームにいては外は楽しめないだろうな。中には立派なテラスもついていて、おまけにテーブルと椅子まで置いてあるような家でもね、変わらないようなんだよ。そのテーブルと椅子も使っているところは見たためしがない。あれは飾りなのかね?庭はその家の住人のためというより、まるで通行人のためのようだよ」
そう言うと、AがCの方を見た。
「うーん。でも、住宅を計画するときは街に対して開くことを考えなくちゃあいけないと教わりましたよ?地域のコミュニティのためには街に対して開くことが重要なコンセプトなんだって」
「ああ。そうだろうね。生活の犠牲なしにそれができればいいけどね」
「えっ?」
「だって開いているのは建物と庭と道路を隔てる塀だけだろ?家の中と庭は実際的には切れている、カーテンでね。それに道路とも。それでいいものかね?」
Aは、謎かけでもするようだった。
「うーん……」
Cはなんと言っていいか、わからないまま考え込むようだった。
「実際は、住み手の側からはほとんど閉じているんだよ」
「ええ、確かに。そうかもしれませんね」
「それはどうしてなんだ?開く方がいいはずなのに?街に対して開くってことは、住宅の外側にいる人と家の中にいる人がお互いに見合う場面があるってことだろ?」
「うーん……。あ、プライバシーのことがあるんじゃないですかね?」
Cは、今度こそわかったというように、勢い込んだ。
「ああ、たしかにプライバシーは大事だ」
「ええ。そうですよね?」
「じゃあ、どうすればいい?開くべきだって教わったのに?」
Aが、また訊いた。
「うーん……」
「だったら、無理に開こうとしないで、道から見えないようにすればいいだけじゃないのか?視界を遮る塀を作るか、窓を小さくするか、開く方向を変えるか。大事なプライバシーを守るために、道に対して開くのを諦める。簡単だよ。そうだろ、結局後からそうした結果が、今の状況だってことなんじゃないのかね?」
Aは少しせっかちになってきたようだったが、相変わらずちょっと意地悪な訊き方を続けた。
「そうですねえ。ということは、教わったことは間違いってこと?でも……、でもですねえ……」
Cは、そんなに簡単には割り切れないという表情をしたが、どうすればいいかについては考えが及ばないようだった。
「なら訊くけど、お前さんもやっぱり、そう思うのかい?それでも、住宅は外に向かって開く方がいいって?」
Aはそう言ったが、なぜかややあかるい調子を含んでいるようだった。
「はい、まあ……。でも、住んでいる人も、もしかしたら建てる時は屋外の生活に憧れがあったんじゃないですかね?」
「ああ、そうなのかもね。憧れはあったけれども、実際にやってみたら慣れることができなかったってことなのか?」
「ええ。それに、近所の人や外を通る人たちから、あんまり閉鎖的な家だと思われたくなかったのかもしれませんね」
「なら、住んでみたら理想と現実は違ったってことかい?生活する方の考え不足だった?それとも、やっぱり設計者の独りよがり?」
「うーん、そうなのかなあ」
「でも、そもそも開く方がいいというのにはどういう理由があると思う?」
Aが問いかけると、
「うーん、街を楽しいものにしたいから……?」
Cは、自信がなさそうに言った。
「たとえば?」
Aがさらに畳み掛ける。と、
「うーん、見えるものが、塀や壁ばっかりだったらいやじゃないですか?」
Cは、やや自信を取り戻したようだった。
「そうか。でもどうして?」
「なんだか、ええっと、それだと楽しくなさそうだし、それになんだか窮屈で鬱陶しくないですか?」
「なるほどね。で、他には?何がある?」
「たとえば、人と顔を合わせることができなくなるとか……」
「うん。確かにね、あるよね」
「ね、そうですよね。他にはせっかくの庭を見てもらうことができない、逆に言えば道を歩いている人にとっては見ることができないとか。家の中と外が無関係のままじゃつまらないってことですかね?」
「うん。そうだね。でもそのおかげで、実際には家の中にいる人と庭の関係はほぼ無くなってしまっているというのが今の状況なんだよね?だったら、どうすればいいんだい?」
Aは、相変わらず、問いかけるばかりのようだった。
「そうですねえ。やっぱり開くことを考えるしか……」
困惑を隠しきれないまま、CがAの方を見た。
「そうなのか。でも、プライバシーも大事なんだよな?」
「はい。うーん。だから……、外からは覗かれないで、中にいる人も外を楽しめるようにするとか?」
「ああ、確かにね。でも、具体的にはどうすればいい?」
「ええ。それは、つまり……。見られてもいものは見せて、見られたくないものは見せない、そして自分の方は見たいものを見ることができる、ってことだから……」
Cが、時間を稼ぐように言う。
「ああ、そうだよ。で、どうするんだい?」
Aはいつまで経っても、Cの問いに対して問いを返すばかりだった。
2025.12.21
FANTASY 47 年末・年始企画 デザイン事務所の副業と生活 新たな出発・2
メニュー編・2
そんなふうにして、カフェではまたAとCの料理教室をやることになったのだった。
「さあ、やってみようか。久しぶりだよな。ところで、お前さんは焼きそばが好きなのかい?」
Aが訊くと、Cは恥ずかしそうにうつむいた。
「ええ。でも……、正直に言うとふだん食べるのは、カップ麺ですね、お湯を注いで温めるだけの」
「ふーん、そうなのか。ま、まずは材料の準備と確認からだね」
Aは、それが料理の基本の一つだと思っていた。特に、段取りを忘れることの多い自分にとっては、それが不可欠だったのだ。必要なもののほとんどは、あらかじめ切ったり刻んだりして、目の前にきちんと並べる。調味料もできる限り合わせておく。そうすることで、慌てなくて済むし、忘れる心配もない。
「ええ。どんなものなのかしら?」
Cは、自分が提案したものがどんなものになるのか、不安のようでもあったが、興味津々でもあるようだった。
「まずは、焼きそば用の麺。いろいろ売っているようだから、好きなものをね。今日買ってきてくれたのは、中太麺だな。それに、具材はピーマンとシーフードミックス、これだけ。なければ、ちくわでもかまぼこでもいいと思うよ」
「はい。でも、それだけ?」
「そう、それだけ。オリジナルにはないピーマンが、案外ポイントのような気もするけどね。調味料は、オイスターソース、醤油にお酒。それに、みじん切りのにんにく。オリジナルのものはさっきも言ったとおり、オイスターソース、醤油は同じだけれど、お酒の代わりに水、それに生姜とねぎのみじん切り。それだけだった。でも、作ってみた感想は、生姜もねぎもない方がさっぱりしている気がしたんだよね。シーフードやピーマンを入れたせいかもしれないし、作り方も簡単にして生麺ではなく蒸し麺を使っているけどね」
「へえ、そうなんですね。でも、それだけ?」
「そう、これだけ。簡単だろ?」
「はあ」
Cは、まだ半信半疑のようだった。
「さっそく取りかかるとしようか」
「はい」
「まずは材料の下ごしらえから。適当な大きさに刻んだ野菜、ま、麺は細いから、ピーマンも細切りにするのがいいかもね。シーフードミックスはザルにあけて流水でさっと洗ってから水気を切っておくといい。そして、合わせ調味料も前もって作っておく。これが大事だね」
「はい。段取りですよね?」
「ああ、そうそう。よくわかっているね」
Aが褒めると、
「ええ。前に教わりましたから」
Cは、まんざらでもなさそうな表情になり、そして訊いた。
「でも、分量は?」
「ああ、分量だね。だいたいだけれど、一人当たり、オイスターソース、醤油、お酒をおよそ大さじ1杯ずつ。これが目安だね。ただ、醤油は少し減らしてもいいと思うけどね。その代わりお酒を増やす。まあ、それぞれ銘柄によっても違うだろうから、あとは好みで調整するってことだね」
そう言うと、Aはさらに続けた。
「それができたら、中華鍋を中火であっためて、ごま油を入れて、鍋を回して油を行き渡らせる。少し煙が立つのが見えたら、焼きそばの麺を投入して3分ほど焼き付ける。少し焦げるくらいでちょうどいいね。何と言っても焼きそばだからね。それから裏返して2分ほど」
「はい。まず、焼くんですね。焼きそばですもんね」
Cが、名前の由来に改めて気づいたように言った。
「そう。なんと言っても、焼きそばだからね。焼かないことにはね。パリッとした食感が大事だよね」
「ええ」
「両面に焼色がついたら、あっためておいたお皿に一旦取り出しておこう」
「はい」
「あんまり手順は増やしたくはないんだけどね、こうする方がいいと思う。さあ、次は具を炒めよう。まず油を少し足して、たいていの足りなくなるからね。温まったら、まず弱火でにんにくを。香りが立ったら中火にして、シーフードミックス、そして細切りにしたピーマンを入れて、炒める」
「はい。具の分量は?」
「ま、食べたいだけでいいんじゃないかね」
と、Aが言うと、
「ふーん」
Cはなあんだと言うように、つぶやいた。
「まあ、ニンニクひとかけ、ピーマン1個、シーフードミックスは1/4袋ほど、だいたい50~60gくらいでいいんじゃないかね。炒まったところで、あらかじめ合わせておいた調味料を少し入れて具材に味をつける。それから、取り出しておいた焼きそばを戻して、かき混ぜたところに残りの調味料を投入する」
「はい。でも調味料を2回に分けているのはどうしてですか?」
「ああ、具の方にも味をつけておく方がいいかと思ってね。シチューのように、じっくり煮込むような調理じゃないので、何しろ時間が短いから。で、よくかき混ぜて絡めたらおしまい。それだけ。簡単だろ。その間に、皿も温めておくこと。熱い料理は熱い器にってことだね」
「はい。でも、案外簡単ですね」
Cは、ちょっと拍子抜けしたようだった。
「だろ?でも、悪くないよ」
Aはそう言って、にんまりした。何しろ、自信があるのだ。
「へえ。楽しみです」
「じゃあ、温めておいた皿に盛り付けよう」
「はい」
「この盛り付け方に、何か工夫があるといいと思うんだけどなかなかね」
Aは、やや残念そうに言った。中華鍋の中でぐるぐるかき回して、麺を渦巻状にするのを見たことがあるが、それをそのまま皿の上に移すのは簡単じゃないのだ。
それでもAは、密かな自信を押し隠すようにしながら、促した。
「さて、食べてみようか?」
「はい」
「どう?」
「あ、おいしい!」
Cが、予想外だったように言った。
「だろ?カップ麺並みに簡単だけどね、案外、いけるだろ?」
「はい。カップ麺とは全然違います。第一、ソースが違いますもんね。でも、どうやって思いついたんですか?」
「さっき言ったようにね、オリジナルっていうわけじゃないんだ」
「ああ、そうでした」
「元は中華店の人気メニューということなんだけど、いくら人気だと言ってもね。具なしは栄養上も、彩りから見ても、もちょっと寂しい気がしたんで、家にあったピーマンやらミックスシーフードなんかを足してみたら、案外いける気がしたんだよね。元のはね、蒸し麺じゃなくて生麺を茹でて使うんだけど、面倒だろ?」
「へえ、そうだったんですね」
Cが感心したように言った。
「そう。でも、味は悪くないよね?」
「ええ。おいしいです」
Cが、大きく口を開けて食べながら、また言った。
「案外、うまい」
Aも返した。
「ええ。お店に出してもいいと思います」
今度は、Cが請け負った。
しかし、Aはかねての懸案を解決できないものかという思いで、もう一度切り出した。
「でも、何か盛り付け方を工夫できたらね。特徴が出ていいと思うんだけどね」
「はい。私も考えてみます」
Cは言ったものの、とくに成算があるようではなかった。それでも、AはCの方を向くと、
「ああ。よろしく頼むよ」
と言った。
すると、Cは、急に思い出したように不安な表情になったのだ。
「あ、でもHさんのところのことは、大丈夫ですかね?」
と、訊いたのだったが、Aは大して気にならないようだった。
「うーん。まあ、大丈夫だと思うけどね。だってお前さんが言った通り、あそこはあんかけだしね。それに、一般的なソース焼きそばも中濃ソースとかウスターソースだろ?それに向こうは中華料理店だし、こっちは簡単な食事を出すカフェだからね」
「まあ、そうですね」
「気にしないんじゃないかと思うけどね。ま、念のために、あとで話してみるよ」
「はい」
そんなふうにして、久しぶりの料理教室は終わった。Aが思いつきで作った焼きそばを、Cは気に入ってくれたようだった。それで、メニューがひとつ増えることになった。
2025.12.14
FANTASY 46 年末・年始企画 デザイン事務所の副業と生活 新たな出発・1
掲載にあたってのささやかな思い
まあ、掲載しても誰も読まないかもしれないし、反応もないだろうということは十分に想像がつくのですが、それでも書かないことには上達しないはずと思うので。
それにまあ、何であれやってみないことには始まらない。
ということで、今回は「メニュー編」、「デザイン編」、「生活編」の3部構成を、それをそれぞれ2回か3回に分けて連載することにしようと思います。
またしても、詰めが甘い、見切り発車の懸念もありますけど。
*
メニュー編・1
ちょうどお昼時にやってきたランチのお客の第一陣、このカフェが一番混む時だ、この集団が引けた後、Aはふーっとため息をつくと、食器を下げてテーブルの上を拭いているCの方を見た。Aがこの店を引き継ぐかたちで、デザイン事務所の副業としてCとともに営むようになって、もう1年半以上が経った。早いものだ。本当に早い。うかうかしていたら、人生なんてあっという間。歳をとったらなおさらだ。そんなことを考えながら、Aは少し前にふと思ついたことを切り出そうと、声をかけた。
「なあ、メニューのことだけれどね。お前さんは、どう思う?」
これを聞いたCが顔を上げて、布巾をもったままAの方へ歩み寄ると、
「えーっ、なんですかあ?」
と、のんびりと応じた。さすがにもう語尾を伸ばすことはしなかったが、この喋り方は来たときから変わらない(一時、辛い時があった時は別にして)。Aは、ま性格なんだろうと改めて思った。
それからおもむろに、
「なあ、メニューはなんだかマンネリ気味じゃないか?」
と、続けて訊いたのだったが、Cはやっぱり変わらずにのんびりとした調子で応じた。
「あ、そうですねえ」
「お客も案外、飽きていているんじゃないかという気がするんだよ。数も少ないしね」
Aは、今度はもう少し真剣さが伝わるようにと思いながら、言ったのだったが、
「うーん、そうかもしれませんねえ。ちょっと少ないですよねえ」
Cは相変わらず間延びしたような言い方だった。
すっかり慣れたように見えるものの、元々はデザインの勉強をしようと思って上階のデザイン事務所にやってきたのだ(今や、こちらは開店休業状態だけれど)。だから、彼女にとってカフェの運営は、所詮他人事なのかもしれない。Aは訝りながら、続けて訊いたのだった。
「だよな。やっぱりな。お前さんもそう思うんだよな?」
「まあ、ちょっとですけど。そんな気がします」
「じゃあ、新しいメニューを考えなくちゃあな?」
Aが真剣な面持ちで言うと、Cもその気配を感じたらしく、少し真面目な顔つきになった。
「はい」
「何がいいかな?」
Aにはすでに思いついていたものがあったが、言わないでおくことにしたのだった。Cを巻き込むのがいい、という気がしていたのだ。彼女にも積極的に考えて欲しかったし、それになんといっても、お店の共同創業者だし、大事な相棒なのだ。
「短時間で作れて、お客の皆さんが好むもの、ですよね。特に、常連の人たち?」
Cが、なんとかアイデアを思いつこうと、真剣に考えるようになってきたようだった。
「そう、そう」
「それに、何か、今あるのものとは違うもの……、ですよね?」
「そうだね。で、何がいいんだろうね?」
Aは、さらに考えるように促そうとして、Cの方を見なた。
「うーん。たとえば……」
Cは、懸命に考えてはみるものの、なかなか思いつかないようだった。しかし、Aはさらに畳み掛けて訊いたのだ。
「たとえば?」
すると、Cが顔を上げた。
「たとえば、……。いままでは洋風のものばかりですよね?」
なんとか絞り出そうとしていたようだったが、何か思いついたのかもしれない。Aは、はやる心を気取られないように、言った。
「ま、いちおうカフェだからなあ」
「でも、なんか、もうちょっと変わったものがあってもいいんじゃないですかね?」
Cの考えは、少しずつ具体的になって来ているのかもしれない(ようだった)。
「ああ。たとえば、どんなものがある?」
「うーん、焼きそばとか……?」
「ああ。焼きそばね」
Aは心の中でにんまりしたが(やっぱりね)、顔には出さないようにした。
カフェのメニューは極力少なくしようと思っていたが、それも限度がある。作る方もマンネリになるし、そのせいで客も飽きてくるだろう。さて、何がいいだろう。少し前から考え始めていたのだった。
もとより複雑なものは論外。すぐに出来て、多くのお客が好きなもの。しかも、材料が日持ちして使いやすいものでなくちゃいけない。フードロスは極力なくさなければいけない。片手間に始めた仕事とはいえ、赤字が出るとやっていけなくなるのだ。で、思いついたのが、焼きそばだった。それで、実はAにとってはこれは何回も作ったことがある、すでにもう家での昼の絶対的な定番料理とのひとつ、と言っていいほどのものとなっていたのだった。
「だめですかね?」
Cがまた、やっぱりダメかという面持ちで、不安そうに訊いた。
「いや、案外いいかも……」
Aは、またしても焦らすように答えた。
「そうですか?」
「焼きそばか。焼きそばね。たいていの人が好きだものな。でも、Gのところの下のHの店とかぶらないか?」
さらに促すように言う。Cに考えて欲しいのだ。
すると、Cの表情が明るくなったようだった。
「いや、あそこはあんかけですから、味を変えて、ソース焼きそばは?どうでしょうね、作るのもそんなにむづかしくなさそうだし、どうでしょうね?」
「そうか。いいかも。でも……」
「でも?よくないですか?」
Cは、焼きそばというのはいい案だ、と思っているようだった。
「ありきたりじゃないかな?カップ麺と同じだし、わざわざうちの店で食べるかな?」
「うーん。そうですねえ」
「さて、どうしたものかねえ?」
実はもうレシピがあることを、いつ切り出すべきか考えながら、AはCの顔を見た。
すると、Cはすぐさま応じたが、思わぬ反応だった。
「あ、私はいやですよ。絶対にいやですからね。できませんよ」
Cが、今まで以上に真剣な面持ちで、きっぱりと言ったのだ。
「何がだよ?」
Aは、すぐに想像がついたのだったが、素知らぬ顔で言った。Cはすぐに応じた。
「焼きそばのレシピ作りですよ。これはダメですからね、絶対」
彼女には、以前メニューにアップルパイを加えようと相談された時の、苦い経験があったのだ。それは、Aにとっても変わらなかった。で、すぐに引き取ると、さらりと言った。
「ああ、そのことね。じゃあ、こっちでちょっと考えてみるよ」
それを聞いたCは、もうすっかり安心したようだった。
「はい。お願いしますね」
*
翌日だったか、翌々日だったか、勢いよくドアが開いてCが入って来た。そして、
「できましたか?」
Aの顔を見るや否やすぐに、訊いたのだ。やっぱり気になっていたのだ。
「おっ、早いね……」
Aが応じたところで、
「できましたか?」
と、もう一度勢い込んで訊いたのだ。それで、
「まあね。いちおうはね、できた。新しい焼きそばのレシピ」
Aは、余裕ありげに応じた。まあ、先日Cに話す前にはもう出来上がっていたのだから、確認するだけでよかったのだ。
「はい。だったら、よかったです。でも、むづかしいのはだめですよ」
Cが半ば安心し、半ば冗談めかすように言った。
「えっ?」
「だって、私も作る時があるでしょ?」
その言葉とは裏腹に、Cはまんざらでもないようだった。案外自信があるのかもしれなかった。
「ああ。それは心配ない」
Aが、請け負った。
「ならいいですけど」
「ある中華料理の名店の人気メニューをもとに、考えてみたんだけどね」
Aが言うと、Cは慌てて、
「えっ、名店の?やっぱりむづかしそうです。無理かも……」
と言ったので、Aはすぐさま付け加えた。
「いやいや。具もネギと生姜だけで、ほとんどないんだから」
「へえ。でも……?」
Cは、まだ不安そうだ。
「でも、何だよ?」
「でも、なんでもシンプルなものほどむづかしいと言いますよね。シンプルだからこそ、何か特別の技がいるんじゃあ?」
Cが言いかけると、Aは、彼女の不安を消してやろうと、
「ああ。でも大丈夫。もう何回か試してみたし」
と急いで答えた。
「えっ。そうなんですか。むづかしくないんですね?」
「ああ」
と、Aがもう一度請け負った。すると、Cはすぐさま、
「ならよかったです」
安心したように言ったが、先ほどの反応と同様、実はさほど不安に思っていたわけじゃなかったのかもしれない。何しろ彼女の料理の腕もなかなかのものだったし、覚えるのも早かった。
ともかくも、それを訊いたAは、さらに付け加えたのだった。
「食べてみたいかい?」
Aが訊くと、Cは即座に答えた。
「はい」
「じゃあ、焼きそばの麺を買ってきてくれ」
Aが言い、それを聞いたCは、
「はい。わかりました」
と元気よく答えて、すぐに扉を開けて、走り出して行ったのだった。
これを見たAはふたたびほくそ笑むと、店の外に急ごしらえの休憩中の札をかけた。
2025.12.07
FANTASY 45 臨時増刊号 ひまわりと女の子(仮題)第5弾・長い休みの終わり
その日の朝は、少しだけ早く散歩に出ることができた。いつもの公園を目指して歩いていくと、家と家の間から光っている海がわずかに覗いて見えた。公園に着くと、いつものように奥のベンチにひまわりと女の子がいるのが見えた。とすぐに、ぼくは声をかけた。
「やあ、おはよう。雲の観察はどうだった?うまく行ったかい?」
まあ、半分はあいさつ代わりというところ。あとの半分は、夏休みの自由観研究の課題として雲の観察をするというのは元はと言えばぼくも関わったことでもあったので、気になっていたのだ。このところは何かとあったせいで、ひまわりと女の子とはしばらく会えずにいた(なにしろ、歳をとるといろいろとまあやっかいなことが起こる)。
「ええ。たくさんの雲を見たわ」
女の子が大きな声でうれしそうに言ったので、ぼくは少し安心した。急ぎ足でベンチのところまで行き、ひまわりの隣に座った。ひまわりはいつものように、顔を寄せて手をぼくの足の上に載せた。
「そう。それでどうだった?」
ぼくがあらためて訊くと、女の子はすぐに、
「いろいろな形のものがあって、おもしろかった」
と答えた。
「そうだね。たくさんの種類があるし、おなじかたちに見えても少しずつ違っているからね」
ぼくが言うと、女の子は新しい発見を伝えようと、勢い込むようにして言ったのだ。
「ええ。それにずっと眺めていると、別のかたちに見えてくるの」
「うん。たとえば?」
「えーっと、口を開けた龍のようだったり、怒っている鬼のようだったり、にっこり笑っているアンパンマンのようだったり、それに追いかけっこしている鳥の親子もいたし……」
女の子は、思い出すように、そして愛おしそうに言うのだった。ぼくも同じようなことを経験することがあるけれど、こちらは自分の気持ちのありように関わっているような気がしてきて、ついどうしてそんなふうに見えるのだろうかと考えてしまう。彼女の場合はどうだったのだろうと思ったけれど、考えるまでもない。まず、そんなふうに見ることはないに決まっている。ただそのことに感心して、面白がっているだけなのだ(素敵なことだ。ある時期を過ぎたらもうできない。余計なことを知って大人になる前の、特別の期間にだけ許されることなのだ)。
しばらくの間ぼくたちは空を見上げて、雲を眺めていたが、早い朝の雲は綿菓子のはしっこのようにうすくて、軽やかにのびたままじっとして動かなかった。
それから、ぼくは話しかけた。
「夏休みもそろそろ終わりだね」
年をとると、長いはずの時間もすぐに過ぎ去ってしまう。本当に、あっという間なのだ。不思議なことに、同じようなことを言う人は多い。研究した人もいるくらいで、そのひとつに「ジャネーの法則」というものがあって、これによると、人が生涯のある時期に感じる時間の長さは、年齢に反比例する」というのだった。その理由は、①脳の活動が活発なほど時間はゆっくり流れるように感じる、②年齢にたいする1年の占める比率が小さくなる、というもの。本当にそうなのだろうか。まあ、合理的なような、そうでもないような気がするけれど。
すると、女の子が応じた。
「ええ」
いつもの言い方だった。子どもらしくない言い方だけれど、これにはちゃんとした訳があるのだ。
「楽しかったかい?」
ぼくが訊くと、女の子が答えた。
「ええ。でも、もう終わってしまうわ」
「ああ。そうだね」
「あんなに長いと思っていたのに、もうすぐ終わってしまうなんて……。さびしいわ」
女の子が言ったので、ぼくも慰める気持ちで、
「ああ。でも、何にでも終わりはあるさ」
と言ったのだった。
「ええ。そうなのね」
「夏休みだって終わる時がくる」
ぼくが言うと、女の子が、
「ええ。うんと長くて楽しいのに」
と応じた。現在進行形の言い方だった(たしかにまだ終わっていないのだからこの方が正しい気がするけれど、大人はたいていがもう終わったかのように「楽しかったのに」と過去形で言うことが多いのだ)。それでぼくは、
「ああ。そうだね」
といい、さらに続けたのだ。
「アイスクリームだって」
すると、女の子が付け加えた。
「とっても冷たくて、甘いのに」
「ケーキだって」
「甘くておいしいのに」
「キャンディだってそうだ」
「きれいな色をしていて、かわいいのに」
「それに、きみの好きなおはなしだってね」
「ええ。とってもおもしろいのに。でも、終わるとやっぱり寂しい」
「でも、それでいいんだと思うよ」
ぼくは確信があるわけじゃなかったが、女の子を安心させようとして言った。それに、彼女には、これから何度でもその機会があるはずなのだから。
「えっ。どうして?」
女の子が訊いたので、ぼくは答えた。
「だって、いつもあるのなら、うれしいとは思わなくなってしまうんじゃないかな?」
「えっ?」
「アイスクリームだって、ケーキだって、いつまでもなくならないで食べられたなら、どんなにおいしくても、ずっと食べていたいと願ったり、うれしいと思ったりすることはなくなってしまう」
「あ。ええ。たしかにそうね」
女の子が応じたので、僕はさらに続けたのだった。
「きっとありがたさがわからなくなるんだね。それに、飽きちゃいそうだし」
「ええ」
「それに、楽しかったことやうれしかったことは、思い出したいときにいつでも思い出せるだろ?」
「ええ。そうね。もちろん……」
と返事をしたものの、女の子はまだ半信半疑のようだった。それで、
「思い出はね」
ぼくはまた説明を続けた。
「望めば何度でも思い出すことができるんだ。きみがそう願うかぎりはね」
ぼくは、ゆっくりと言い聞かせるように言ったのだったが、さて、これがよかったのかどうか。
「ええ、そうかもしれないけど……」
女の子は口ごもり、まだ安心することはできないようだった。それでぼくは、さらに続けたのだ。
「大事な思い出は、いつまでもなくなることはないないよ」
「そう?ほんとうにそう思う?」
「そうさ。きみが大事に思っているかぎりはね。でも、きみがそう思わなくなったなら、どこかに消えてしまうだろうけどね」
「ええ」
「そう。そして、すっかり忘れてしまう」
「ええ。そうなのね」
女の子が、ようやく同意してくれたようだった。
それで安心したのか、ぼくはどうしたことか、
「たとえば、ぼくがいなくなったら、きみはどう思う?」
その話の流れのままに、つい切り出していた。
「えっ、いなくなるの?」
女の子が驚いて、声をあげた。その声に反応して、すっかりくつろいで眠り込んでいたようだったひまわりが顔を上げ、目をあけてこちらを見た。
「いなくなったら、さびしいに決まっている」
それで、ぼくは急いで付け加えたのだった。
「そうじゃないさ」
「えっ?」
「たとえば、ということだよ」
「ええ、そうなのね」
「そうさ」
「よかった」
女の子はほっとしたようだったが、
「でも、さびしくなるに決まっているわ」
もう一度繰り返したのだった。それで、ぼくはさらに訊いた。
「そうか。でも、きみにはきみが大好きなおばあさんがいるし、ひまわりだっているだろ。それに学校には、お友だちもたくさんいるんじゃないのかい?」
「ええ。そうね」
「そうだろう。だから、ぼくがいなくなったとしても、そのことを楽しめばいいのさ」
目の前にあらわれないものをさびしがるより、そばにいるものを大事にする方が好ましいということを、言い聞かせるような気持ちで言った。
「ええ、そうよね。でも、さびしいわ……」
女の子が足をゆっくりとぶらぶらさせながら、またつぶやいた。ぼくはちょっと嬉しい気がしたが、そのことを知られないように気をつけながら言った。
「でもって。いろいろな人たちといっしょにいたら、きみは楽しいだろ?さびしくならないだろ?」
「ええ。でも、忘れてしまわないかな……?あなたのことやいっしょに見たものや、おはなししたことを」
「大丈夫、ほんとうに楽しいと思ったのなら、忘れないさ。もし、忘れたらそれはもう必要がないってことさ。たとえ忘れたって、なんてことはない。だから、安心していいよ」
ぼくは、言った。
「そんな、そんなのいやだわ」
女の子が憤慨したように言ったので、ぼくはもう一度、すぐに付け加えたのだった。
「でも、大丈夫。また会えるさ」
「そうよね」
「そうさ。きみと、それにぼくが望みさえすればね」
「ええ。そうなのね」
女の子は、半ば安心し、半ばまだ不安なままなようだった。
「(望むなら、何回でも思い出すことだってできる)」
ぼくは、心の中でつぶやいた。
そして、思った。次に、女の子が楽しみにする大きな行事は、クリスマスだろうか。
*
後書き
第5弾を。今回もまた、出来栄えよりも、スピードを重視。そうしないといつまでも終わらないので。まずは、掲載します。
2025.08.31
FANTASY 44 夏休み臨時増刊号 ひまわりと女の子(仮題)第4弾・β版
雨がほとんど降らなかった梅雨が明けた後、いよいよ本格的な夏に入ろうかという頃になってからも、僕は毎日朝夕2回の散歩を欠かすことはなかった(雨が降らない限り、あるいはごく稀にある用事がない限り、ということだ)。ただ、暑さを避けるために、朝はより早く、夕方はさらに遅くするようにした(何しろ歳を取ると温度に鈍感になって、熱中症のリスクが大きいというのだ)。したがって、ひまわりと女の子と会うことがなくなってしまったのだ。
さびしい気がしたけれど、朝の早い時間の銀色に光る海を眺めたあとで、誰もいない公園のベンチに座って本を読んだり、思いついたことを書きつけたりしていると、時間は静かで穏やか、ふだんよりもゆっくりと過ぎていくようだった。自身の気持ちも落ち着いて、なかなか得難い時間となった。本格的な夏に入ったとはいえ、早朝の空気はまだ温められてはいなくて、吹く風はひんやりとして気持ちが良かった。
*
その時、犬のうるさく吠える声がした。顔を上げて声のした方を見ると、若い男女の二人連れに引かれた黒い犬が見えた。ああ、やっぱり。ひまわりじゃなかった、ひまわりはあんなに大きな声で吠えない。もし吠えたなら、きっとたしなめる声がしただろう。それでも、ちょっと残念な気がした。あの小さな女の子は、今は夏休みのはずだ。それで、こちらにいるのかどうかわからないし、もしかしたらどこかに出かけているのかもしれない、と思うことにした。
ともかくも、僕の早朝の散歩はすっかり定着した。しかし時にはつい夜更かしして遅くなることがある。そういう時は、早く目が覚めても起きないで、横になっているようにしている。睡眠時間を確保しようというわけだ。これが実際のどのくらい効果があるのかはわからないけれど、とにかくできるだけそうするようにしているのだ。
何かの拍子で朝の散歩が遅くなった日、いつものようにベンチに座って、思いついたことを書きつけていると、さすがに陽の光が熱くなってきて、ジリジリと焼かれるような感じがしてきた。そこで、そろそろ引き上げる頃合いだと、手帳を閉じ、顔を上げてもう一度海を見やったあとで、腰を上げようとしたら、走り寄ってくるものが見えたのだった。そして、その小さな生き物はベンチに飛び乗ると、僕の膝の上に手を載せたのだった。
向こうには、なつかしいぼくの小さな友人が立っていた。
「やあ。久しぶりだね。元気だったかい?」
まだ少し離れていたが、僕は声をかけた。
「ええ。あなたは?」
女の子も、大きな声で応じて、訊き返した。
「まあまあってとこだね。なんと言ったって、この暑さだしね」
ぼくが言うと、
「ええ、そうね。おばあさんも暑くてたいへん、といつも言っているわ」
女の子はいかにもというふうに言った。そこで、ぼくは、
「そうだね。きみは毎日どうしているんだい?」
とたずねたのだ。すると、ぼくの小さな友人は
「毎朝宿題をやって、夜は日記を書くの」
と言うのだった。ぼくは、感心して言った。
「ふーん。きちんと続けるというのは偉いなあ」
「そうかしら。おばあさんは、毎日少しずつやると楽だと言っているわ」
彼女は、こともなげに言ったのだった。
「へえ、そうなんだ」
「ええ。あなたは?」
小さい女の子が訊いたので、ぼくは正直に言った。
「つい溜めてしまうことが多いね」
「そう。おばあさんは毎日、新聞の切り抜きをやっているわ。私が、毎日やるのはどうしてって訊くと、『毎日なら少しで済むけど、溜めてしまったら一度にやるのは大変だからだよ』って言うの」
「たしかに、そうだね。おばあさんの言うとおりだ」
わかっているということと、実行しているというのとは決定的に違う。まったく別のことなのだ。
「だから、私も毎日、朝は宿題をやって、夜は忘れずに日記をつけることにしているの」
そう言った女の子にすっかり感心したぼくは、
「ふーん。きちんと続けられるというのは偉いなあ」
と素直に言っただけれど、でも女の子は、
「あら、なれると、ちっとも大変じゃないわ」
とあっさりと言うのだった。それで、ぼくはまたまた感心して言うだけだった。
「へえ、そうなんだね」
しばらく、銀色に輝いている海を見ながら話をした。何しろ久しぶりだったのだから。
*
「ところで、ひとつ聞いていいかい?」
ぼくは言った。ある時から、ずっと気になっていたことがあったのだ。
「ええ。いいわ」
彼女は、相変わらず、即座にいやと答えるようなことはしなかった。
「その、きみはよく、ええ、と言うだろう?」
ぼくがそう言うと、女の子は否定することもなく、至極当たり前のことのように言った。
「ええ。そうかも」
「ほらね、また言った」
「ええ。はい」
今度は、途中で何やら気づいたようだった。
「それって、きみのようなまだ小さな子はあんまり言わないんじゃないかって言うことなんだけれど」
「ええ。そうなのかしら?」
女の子は、気にしたことがないようだった。
「ある人にね、きみのことを話したら、そう言われたんだけどね」
「ふーん。じゃあ、そうなのかもしれないわ」
女の子がそう言ったから、ぼくもわからなくなって自問するように言った。
「どうなんだろうね?」
すると、
「ええ。でも、ママはいつもそう言っていたの」
女の子は、そう言ったのだった。
「へえ。そうなんだね」
「私がなにか言うと、まず、ええ、と言ったの」
「うん」
「それから、どうしたの?とか、でもね、とか言ったの」
「ああ、そうだったんだね。どうもありがとう」
ぼくはすっかり納得した気がして、お礼を言うと、女の子は、
「どういたしまして。あ、もちろん、ママはもう子どもじゃなかったけれど」
と言うのだった。やっぱり、幼い子どもの言い方とはずいぶん違っているようだった。
「今度会ったら、そう伝えておくよ」
ぼくがそう言うと、女の子も
「ええ」
そう言って、笑ったのだった。ぼくの小さな友人は、時々、子どもじゃないような気がすることがある。
*
「ここに座っていると、いろんな人が見える。たくさんの人が通るからね」
ぼくがそう言うと、女の子は、
「ええ。あ、また言っちゃった」
と言って、小さく笑った。
「いいさ。気にすることはないよ」
「ええ。そうよね」
「それでね、こないだ走っている人を見たんだよ。おじいさんのようだったけど」
ぼくは、そう切り出した。
「はい」
「その人は帽子をかぶっていたんだけどね」
思い出しただけで、笑いがこみ上げてくるような気がした。
「その帽子が変わっていたんだよ。ふつうの野球帽のようなのじゃなくて、ほら周りに小さな鍔がついているようなものをさ」
「へえ」
「どう思う?」
ぼくが聞いても、女の子はなんのことかわからないかのようだった。
「どうって?」
「だから、その帽子のことだよ」
ぼくがあらためて説明すると、彼女は、
「いいんじゃないかしら」
と、さらりと、そう言ったのだった。
「そう?変だと思わない?」
「どうして?」
「どうしてって、走るときはふつう、そんな帽子は被らないだろう?」
ぼくは、またその時のことを思い出しながら、訊いた。
「そう?でも、かまわないと思うわ」
小さな女の子は、やっぱりそう言うのだった。変だとは思わないようだった。それで、ぼくは、また訊くしかなかった。
「どうして?きみは、どうしてそう思うの?」
すると、女の子はこう答えのだった。
「おじいさんがいいと思っているのならね」
「そうかい?」
そう言いながら、ぼくは少しずつわかってきたようにも思ったのだったが、やっぱり不思議な気がした。
「それに、それしか持っていないかもしれないし、もしかしたら、その帽子がとっても好きなのかもしれない」
女の子は、おじいさんのことを想像するように、そう言ったのだった。それでも、ぼくはまだ納得がいかない気がしていた。で、言った。
「そうなのかな?」
すると、ぼくの小さな友人は、
「ねえ、あなたはおじいさんの帽子で嫌な思いをしたの?」
と訊いたのだった。
「いいや」
ぼくは、正直に答えた。
「だったら、問題ないんじゃないかなあ」
女の子がそう言った時、ぼくはようやくわかったのだった。それで、
「そうだね。確かにそうだ」
と言った。すると、女の子は、安心したように、
「ええ。よかった」
と言った。また、ええという言い方が戻ってきてよかった。そうじゃないと、その小さな女の子は、なんだかぼくが知っている小さな友人じゃないような気がしたのだ。
「うん」
ぼくも、心からそう思って言ったのだった。
*
「あっ、見て。ほら、あの雲。とっても白くてお餅みたいにふくらんでいるわ」
小さな女の子が言った。今度は、子どもらしい言い方だった。
「ああ、きれいだよね」
ぼくも素直に応じた。
「ね、そうでしょう?わたし、あの雲のことを観察することにしようかしら」
女の子が言った。
「へえ、それもいいかも。雲は一つとして同じ形じゃないし、いつも形を変える」
ぼくは特に何かを思ったわけじゃなく、ただなんとなくそう言ったのだったが、女の子はすっかり安心したように、言ったのだ。
「そうなのね。きっとアサガオの観察よりも楽しいかもしれないわ」
「アサガオの観察?」
なんのことだろうと思って、ぼくは訊くと、女の子は、
「ええ、宿題なの。お友達はたいてい、朝顔の観察をしているの」
そう答えた。
「ふーん」
学校では、まだずいぶん小さい頃から宿題というものがあったことを、ぼくはすっかり忘れていたのだ。すると、
「あ、あの雲、少し動いて、右の下の方に灰色の影ができている」
また女の子が言った。
「風が出てきたんだね」
ぼくが言うと、
「あの雲の名前はなんて言うのかしら?」
女の子は、また質問した。とにかく、知らないことはなんでも訊くのだ(ぼくは、いつの頃からかすっかり忘れてしまったようで、恥ずかいい気がした)。
「入道雲だね。積乱雲とも言うけどね」
幸い知っていたぼくがそう言うと、
「へえ。ニュウドウグモ」
と女の子がが復唱した。
「それに、セキランウン。やっぱりよく知っているのね」
そこで、ぼくは説明した。ちょっと得意な気分になっていたのかもしれない
「あたたかくしめった空気が、夏の強い日差しで温められて高く持ち上げられて、できるんだね。だから、雷やはげしい雨を降らせることがあるよ」
すると、女の子は、また感心したように、言った。
「あなたって、ほんとうによく知っているのね、やっぱり雲の観察にしようかな」
「ふーん」
ぼくは、そう言うしかなかったのだけれど、女の子は、さらに、
「それに、あなたと一緒に見ていると、いろいろ知ることができて楽しいもの」
と言ったのだった。
「そう?」
ぼくは、できるだけ平静を装って、言った。すると、
「ええ、それにお家の窓からだって見ることができる」
彼女がそう言ったものだから、ぼくは、
「そうだね。その時は、30分から1時間くらいずっと見ていてごらんよ」
と言った。すると、彼女は、すぐに
「えっ、どうして?」
と訊いたのだったが、
「見ていればわかるよ。それが観察というものだろう?」
ぼくが言うと、すぐに、
「ええ。たしかに」
と言って、理解したようだった。
「そうさ」
ぼくも応じた。
*
それから、女の子はこんなことも話してくれた。
「あ、時々ね、朝だけじゃなくて昼や夕方にも天使の梯子でママのところに行くのよ」
「えっ?」
ちょっとどきりとしたぼくが言葉に詰まると、彼女は、
「あなたが教えてくれた天使の梯子が見えたときに、ママに会いにいくのよ」
と、嬉しそうに言うのだった。
「そうなんだね」
ぼくはすっかり安心して、うなづいた。
「ええ、おかげでとっても楽しいわ」
彼女はそう言ったのだったが、ぼくは、そのおかげでまた自然の中の草や木や花や星などの名前を覚えようかなと、思い始めたのだった。
*
しばらくすると、女の子が、また言ったのだった。
「ねえ、一つ訊いてもいいかしら?」
ほんとうに、大人のような言い方をするのだった。
「いいよ」
ぼくがそう答えた。すると、彼女は、
「そう。じゃあ訊くわ」
とていねいに言い、ぼくが、
「どうぞ」
と促すと、彼女はこう訊いたのだった。
「あなたは、いくつなの?」
「えっ、どうしてさ?」
驚いたぼくは、おうむ返しに訊いたのだった。すると、
「わたしのおばあさんよりも、……」
女の子はそう言いかけると、口ごもった。ちょっと遠慮したのかもしれない。
「うん?」
ぼくは、わからないふりをして、女の子の方を見た。すると、ぼくの小さな友人は、こう言ったのだ。
「私のおばあさんよりも、もう少し年取っているように見えるのだけれど?」
「ああ、きっとそうだと思うよ」
ぼくが素直にそう答えると、彼女がまた訊いたのだ。
「じゃあ、なんて言えばいいのかしら?おばあさんくらいのおじいさんよりも少しだけ年取った人のこと?」
ぼくはその答えを知らなかったけれど、なんだかあたたかいものがこみ上げてくるようだった。
「好きに呼べばいいさ。おじいさんでも、もっと年取ったおじいさんでも。きみがいつもいうように、ただのあなたでも」
と言った。すると、小さな女の子は、ひまわりの頭をなでながら、
「ええ。そうなのね。それでいいのよね」
と言うのだった。にっこり笑っているように見えた。
*
後書き
第4弾を(ま、出来栄えよりも、スピードを重視)。着想から推敲、完成まで、たったの3日。新記録。途中経過の言い訳(うーむ)、拙速かもしれませんが、しばらくお休みする前にと思ったので。それにちょっとした出来事もあったし。もしかしたら、また少し手を入れるかもしれませんが(で、一応β版)、まずは掲載します。
2025.07.23
FANTASY 44 夏休み直前臨時増刊号 ひまわりと女の子(仮題)第3弾
ある夏の日の夕方、まだ日の光がたっぷりと残っているけれど、西の方から夕暮れ時の空に変わり始めるような頃、ぼくたちはいつもとは違う場所、海の見える公園からほど近いさらに小さな公園のベンチに座っていた。
もちろん、ぼくが誘ったのだった。その日の朝、いつものように海を眺めたあとに、
「夕暮れ時の空もきれいだよ、今度いっしょにどう?」
って。すると、女の子が言った。
「ええ。ぜひ見てみたいわ」
って。
ベンチの上は、そのすぐ側に植えてあるもみじの木の張り出した枝についたたくさんの葉が重なりあって、自然の屋根となっている。もみじは秋になると真っ赤になって見事だけれど、夏の緑の葉も十分に美しい。ぼくたちは、この繁った葉と隣接する少し低いところに建つ集合住宅によって切り取られた、夕暮れ時の空を眺めていたのだった。まだ日の光が残っていて、茜色に染まるにはまだ早かった。しかし、青い空と白い雲は昼のそれとは異なって、不思議な透明感のあるあかるさだった。
「きれいだわ」
女の子が言った。この小さな友人は、どうしてだかぼくには見当もつかないが、まだ幼いのにもかかわらず大人のような話し方をする時があるようだった。
「そうだね」
ぼくも相槌を打った。銀色に光る朝の海や茜色の空とは違い、華やかではない微妙な美しさに、この小さな女の子が反応したことに驚いた。
「夕方の空が、こんなに美しいなんて……」
女の子がまた言った。小さな女の子の言い方ではないみたいだけれど、これは誓ってほんとうのことだ。
「ふーん。きみはこれまで、あんまり見ることがなかったのかい?」
ぼくは訊いてみた。実は、答えはあんまり期待していなかった。この小さな友人を知るにつれ、だんだんわかってきたのだけれど、質問に答えるよりは、質問をする方がだんぜん多かったし、その心はしばしば気ままで、話題によって、あるいはただ単にその時々によってあちこちに飛んで、心ここに在らずというようなことがあったのだ。
「ええ、ゆっくりとは。おばあさんの料理するのを手伝うことが多かったの」
どうやら聞いてくれていたらしく、女の子はそう言った。
「そうなんだ」
「でも、そうじゃないときも、空をゆっくり眺めることはなかったの」
女の子はちょっと恥じるように言ったのだった。今度は、いかにも幼い子どもの口調だった。しかし、小さい頃というのは(若い時だって似たようなものだと思うけれど)、ゆっくりと空を眺めてなんかいられない。ほかにやること、楽しいことがたくさんあるのだから。
「うん。もう少し季節が進むとね、この時間は空が赤くなるよ」
「ええ。そうなのね」
「それに、今なら」
と言いかけて、もしかしたらと思いついて、
「ちょっと後ろを見てみよう」
と言って、立ち上がった。ひまわりもベンチから飛び降りた。
やっぱり。思ったとおり。金網越しで、おまけにすぐ下の木の枝が視界を狭くしていたが、緑の谷あいの向こうの大きな建物の白い壁が夕日に照らされて、淡い金色に光るのが見えたのだった。
「ほら、見てごらん」
もう一度言うと、女の子が声をあげた。
「わあ、きれい!なんてきれいなんでしょう」
「ね、きれいだろう?」
「ええ、とっても」
それからしばらくの間、ぼくと女の子は黙って眺めていた。そしてふたたびベンチに座ると、ぼくは付け加えた。
「今くらいの時間の、あの海の見える公園からの眺めもいいよ。やっぱり夕日を浴びた街の建物が金色に輝いて見える」
「ぜひ見たいわ」
「じゃあ今度だね。ところで、きみは料理をするのが好きなのかい?」
「ええ」
「わたし、おばあさんと一緒に料理するのが好きなの」
小さな女の子は、きっぱりと言ったのだった。
「うん。たしかに、料理は楽しいよね。ぼくも好きだな」
ぼくも応じた。
「でも、それは特別に楽しいの」
いかにも特別で、楽しいということがわかるようで、人を羨ましいと思わせずにはおかない言い方だった。
「ふーん。そうなのか。いいね」
「そうよ。とっても素敵な時間なの。一番……」
と言いかけて、口籠った。
「いや、二番目かな、三番目かも。うーん」
そう続けると、女の子はすっかり考え込んでしまったようだった。
「おや、そんなに好きなのに。どうして?」
「一番は、朝の海かもしれないし、こうやって夕暮れの空を見ることも好きになったし……」
「そうだね」
と言ってうなづくと、彼女がぼくの方を見て言った。
「あなたのおかげね」
「そう?どういたしまして」
僕が応じると、女の子の頭の中ではいろいろなことがかけめぐったようだったが、ようやく
「それに、好きな食べ物だって時々変わるの。ああ、順番なんてつけられない。でも、おばあさんと一緒に料理を手伝っている時がやっぱり、一番かなあ」
そう言ったのだった。
「いいね。誰かと一緒に何かを作るというのは素敵なことだね。でもね、無理に順番をつけなくてもいいんじゃないかな」
ぼくが言うと、彼女はうっとりしたように、
「ええ。おばあさんの作る料理は、とっても美味しいの」
そう言うのだったが、ぼくの言うことは上の空で、きっとおばあさんが作る料理のことを思い浮かべていたのに違いないけれど、それはいったいどんな料理だったんだろう。
「へえ、うらやましいな」
ぼくは、ほんとうにそう思って言った。ほんとうに思うことを、面と向かって人に言うのは簡単なことじゃない。大人になってからは、とくにそうだ。それができるのは、残念だけれど、限られた人に対してだけなのだ。
「おばあさんはね、料理のことをほんとによく知っているの」
女の子はおばあさんのことを、心から感心しているようだった。
「そうなんだね」
「あなたが、いろんなことを知っているようにね」
女の子がそう付け加えたので、ぼくも急いで言った。
「でも、ぼくはほんとのことは何も知っちゃいないさ。きみのおばあさんの方がよく知っているのに違いないよ」
「そうかしら?」
女の子が、不思議そうに言った。
それからしばらくの間、ぼくたちはまただまったまま、ほんの少しずつだけれども姿と色を変えていく西の空を見ていた。仔犬のひまわりはベンチの上でずっとぼくの足に手を乗せたまま休んでいて、時々上目遣いに見上げるだけだったけれど。
「あのね」
突然、あらたまった様子で、女の子が言った。
「なんだい?」
ぼくが言うと、小さな女の子が、
「あなたには、ママはいる?」
と訊いたのだ。
「ああ、もちろんいるよ。幸いまだ生きているよ。もうおばあさんだからね、すっかり元気とは言えないかもしれないけれど」
ぼくは、唐突な気がして驚いたけれど、そう答えた。そして、母のことを思い出し、不意に、この女の子のおばあさんというのは、僕よりははるかに若いはずだということに気づいた。
「そう。でも、それはいいことよね?」
たしかめるように、女の子が言った。
「そうだね。とっても嬉しいことだね」
ぼくも、素直に答えた。ほんとうのことだからだ。
「そうなのね。でもね」
女の子は、小さくそう言うと、さらに続けて言ったのだ。
「わたしのママは、もういないの」
「えっ。どうかしたのかい?」
思わずぼくは訊き返した。ちょっと鋭い調子だったかもしれない。そして、すぐにわかった。自分の愚かしさを反省した。訊くんじゃなかったのだ。でも、いったん口から出た言葉は、もう飲み込むことはできない。取り消して、なかったことにするなんてことはできないのだ。こんなふうに、ぼくはいつも肝心なところで失敗する。幾つになっても同じだ。昔から、ずっと変わることがない。大事なことを理解できないまま、見逃してしまうのだ。
「ママは、もういないの……」
小さな女の子はまた、つぶやくように、繰り返した。
「そうなんだね。ごめんね、辛いことを思い出させてしまって」
ぼくはあやまった。そうするしかなかった。こんなに小さい子が、かなしい思いをするなんて。
「ううん。もういいの」
顔を上げて言った女の子の声が、急に明るくなったようだった。
「えっ?どうして?」
「わたし、わかったの」
小さな女の子が、嬉しそうに言ったのだ。
「なにを?なにをわかったんだい?」
ぼくは勇んで訊いた。
「ママは天国にいて、時々わたしのそばに来てくれる。今までもずっとそうだったの。なんとなくそんな気がしてたの。わたしが遅くに起きた時みたいだったけれど」
女の子は、そう言うのだった。いかにも幼い子どもらしい口調だった。
「そうなんだ?」
「そして、わかったの」
「うん」
ぼくは、少し安心し始めた。
「ほら、天使の階段よ。このあいだ、あなたが教えてくれたでしょう」
ぼくは、あの時のことを思い出した。
「ママはね、あの梯子を使って、会いに来ていてくれていたのね。やっとわかったわ」
「ああ。そうだね」
そう言いながら、この小さな女の子の、なんと大人びていることか。ぼくは驚いていた。それから、彼女の顔をまじまじと見たのだった。
「わたし、あれからずっと考えていたの」
女の子が言った。
「うん、何を?」
ぼくが言うと、小さな女の子がぼくを見て、訊いたのだ。
「わたしも、あの天使の梯子で、ママに会いに行くことができるかしら?」
彼女がそう言った時、ぼくは激しく動揺した。そして、後悔した。これまでで1番の後悔だったかもしれない。天使の梯子、レンブラント光線なんて言うんじゃなかった。こんなに小さな子どもに教える必要はなかったんだ。なんて能天気だったのだろう。
美しいものを見て美しいと思ったら、ただきれいだねと言うだけですむことだった。そして、しばらくの間、いっしょに眺めていればよかったのだ。
結局、自分のことしか考えていなかったのだという気がして、とても恥ずかしくなった。この小さな女の子のことを、ほんとうの意味で思いやることができていなかったのだ。
なぜ、おばあさんのところに一緒にいるのか、ちゃんと考えようとしなかった。そのことに想いを馳せるべきだったのに、そうすることができなかった。ほんとうに彼女のことをまっすぐな心と素敵な目を持った小さな女の子で、大事な友人だと思ったのなら、そうしなければいけなかったのだ。
ぼくはこれまでずっと、自然の中にある草花や木や星の名前を知っていることは素晴らしいことだと思っていた。いや、正確に言うならずっと知らないままでいるのはとても残念なことだと思って、少しずつ覚えようとしてきたのだった(なかなか順調にはいかなかったけれど)。でも、名前なんか覚えないほうがいい時があるのだ、とその時に思った。
「ねえ、あなたはどう思う?」
女の子がふたたび訊いた時、ぼくの口をついて出たのは、自分でも思いもよらなかったことだった。
「ああ、きっと行けるさ」
また、できもしないことを請け負うような返事をしたのだ。
「そう?」
女の子が、ぼくの顔をじっと見た。
「そうに決まっている。きみのママのいるところとおばあさんのところを、きみは自由に行き来できるよ」
それは偽善的に聞こえるかもしれない。小さな女の子のかなしみをただ引き延ばすだけだ、と言う人があるかもしれない。いや、きっといるに違いないだろう。そして、彼女の寂しさをさらに大きくすることになるかもしれないと恐れないわけじゃない。しかし、不思議なことに、自分がそう言ったことに後悔はしなかった。
それは、ただの願いに過ぎないのかもしれなかったが、ぼくは心の底からそう願っていたのだ。ほんとうに願ったことなら、それが叶うこともある。いつもではないにしても。時々かもしれないけれども。何れにしても、ほんとうに叶ってほしいと願ったのだ。
「ほんとうに?あなたは、ほんとうにそう思う?」
小さな女の子が、ふたたびぼくの方をじっと見て、訊いた。とても大事なことを、確かめようとするときの訊き方だ。
「ああ。ほんとうさ。きみは自由だし、きみの心は自由にどこへでも行くことができる。きみが話してくれた、きみのおばあさんが言うとおりさ」
ぼくはためらわずに、正直に言った。すると女の子は、
「ええ。そうね。心の中で、思いさえすればいいのよね。あの時からはずっと、忘れないで覚えているわ」
はっきりと、そう言ったのだった。
「そうだよ」
「ああ、よかったわ」
そう言うと、にっこり笑った。
「ああ」
ぼくも、心の底からそう思ったのだ。
しばらくして、
「ところで、まだ帰らなくて平気なのかい?」
ぼくは、いつかのことを思い出して、遅くならないようにと思って訊いた。
「えっ?ああ、そうだわ。でも、明日は日曜だし。もう少しだけ」
「ならいいけどね」
そうしてぼくたちは、また西の空を眺めた。
「あ、もう行かなくちゃ。きっとおばあさんが、まだかと思いながら、待ってるわ」
女の子が言った。やっぱり唐突に、だ。ぼくのこの小さな友人の気持ちは気まぐれのようだけれど、それはきっと一瞬一瞬の気持ちが大事なせいなのだろう。今は何よりも、おばあさんのことを思い出したのに違いないのだ。
「そうだね。きみのためにとびきりおいしい料理を準備しながらね。じゃあね。どうもありがとう」
ぼくは、お別れの挨拶とお礼を言った。
「はい。さよなら」
女の子は、そう言うと、もう一度にっこりした。素敵な笑顔だった。そして、ベンチの上ではずっと眠っていたようだったひまわりも、ベンチから降りると、片目をつぶったように見えた。
そして、ぼくたちはそれぞれの家へ帰ることになった。西の空はまだあかるさを残していたが、透明さは変わらないままで美しかった。もうしばらくすると、一面の茜色に変わるだろう。
*
後書き
とりあえずはなんとか、第3弾までたどり着けたかも(ま、出来栄えはこの際、気にしないことにします。推敲するたびに、どういう言葉が、使い方が適切なのか、わからなくなってしまいます)。やっぱり途中経過か(うーむ)。
2025.07.19
FANTASY 43 夏休み直前臨時増刊号 ひまわりと女の子(仮題)第2弾
その日の朝は、曇っていた。晴れの予報だったのに、外れたようだった。残念だけれど、こういう日もある。ま、そう悪いことばかりでもないだろう(たぶん)。そう思うことにした。
あの日以来、ぼくはまた朝早くの散歩に出かけるようになったのだった。久しぶりに出かけたときには、思いもしないような出会いがあって楽しかった。でも、一人のときだって気持ちがいいことには変わりがない。それに、何と言っても海を見ることができる。
海は、その時々で表情を変える。輝いて見えるときでも、そうでないときでも。青く見えるときも、灰色のときも。雲の量や太陽の角度、温度や湿度などが関係するのだ。晴れているからといって、必ずしも輝くとは限らない。時間帯によっては、雲がないと光らないときがある。それに輝くものだけが美しいわけでもないし、光るものが全て美しい、ということでもない。光るもの必ずしも金ならず。散歩をして、眺め続けていたら、そうしたことにも気づくようになる。
その朝の海は、辺り一面を雲に覆われていたせいで霞と薄い灰色の雲と溶け合い、空と一体となって、見えなかった。
それでもぼくは、一応は滑り台に上り、写真を撮り終えた。毎日やるべきことをやる。自分を甘やかさないこと、それが大事だと思うことにしているのだ(それはぼくにとって、簡単なことではないけれど)。滑り台から降りるときには、階段ではなく滑って降りてみたいものだ(だって滑り台なのだから)と思うのだけれど、まだ果たすことができないでいる。その日も、階段を注意深く下りた。
それから木製のベンチに腰を下ろして、本を取り出して読みはじめた。外で本を読む、しかも朝早くにというのはずいぶん久しぶりのことだったが、とても気持ちがいいものだった。静かだったし、眩しくもなかった。吹いてくる風が心地よかった。珍しく穏やかなとき間が、いつもよりゆっくりと過ぎていくようだった。
とそのとき、足元になにかがいるような気配がした。
もしかしたら……。そう思って、本を読むのをやめて、下を見た。思ったとおりだ。仔犬のひまわりだった。あのときと同じように、やっぱり鼻先をぼくの靴に近づけ、こすりつけるようにしながらクンクンしていた。
「やあ」
ぼくが声をかけると、ひまわりが顔を上げ、目が合った。すると、すぐにベンチに飛び上がって、ぼくのそばで体を伸ばしたのだった。すっかり安心して、いかにも気持ちよさそうに、だ(ほら、やっぱり……)。ぼくは、ひまわりの頭をそっと撫でてやった。すると、ひまわりは気持ちようさそうに、目を閉じた。撫でるのをやめると、催促するように目をあけてぼくを見上げた。
それからすぐに、
「おはようございます」
という声が聞こえた。もちろん、あのときの女の子の声だっだ。
「やあ。おはよう。また会ったね」
ぼくが言うと、彼女も
「ええ」
と言って、にっこりした。何日かぶりに目にした笑顔だった。とても素敵で、なぜだか懐かしい気がした。
「会えて嬉しいよ」
「私も、おじ(い)さんと会えてよかった」
と言ったのが聞こえたが、耳のせいか、じの次にいの音が含まれていたかどうかは、わからなかった。女の子は続けて、
「今日は、海が見えないのね」
残念そうに言った。
「ああ。雲が多くて、霞んでいる」
「今日こそ、光る海を見ようと思っていたの」
このところは、どういうわけかずっとこういう天気と景色が続いていたのだ。
「うん。実は、ぼくもそうなんだけどね。でもね、この景色もそう悪くはないよ。そうは思わないかい?」
ぼくは、慰め、そして励ますように言った。
「はい」
「霧がかかったようにも見えて、ほら、ちょっと幻想的だしね」
「そうね……」
彼女が同意しながらも、残念な気持ちを隠せずに返事をしたとき、ぼくは頬に温かいものを感じた。空を見上げたら、重なり合った雲の間から太陽の光が漏れだしたのだ。やがて、雲はさらに分かれて、明るく光る芯が見えた。そこからいく筋かの光をはっきり見ることができた。
「あ、ちょっと見てごらん!」
ぼくは、彼女の方を向いてそう言って、光の方を示した。
「えっ、なあに?」
女の子が、訊き返した。
「あの雲だよ」
「はい」
「光の筋が見えるだろう?」
「あ。ああ、きれい。なんてきれいなんでしょう」
よほど感心したようだった。
「あれはね、レンブラント光線と言うんだ」
ぼくが言った。
「レンブ……?」
「レンブラント光線、ちょっとむづかしかったね。レンブラントというのは、今から400年ほども前に活躍したオランダの画家の名前なんだけどね」
「はい」
その小さな女の子はうつむいてしまった。
「それよりね、天使の梯子、そう呼ぶこともあるんだよ」
ぼくがいうと、
「天使の梯子。すてきな名前ね。はじめて見たし、はじめて聞く名前だわ」
彼女はまた顔を上げて、そう言った。すっかり感心したようだった。
「うん。天使たちはね、あの梯子を使って、天国と地上を行ったり来たりするらしいんだよ」
ぼくは気を良くして、さらに説明を続けた。
「へえ、そうなのね。あなたは、いろんなことをよく知っているのね」
「まあ、長く生きているからね、君の何十倍もね」
長く生きていれば、誰でも多少のことは知るようになるのだ。それなりには、だけれど。
「私も、いろいろなことを知ることができるかしら?」
女の子が、そう呟いた。
「もちろんさ。それに、君はもうぼくより大事なことをもう知っているみたいだ」
と、ぼくは答えた。本当にそう思っていたから。
「えっ?あっ、天使の梯子が消えちゃったわ」
女の子が、小さく叫んだ。
「ああ。そうだね、消えちゃったね」
「天使はどこに行っちゃったのかしら?ちゃんとまた、もとのところに帰ることができるかしら?」
女の子は、天使のことを心配し始めた。
ぼくが知っていることといえば、本を読みさえすればわかることばかりだ。皆、本に書いてあるのだ。しかし、この小さな女の子が教えてくれるのは(もちろん、意識してそうしようとしているはずもないけれど)、そういうものじゃない。素直な心とまっすぐな好奇心がないと決してわからないことだ。これは疑いようがない、確実なことなのだ。
「あ、また降りて来たわ、天使の梯子」
女の子が、ふたたび小さく叫んだのだ。もうすっかり夢中になったようだった。
「ああ」
「やっぱり心配していたのね。でも、なんてきれいなんでしょう」
「きれいだよね、天使の梯子」
「あ、見て。あそこの色のついた屋根も光っているみたい」
女の子はそう言って、光る屋根を指差した。
「そうだね」
「きっと、あそこにいたのね。迷子にならなくてよかったわ」
「ああ。よかった。光っている海だけじゃなくて、きれいなもの、美しいものがたくさんあるんだ」
ぼくはつぶやくように言った。
「ええ。たくさん」
女の子は、すぐにそう言った。ぼくの小さな声を聞き逃さなかったのだ。ぼくは、自分自身に言い聞かせるつもりで言ったのだったのに。
「ああ、わたしったら、おばあさんが話してくれたことをすっかり忘れていたわ……」
女の子が、突然言った。
「えっ。どうしたんだい?」
「わたし、夢中になるとすぐに忘れることが多いの」
ちょっと恥ずかしそうにそう言うと、女の子はおばあさんの話をした。こんな話だった。
*
おばあさんは花が大好きで、家のあちこちに花が飾ってあるらしかった。もちろん、テーブルの上にも花が飾ってあるのはいつものことだ。でも、天気が悪いときなどは、花がないことがある。買い物に行けないからだ。
「あら、おばあさん、今日はお花がないのね?」
そのことに気づいた女の子が言うと、おばあさんがこともなげに答えた。
「ああ、このところ買い物に行けなかったからね。雨が続いたからね、だからないんだよ」
「そうだったわ。でも、おばあさんはさびしくならないの?」
女の子がそう言うと、おばさんがすぐに答えて、そして訊いた。
「いいや。そんなことがあるものかね。でも、お前はさびしくなるのかい?」
「もちろん、さびしくなるけど……。おばあさんは大好きなお花がなくても平気なのは、どうして?」
女の子が尋ねるとと、おばあさんが教えてくれた。
「心の中で、花のことを思うのさ」
「ああ、そうなのね」
女の子はうなづいた。
「そうだよ。さびしいときは、我慢なんかしないで、心の中で思い出せばいいんだよ」
おばあさんが、もういちど言った。
「ええ」
「それだけのことだよ」
おばあさんはそう言った、ということだった。
女の子はすっかり感心して、このことはぜひ覚えておこうと思ったのだったが、忘れていたらしいのだった。ま、それもしかたがない。何しろ小さいころというのは、次から次に新しい経験がやってくるのだ。
*
「おっといけない、もうすぐ7時だよ」
ぼくが時計を見ながら言うと、
「えっ、どうかしたの?」
女の子は不思議そうに言うのだった。
「だって、おばあさんが待っているんだろう?」
また、忘れてしまったのかもしれない。ぼくは、思いださせようとして、言ったのだったが、女の子は、
「ああ、今日はいいの」
そっけなく答えるのだった。
「えっ、どうしてさ?」
「だって、今日は日曜日よ。おやすみの日でしょ」
「ああ、そうか」
「学校はおやすみだから、おばあさんもゆっくりしているの」
「ああ、そうだったんだね。それなら、よかった」
「あなたは?あなたはおやすみじゃないの?」
女の子が訊いた。
「もちろん、おやすみだよ」
ぼくは、すぐにそう答えた。実際には毎日が休みなので、もう日曜日が特別の日というわけじゃない。でも、それは、日曜日が特別だと思っている小さな女の子が知る必要のないことだった。
「よかった」
女の子が安心したように、言った。
それから、ぼくたちはもうしばらく話をした。その間中、仔犬のひまわりは静かにベンチに横たわっていた。時々、目を開けたり閉じたりして。彼女は、ぼくたちの話を聞いていたのだろうか。
そんなふうにして、ぼくたち大人と小さな女の子と仔犬のひまわりの2人と1匹は楽しい時間を過ごしたのだったけれど、ぼくはやっぱり名前を聞くことしなかった。だから、相変わらず知っていることと言えば、白と茶の、そして大きな黒い目をした仔犬の名前がひまわりということだけだ。それから、あの小さな女の子がなかなか素敵だということくらい。それで十分だ、という気がしていたのだった。
でも、正直に言うなら、ちょっと後悔したことがあった。言いたいことがあったのだ。どうしてだか、言い忘れてしまった。
「今度は、夕焼け空を見るというのはどうだろう?」
ぼくは、そう言いたかったのだ。
朝早く眺める東の海もいいのだけれど、近くの別のところにある小さな公園から見る夕暮れときの西の方の何層も重なりながら少しずつ調子が異なるような茜色の空も、なかなか素敵なのだ。
*
後書き
ぼくが懲りずにぼくがFANTASYに掲載し続ける理由、そのうちの一つがわかったような気がしました。ぼくには会話体で書くことが必要なようなのです。まあ、一種の自己セラピーのようなものかもしれません。
それに、今回は挿し絵をつけませんでした。何も下手な絵をつける必要もない気がしたのです。だから、今回は、いわば、絵のない絵本のようなものになりました。
2025.07.12
FANTASY 42 夏休み直前臨時増刊号 ひまわりと女の子(仮題)
その日の朝、ぼくはいつもよりも早く散歩に出かけることにした。何しろ、その年は、まだ6月だというのに、すでに真夏のような暑さが続いていたのだから。8時を回る頃には、空気はもうすっかり蒸し上げられて、暑くなっているのだ。
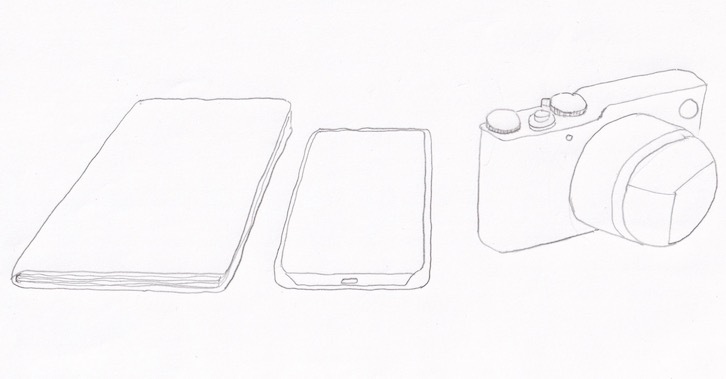
それでぼくは、ノートが入るような大きくて軽いバッグとカメラ、そして歩数計のための携帯電話を持って、帽子も忘れないようにしながら、玄関の扉を開けたのだった。
外はよく晴れていたけれど、空気はまだぬるくも暑くもなっていなかった。それどころか、時折り吹く風はひんやりとするくらいで心地よかった。ああ、やっぱり朝早いうちの散歩は気持ちがいい。ちょっと前まではそうしていたのに、どうしてだかいつの間にかその習慣が消えてしまっていたのだ。
まず目指すのは海の見える小さな公園だ。なんといっても、海を眺めるのは楽しい。見ているだけで嬉しい気持ちになって、嫌なことはすっかり忘れてしまう。いつまででも、見ていることができる。小さいのは、公園だけじゃない。海だって小さい。いや、正確にいうなら、海が小さいわけじゃない。遠くにあるから、小さく見えるというだけのことなのだけれど。それでも、毎日の楽しみであることには変わりがない。
近くまで行くと、建物と建物の間から、遠くで銀色に輝いている海が見えた。朝早い時間、東の方の遠くて小さな海は、光るのだ。
おっと思って、思わず歩を早めた。海が見えると、ついそうなってしまう。
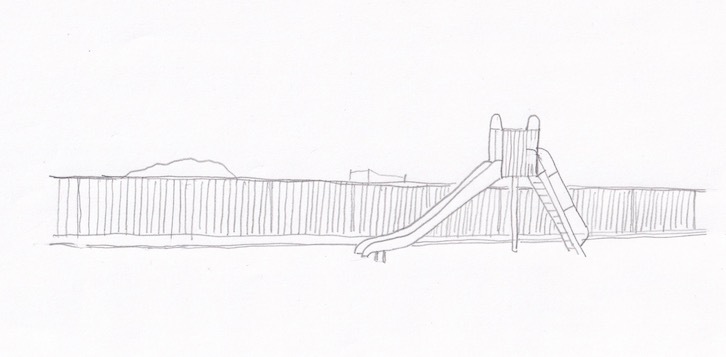
公園に着くと、誰もいなかった。けれど、何かが違って見えた。なんだろう、何が違う、と考えて気がついた。ああ、さっぱりしたのだ。昨日まであった、伸び放題になっていた雑草がきれいに刈り取られていたのだ(昨日は、少しとはいえ雨が降ったのに、刈り取ってくれた人たちがいたのだ)。
ひとしきり眺めると、いつものように子ども用のすべり台へ向かった。

と、先客がいることに気づいた。少し離れたところにある、木製の古びたベンチに座っていた。座っていたのは小さな犬で、そのそばにはやっぱり小さな女の子が立っていて、なにやら一生懸命に言い聞かせているようだった。
ぼくは邪魔をしないように、小さくおはようと声をかけると、輝く海の写真を撮るために子ども用に作られた小さな滑り台の急な階段を上った(どうしてこんなに急勾配なのかは、ぼくには全く見当がつかない)。それから、いつものように、カメラの電源を入れ、精一杯の望遠にして、写真を撮り始めた。とその時、女の子の声が聞こえた。早く帰ろうと促しているのだけれど、仔犬は座り込んだまま全く動こうとしないようなのだった。
「ねえ?」
下から呼びかけるような声がした。女の子の声だった。あの女の子だ。だって、他に誰もいなかったのだから。ということは、話しかけられているのは、ぼくに違いなかった。
「えっ?」
下を向くと、仔犬を連れた女の子がぼくを見上げていた。
「ねえ、何をしているの?」
まるで初めて見た不思議なもののことを尋ねるような口ぶりだった。
「ああ、写真を撮っているんだ」
「写真?」
「うん、写真だよ」
「なんの?」
「海だよ。海を撮っているんだ」
「あなたは、海が好きなの?」
「ああ。きみはどう?」
「好きよ」
「それはよかった」
「でも、子ども用のすべり台で?」
その小さな女の子はなぜだか、すっかり興味を持ったようだった。
「ああ、そうだよ」
「あなたは、大人のように見えるのに?」
「えっ?」
「ほんとうは、大人じゃないのかしら?」
ぼくが大人かどうかは何で判断するかによる。それに、還暦というものを考慮に入れるかどうかもだ。
「うん、ちょっと待ってね、今降りていくからね」
急で狭い階段を降りはじめた(なにしろ子ども用なのだ)。
「はい。あら、すべらないのね。すべり台なのに?」
女の子が聞いた。子どもはなんでも聞きたがるが(けれど、やがて忘れてしまう)、この子は特別だ。
「そうさ」
ぼくが答えたら、女の子は
「どうしてなの?」
と、また聞く。
「ちょっと狭いし、台のことだよ、それにもうきみのように……。あ、そうだ」
ぼくは、彼女を階段の方へ手招きした。
「ちょっと、上ってごらんよ」
「ええ」
「どう?」
「海がよく見えるわ」
「そうだね。じゃあ降りて」
こんどは、フェンスのそばの地面に立ってもらった。
「これはどう?さっきと同じ?」
「うーん、ちょっとちがうような気がする……」
「じゃあ、もう一度試してみよう。今度は、もう一段高く上っててみてごらんよ」
「はい」
「どう?」
「さっきより海が高くなった。屋根も広くなったよう」
「そうだね。よく気がついたね」
「ああ、海も屋根もキラキラしている」
「そうだよね。光っていたきれいだ」
「うん」
「実はね、目の高さによって、見え方が違うんだよ。ぼくの場合はね、地面からでは、電線が邪魔をしてしまうんだよ、海を見るのにね」
「へえ、そうなのね」
女の子の声が響き、表情は光る海のように見えた。
「ああ、そうなんだよ」
そんなふうにして、ぼくと小さな女の子は知り合ったのだった。
ぼくたちが話している間、体全体を覆う白と目元から耳にかけての薄い茶色の長い毛の大きくてまんまるい目をした仔犬は静かにしていた。時々ぼくの足元に手を伸ばしてみたり、鼻を近づけてみたりしていたくらい。それに、時々上を向いて、ぼくを眺めていたこともあった。
「あっ、めずらしいわ。どうしたのかしら?」
女の子が、突然声を上げた。
「えっ、どうかした?」
驚いたぼくが聞く。すると、女の子は不思議そうに言ったのだった。
「ひまわりが、吠えなかったわ」
「ああ、ひまわりというんだね」
「はい。2月生まれなのにひまわり。変でしょう」
「ああ、そうかな」
「でもかわいいわ。この子にぴったりでしょう?おばあさんがつけたの」
「そうだね。そうか、ひまわりは2月生まれなのか。じゃあ、ぼくと同じだ」
「そうなの?」
「そうだよ。ところで、ひまわりはよく吠えるのかい?」
「ええ、時々。知らない人にはね。それに、傘を持った人にも」
「へえ。そうなんだね」
そう言いなが、やっぱりと思った。ぼくは、どういうわけか犬と猫だけには好かれることがあるようなのだ。昔から、そうだった(ぼくの、数少ない美点のひとつだ)。
「ひまわりはここが、大好きみたいなの。だから、ここに座ると、なかなかうごこうとしないの」
と言うのだった。
「へえ。そうなんだ」
「生まれたのは山の方だけれど、生まれてすぐここに来たみたい」
「うん。海が大好きな仔犬は、めずらしいんじゃないかな」
「ええ。でも、めずらしいのかな?」
女の子は、なんでも疑問を持つ質らしいかった。
そんなふうにして話をしながら、ぼくたちはまだ爽やかな朝の時間を楽しんだのだった。
「あの、今何時ですか?」
女の子が、思い出したように聞いた。
「もうすぐ7時になるところだね」
ぼくが時計を見ながら、答えた。すると、
「あら、たいへん。もう帰らなくちゃ」
と、言ったのだった。
「うん」
「おばさんが朝ごはんを作って、待っているの。おばあさんは私が帰るまで食べないの」
「そうなんだ。じゃあ、急いで帰らないとね」
「ええ。じゃあね。さよなら」
そう言うと、女の子とひまわりが後ろを向いた。
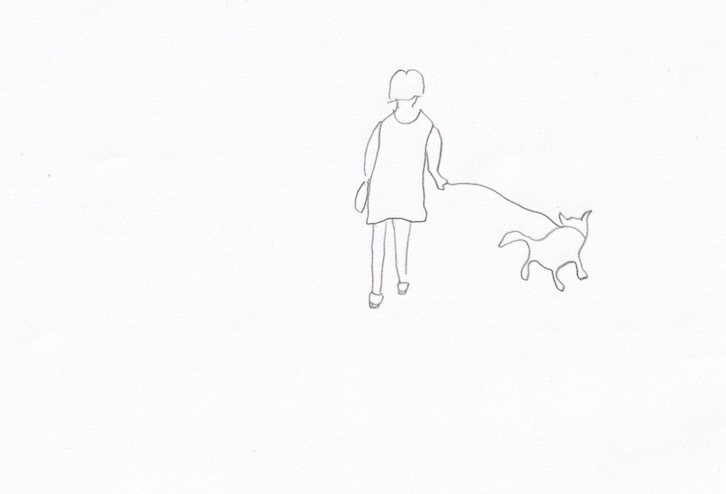
「じゃあね」
ぼくもそう言ったのだけれど、またねとは言わなかったし、名前も聞かなかった。ぼくたちはそうして別れたのだった。だから、ぼくは仔犬の名前は知っているけれど、あの女の子の名前は知らないままだった。
なぜって、また会うことがあるかもしれないなどとは思いもしなかったのだ。
*
ささやかな後書き
そこに魚はいないと分かっていても竿を振り続ける釣り師のように、餌を変え、違うポイントを狙ってみるのですが……。
ともあれ、このページもいよいよ修養の場、一人きりで竹刀を振る道場、一本の棒のようになりつつもなおフライを飛ばし続ける釣り師の立つ川に似てきたようです。
2025.07.06
FANTASY 41 小さな付き添い
先日、私は紹介状を書いてもらうために、病院に出かけることにしたのだった。ともあれ、まずは第一歩を踏み出さなければならない、いつまでも先延ばしにするわけにはいかないと思ったのだ。予約なしだから少し早めに出るつもりだったが、やっぱり8時半頃になってしまった。なかなか思った通りにはいかないけれど、まあ、それが高齢者の生活というものなのかもしれない。
待ち合い室に入ると、すでにもうたくさんの人が座っていた。世の中には、病気を抱える人のなんと多いことか。小児科も併設されているから、中には小さな子供たちもいる。なんとか、受診の順番を知らせるディスプレイの見えるところに座ることができ、一息ついた。初めはまあ、午前中一杯は待つつもりでいようと思い定めて、平穏でいられたのだったが、周りの受診を待つ人々を見ているうちにだんだん緊張が増すようだった。
ベンチに座っている人はもちろん皆が押し黙ったままだし、一方、時折り耳に入ってくる看護師と話をしている人の声ははたいてい、平常よりもちょっと気持ちが高ぶっているようで、不安そうな調子がある。当然のことだ。普通だったら気にしないようなことを、繰り返し何度も尋ねる人もいる。病院のかち合い室のいつもの光景だけれど、なかなか慣れることができない。
そして、前の人が広げた新聞を見て思い出した。前日には、あろうことかアメリカがイランの核施設を空爆したのだ。とても考えられない暴挙。いまだに戦争を武力で終わらせることができると考える人たちがいるのだ。戦争の世紀と呼ばれた20世紀が終わり新しい時代になってすぐまた、こんなことが続けざまに起きるなどとは、誰が想像していただろう。しかも、このことがホワイトハウスでのテレビ会見に先立って、大統領自身のSNSに書かれていたというのだ。
幸い、その後でイスラエルとイランの間で停戦合意がなされたとする当の大統領の投稿があったという。その後の展開も予断を許さないようだけれど、このようなことがまず個人的なSNSを通じて知らされるということにも驚かされるのだ(もしかしたら、これも高齢者ゆえのことなのか)。これから先、いったい世界はどうなっていくのだろう。自分に起こったことがとても小さなことのように思えてきたけれど、それにしても……。
何だかやるせない気持ちで目を横にやると、パナマ帽らしいものを被った男の人の姿が目に入った。目の端でしばらく眺め入った。その出立ちに目を奪われたのだ。太くて青い縦縞のロンドンストライプの長袖のシャツにテーパードの白いズボン、それに白いスニーカー、間からのぞいている靴下は赤だった。
周りの人たちはTシャツと短いパンツという真夏の服装がほとんどだったから、あきらかに周りの人々とは違っていた。これに麻のジャケットかなんかが加わったなら、さらにその印象は強まったのに違いない。なにしろ、まだ6月だというのにもう、真夏並みの暑さがずっと続いていたのだ。それでさしものダンディも、流石に季節外れの暑さには勝てなかったのだろうか。私は、どういう人なのか顔を見てみたいと思ったが、帽子を深く被り、サングラスをかけ、黒いマスクをしているせいで、表情はわからなかった。痩せているのだが、ただお腹だけがまるくぽっこりと出ているようだった。それが病気のせいだということもあるから、不謹慎かもしれなかったが、ちょっと面白かった。
その後も私の番号は、なかなか表示されなかった。数字が変わったことを知らせる音がするたびに、目をあげて確認するのだが、私の番号はなかなか現れなかった。似たような数字で予約なしのものらしい番号が一度だけ表示されたことがあったけれど、最後の二桁が違った。思わずふーっとため息をついた(なにしろ、待ち時間は長い上に、長引くほどに余計なことが思い浮かんで不安が募るような時があるのだ)。その後も、どうしたことか、それから名前を呼ばれるまで、私の番号が表示されることはなかった。
それから結構な時間が経った頃、また音がして、目を上げると、一つ空けたところに座っていたパナマ帽の男の番号になったようだった。男は悠然と立ち上がると、診察室の方へ歩いて行った。特に急ぐふうでもなく、落ち着いて見えた。このことも、他のたいていの人と違っているようで、私の興味を掻き立てた。
するとまもなく、小さな男の子が私のすぐそばに寄ってきた。子どもの年齢のことはよくわからないが、たぶん小学生で、10歳前後といったところだろうか。
「あれ、おじさんは?」
男の子が言った。
「えっ?」
私はなんのことかわからず、思わず訊き返した。
「ここに座っていたおじさんだよ、白っぽい帽子をかぶっていた人はどこ?」
「あ、その人ならさっき呼ばれたみたいで、中に入って行ったよ」
「そうなんだ。ならよかった。ありがとうございます」
少年が、安心したように言った。
「ああ、何でもないことさ」
「あのおじさんのこと、怖くなかった?」
少年が不意に、訊いたのだった。
「えっ、そんなことはなかったけど、どうして?」
私は確かに気にはなったものの、だいたいよく見てはいなかったし、目が合うことももちろんなかったのだ。
「ふーん。ねえ、僕がどうしてここにいるかわかる?」
少年が、今度は意味ありげに訊いた。
「いや、全然」
僕は正直に答えた。
「わからない?」
不思議そうに訊いた。
「ああ。どうして?」
私は退屈しのぎのつもりで訊いてみた。
「もし、若くて怖そうな男の人が付き添っていたら、おじさんも嫌でしょう?」
私も、マスクにメガネ、そして帽子をかぶっていたのだった。
「……?」
私は、何のことかさっぱりわからなかったのだ。
「あの格好だよ。それでわからなかったの?」
「ああ、残念ながら」
「あの人はね、実はね、東南アジアのギャングの偉い人なんだよ」
少年が、秘密を打ち明ける時のように口を手を当てながら、低い声で言ったのだ。
「……?」
驚いた私は、言葉が出なかった。ぽかんとして口を開けていたかもしれない。少年はおもしろそうに、私を見ていた。
やがて、パナマ帽の男が診察室から出てくるのが、少年の肩越しに見えた。改めて遠目に見ると、長身痩躯で、あたりを睥睨するかのような趣があり、周りの人も思わず身を引いたようだった。
「ほら、出てきたようだよ」
私が顎で示しながら、言った。すると、男の子は、
「そう。ぼく、ちょっとおしっこをしたくなっちゃった」
そう言い残すと、行ってしまったのだ。
そういえば、映画の中のギャングたちは、たいていがお洒落だったことを思い出して、なるほどそういうわけだったかと合点がいった気がしたけれど、やがて少し怖くなった。
男は元の席に戻り、腰を下ろすと、小さなバッグから何かを取り出して、口に運ぶとニンマリしたようだった。いったい、あれはなんだったのだろう。気になって、もう一度ちらりと見やると、男はもう笑ってはいなかった。それでも、やや上向きになったお腹がぽっこりと出ているのが、やっぱりおかしかった。
それからまたしばらく時間が経ち、今度は窓口から会計の用意ができたことを知らされたパナマ帽の男が、ゆっくりと立ち上がった。お腹こそ出ているものの、姿勢が良かった。そして、悠然と歩き出した。たいては、診察が終わっても、会計の準備が整って呼ばれるまでは数10分は待たされるから一刻も早く済ませたいと思って急ぐのが常なのだけれど、パナマ帽の男の場合は違っていた。
「あの、すみません」
私は、思い切って声をかけた。
「何か?」
パナマ帽の男は訝しげにこちらを見ると、低い声で言った。
「あのお子さんは?トイレに行くと言って席を離れて行ったんですが?」
「えっ?その子がどうかしたの?」
男が訊き返した。意外に優しい声だった。
「まだ戻りません」
「それが何か?」
「あなたに付き添ってきたんじゃないんですか?」
私が訊くと、
「えっ?そんなことがあるわけはないでしょう?その逆ならまだしも」
呆れたように言うのだった。
「ええ、確かに。でも、あの男の子がそう言っていたんです」
「へえ。他にはどんなことを?」
男は、俄かに興味が沸いたらしかった。私の方へ少し戻ってきた。
「はい。こんなことを言っていいのかどうか……?」
私が続く言葉を飲み込んだままでいると、男は、
「かまわないから言ってみて」
と急かせた。仕方なく、私は正直に言うしかなかった。
「実は、あなたが東南アジアのギャングで、若い男が付き添いだったなら皆を怖がらせるから、自分が一緒についてきたんだって、言ったんです」
「ああ。そうだったのか?」
男は驚いた風でもなく、そう言った。いったいどうなっているのかわからないまま私が黙っていると、
「うん、それもいいかもな」
独り言のようにつぶやくと、ニヤリと笑った。そして、また悠然と歩き始めたのだったが、すぐに振り返ると、
「あ、教えてくれてどうもありがとう」と言ったのだった、その時は、なんだか気圧されるような感じがした。私は、しばらくの間その後ろ姿をぼんやりと眺めていたのだが、部屋の端の方で、パナマ帽の男と小さな少年が交錯したようだった。
それにしても、その日はくたびれ果てた。家に帰り着いたら、恐ろしく疲れた感じがして、血圧も上がって身体中が火照るようで、とても尋常じゃないような気がした。ただ、紹介状を書いてもらうよう頼むだけだったのに。このところはいろいろなことが重なって、知らず知らずのうちに、ストレスになっていたのかも知れない。おまけに、あのパナマ帽を被ったいわくありげなダンディな男のことがあった。思い出すと不気味なようでもあり、不思議な気がしたが、自分のことに関しては、とにもかくにも1歩前に踏み出すことができた。それだけで、良しとすることにしよう、と思うことにした。あとは、ケセラセラだ。なるようになる。いや、なるようにしかならないのだから。
それにしても……。
2025.06.28
FANTASY 40 光る海ふたたび − 一人だけのエクソダス
少し長い前書き
以前に「光3部作」として掲載したものを改稿、改題しました。3部作を1つにまとめて、某出版社の無料講評サービスに応募した時の講評を受けて加筆修正したものです。その時の指摘は、以下のようでした。
・一部の会話や回想が長くてテンポを損なう恐れがある
・Iの背景や感情が断片的に語られているため、彼女の存在がやや淡白に感じられる。彼女の視点や感情をもっと掘り下げると、物語の対比が際立つ
1番目の指摘は、自覚しているのですが1種の癖のようなものですね。貧乏性のゆえ、削り取って無くしてしまうのがなかなかできないのです。切れのいい文体に対する憧れはあるのですが、つい長くなりがちでなかなか簡単にはいきません。そこで、今回は2番目のことを意識して加筆・修正しました。
先日の散歩の時にも原稿を持ち歩いて、公園でベンチで推敲してみたりしたのですが、(1)はずいぶん暗いし、冗長。すでに暑くなった日差しの中で読むと、なおさらです。もう少し、考え直すべきかも(バッサリ削るべきか)。おまけに、変わり映えがしないような……。なんだか、大幅な見直しをしないとだめなままという気がしてきましたが、まずは一区切りつけるために。
*
「暮しが仕事 仕事が暮し」
「確かなものを作りたかったら、確かな暮らしをせよ」(河井寛次郎)
きみたちも また
寂しい夜を耐えただろうか
今宵借りもののラジオから流れてくる
東京放送もうねっている
----『新鮮な日々』の一節
(1)影と光の日
その年の桜は遅かったけれど、辺りはすっかり春めいてきて、もはや夏日を通り越して真夏日というところがあるらしい。桜が咲くのもすっかり年毎に違うようになった。常識も通用しなくなったようだ。変なことは、気象だけにとどまらない。世界のリーダーたちが悪びれることもなく、堂々と自国第一主義や、領土拡大のための他国への侵攻等々を生み出している。地球上の異常は、いったい、いつまで続くのか。指導者たちが受けたはずの高等教育はなんのためだったのだろう。
最近は、人と会うことがほとんど無くなった。コロナ禍を経験して以来、外出することがすっかり減ってしまって、それが今でもずっと続いているのだ。特に若い人と会うことがなくなった。何より、働く環境を始め、生活を取り巻く環境が大きく変ったことがあるに違いない。そして、お互いに、と言うよりはこちらが一方的に歳を取り過ぎたことのせいが、大きいのかもしれない。まあ、老兵は死なないまでも、忘れ去られる運命なのだ。それも仕方がないことだ。
もとより、若さに対する信仰があったわけではない。それどころか、早く老成することに憧れていた(いまから思えば、たぶん、若者としての自分が他者に受け入れてもらえそうにないことを感じ取っていたためなのだろう)。
だから、ハタチを超えたばかりかというくらいの若者が「もうおばさんなので」とか「もう若くないから」とか言うのを聞くと腹立たしいようで、「馬鹿言うんじゃない」と叱りつけたいような気分になったくらいだった。それでも、年を取っていざ老年期に入ると、やっぱり若さがまぶしく思えてくることがあるし、羨ましくなることもある。若い人たちが自分たちの世界のことで忙しくて、年寄りとつき合う時間が無くなるというのは、さもありなんという気にもなるのだ。
そのとき、僕たちは海辺の小さな町の古いバーのカウンターの隅に座って、随分と久しぶりに飲んでいた。
僕はハイボール、Kはシングルモルトに水を少しだけ入れたものを。Kは最初の職場を定年退職した後の第2の職場で働き始めたばかりだったし、僕はといえばずっと自由業のようなものだったけれど、周りの環境が変わって働き方について考え直さなければいけない時期だったのだ。二人ともが、そろそろ来し方行く末を考えてもいい時期でもあった(もしかしたら、少しばかり遅いのかもしれなかった)。
その日は、金曜だったせいなのか、お店にはいつになくお客がたくさんいて、にぎわっていた。ただ、ふだんとは違って若者のグループが多かった。たぶん近所の大学の学生に違いない。彼らはそれぞれテーブル席のソファに陣取って大声をあげながら話しており、カウンターに座っているのは僕たちと同じかそれ以上の年恰好の数人だけで、隣を含めていくつか空席があった。
その時に何を話していたのかは、もう細かいことは忘れてしまった。ほんとうに久しぶりだったから、たぶん近況報告のようなものだったのだろう。そのせいもあってか、けっこう早いペースで飲んでいたような気がする。Kは昔からそうだったし、僕は逆にゆっくりと飲むのが常だった。
音楽の話もした。最近は、ラジオで聴くことが増えた。それは、いったいどうしたことだろう。新しい音楽に触れるためなのか、それとも面倒を避けるためなのだろうか。
ラジオでは、古い曲が新しくアレンジされて演奏されるものもよくかかる。
だから、もしかしたら、こんな話だったかもしれない。
「新しいかどうかというより、なつかしさの方が先に立つんだよね」
「ああ。どうしたことだろうね」
「一挙に、当時の時代に舞い戻るような気がする……」
「そうなんだ」
「といって、当時のことを具体的に思い出すことはないのにね」
「へえ。昔のことはほとんど覚えていない、と言っていたものね」
「若い人は、新しい曲として聴くのかね」
「うーむ。どうだろうね」
「ごくたまに、なんだこれは、と思うこともないわけじゃないけれど」
「うん」
「ただなつかしい、という気分だけなんだよ」
「へえ。そうなんだ」
「新しくCDなんか買ったことはある?」
「そういえば、ないなあ」
「僕もそうだけれど、たまに買うのは中古の古いアルバムなんだよ」
「どうしたことだろうね」
「まずいよね」
「ああ、ちょっとね」
「生きる力が欠如し始めている、ということなのか?」
「なんだか、とってもまずい気がしてきたよ」
「うん。……」
「……」
とまあ、こんな具合だ。
そして、忘れられないことがあった。
「ここ、空いているかしら?」
と訊く声が聞こえたような気がした。声の方向を見ると、いつの間にか人が立っていた。かすかに革の匂いがした。暗かったし、おまけに陰になっていたが、若い女性のようだった。
「どうぞ」
Kが、素っ気なく応じた。
「ありがとう」
と言うと、その女性は、Kと壁の間の一つ空いていた席に座った。バーテンダーが、やあいらっしゃいと声をかけながらやってくると、彼女が
「何か、さっぱりとしていて軽いカクテルをお願いします」
と言った。それから、ホッとしたように、軽くふーっとひと息吐くと、
「ここは、いつでもこんな風なのかしら?」
と、独り言とも尋ねるともつかない口調で呟いたのだった。
「ああ、今日はなかなか賑やかのようですね」
と、一瞬間をおいて、またKが言った。彼が見知らぬ人に応じるのは珍しいことだった。
「というと?」
若い女性は、こちらを向いて、確かめるように訊いたのだ。今度は、その姿がはっきり見えた。周りの大学生よりは、ほんの少し年上のようだった。大きな目をしていて、髪をポニーテールに結んでいた。体をピッタリ包む黒の革ジャンとジーンズ、そして同じく黒のロングブーツというかなり目立つ出で立ちだ。おまけに、姿勢がいい(残念ながら、姿勢が良ければすべて良し、というわけではないことはもう知っていたけれど)。膝の上には、金色に光る2つのCが重なる小ぶりのバッグを載せていた。
若いのに、カウンターにバッグを載せないのは好ましい、と僕は思った。うんと昔、まだ若かった頃に恩師に連れて行ってもらった老舗のバーで、カウンターに荷物を置いたお客がたしなめられたのを覚えていたのだ。荷物は床に置かれたりして汚れていることがある。これをカウンターに載せたら、他のお客が不快に思うことがあるかもしれない。だから、荷物をおいてはいけない。当たり前のことだけれど、肘をつくのもだめだ、と教えられた。バーは、凛とした空間の中で飲む場所なのだ。とすれば、愚痴じみた話や湿っぽい話題は似合わない。
「ふだんは、いたって静かなものだよ」
今度は、僕が答えた。
「へえ、そうなんだ」
彼女がうなづいた。訝る様子はなかったし、ごく自然な受け答えだ。しかし、なんだか独特のイントネーションのようだった。
「上品な年寄りばかりだ」
さらに、Kが付け加えた。
「それで、彼らは?」
彼女が、問いただすように訊いた。
「めったに見ないね。他が空いていない限り、来ないようだけどね」
「ああ、それはよかったわ。どうもありがとう。お話を邪魔してしまいました。ごめんなさい」
そう言うと、背筋をピンと伸ばしたまま向きを変えると、携帯を眺め始めた(やっぱり、今時の若者なのだ)。
「なんでもないさ」
そう言って、僕たちはまた二人の会話に戻った。
「あんまり旅行することもなくなったね」
Kが、ポツリと言った。
「ああ。コロナがあったしね。年を取ると、いろいろむづかしいことばかりが増える」
僕が応じた。
「そうだね」
「たまには、うまいものを食べに出かけたいもんだね」
今度は、僕が言った。せめて日常のダラダラと続く閉塞感を打ち破りたい、と思いながら言ったのだ。情けないけれど、そのくらいしか思いつかなかった。
「ああ。たしかにね」
「だけど、なかなかね」
「うん。いろいろあったしね」
「ところで、地産地消って言うだろう?」
僕は、思い出すことがあって、訊いた。
「ああ、言葉ばかりで、あんまり経験することはなくなったようだけどね」
「まあ、経済や効率重視の社会だからね」
「ああ。しかたがないのかね」
「ああ。でも、羨ましいね?」
「やっぱり、獲れたての新鮮なものはうまいよね」
「ああ、魚や野菜だね」
「生産者たちが持ち寄るマーケットなら、言うことはない」
「ああ。それに、近隣の住民同士の関係が生まれるしね」
「いいよね」
しばらくそんな話が続いた。どうってことのない、たわいのない話だ。
「昔、初めてカナダに行った時にね、バンクーバーだったけれど、同行した先輩が言ったんだよ」
僕はうんと若い時のことを思い出して、なつかしい気分で、言った。初めて外国旅行をした時のことだった(ずいぶん遅かった。それまで機会がなかったわけじゃなかったが、いろいろな事情が重なってそうなったのだった。ま、しかたがないことだ)。
「ああ」
「カナダのビールはこれが一番うまい、って言われたんだ。何回も来ていた先輩にね」
「うん」
「でもね、それが。これを日本へ持って帰って飲んだら、全然うまくないんだ、って言うんだ。なんという名前だったか。もう名前は忘れてしまって、思い出せないけどね」
「なるほどね。ほら、ビールは新鮮さが大事だし、飲むときの温度もある。これは気候と大きく関わるんじゃないのかね」
「うん。初めは、全然信じられなかったけどね」
「おまけに、食べ物と飲み物はその土地のもの同士を合わせるのがいいんだね。なんて言ったって、同じ水と空気の中で育ったものだからね」
「ああ」
今は運送手段が発達して、世界中のなんでもすぐに手に入る。そうした時代に慣れすぎてしまった。その代わりに失ったもののことは、すっかり忘れている。
「グランヴィル・アイランドのマーケットには驚いたな。それまで見たものとは全く違っていた。……」
Kが、懐かしそうに言った。
と、その時、
「Oh、It’ nostalgic! なつかしいわ」
と言う声が聞こえた気がした。隣の女性のようだった。
「えっ?」
また、反応した。
「オゥ、ごめんなさい」
「いえいえ。どうかしましたか?
「私、ずっとバンクーバーに住んでいたんです」
と言うのだった。改めて見ると、異邦人の趣があるようだった。
「あらま。それはそれは」
今度は、Kが言った。
「グランヴィル・アイランドのマーケットとか、小さい頃から祖母に連れられてよく行ったから」
話をしているうちにわかったのは、どうやら、会社の研修で1年ほど滞在する予定ということだった。両親ともに日本人ということだったが、父方の祖母はカナダ人で少し離れているが、母方の祖母は日本人で何年か前にカナダにやって来て一緒に暮らしているということだった。彼女自身は、バンクーバーで生まれて、ずっとそこで育ったらしい。父親の転勤でカナダの内外のいろいろな場所で暮らしたこともあったようだけれど、本人が働きはじめてからは、一時やっぱり短期の研修か何かロンドンにもいたことがあるらしかった。だから、もしかしたら、ここにもパブのつもりで入ったのかもしれなかった。
今や世界の住みたい都市の最上位の常連となったバンクーバーは、ある時から地産地消にこだわった街づくりをするようになったということらしかった。アリッサ・スミスとジェームズ・マッキノンの二人が著した「THE 100-MILE DIET~A YEAR OF LOCAL EATING~」という本がきっかけで、2010年前後に始まったようだ。ダイエット等のはもともと日常の飲食物という意味があるから、「100マイルダイエット」というのは、住んでいるところから100マイル(約160キロ)の範囲で獲れるものを食べようという地産地消の運動らしい。
僕が訪れたのはそれよりずいぶん前のことだったけれども、それでももう獲れたてだという魚介類を売るマーケットやこれを食べさせる店もすでにあったようだった。当たり前と言うか、それが基本という気がするけれど、それが当たり前でなくなってからもうずいぶん長い時間が経った。そして、多くの食べ物が誰の手になるものかわからず、長持ちさせるための添加物まみれになってしまった。
そんなことで、しばらくの間、どおってことのない話しをしただけだったが、思いもかけない時間を過ごすことになった。そして、
「じゃあ、私はこれで失礼します」
不意に、彼女が切り出した。
「ああ。なんだか質問ぜめにしたようで、悪かったね」
「いえ。こちらこそ、すっかりお邪魔してしまいました」
「おかげで、楽しかった」
「私も」
「楽しい日本での暮らしを。お元気で」
「ありがとう。また、お会いしましょう」
「ああ。ここにいるよ」
「ええ。それでは、さよなら」
彼女は、帰っていった。
*
I が自宅に帰ってきたとき、にっこりした思わず笑みがこぼれたのだった。少し嬉しい気持ちだったのだ。こんな気持ちになったのは、久しぶりのことだった。日本にやってきて以来、何かと気ぜわしく、落ち着くことがなかった。せっかく、日本にやって来た、というのにだ。
自宅はリビングダイニングと台所、そして寝室が一つのいわゆる1LDKタイプの小さなアパートメントだった。部屋には、彼女らしく設えられた家具はほとんどなかった。越してきたばかりだったから、それも仕方がないことだった。おいおい揃えていけばいいと思っていたのだが、一方でうまく馴染むことができるか不安でもあった。それに、滞在期間は1年間の予定と短かかった。
それが今日たまたま入ったバーで、思いもかけない経験をすることができた。懐かしい故郷バンクーバーの話をすることができた。この見知らぬ街に、故郷バンクーバーの話をする人がいることがわかったのだ。案外楽しく過ごすことができるかもしれない。そう思うと、我知らず笑顔になるようだった。
それから、祖母のことを思い出したのだった。母方の祖母とは物心ついてからずっと一緒に暮らしてきたのだった。だから、いろいろなことを共有してきた。両親は二人とも働いていたから、祖母と過ごす時間は長くなった。祖母は英語は決して堪能というわけではなかったが、たくさんのことを話してくれた。日本語も教えてくれた。
I がとりわけ興味を持ったのは、祖母の故郷日本のことだった。
でも、その祖母ももう会うことはできない。3年ほど前、正確には3年と1ヶ月と2日目に亡くなってしまった。忘れることは到底できない。このところは、むしろ後悔が募るばかりだった。もっとよく祖母が育った日本のことを聞いておけばよかった。いや自分でも日本のことを体験して、それを共有することがでいたらどんなによかったか。でももはや、それは叶わない。取り返しのつかないことがあるのだということを、改めて思い知らされたような気がした。
となれば、せめて実際に日本のことを知るしかない、祖母が育った街に暮らしてみることこそが最上の方法だという気がした。自分のアイデンテティについても考えたかった。それで、志願して日本支社に転勤することになったのだ。
*
彼女が去って、また二人だけになった。なんだか急に寂しくなって、明かりがひとつ消えたような気がした。やっぱり、ふだんは若い人、特に女性と話す機会がないせいなのだろうか。こうした彩りに欠けること、おびただしいのだ。だから、彼女が会話に加わって入る時は、つかの間、華やいだ気がしたようだった。それで、二人して、顔を見合わせると、ふっとため息をつき、黙り込んだまましばらくグラスを弄んだ。それから、
「この頃は、なんだか、自分は罰せられているんじゃないかというような気がする時があるんだよ」
Kが唐突に、ポツリと呟いたのだった。
「えっ?」
僕は思わず訊き返した。
「自分は罰を受けているのではないか、と思うんだ」
Kがもういちど言った。今度は、少し大きな声で、はっきりと。
「いったいどうしたっていうんだい。何があった?」
僕は驚いて、訊いた。すると、Kはすぐに、
「いや、何でもないさ」
と言ったので、ああまたからかっているのかと思って安心した。彼は、ふだんからよくそうすることがあった。しかも、自虐的と言うのか、自嘲的な言い方で。だから、そのときもそうだと思ったのだ。
「でも?」
なんとなく訊いた。
「何も起きないんだよ。何をやってもうまくいかない」
と、Kが言う。
「たとえば?」
「たとえば……」
「たとえば?」
「新しい仕事も楽しめないし、環境にも馴染めない、とか」
「それだけ?」
「自分が作った書類には、ミスプリントが目立つ、とか」
「ふーむ。他には?」
「何を書いても、反応がない」
「ああ」
「誰も読まない……」
「そうなのか?うーん」
Kは、ブログやら短い物語風のものを書いて、自身のホームページに掲載しているのだった。
「いろいろ考えて、手を変え品を変え、工夫をしてはいるんだけどね」
「うん」
「でも、なにも変わらない。誰も読まない。楽しんでいる人はいないようだし、喜ばないんだね」
「そう?それはわからないんじゃないか?」
「何の反応もないんだよ」
「そうなのか?」
それから、Kはテレビで見たという人たちのことを語り始めた。曰く、
無名の人の働きの偉大さ、すごさ、素晴らしさ、志の高さには驚かされることが多い。声高に主張することなく、地域の住民の思いを汲み取り、人々にとっての望ましい姿やあるべき姿を思い描き、実現すべく地道に作業を続け、取り組む。
例えば、震災後の鉄道の再開のために尽力した会社の人々。「日常を取り戻す光」のための一助にしようと労を惜しまずに取り組んで、地震からおよそ3ヶ月後に実現にこぎつけた。また、地元の高校生たちは、駅の清掃を行った。
また、日本初という難工事に取り組んだと鳶職をはじめとする職人や現場で働いた人々の奮闘ぶり。ちょうど東日本大地震と重なり、倒壊の危険を減らすために自身の命を顧みず、鉄塔に登った人たちがいたこと。
あるいは、Jリーグに参加することでコンビナート砂漠と言われた町で町おこしを図ろうと立ち上がった人々についても。当時のチームは、とても参加できる状況にはなかったし、しかも要件を満たすスタジアムもなかった。しかし、彼らの尽力で、チームの親会社はチーム名から会社名を外し、賛同者は増えて参加が認められたという。しかも、初年度には優勝した。
まあ、そんな話だった。
演出された部分もあるだろうけど、それにしてもたいしたものだし、本当にえらいものだとも思うけれど、Kは自分はこうした志を持って努力した人々と全く違うのだ、と言うのだった。憧れてそれに向かおうとするのではなく、そうなることのできない自分を蔑み、自嘲するような調子だった。
「何かを成し遂げられなかった、ってことか?」
僕が訊いた。
「いや。それもないとは言わないが、いちばんは、やるべき努力をして来なかったということだね」
Kが言った。
「そうなのか?」
「ああ、うまくいくかいかないかが問題じゃないんだ」
「うん」
「真剣に取り組むことができなかった。それは、ちゃんと生きて来なかったということだ」
「じゃあ、今からやればいいじゃないか」
「ああ」
「そうすればいい」
「うん。でもね、価値のない、とても卑小な人間のような気がするんだよ」
「過ぎたことを言っても、仕方がないよ。これからどうするかが大事さ」
僕がいうと、Kはすかさず、
「こないだは、早く目覚めてラジオをつけた時に、「愚か者」という声が聞こえたんだよ。まいったね」
と言うのだった。なんでも、若くして亡くなってしまった歌手の特集の中で出て来た曲名らしかった。さらに、
「たまに出したメールには、返事さえ来ない。来るのは通販の会社だけだ」
と続けた。
「ああ、僕だって似たようなもんだ」
僕は、なんとかこの話を終わりにしようとして、言った。彼の様子はいつになく変な気がしたのだ。しかし、
「誰からも相手にされず、なんだか社会から切り離されたというか、放り出されたような気がする」
Kは、なおも続けたのだ。
「そう?マッカーサーのように?でも、悪いことばかりじゃないだろう?」
「ああ。そうかも」
「そうだろう?」
「まあ、昔からそんな気もするけどね。でも、考えもしなかったような相手に、手ひどい仕打ちを受けたことも何度かある」
「えっ?」
「信じられないような裏切りも。一度ならずね……」
「ああ、それなら僕にだってある。嬉しいというわけじゃないけどね」
「うん。不当だと思うけれど、でも、彼らなりに理由があるのだろうね。盗人にも三分の理。想いは、人それぞれだから。それに、僕だって聖人君子というわけじゃない」
「……」
「やっぱり、持って生まれたものなのかね……」
と、独り言のように呟いたので、
「何?」
と訊き返した。
「やっぱり神様の罰かも、一時の間恵まれた幸運に甘えすぎたのかも」
Kはそれに応える風もなく、ひとりごちるのだった。
「(うーむ……)」
しばらく間があいて、Kはこう言ったのだ。
「おまけに、宝くじには当たらない」
「買ったのかい?」
僕は拍子抜けして、半ば呆れながら訊いた。
「いや」
「それじゃ当たるわけがない」
「前に買ったときも当たらなかった」
「……」
僕は、ようやくほっとして、笑い出しそうになった。やっぱり、今度こそ、からかっていたんだな。しかし、Kはさらに
「年賀状にも、当選番号はなかった」
と言ったけれど、いつまでも言い続けて、何か変な感じだった。
「ああ」
僕がうなづいてから、またしばらく間が空いた。
その時、テーブル席でまた、ひときわ大きな笑い声が起こった。なんと場をわきまえない若者たちであることか。まあ、ちょっとムッとしたけれど、それでもすぐに気を取り直した。なんと言っても、若者たちなのだ。希望と自信に溢れていて、自分に悪いことなんかは起こりはしない、ありえない。自分に非があるなんてことは、毛頭思いもしないだろう。少なくとも僕は、私は、と思える時なのだ。確かに、若者は少々ハメを外すこともあるし、それがどうしたっていうんだ。それで、誰かに大きな迷惑をかけるというわけじゃない。仮に少しばかり不快な思いをした人があったとしても、目くじらを立てるほどのことじゃない。少なくとも、目くじらを立てるほどのことじゃない。
「彼らを見習うといいよ」
と、大きな声の方を顎で示しながら、僕は冗談のつもりで言った。
「ああ。羨ましいな。でもね、この歳になっても、自分の気持ちに正直になれない。素直に伝えることができない。ますますむづかしくなったようなんだな」
Kが小さな声で続けた。
「……」
「受け止められてもらえないかもしれないし、誤解されるかもしれない。変な圧力をかけることになることだってあるかもしれない。別に力があるわけじゃないから、別に実害はない。でも、気分はね。なんと言っても、たいていの場合、だいぶ年上だからね。そんな気がしてしまうんだよ」
「そう?でも、きっと思い過ごしだよ」
「ああ、確かに。そうかもしれない。ただね、それがまた、悪い方に働く」
「そうだよ。気にしすぎるからうまくいかない」
僕は言った。
「負の連鎖ってやつかもしれない」
彼は、自分に言い聞かせるようにつぶやく。
「そうさ。だって、たいていのことが、そんなにうまくいかないのがふつうだろう?」
僕だって、いい時ばっかりじゃない。むしろ悪い時が多いくらいだ。
「ああ」
「ねえ、そうだろ?僕は君と知り合ってから、もう長いよ。これまで、ずいぶん話もしたし、一緒に出かけたりもした。それに、よく飲みもした。僕が知っている限り、君はそんなに悪いやつじゃない」
僕は言った。まあ、確かに、そう思っていたのだ。
「ありがとう」
「だから大丈夫だよ」
「ああ。こんなことを言ったからと言って、別に大きな罪を犯したわけではないよ。もとより、気が小さいし、自分では人との争うことを好まないたちだと思っている。少なくともこの頃は、嫌な人間になりたくないと思っているし、気をつけているつもりだよ。ただ、そうとは気づかずに傷つけた、または傷つけているということは大いにありそうだと思うんだよ。もとより、僕は聖人君子なんかではないのだから」
Kが、自分の心の中にずっとくすぶっているものを吐き出そうとしているかのようだった。
「もちろん。誰だってそうだよ」
僕は、他に言いようがなくて付け加える。
「小さな嘘や裏切り、精神的な圧力だってあっただろうと思うよ。まあ、お互い様ということもあるかもしれないけれど。それから、こちらは大きな罪だな。幸運にかまけて、やっぱり父親譲りと言う以上の筋金入りの怠け者ということだね。等々、挙げればきりがないよ。でも彼はは、仕事はちゃんとできたらしい。彼が作った指針がずっと使われ続けていた。そして、そのことに苛立ったらしい」
「だから、それもこれも誰にもあることだよ。聖人君子じゃない限りね。そうそう、僕なんか柿ピーを一度に2袋食べてしまうことだってある」
僕は、そろそろ終わりにしたいと思って、言った。
Kがようやく笑った。それで僕はほっと一安心したけれど、
「自己憐憫が過ぎているんじゃないか、という気がすることもある」
と、Kはそれでもやめることなく、さらに続けたのだった。もはや止まらなくなったようだった。
「うん」
「もう一方で、そう言う声が聞こえる気がする……」
「なら、やめればいい」
僕は、慰める代わりに思い切って、突き放すように言った。
「何を?」
「その自己憐憫ってやつを」
「うん」
「自分を哀れむことを、やめるのさ」
「やめてどうする?」
「ありのままを受け入れるんだよ」
「ああ。それで、受け入れてどうなる?」
「楽になる」
「それだけ?」
「ああ。簡単なことだろ?他に何を?」
「そう?」
「そうだよ。でも、それだけで十分じゃないか?」
「そうか?」
「そうさ。他に何を望む?」
「ああ」
「じゃあ、すぐにやめればいいんだよ」
「うん」
「そして、新しく始めればいい」
「ありがとう」
そう言うと、彼はしばらく黙ったままだった。それは心から発せられたというようなものではなかった。いや、そうだったのかもしれないが、もはやすっかり諦めたような響きを含んでいるように聞こえたのだった。
たぶん、Kもそのくらいのことは、自分でもわかっているのだ。ただ、それでも、これまでの何か澱のようなものが、残っているのに違いない。長く生きれば、当然、誰にだってあることだ。人は、そうしたものを抱えながら生きるしかないのだろう。それがなんなのか、それは人によって違うだろうだろうから、言っても仕方がない気がしたのだ。だけど、つい言った。
「それが、人生というものだろう?」
「ああ」
Kは、もはや心ここに在らずというようなふうだった。
なんだか、もうここにいても仕方がない気がした。何を言っても、言葉はもはや届かず堂々巡りするばかりのようだった。言葉は若者たちの声とぶつかり、闇の中に吸い込まれて、ついに届くことなく、居場所を失って、宙を彷徨うだけだ。
それで、僕たちは帰ることにした。バーでは、相変わらず若者たちのうるさくて明るい笑い声が響いていた。
駅まで一緒に歩いた。途中で、彼はふいに、
「自分の好きにしつらえた家に住みたかったな。結局、何にも手にすることができなかったな。誰のせいでもなく、自分のせいだけどね」
と呟いた。そして、
「世の中には、偉い人たちがたくさんいるものだねえ。それにこのところは頌栄451番ばかりが口をつくんだ。以前は、ほとんど声に出して歌ったことはなかったないし、それにクリスチャンでもないのに」
とも(この時は、不思議な軽さが感じられたような気がした)。
駅に着くと、彼は改札口に向かい、僕はバスの乗り場まで歩いた。今日のKは明らかに変だった。もともと明るいと言う性格ではなかったが、お酒が入ると饒舌になることがあっても、自分のことを延々と話し続けるということはなかった。しかも、その話はほとんどが自嘲、あるいは自己憐憫から離れられないいようだったし、そのことを自覚していたのだ。
そして、それ以来、Kとの連絡がふっつりと途絶えてしまったのだった。メールを出しても、電話をしても、手紙を書いても返事はなかった。他の何人かに聞いても同様で、やっぱりわからなかった。彼は、突然、僕たちの前から姿を消してしまったのだ。いまでも、その行方はようとして知れない。生きているのか、どうかさえもだ。
(2)緑の葉を抜ける光
*
Kがいなくなってしまってからは、ずっと心にぽっかりと穴が空いたようだった。最後に会った時は、重苦しい気分になったのに、いざ会えなくなったら妙に寂しい気持ちが募った。人の気持ちというのは、不可解だ。そして厄介だ。なんだか自分一人だけで、砂漠かジャングルのようなところに取り残されたような気分だったのだ。
別に、それほど頻繁に会っていたわけじゃなかったし、最近は年に数回くらいしか会うことがなくなっていた。だから、物理的にはそんなに変わったというわけじゃない。しかも、最後にあった頃のKの様子は明らかに変だった。自己否定や自己憐憫が端々に現れるようで、聞いていて辛い時もあったのだ。
それなのに、二度と手に入れることができないものを失ったような気がしていたのだった。たぶん、僕自身の中にあるそうした部分を代替してくれていたのかもしれない。だから、自分はそうしたことからしばらく遠ざかることができていたのでは、と思ったりすることもある……。
でも、もしかしたら、いくらかでもその穴を埋めることができるかもしれない。今は、そんな気がしている。そろそろ何かを始める頃だ、そう考えると、少なくとも、しばらくの間はあかるい気分になる。まあ、もしかしたらまた……、という不安がないわけじゃないけれど。でも、先のことを案じてばかりいるのはつまらない。志村喬が歌う「ゴンドラの唄」を思い出した。作詞は吉井勇。いかにもかららしい気がうる。そして、ブランコに揺られながらしみじみと歌った志村の年齢をはるかに超えてしまった我が身のことを思った(彼は、今から思うと、ずいぶん老成して見えた)。
*
ある晴れた日曜日、気分天下のためにいつもとは少し違う道を試してみようとした散歩の途中で、思いのほか歩く距離が長くなり、道沿いにあった小さな公園のベンチで、ぼんやりと空を眺めていた。いかにも春らしい柔らかな青空に一つだけぽっかりと浮かんだ雲が、ゆっくりと形を変えながら流れていくのだ。その時、僕の足元につまづきかけた人がいたのだった。
「Oh, very sorry !」
外国人の女性のようだった。
「OK. That’s my fault. 大丈夫?僕が足を伸ばしていたのが悪かった。I’m so sorry.ごめんなさい」
咄嗟に言って、顔を上げた。と、
「Oh. こんにちは! 覚えていますか?」
その人は、そう言ったのだ。
驚いて、もう一度よく見てみると、ひと月ほど前に、海辺の鄙びたバーで偶然隣り合わせた日系カナダ人女性のIだった。その彼女と、ばったり出くわしたのだった。
「もちろん ! いったい、どうしたんだい?」
「道に迷ったようなんです。それで、ちょっとぼんやりしてしまって……」
視線をそらして、ちょっと恥ずかしそうに言った。
「ふーん。でも、また会えてよかった」
ぼくは、驚いたけれど、なんだかとても幸運なような気がした。率直にいえば、再会したことが嬉しかったのだ。
「私も!あなたは、今日は何を?」
彼女が訊いた。
「散歩の途中だよ。ただの退屈しのぎさ。で、君は?」
僕はそう言って、訊き返した。
「町の探検、かな。ふだんは自転車なんですが、今日は、ゆっくり歩いてみようと思って。でも、道に迷いました」
「そうなんだね。あれから、どうしてた?日本での生活にはもう、慣れたのかな?」
「まあ、少しずつ……。なかなか、簡単じゃありませんね」
「ああ、確かにね」
言葉は通じるものの、何といっても、文化も習慣も何もかも異なる国で暮らす、というのは簡単ではない。
「実は、あの後で、あのバーにも何回か行ったんです」
と、Iが言った。予想もしなかったことだった。
「へえ」
「でも、会えませんでした」
「ああ。それは、悪いことをしたね。実は、僕もしばらく行っていないんだよ……」
「そうなんですね」
「ああ、いろいろあってね。ところで、君はすごく急いでいるの?」
「いいえ」
「じゃあ、よかったら桜を見に行ってみないかい?」
僕はあんまり期待しないで、訊いてみた。期待しすぎるのは、問題だ。そうした時の答えは、だいたい想像がつくのだから。
すると、Iの顔がパッと輝いた、ような気がした。 そして。
「ええ、ぜひ。私も、とても見たかったんです。私のおばあさんがよく話してくれたんです」
と言ったのだった。
ぼくは、思いもしなかった答えに少なからず驚いたけれど、それで、近くでまだ満開の桜が見ることができて、しかもあんまり人の多くなそうな場所へ行くことにした。一つだけ、よく知っている場所があったのだ。それほど遠くじゃない。それで、海沿いの道をゆっくり歩いて行くことにした。
「ホームシックにはなっていない?」
歩きながら、訊いた。
「少しだけ、かな。いつもは忙しいから、あんまりそういうことはないけど、お休みの日はちょっと寂しいです」
この時ばかりは、まさに異国でゆきくれた人のように、沈んだ声で答えた。
「ああ。そうだね。誰だって、寂しくなる」
僕も相槌を打つ。
「ええ、そうですね。ありがとう」
「この辺りは海といっても、グランヴィルの景色とはずいぶん違うものね」
「ええ。でも、好きです」
彼女が言ったのだった。
「へえ。どうして?」
「まず、海。海には変わりがありません。そして、素朴な気がします」
「ああ。なるほど。確かにね」
「そう……。でも時々、おばあさんが恋しいです。桜のことを話してくれたのは母方のおばさんなんです。彼女はもういなくなってしまったけれど……。父方のおばあさんは両親の家とは少し離れたところに住んでいます。父と母はメールやチャットで話せるけれど、まだおばあさんとは、話せていないんです……」
今度は、本当に寂しそうで、まるでおばあさんに甘える年頃の少女のようだった。
「ああ、そうなんだね」
「ええ。でも、もうすぐ話せそうです」
また、元のあかるい口調に戻った。
「それはよかった。きっと、おばあさんも喜ぶね」
「はい。とっても、楽しみにしてるんです」
彼女が言い、僕もなんだかすっかり安心した気分だった。
しばらくすると、桜の咲いている場所に着いた。ここは、久しぶりだ。小さな公園だけれど、それでも桜の木は何本もあって、じゅうぶんに見応えがある。
「さあ、着いたよ。桜を見るのは、ここだ」
そう言いながら、ちょっとばかり複雑な気分になった。ずっと前に、Kたちとここで花見をしたことがあったのだ。
「おお。なんて綺麗なんでしょう」
Iが声をあげた。まだ、満開の時に近かったのだ。
「気に入ってくれたようだね。よかった」
僕は、ホッとして言った。
「ええ、とっても。ありがとう。ああ、これが、日本の桜なのね」
ずっとこの時を待っていた、というかのようだ。
「そう、でも、バンクーバーにも桜はあるんだよね?」
僕は、少し訝りながら訊いた。
「ええ。スタンレーパークとか、街のあちらこちらに。日本からの贈り物です。ワシントンの桜と同じですね」
「ああ、そうだった。確か、最初は横浜や神戸からだったんだね?」
「ええ、そうです」
「それでも、日本の桜は格別?」
「ええ。やっぱり、元々の場所で見る方が、ずっと素敵。おばあさんが話していたとおりです」
「これも、地産地消、かな?」
僕は、Iと初めて出会った海辺のバーでのやり取りを思い出しながら言った。
「えっ?あっ、そうですね」
Iが笑った。
「日本ではね、お花見といって、家族や友人たちと集まって、食事やお酒と一緒に、桜を楽しむ習慣があるんだよ」
「へえ。私も、ぜひやってみたいわ」
「でも、桜の季節は短いからね。もうすぐ終わる」
「そうなんですね」
「残念だけどね」
「ええ。残念。来年か、再来年か。また今度ですね」
「ああ。また今度、帰国しても、また来ればいい」
「はい。そうですよね。ぜひ、そうしたいわ。でも、今はこの桜を楽しむことにしましょう」
と、Iが言った。若いのに、まるで僕より先輩のような気がした。確かにそうなのだ。明日のことよりも今日、今この時を大事にしなければならない時があるのだ。で、で精一杯の笑顔で言った。
「ああ。そうしよう」
それからしばらくの間、黙ったまま、桜を眺めていた。時々口にした言葉といえば、「綺麗だね」、「はい」、「いいよねえ」、「とても美しいわ」、「いいなあ」、「ええ」、「ほんとにね」、くらい。
「実はね、この隣が、Kが働いていた場所だよ、こないだバーでいっしょだった……」
思わず、口をついて出たのだった。
「ええ。はい、そうなんですね。彼は元気ですか?」
「いや、それがね……」
言わないでおいたほうがよかった、という思いがよぎった。でも、もう遅い。一度口を飛び出た言葉は、もう飲み込めないのだ。
「何かあったんですか?」
彼女が訊いた。
「ああ。いなくなってしまった……」
僕は、正直に答えるしかなかった。
「えっ。どうしたんですか?」
「消えてしまったんだよ」
「消えた?なぜ…?どこに……?」
心配そうに訊く。
「それがわからない」
もどかしかった。
「はい……」
「連絡も取れないし、目の前からいなくなってしまったんだよ」
「どうして?」
「……」
何も言うことがなかった。
それで、しばらくの間、沈黙が続いた。
「君さえよければ、そのうちに、ゆっくり話せるような時があったら話すことにしよう」
話題を変えたかったのだ。
「ええ。そうしましょう。もし、迷惑じゃないのなら」
彼女が応じた。
「とんでもない。君の方こそ、大丈夫なのかい?」
「いいえ、助かります!」
元の姿に戻ったようだったのが、救いのように思えた。
「それはよかった。もともと暇だしね。それに、近くに一緒に桜の花を楽しむような友達もいないし……。Kも消えてしまったのでね……」
また、言ってしまった。
「ええ。残念ね」
「ああ。残念だ……」
僕は言葉を飲み込んだ。
それから、また咲き誇る桜を眺めた。今度は無言のままだった。
しばらくの間、眺めていたその後で、メールアドレスを交換し、近いうちにまた会うことを約束して別れた。
帰りながら、Iとまた会えたことは嬉しかったが、そのせいでKのことを思い出すと、また辛くなった。
*
I は家に帰ると、今日の体験を思い出していた。いや、帰路の途中からそうだった。素晴らしい体験だった。日本で見る桜のなんと美しかったことか。祖母が話してくれていた通り、そのまんまだった。いやそれ以上、彼女が想像していたよりももっと美しかったかもしれない。それは日本に来て以来、最も楽しんだことだった。何より、祖母に少しかもしれないが、近づくことができた気がした。やがて、それは十分ではないという確信に変わったのだった。
今日は桜の樹の下を歩きながら見ただけだった。確かにそれは美しかったけれど、しかし祖母は、日本では桜の木と木の間にカーペットそれは、ヒモウセンと言ったのだったか、を敷き、その上に座って食事やお酒を楽しむのだと言っていた。祖母がそのことについて話すときはうっとりとして、思い出すような様子だったから、きっとそれは自分の想像以上で、直接体験しない限り自分には到底理解できないことだと感じていたのだ。それがとても残念な気がした。
それが思わぬことから、実現しそうなのだ。I は思わず両の拳を胸の上で握りしめ、祖母に話しかけた。声に出して言った。とても、心にしまっておくことなどはとてもできなかった。
「やっとできそうだわ、おばあさん。あなたが、日本での最も楽しくて美しい体験の一つと言っていたことを。お花見というものを体験できそうなのよ」
*
それから何日か過ぎた頃、僕は久しぶりにバーのカウンターの前に座っていた。まだ、お客は誰もいない。バーは、開けたての凜とした空気に満ちていた。この雰囲気が好きなのだ。て少し気恥ずかしい気もしなくはないけれど、古い時代のアメリカの作家が書いていたように、空気がまだひんやりとしていて、全てが新鮮で光っている。背筋が伸びるような気がする。それは、鄙びたバーでも変わらないのだ。どんな時でも、どこであっても変わるところがない。
僕は、あの日と同じ壁から3つ目の席に陣取って、壁側の席には荷物を置いた。今日は、ここを空けておかなければならない。カウンターの向こうの店主兼バーテンダーに小さく声をかけて、スコッチに少しだけ水を足したものを頼んだ。
「お久しぶりです」
「ああ。悪かったね」
「いえ」
「いろいろあってね。来れなかったんだよ」
「ええ。ところで、今日はいつものハイボールじゃないんですね?」
「うん。ちょっとね」
「このスコッチの飲み方は、Kさんがそうでしたよね?」
「そう。そうだね」
「そういえば、このところKさんも見ませんけど?」
彼が言った。はっきりと訊くわけではないが、明らかに知りたがっているようだ。
「ああ。それなんだよ……」
ちょっと困ったけれど、仕方がない。
「はい?」
「いなくなっちまった」
「えっ?」
「姿を消してしまったんだよ」
「へえ。何かあったんですか?」
「それが、さっぱりわからない」
また、同じようなことを繰り返さなければならなかった。
ちょうどその時、バーのドアが開く音がして、振り返るとIが入って来るのが見えた。今日は、白いTシャツの上に薄手のジャケットを羽織って、下はやっぱり細い黒のジーンズだ。
「やあ、いらっしゃい」
「こんばんは」
バーテンダーとそつなく挨拶を交わしながら、奥の席の方にやってきた。
「こんばんは」
Iが、あかるい声で言った。
「やあ、こんばんは」
「お待たせしました?」
「僕も、ほんの少し前に来たばかりだよ」
「そう。よかった」
「元気にしてたかい?」
あの桜の日からさほど日は経っていないにのに、僕はホッとして言ったのだった。
「ええ。あなたは?」
彼女も訊く。
「よかった。僕は、まあまあってとこだね」
いかにも日本人らしい答え方だ。
「まあ。この間はありがとう。あなたのおかげでとってもいい経験ができました」
「どういたしまして」
僕が言うと、彼女は隣に座って、小さな鞄を壁際の椅子の上に置いた。今日は、うるさい若者もいないし、まだ早いせいで常連の老人たちもいなかった。
「あら。今日はクラシックがかかっているのね」
Iが気づいて、言った。
「ああ、小澤征爾が亡くなったようなんだ」
「ええ。残念ね」
「ああ。小澤は知ってる?」
「ええ、まあ。セイジ・オザワはトロント響の専任だったことがあるから……。名前は小さい頃からよく聞かされていたわ」
「ああ、そうだった。海外で活躍する日本人指揮者の草分けだった」
「そう。それに、バンクーバー響にはカズヨシ・アキヤマがいたのよ」
「へえ。そうなんだ」
「今は、世界中のどこでも日本人指揮者が活躍しているわね」
「そうだね。ところで、君はクラシック音楽が好きなのかい?」
「ええ。クラシックだけというわけじゃありませんけど」
Iがそう言うと、僕は、確かにと思った。彼女が初めてここに行ってきた時の格好を思い出したのだった。
「なるほどね、そうなんだ」
「家では、家族が皆楽器を弾いて、よく合奏していたんです」
「へえ、いいね。うらやましいな。それで、君は何を弾く?」
「ヴァイオリンを少し、日本風に言うならね」
彼女が、おどけるように言った。
「ふーん」
「あなたは?」
「残念ながら、聴くだけだね。まだ小さかった頃、家にはピアノがあったけれど、弾けるようにはならなかった」
「それは、残念」
「うん。今でも、後悔している」
「どうして?」
「やっぱり、自分で弾かないで、音楽を楽しむと言ってもね。なんだかね」
「そうなんですか。でも、どうして?なぜやめたんですか?」
「怠け者なんだね。それにね……」
「何?」
「きっと、何に対しても中途半端な性格のようなんだ」
そう言いながら、まるでKのようだと思った。彼がいなくなってから、なんだか急に似てきたようだ。もしかしたら、いや、彼が僕の代わりに引き受けて代弁してくれていたのかもしれない。でも、余計なことを言うのは、いいことじゃない。で、そのことには触れないでおくことにした。
「そう?」
「それで、君はどういったものを弾くのが好きなんだい?」
話題を変えようとして、訊いた。
「やっぱり、バッハかしら……、ね」
ちょっと考えてから、言った。
「やっぱりね。バッハはいいよね。特別だ。Kも好きだった。ヴァイオリンといえば、やっぱり無伴奏ヴァイオリン組曲だけれど。彼はフランクのも気に入っていたようだった……」
「あら。わたしもフランクのソナタは好きよ。あなたは?」
「フランクのものは、いくつかCDを持っているよ。昔は、バッハやモーツァルトが好きだった。でも、今はあんあまり高尚じゃないものが好きなようだという気がしている」
僕の喋りたがりは、治らないようだ。
「コショー?ペッパー?」
「いや、コウショウ。あんまりハイブロウなものより、もう少し人懐っこくてやさしいものが好きなようなんだ」
「なるほど。たとえば?」
「バッハよりもヘンデル。モーツァルトよりもシューベルトやブラームスと言えば、わかるかな?」
「うーん。はい、なんとなくだけど。でも、わたしもヘンデルは好きです。合奏協奏曲は、家族と一緒に弾いたことがある」
「指揮者になる前のブリュッヘンの弾く『木管のためのソナタ全集』もいいよ。休日の朝にぴったり、と思うけどね」
「へえ。聴いたことがないな」
「じゃあ、今度貸してあげよう。気に入るかもしれない」
「楽しみです。ぜひ、お願いします」
彼女が言ったのが、嬉しい気がした。
僕はこれまでずっと、バッハとモーツァルトが一番好き、と思っていた。もちろん、それは今でも変わらないけれど、もしかしたらバッハよりもヘンデル、モーツァルトよりシューベルトが好きなのかもしれないと思うようになったのだった。それに、シューマンもブラームスも、メンデルスゾーンも。バッハと同時代のヘンデルは別にして、皆ロマン派と呼ばれる人たちだ。理論や理屈よりも感覚的に受け入れやすいものを好むようになったということかもしれない。
ヘンデルはバッハに比べると、構成の緻密さというよりも、愉悦感や寂寥感といった感覚の方が優っているような気もする。バッハやモーツァルトにも愉悦感に満ちたものはたくさんあるけれど、それらの奥にはもっと別のもの、哀しみや厳しいものが隠されているような気がするのだ。それが、ちょっと辛く感じる時があるのだ。
思えばこれは、自分の性向をよく示している気がする。構成や精神性といったものよりも叙情(というか、もしかしたら情緒というべきか)を、全体よりも部分の方を気に入るのだ。なぜなのか、わからないけれど、ちょっと残念な気がしないでもない。それは、全体を把握する力や仕組みを理解したり、受け止めたりする力が不足しているということなのかもしれない(致命的なのかも、という気もする)。いや、それもあるには違いないけれど、構造や構成よりも感覚的で情緒的なのが第一なのだ。それは、クラシック音楽だけじゃなく、ポップスやロック、そしてジャズでも変わらない。確かに、考える力は不足しているのかもしれない、と改めて思った。それは、ポップスやロック、それにジャズの時でも変わらないのだろう。一事が万事、と言うように。
「で、クラシック以外は?聴かない?」
「もちろんちがうわ。当然、ポップスやロックも聴く」
当たり前だというように言った。
「あ、そういえば、ザ・バンド、ニール・ヤング、それにラッシュのようなちょっと知的な歌詞と難解で複雑なプログレなど。カナダ出身のロックスターはたくさんいるね。それに、ジョニ・ミッチェルも忘れてはいけない」
「ええ。でも、残念ながらそのいずれもが、おばあさんの時代のアイコンね」
彼女が笑いながら、言った。
「うーん。そうか。確かに、そうだね」
改めて自分の年を思い知らされた気になったけれど、ほかに知らないのだからしかたがない。
「私も、日本のグループのことはよく知らないし、正直に言うと、カナダのグループだってそうなの」
と彼女が言った。慰めようとしてくれていたのかもしれない。
「そうなんだ。じゃあ、何を聴いていた?」
「ジョニ・ミッチェルは好きよ。でも、ちょっと恥ずかしい気がするけれど……、まだ幼かった頃は、ガールズバンドや女性のスターをよく聴いていた。主にアメリカのものね、ちょっと古いもの。例えば、ジョーン・ジェット、シンディ・ローパーなどね。なつかしいわ」
彼女は、ちょっと微笑んで、遠くを見るように顔を上げて言った。少女時代を思い出したのかもしれない。でも、たいして昔じゃない。僕なんかに言わせれば、ほんの少し前っていうところだ。それでも若い彼女にとってはなつかしいのだろう。なんと言っても若いのだから。
「へえ、なるほどね。でも、それもおばあさん、とは言わないけれど、お母さんくらいのものじゃないか?」
僕が、訊いた。
「ええ。そうね。大学に入った頃からは、もうほとんど聴かなくなったけど」
「ふーん。そうなんだね。でも、なんとなくわかるような気がする。でも、黒づくめのファッションは?」
「ああ、あれね。初めてここに来た時に、着ていたもののことね?」
「そうそう。てっきり、ハード・ロッカーかと思った、それもヘビーメタル系の」
「ふだんはあんまり、あんな格好はしないけど。きっと、それは祖母の影響ね、父方のね」
「えっ?ところで、おばあさんとはもう話せたかい?」
「いいえ。まだなの。父がちょっと忙しいようなの。でも、もうすぐね」
「それはよかった」
「彼女は若い頃は、フランソワーズ・アルディやマリアンヌ・フェイスフルが好きだったみたい。とくに、イギリス人のマリアンヌね。彼女を真似た、黒づくめの服装の写真を見たことがある」
やっぱり、フランス系カナダ人と言っていたから、そのせいなのだろうか。
「なるほどね。それはたぶん、アラン・ドロンと共演した映画だ。映画そのものは、あんまり関心しなかったけどね。マリアンヌのことは日本でも話題になった」
「そうなの?でも、祖父はフランソワーズの方が好きだったみたい。もっと厳格な人だと思っていたから、驚いたわ」
「ふーん」
「彼は、亡くなる前に白状したのよ。他に誰か会いたかった人がいるかって訊いた時に、『フランソワーズ・アルディ、かっこよかったな』、と言ったの」
「へえ。やっぱり、映画みたいだ」
そう言いながら、「みなさん、さようなら」は、たしかカナダじゃなかったか、と思った。もしかしたら、彼女の祖父はしゃれで言ったのかもしれない。
「ああ。確かに、そうよね。でも、そんな話は、全くしなかったのに。祖父のことは、ずっと堅物だと思っていた……」
「ああ。でも、案外そんなものかもね。誰に対しても、大好きな孫娘にだとしても、全てのことを話すわけじゃない」
不意に、またKのことを思い出した。
「そうね。でも、また話せてよかったわ……」
Iが言った。きっと、彼女も祖母や祖父のことを思い出していたのに違いない。
それからしばらく話をした。そして、遅くならないうちに帰ることにした。何にでも潮時というものがある。
そして、何日か経ったあと、僕は思い切ってIにメールしてみることにした。
「終わりかけの桜の下で、もう一度ピクニックはどう、最後のお花見をするってのはどう?」
と、すぐに返事が来た。
「うれしいわ。ぜひ、そうしましょう」
まあ、あんまり興味はないだろうと思っていたのに。少々大人びた外国人とは言っても、何しろまだ、20代半ば、若い女の子なのだから。
*
で、またあの場所で会うことにしたのだった。このあいだの公園で待ち合わせをして、お昼ご飯を持ち寄っての、ちょっとしたピクニックだ。僕は行楽弁当の定番を作った。鮭とかつぶしと梅干、彼女のためにカニカマ(バンクーバーで食べたカニが、美味しかったことを思い出したのだ)とツナマヨのおにぎりに、卵焼き、牛肉のしぐれ煮などを詰めた。彩りのために、スナップエンドウやトマトを添えることにした。彼女は、ローストビーフと野菜を挟んだカスクートと、見た目も鮮やかなシーザーサラダを作って来た。
とくに、ローストビーフは絶品だった。僕が知っているローストビーフといえば、ビュッフェ形式の時に出てくるものだったが、大抵は薄切りで、しかもパサついていた。それが彼女が持ってきたものは、ジューシーで程よい厚みもあって、いかにも肉を食べていることが感じられた。やっぱり肉食の文化の賜物なのか。
残念ながら、桜の花はもう散りかけていて、もうすぐ葉桜と言っていいくらいになりそうだったから、周りには誰もいなかったけれど、それでも日本風にブルーシート(さすがに、緋毛氈は無理というものだ)を敷き、座ることにした。念のために、彼女が楽なようにと折りたたみの小さな椅子も用意したのだったが、
「ありがとう。でも、必要ないわ」
と、言われた。本当は楽じゃないのかもしれないけれど、あくまでも、日本風を楽しみたいのだろう。
それから、Iはバスケットを開けると、小さな包みを取り出した。
「ところで、デザートはどうですか?」
「えっ。デザートがあるのかい?」
「ええ。食後には大事なものだから、きっとお花見にも思ったんですけど?」
Iは秘密めかすように、言った。
「そうだね。いったいなんなんだろうね?」
「これよ」
そう言って、包みを解いて現れたのは、桜餅だった。
「おう、これは。桜餅だね?」
「ええ」
「よく知っていたねえ。日本のお菓子のことを」
Iはにっこり微笑むだけだ。
「ええ。これは今朝作ったんです」
「えっ?生菓子を?」
「ええ。これにはちょっとした秘密が。昔から毎年作っていたんです」
Iはそう言うと、桜餅を作るきっかけになった時のことをおばあさんとのことを話してくれたのだった。
*
桜を見ながら、I はおばあさんとのことを思い出していた。3月の終わりか、4月の初め頃。ちょうど、今頃のことだ。
ある日、Iが学校から帰ってくると、挨拶にいく間もなく、おばあさんが大きな声で呼んだのだった。
「おかえり、I。早くこちらにいらっしゃい。その前に、手を洗ってね」
いつも落ち着いて静かななのに、珍しいことだった。何事かと思ってIは駆けつけた。
「ただいま。なあに?どうしたの?」
「お前は、日本のお菓子を食べたことはあったかしらねえ?」
「ええ、いくつかね」
「じゃあ、これはどうだい?」
見ると、お皿の上に、薄いピンクの皮の間に餡を包んで、さらに緑の葉でくるんだものが並んでいた。
「あっ。初めて見たわ。綺麗ね。なんていうお菓子?」
「これはねえ、桜餅と言ってね、生菓子、焼かないお菓子。日本の古くからあるお菓子さ」
「へえ」
「じゃあ、どうぞ、召し上がれ」
そう言って、にっこりした。その時、Iはお婆さんの別の一面を見たような気がしていた。それまでもおばあさんはI に対して優しく接してくれていたのだったが、どこか堅苦しくて打ち解けてくれないような気がしていた。威厳のようなものを感じていたのかもしれない。
「この、緑の葉っぱは?」
「好き好きだけどね、まずはそのまま食べてごらんよ」
そう言いながら、お婆さんはお茶を淹れてくれた、もちろん日本茶だ。日本茶は紅茶と違って、少し冷ましたお湯で淹れるのだった。
「あ、少ししょっぱい。でも、いい香り、そして甘い。とってもおいしいわ」
「しょっぱいのはね、桜の葉っぱを塩漬けにしたもので、甘いのは小豆を砂糖と一緒に煮て、裏漉ししてなめらかにしたものだよ。日本人は、好きな人が多いわね」
「へえ。おうちでも作れるのかしら?」
「え、お前は作ってみたいのかい?」
「ええ」
「じゃあ、今度一緒に作ってみるかい?」
「ええ」
翌日だったか、翌々日だったか、お婆さんが材料を揃えてくれて、一緒に作った。それはI にとって初めての和菓子作りだった。母と父にも食べてもらった。初めて作った桜餅は、形が少し歪だったが、それでも二人はおいしいと言って食べてくれた。それからは、おばあさんと一緒に毎年作るようになったのだ。
それまでもお婆さんはIに優しく接していたけれど、何か威厳のようなものがあって、完全には打ち解けきれないものを感じていた。
それが和菓子作りを通じて、Iとおばあさんとの絆がさらに深まったのだ。
*
彼女は、話し終えると少し涙ぐんでいたようだったが、すぐににっこり笑って明るい表情に戻った。素敵な笑顔だった。
ほんとうに、楽しかった。彼女も喜んでいたみたいだった。2人顔を合わせてにっこりした。それから、また桜を見た。目があうと、彼女が微笑んだ。素敵な笑顔だ。笑顔を見るのは嬉しいことだ。
満開の桜が美しいのはもちろんだけれど、わずかに残った花もまた、なかなか風情があっていいものだ。時折風に吹かれて舞う花びらも素敵だった。
その時、ほとんど緑の葉ばかりになった木々の間から一筋の光が差し込んで、彼女の顔を照らした。続いて、僕の顔も。
「あっ、眩しい」
彼女が言う。
「あっ、僕もだ」
それからも、時々会うことになった。年甲斐もなく、なんだかあかるい気分になった。単調な生活に少し彩りが添えられたようで、久しぶりに楽しいと思える日々が戻って来た気がしたのだった。しかも、何であれ避けようとするのではなく、いったん受け入れて、それから前に進むのがいいということを教えられたのだ。
ただ、Iは1年も経たないうちに、帰国するのだ。そのことはもう、わかっている。今の僕は、彼女にとっての日本での父親みたいな役割だ。年からいえば、祖父と言う方がふさわしいかもしれないけれど。ともあれ、その役割を楽しんでいるのだけれど、本当の父親はもっと若くて、背が高いくてかっこいいようだった。それに比べるとこちらは残念ながら、ちょっと貧相。残念ながら背も低いし、足も短い。Iが帰国したら、すぐに忘れられてしまうのかもしれない。ま、しかたがないことだ。
その役割も、やがて終わる。始まりがある限り、終わりもまたあるのだ。ま、それもしかたがない。それでも、きちんと引き受けることができるようにならなければならない。しばらくともに過ごした時間を通じて、彼女が教えてくれたように。そして、前に進むのだ。
前に、進もう。前に進まなくてはならない。先のことを思い患っていても、いいことはないのだ(たぶん)。
(3)日常から脱出
*
その夜は、いつもの鄙びたバーの、いつもの席に座っていた。ありがたいことに、馬鹿騒ぎするような輩もいない、いつものように静かなバーだ。
「いよいよだね」
僕は、切り出した。
「ええ」
Iが、答える。
「寂しくなるな」
正直に言う。
「そうね」
「ああ」
「でも、いろいろな経験をすることができました。ありがとう」
「こちらこそ。おかげで、楽しかったよ」
「祖母の故郷での、あっという間の一年でした」
「ああ、早いよねえ。でもね、脅かすようで悪いけど、年取るともっと早くなるよ」
また、笑いながらだったが、余計なことを言った気がした(悪い癖だ)。それで、慌てて、
「なんでもないよ」
と付け加えた。
「そうかしら?」
Iが不思議そうに言う。それも無理からぬことだ。彼女はまだ若くて、無限の可能性を信じられる頃なのだ。
「ああ、そうとも。人生は短いから、『やりたい事やんなさい。後で後悔しなさんな。やりたい事やんなさい。グラスのふちに唇つけたらとことん、一滴残らず飲み干しなさい。後で戻ってきても、もう雫は残っていない。今のうちに飲みつくしなさい』と言った日本の作家がいるよ」
「へえ。誰ですか?」
「開高健。博識で、釣りやグルメ紀行でも有名だけれど早くに亡くなってしまった。あ、そういえばあまりかの女優、ブルック・シールズもファンだったらしい。この言葉の元は、オーストリアの医師で劇作家のもののようだけどね。アルトゥール・シュニッツラー、いくつか、有名な映画の原作もある」
「そうなんですね。覚えておきます。でも、ブルック・シールズって?」
「それはもう、忘れて……。それにしても多才な人がたくさんいるんだね」
僕は、半ば自分に言い聞かせるように呟いた。
「ええ」
「……」
「ところで、どうしてこんなに親切にしてくれたのかしら?」
彼女が不思議そうに訊いた。
「バンクーバーがなつかしかったしね」
「えっ⁉︎」
「それに、何と言っても、君みたいな若い女性と話すのは楽しい」
僕は笑い話にするつもりで答えた。
「えっ?」
「K もいなくなった……」
また、余計なことを言ってしまった。
「はい」
「実はね、うんとむかしに、僕がそんなふうにしてもらったことがあったんだよ」
こうなったら、本当のことを話して雰囲気を変える方がいい、と思い定めて言った。
「そうなの?」
「ああ」
僕は、うんと昔のフランクフルトの夜のことを思い出したのだった。思えば、なんとも珍しくて、しかも本当に素敵な体験だった。
初めてのドイツ。バウハウスを巡る旅だった。
「バウハウスは知っているよね?」
「ええ」
「ずっとバウハウスを巡ろうと思っていて、それがようやく実現したんだ」
「ワイマール、デッサウ、そしてベルリンね」
「ああ。よく知っているね」
「いちおう、デザインの勉強もしましたから」
「そうなんだ」
「はい」
「それで、とくに行きたかったのはデッサウだよ。ヴァルター・グロピウス、2代目の校長でもだった彼が設計した校舎がある。グロピウスは、20世紀の建築家の4大巨匠の一人でもあるよ。ま、後の3人と比べると、忘れられがちで、ちょっとかわいそうだけどね。バウハウスを象徴するアイコン、と言っていいと思う。これを見た時は、とても感動したことを今でも覚えているよ」
「へえ」
「君も知っているように、バウハウスは世界中のデザインを教える学校のモデルとなった。僕が通った学校もそのひとつだった」
まだ出来たての学校で、若い教員たちを中心に上級生たちも一緒になって、バウハウスと同じように理想と希望に溢れていた。
「そうなんですね」
「それから、その後でフランクフルトへ行ったんだよ。短い滞在だったけれど、見たかった美術館がいくつかあったからね」
「ええ」
「フランクフルトに着いた時はもう遅かったし、地元らしい食事を楽しみたかったけれど、食べる所の手配までは気が回っていなかった(たいてい、こうしたものだ)。そこで、ホテルのフロントで訊いて、フランクフルトらしいレストランを教えてもらって、出かけたんだよ」
「へえ。ドイツ語ができるんですね」
「ヤァ、もちろんドイツ語でと言いたいところだけれど、英語らしきものでね」
冗談ぽく聴こえるように言った。
「実は、英語もからきしダメさ。だいたい耳も頭も悪いんだ」
「えっ?」
「店は、さほど苦労することもなく見つかったよ。特に気取った様子もなかったので、安心したんだ。ドアを開け、中に入ると、満員であることがすぐにわかった。テーブルは全て埋まっていて、入り込む余地はなかった。それで、ちょっと呆然として立ち尽くしたんだ。そこしか行くところを知らなかったからね」
「あら、大変だわ」
Iが言った。僕は、改めてその時の場面を、つい昨日のことのように思い出したのだった。不意に、込み上げるものがあった。
*
その時、しばらく呆然とする外国人の僕を見て、
「どうしたんだい?」
声をかけてくれた人がいたのだった。
「フランクフルトらしい食事をしたいと思ったんですが……、遅かったようです……」
「そうなんだ。じゃあここに座ればいいよ」
それぞれ、黄色と黒のセーターを着た、夫婦らしい中年のカップルが言ってくれたのだった。2人ともが、なんとなく抱いていたドイツの中年のイメージとは異なって、痩身だった(だから、はじめに目が合った時には愛想がいいという印象ではなかった)。
「ありがとうございます。でも、いいんですか?お邪魔じゃありませんか?」
僕は、思いがけない親切な申し出に驚いた。
「もちろん。いいからおかけなさい」
にっこり笑って、空いた席を示してくれたのだった。何にも増して素敵な笑顔だった。
「ありがとうございます」
「ところで、どこから来たんだい?」
「オックスフォードからなんです。しばらく滞在しているんですが、元は日本から」
「そうなのかい。ようこそ、フランクフルトへ」
そして、食べるべきフランクフルトの名物料理も勧めてくれた。もちろん、陶製の器に入った、あのお酒も。
「まずは、リンゴ酒、アプフェルヴァインから。お酒が飲めるならね」
夫のハンスが笑いながら言う。口ひげにはもう、白いものが混じっていた。
「はい」
「それから、リップヒェンね。塩漬けにした豚肉を茹でたものに、ザワークラウトを煮たものを添えた料理よ」
すかさず今度は、妻のブリギッテが教えてくれた。ハンスはこの近くで貿易会社を経営していて、彼らはこれを食べるために久しぶりにこの店にやって来たということだった。
「それで、僕は無事にフランクフルト名物の料理を楽しむことができた」
「よかったわ。親切な人がいて、幸運だったのね」
Iも驚いて、そして安心したように言った。
「うん。でもそれだけじゃなかったんだ」
「何があったの?」
心配そうに訊いた。
「ハンスとブリギッテに翌日のことを話すと、彼が言ったんだよ。『じゃあ下見をしておかなくちゃね』って」
「えっ?なんですって?」
心底、驚いたようだった。
「時間がないなら、効率よく回らなくてはいけないからね、と言うんだよ」
「そうなの?」
それで、
「ええ。でも、僕にはそんな余裕がないんです、と答えると、『じゃあこれから行こう』と言って、僕を外に連れ出したんだ」
「それで?」
「外には、黒い大きなベンツが停まっていた」
「それで、どうなったの?」
「そして、案内してくれた。フランクフルトで見るべきところを。それから、ホテルまで送り届けてくれたんだ」
「ワオ!アンビリーバブル!すごいわ」
「ああ。今から思うと、ちょっと無防備だったような気もするけどね」
「ええ!」
「そんなことがあったからね」
「へえ?。確かに、そういうことがあった。それで、自分もできることをしようと思ったんだよ」
「じゃあ、私もハンスとブリギッテに感謝しなくちゃあね」
「えっ?あ、そうかもね」
そう言うと顔を見合わせ、そしてにっこりした。
それから、ハンスとブリギッテとはメールをしたり、クリスマスにはプレゼントを交換したりしていたのだけれど、ハンスが突然亡くなってからは、次第に疎遠になった。幸運は、続かない。ブリギッテは英語が不得意で、ハンスにもう少し英語を勉強したほうがいいねと言われていたそうだ。そういえば、僕も同じことを言われたことを思い出した。
「オックスフォードにいるにしちゃあね」
思えば、僕はそれだけじゃなく、その時々で、ずいぶん親切にしてくれた人たちがいたのだ。
「僕は、恵まれていたんだね。ハンスとブリギッテの他にも、そうした人がいたからね」
「へえ」
「だから、自分にもできることを、ね」
「ええ」
*
I はどうしたことか日本に来て以来、花見をしたり、鄙びたバーで飲んで話をしたりするようになって、カナダでのことを思い出すようになったのだった。初めは祖母のことを理解したいと思っていたのが、次第にカナダでの生活のことにも思いを及ぼすようになっていた。
それは、カナダにいる時からぼんやりと考えていたことだった。
私は一見周りの多くの人と違うところはないように見えた。しかしよく見ると少し違っているようにも思えた。背は高いし、肌の色や目の色、髪の色も違うところはないように見えたのだったが、肌は少し黄色味を帯びているようだったし、目は茶色、髪は艶のある黒だった。私はずっとカナダに住んで、そこで育ってきたし、カナダ風の英語を話す。しかし、家では日本語もフランス語も話す。母方にはカナダ人と日本人の血が入っているし、父親の方も同様だ。したがって、私にはカナダだけではなく、日本とフランスの血が4分の1ずつ入っている。カナダ人と言えるのか、生粋の日本人でもなく、フランス人でもない私は何人なのだろう。
そのことがずっと気になっていて、時々悩まされることがあった。それが日本に来て少しわかったような気がした。一方で、この時代になってなお台頭する自国第1主義や民族主義の排他的なところを嫌悪した。
カナダはアメリカの51番目の州になるべきだと言う、驚くべき発言が隣国である超大国の大統領の発言には呆れたけれど、同時に驚愕したのだった。歴史の流れに逆行しているようで、この時代にあってどうしてと思うのだけれど、こうしたことは減るどころかむしろ増えているのだ。弱肉強食という野蛮な仕組みがまかり通り、しかも、国際社会はそれを止める手立てを持たない。ロシアによるウクライナ侵攻が典型的だけれど、もしかしたらイスラエルのガザ攻撃も同じようなものかもしれない。
共存よりは自国による支配をというこれらの国の指導者たちはきっと高等教育を受けているはずに違いないですだろうと思うけれど、過去から何も学ばなかったようだ。人間の愚かしさは必ずしも時代の進歩ととともに、解消されるというものではないようだ。
だから、祖国、あるいは母国ということも素直には口に出しにくい気がすることもあったけれど、自分のアイデンティティが国という共同体と無関係でありうるのか、一体どこにあるのかということが気にならないかといえば、やっぱり気になるのだった。
私はカナダ風の英語を話すし、その言葉で考えるから、紛れもなくカナダ人なのだ。多くの同国人のより日本やフランスに親近感を抱くけれど、だからと言って」よく知っているわけではない、少し他国の血の混じったカナダ人。一方で、この地球に住む地球人の一人でもある。確実なのは、私というこの世にたった一人しかいない人間が存在しているのだ。このことを大事にしようと思ったのだった。カナダという自分が育った国を大切にしながら、しかし他者を排斥しない。今は、それでいいというような気がしていた。
*
Iが帰国してからは、また元の生活に戻った。正直なところ、ちょっと味気ない毎日だ。例のバーにも、あんまり行かなくなった。それでも時々、K やIのことを思い出す。Iからは、今でもたまにメールが届く。仕事も順調のようだし、おばあさんともいつでも話せるようになったということだった。めでたいことだ。メールがもう少し多く届くようになればいいと思うけれど、たぶん忙しいのに違いないから、それもなかなかむづかしい。今は慣れ親しんだところで暮らし、何より親しい人に囲まれているのだから、それも仕方がないことだ。そうして、異国でのことも、なつかしさを残しつつ、次第に忘れていくのかもしれない、と考えたりすることもある。
それで、思うことがあって、久しぶりにバーに出かけてみることにした。開店時刻に合わせて少し早めに出て、ジャケットを着てネクタイを締めて行くことにした。カジュアルでいいというつもりでいて、きちんとしようと心がけていなかったなら、どんどんだらしなくなるような気がしたのだ(それは、格好だけじゃなく、生活そのものに関わりそうだった)。
そのバーは、決して都会的でもないし、しゃれているわけじゃない、それどころか質素と言うのか、鄙びた、あるいはもっと直裁に冴えないと言う方がいいくらいだけれど、負けず劣らず凛とした空気が漂っている(少なくとも、開けたての時は)。やっぱり、店主の人柄なのだろう。
開店時刻よりも少し早く着いたが、店内は明るかったし、ドアを押してみると予想に反してすんなり開いた。で、中に入ると、予想通り客はまだ誰もいない。開けたての清潔な空気は損なわれていない。
「こんにちは」
僕がそう言うと、
「やあ。いらっしゃい。ずいぶん久しぶりですね」
バーテンダーでもある店主が、そう言って迎えてくれた。
「ああ。ちょっとね」
いつもと同じ、特に変わったところもない挨拶だ。
でも、なんとなくいつもと雰囲気が違っていた。流れていた音楽のせいだ。
「おや、レゲエだね。珍しいね。ジミー・クリフ」
「ええ。ちょっと元気が出るような曲にしようと思って。まだ開店前だし、お客はいないから、と思って。外はまだ明るいようですし。景気付けに、ね」
「たしかにね」
「ジャズの方が良ければ、変えますよ。でも、嫌いじゃないでしょ?」
「ああ、もちろん」
それどころか、……。この歳になって、来し方を振り返ることがある。たいてい恥ずかしくなるようなことばかりだ。でも、この曲を聴くと、そんな自分がさらに恥ずかしくて情けなくなって、前を向かなくては、という気になるのだ。
「そういえば、Iさんはどうしているんでしょうね?」
店主が言った。
「ああ、元気にやっているようだよ」
僕が答えた。
「なら、良かった」
安心したように言う。
「うん」
「でも、さびしいですね」
「ああ」
「あの娘がドアを開けて入ってくると、とたんに雰囲気がパッと明るくなりましたものね」
「うん」
「華やかな雰囲気がありました」
「そうだね」
「日本語は流暢だったけれど、なんだか日本人離れしていましたね」
「4分の1ほど、フランス人らしいよ」
「ああ、そうなんですね。なるほどね」
「父親の母親と母親の父がフランス系カナダ人ということだった。なんだか、ややこしいけどね。だから、家では英語の他にフランス語や日本語で話す時もあった、と言ってた」
「へえ、やっぱりね」
「そのおばあさんともようやく話すことができるようになって、喜んでいるみたいだ」
「日本に居た時は、なかなか話せなかったようだけど。何しろ、僕よりも年上のおばあさんだから、コンピュータやスマートフォンは得意じゃないらしい。あ、それにお前さんのことも。素敵なバーのバーテンダーにもよろしくとさ」
「え。それは嬉しいな」
「ええ」
そんな話をしているうちに、『ハーダー・ゼイ・カム』はすぐに終わった。
「ついでに、ボブ・マーリーはどうでしょう?」
そういって、レコード盤を取り出した。
「おっ、今日はレコードなんだね?CDじゃなくて?」
「ええ」
「おっ、『エクソダス』」
「ええ」
「いいね」
「元気が出そうでしょう?」
彼が言った。
「うん」
「明るい歌詞というわけじゃないようなんですけどね」
「そうだね。こうやって聴いていると、僕なんかはジャズよりもロックやポップスの方が相性がいいみたいだ」
「そうなんですか?」
「大雑把に言えば、ロックは直接的だし、それに対してジャズはある種知的な操作が加わって、内省的なところがあるような気がするんだけどね。例外もあるだろうけれど」
「うーむ。確かにね。でも、ジャズでも、このところまたバップが戻ってきているようですよ」
と、教えてくれた。こういうことを教えてくれる人がいるのはありがたい。偏狭さから逃れることができるはずだから。
そんな話をしていたら、タイトル曲の『エクソダス』がかかった。その時ふいに、思ったのだ。
(「旅に出よう」)
そうだ、そうしよう、そうするのだ。いやそうしなければいけない。
で、言った。
「そろそろ退散するよ。ごちそうさま。どうもありがとう」
「えっ、もうですか?」
店主が言った。
「ああ、誰かと会う前にね、帰るのが良さそうだ。ちょうどいい潮時だよ。ありがとう」
「あ、はい。また、よろしくお願いします。ありがとうございました」
「それじゃ、また」
僕は、外に出た。街には、まだ春の夕日の残照が残っている頃だった。
その夜、僕は、死者の安息を願う鎮魂歌でありながら不思議なあかるさのあるフォレのレクイエムを聞きながら、トランクに荷物を詰めた。
*
その時に、うんと昔に作った詩を思い出した。もう何十年も前のものだ。手づくりの本にしたものが、それがまだ手元にあった。その時のように、前を向くなければいけない、という気がした。かつては、見るたびに赤面するばかりのようだった。それがいつの間にか、愛おしいものに変わっていた。
『ぼくたちがながい夜を旅するとき』。
それは、ちょっと長い、というかそうとうに長い。渡辺武信や泉谷明に憧れていた頃のものだ。たぶん、直接的な影響を受けているだろうと思う(もしかしたら、ただの模倣と言えるほどかもしれないけれど、当時のことはもう忘れてしまった)。たしかに若かった、少なくとも今よりはうんと。
引用してみることにしよう。ちょっと長いし、おまけにこの話には関係ない部分が多いけれど、誰かが文句を言ってくる心配は皆無なのだ(ま、「ぎゃっ」と叫んで放り出すことはあるかもしれないけれど)。1行さえあればいいと思ったりもするけれど、この際、全部を載せても問題はないはずだ。日の目をみる可能性を与えることにしよう。そうしたところで、誰も文句は言わないだろう。
*
ぼくたちがながい夜を旅するとき
1
膨らみ過ぎた都会の幻影が あらゆる記憶を捨ててぼくたちを襲い
ぽっかりと口を開けた闇の切り口から いくつもの夜があらわれてくる
かすかに光りを放ちながら溶け出る鉛の渦が
音もなく拡がりつづけている
次々にめぐってくる夜にやさしく罠をしかけるのは
きみの唇だ やわらかなきみの髪だ
複雑にからみあい もつれあった夜々は
きみのしたによってほどかれて
新しい夢を編み込んだ一枚の毛布となって
ぼくたちを包み込む
が しかし
まぶたを閉じるならば
都市の重たい鼓動が
ほのぐらい血管を逆流する
2
ぼくたちは まず
小さな部屋で ささやかな宴を張ること
から 始めよう
もういちど
都市を
ぼくたちの手の中に
獲り戻すために
明るい電灯の下でかかげられたワイングラスの中で
光りをはね返し
ゆらゆらと ゆらめいているぼくたちの海
で キッド船長のように
勇ましく
宝捜しをつづけることができるだろうか
いつまで
帰っていく場所のない ぼくたち
は いったい
何処へいけばいいのか
いつも
問いは
遠い彼方に消える
3
テレビを消し 灯を消し
すべてを消してみても
決して消しきれない
ぼくたちの記憶
いつでも 闇は
不安のかたちをすることを やめない
しかし
闇の中で眼を開け
おたがいの眼差しの中に宿ったひとすじの光り
のうちに
輝く海を見つけ出せ
4
悪い時代なのかもしれない
けれど
もはや誰も止めるな
ぼくはどこまでも行くのだ
暮れていく街
暮れていく海
暮れていくやつはみんな勝手に暮れていけ
そんな感傷は 激しい波にくれてやる
やぶれかけた帆船は完全に沈めてしまい
虹のしぶきの光る海へ行くのだ
激しく夢見ること
それだけが 僕たちの持ちうる武器だ
脆弱なやさしさよりは
くるしい暴力を!
激しく夢見ることで
悲しみを断ち切れ!
*
それから、ドアを開けて外に出ると、鍵を閉めた。頭の中では、あの「エクソダス」が鳴っていた。もはや、アパートの1室で宴を張ることはないけれど、光る海を求めて行くことにするのだ。今なお、どこかにあるかもしれない光り輝く「海」を見に。
そして、何かを見つけて戻ってくることができればいい、と願った。
(了)
*
後書き
出来栄えはともかくとしても、ほんのちょっとした指摘で変わります。
忙しい中で読んでくれたあなたが、もしなにか思うことがあったのなら、ぜひお知らせください。もう少し書き進めてみようと思うのです。
よろしくお願いします。
2025.06.22
FANTASY 39 GとGの物語のために(ふたりのGについての素描・2)
GとGの物語のために(ふたりのGについての素描)・後半
*
ところが、ある時からGは、だんだん焦りのようなものを覚えはじめるようになったのだった。年齢を重ねるにつれ、たいていの人がそうであるように、いくつかの不具合が判明するようになった。特別なこと、というわけじゃなかった。あるいは、単に年をとったせいなのかもしれない。いわば数十年遅れのミドルエイジ・クライシス。すなわち、オールドエイジ・クライスともいうべきもの。身体的な不具合は、不治の病というわけではなかったが、すぐに治るというほど易しいというのでもなかった。それまでは、なすべきこと、あるいはなし得たことといった類については全く気にしていなかった。将来を考えるということもなかった(なんと能天気なことだったことか)。それなのにある時から急に、周りの人々がそれぞれに着実に何らかの実績を積み重ねていた中で、自分が何もなし得ないままでいることが、なんだか急に寂しいことのように感じられるようになったのだった。
まさか、……。Gは、そんなことを思うとはつゆほども想像していなかったのだ。彼は、もとより自身の能力を信じていなかったし、期待もしなかった。多くを望まずに、自分の周りの極く小さな世界で、できる範囲のことをしながらひっそり暮らせるならばいいと願っていたのだ。それなのに、どうしたことか、今頃になって、そのことが間違っていたのだと思い、悔やまれるようになったのだった。それは、何かを成し遂げたいととか、名声を得たいとかいうものではなく、そうすることで自分のことを思い出してほしいという願望のような気がした。
Gは、もう一人のGのことを妬むことは全くなかったけれど、それでも時々羨ましいと思うことがあった。何が二人を分けたのだろう。二人の違いというのはさほど大きくないはずだ。ふと、そんなふうに考えることもあった。しかし、それは幻想に過ぎないこともわかっていたことだった。努力できなかったせいなのか。Gは自分が、長く努力をし続けるということができないということをよく知っていた。ただ、無論それもあっただろうが、端的に言うなら、単に能力の違いのような気がした。それならば、仕方がない。受け入れるしかないのだ。あるいは、外の世界に対する思いの強さの違いというものが、さらにそれに輪をかけたのかもしれなかった。
何にせよ、できることは限られていることは明らかだった。もはや潤沢とは言えない残された時間を、あるがままを受け入れて静かに暮らすか、自分をさらけ出して衝突をいとわずに過ごそうとするのか。後者に憧れはあったが、できそうにないことは容易に想像がついた。それは確かに刺激的かもしれないが、きっとそのことがもたらす結果にくよくよと悩んだりするに違いない。とすれば、今と大して変わるところはないようだった。ならば、これから何ができるだろうか。
一方、もう一人のGも平穏ではなかった。二つの分野で大きな賞を獲得したし、それ以来さらに多くの人が近づいてきて、賞賛してくれた。自分でも、達成感と高揚した気分を味わって来もした。しかし、それは長くは続かなかった。果たして自分がつくるものは、賞に値するのか、今後も周囲の期待に応えることができるだろうか。そんなことを考え始めると、次第に不安になり、疑心暗鬼となって、平穏ではいられないようだった。周りとの距離が遠くなり、自然と心を許す人の数も少なくなっていった。いつの間にか、裸の王様になったような気分だった。
褒められることに慣れすぎたのかもしれない、と思った。褒められなくなることを恐れて、挑戦することを忘れがちだということを自覚するようになっていた。いわば、見えない権威、お客や読者の評判、そして評論家や同業者たちによる批評といったものを気にして、いつしかその従者になっていたのかもしれなかった。
彼は毎年人間ドックを受診していたが、物理的には大きな欠陥はなかった、少々、いやかなり太り気味であることを除くならばだ(心臓に負担がかかっているのは明らかだったし、立ちっぱなしでいると時折り膝が辛くなる時があった)。Gには、料理人は痩せていてはいけない、という信念があった。妙といえば妙かもしれないのだが、痩せていたら美味しそうな料理が出てきそうだという予感を与えない、だから料理人は太っていなければならない、と固く信じていたのだ。ただ一方で、急に忘れっぽくなったことを自覚していた。
たとえば、作り慣れた料理の名前が出てこない、やりかけていたことを何かの拍子に忘れてしまう。あるいは、大事な約束を失念しそうになったり。幸い、今のところは致命的なことには至っていないものの、他にも多々あった。それでも、作り手としての矜持を取り戻すことが最も大事なような気がした。
それで、もう一度、名声の重圧と闘わなければいけないと思った。料理であれ、短歌であれ、自分が作るものは奇抜というのではなく、実はその中に革新が隠されているものでなければいけない。Gは、そのことを改めて強く意識したのだった。
*
振り返ってみれば、二人のGはともに、誰かと共同して得た喜びというものとはほとんど無縁のままだった。指示する立場と指示される立場、そのいずれかしか経験してこなかった。二人ともが力関係がはっきりとした世界で暮らしてきたのだったのだ。
そして、精神的な葛藤だけでなく、歳をとるにつれてそれぞれが身体的な問題も抱えるようになった。それは誰にもある、自然なことだったが、うまく対応できなでいるのだった。自身の思いとは別に、もう若いとは言えないことは十分に自覚していたのに、だ。
大事なことは、挑戦することと自身が望みうる成果のバランスだ。高望みして失敗すればガッカリするし、失敗を恐れて簡単に手に入ることを望めば挑戦することにならない。希望は高く持つべきだ、という人もあるだろう。ただしそれは、カナダの東海岸沖の小さな島の少女のように自身が抱く野心を素直に信じられる時代の間に限られる。失敗を恐れる必要のない時代だ。素敵な時代だが、得てしてそのことが忘れられがちなのはどうしたことだろう。Gは少女のことを羨ましいと思わないわけではなかったが、それこそが高望み、叶わないことだ。少女たちとは大きく年が違うGは、今の自分には小さくとも達成感を得ることこそが大事であるような気がした。ずいぶん遅い気づきだったが、気がつかないよりはマシだと慰めた。
それからGは、背伸びをしないで、自分のできることをやることにしようと思い定めた。ただし、それまでのように自分の世界に沈潜するというのではなく、できる限りのことを自分なりに積極的に取り組みながらやればいい。たとえば、毎日を少しだけおしゃれをして過ごすというのでもいい気がした。これまではあんまり縁がなかったが、真に着るものに気を配る必要のあるのは年寄りと子どもである、という話を聞いたことがあった。子どものことはいざ知らず、年寄りがだらしない格好をしていると、確かにみすぼらしくて貧相な印象を受けるし、寂しいような気にもなる。逆に、質素でも清潔なものを身につけていたら、精神は安定し、豊かであることが知れる。
毎日の生活を、少しずつ美しいものに整えていく。そのことを心に留めて暮らすなら、いささか遅すぎたとしても、これからは幾らかでも前に進むことができるだろう。それがささやかなことであったとしてもだ。考えてみれば、つくることも書くことも同じだ。自身の生活を充実させるためにすることなのだ。実りがあろうとなかろうと、相手がいようといまいと、それは二の次なのだ。そう思うと、少しだけ気持ちが軽くなり、すっきりしたようだった。それから、にっこりした。なんであれ、にっこりすると、気持ちが落ち着く。
一方もう一人のGは、ともかく今の仕事を最後までやり切ろうと思い定めた。それがいかにむづかしいことであるとしても、だ。彼は、そののんびりとして優しげな風貌とは別に、胸の奥には思いもかけないような激しく沸る気持ちを抱えていたのだった。人は、見かけ通りとは限らない、良くも悪くもだ。Gと同様にもう若くはないことも自覚していたので、半ばヤケクソのような気もしたが、どうでもいいと思うことにした。
それから顔を挙げると、拳を握りしめ、小さく良しと声に出した。そして、笑った。
いつだったか、新聞で読んだホスピスの医師の話によれば、途中までジタバタもがいていた人ほど最後は受け入れて安らかな気持ちで逝くというのだった。
自分が憧れるものになろうとする時、若くても歳をとっていても、それは関係がないことなのだ、と思うことにした。うまくいかなかったとしても、やらないよりはマシだ(たぶん)。
*
それからしばらくして、二人は会うことになった。久しぶりに、Gから届いたメールをもう一人のGが読んだのだった。
「やあ。久しぶり」
Gが声をかける。
「ああ」
Gが応じる。これまでと同じだった。変わるところがない。ただ、少し疲れているように見えた。
「どうしたっていうんだい?」
「ああ、すまなかったね、急に」
「驚いたけどね。ま、いいさ。どうせ暇なんだからね」
「そうか」
「で、何があった?」
Gが訊くと、
「うん、書けなくなっちまった」
Gが答えた。
「えっ」
ああ、短歌の方だったかと、Gは少し安心した。
「すっかりね。全然書けないんだよ」
「どうしてさ」
「書いても、みんな昔の焼き直しのような気がするんだよ」
「ふーん。でも読んでくれる人がたくさんいてくれるからいいじゃないか」
「ああ。でもね、……」
「でも?」
「裏切っているような気がしちまうんだよ」
「なるほどね」
「……。でもね、裏切られているんじゃないかという気がする時もある」
「なんでも書けばいんじゃないか」
「えっ」
「あ、でも、いでも、かでも。それがなんであれ、なんでも書けばいいんじゃないかのね」
志賀直哉だったかが、書けなくなったと言う作家に問われて答えていた場面を思い出したのだった。
「でもね、全く書けないんだよ」
「中身を考えるからそうなるんだよ、きっと」
「どういうことだい?」
「俺が言うのも変だけどね、書いた後に考えればいいんじゃないか。スコットランド出身の作家がそんなことを言っていたような気がするよ。それに、日本の作家も同じようなことを書いていた」
「あ。なるほどね」
「そうだよ」
「そう……。でもね、実は料理の方もスランプだ」
Gが呟くように言った。
「そうなのか。でも同じことだよ。作ってみればいいんだよ」
Gは、やっぱり同じように応じた。
「そうかもしれないね」
「うん、自分だけが食べるためのものでもさ。ところで、ビールでもどう?」
「えっ。うん、いいね」
Gが小さい声だったが、ようやく笑顔で応じた。
「そう。ビールを飲めば、なんとかなる」
「そうだね」
「そうさ。若かった時みたいにね」
「なるほどね。でも、若い頃を思い出すというのは、なんだか恥ずかしいね」
「ああ、そうさ。恥ずかしいことばかりだよ」
「今の若い人たちもそうなのかね?」
「どうだろうね。あんまり変わらないような気もするけどね」
「うん。でも、しっかりしているからね」
「そうだね。で、戻りたいと思うかい?」
Gが、真顔で尋ねた。
「えっ、若い頃にってこと?」
Gも、驚いたように聞き返す。
「そう」
「うん。やり直せるのならね」
「やり直せそうかい?」
「いや。むづかしそうだ」
「ま、それができれば、もう自分とは違う人間だってことかもしれないしね」
「確かにね。でも、消せるものなら消したいけどね」
「そうだよね。それに、今だってじゅうぶん恥ずかしいよ」
「そうなんだよ。それに、こないだなんかは、電車に乗ったら、座ろうとしていた若い外国人の青年がいたんだよ。その彼がね、僕を見るや否やすぐに立ってくれたんだよ。遠慮したんだけど、何度も勧めてくれるもんだから、最後は甘えることにした。帽子を被ってマスクをして、おまけにメガネもかけていても、年寄りだということがわかるのかね?」
「ああ、たぶんね。気持ちのいい若者もいるね」
「うん。そういえば建築をやっている友人に聞いたんだけどね、これまでの建築家の中で3本の指に入るほどの大家がね、面白い人と思われるより、いい人間でありたいと言ったそうだよ」
「そう。口に出して言うのは恥ずかしいけど、いい人になりたいね」
「そうだよ、やっぱりね。でも、やれやれだ。おまけに、世界はまた力の支配に逆戻りのようだし」
「ああ。自分のことだけ考えて、恥ずかしくもなんともないようだ」
「僕らが初めて会った頃と同じだ」
「進歩しないね。いったいどうしたんだろうね」
「なんとかならないものかね?」
「ねえ。ところで、ビールをもう一杯どう?」
「いいね。ビールを飲めばなんとかなる」
「うん、自分のことだけならね」
「そうさ。若かった時みたいにね」
そう言って、笑い合った(まあ、からりと晴れた笑いではなかったけれど)。
「そう。皆それぞれだとしても、だね」
「ああ、世界を救うことはできないけどね」
「確かにね。ありがとね」
「こちらこそね」
そう言いながら、新しいグラスを合わせた。
ひとまず、素描はおしまい。あとは手を入れながら、膨らませていくだけ(さて、うまくいくだろうか)。
今晩は、ビーチボーイズ三昧。ブライアン・ウィルソンが亡くなった(82歳だという)。まずは、レコードから。それから、名盤「ペット・サウンズ」、そしてCD3枚組のベスト盤を。
そのため、予定を早めて掲載することにします。
2025.06.14
FANTASY 38 GとGの物語のために(ふたりのGについての素描・1)
GとGの物語のために(ふたりのGについての素描)・前半
思いついた話を忘れないために、書き付けておくことにします。備忘録。完成させてからなんて言っていると、いつまでもちまちまと手を入れるだけだ(吉田秀和は、それが文章を書くことだと言っていたけれど、進まないのは困る)。無論、ここに掲載したとしても反応がないのは毎度のことなので、 ほったらかしにしないようにというためですね。時々(進展があれば)掲載するつもりでいるのですが……。
仲のいい2人のシェフ。一人は3つ星シェフ、もう一人は腕はたつが無名のシェフ。それに共通の知人がいる。
*
Gは、重苦しい雰囲気からようやく解放されて、半ば駆け出すようにして会場から出てきた。海のそばにある料理を教える学校の、入校式というのか、校長による永遠に続くのかと思うほどの長い訓示が終わったのだ。中庭のある小さな噴水のそばで、よく晴れた空を見上げると、両手を広げて、フーッと息をついた。とその時、声をかけるものがあった。そうして、Gともう一人のGが初めて会った。
「やあ。はじめまして、Gです」
Gが言った。ちょっと素気ないような言い方のようでもあった。少し緊張していたのかもしれない。背は高くないが少し太っていて、丸い顔の中の目が大きかった。
「どうも、僕はG」
もう一人が応えた。こちらはやや長身で、痩せていて、何もかもが細造りだった。
「えっ?ああ、そうだった」
驚いたGが言った。
「そうなんだよ。新入りは二人だけだというのにね」
二人の会話はこんなふうに始まった。
「ああ、そうだね。よろしくね」
「こちらこそ、よろしく」
「ところで、オタクは何が専門なの?」
緊張が解けたのか先ほどとはちょっと違って、少し粘り気のあるような声で、しかもそれまであんまり馴染みのないような言い方だった。ただ、何か他意があるようでもなかった。それで、すぐに聞き返した。
「フランス料理だよ。君は?」
「まあ、イタリア料理だね」
「ふうん。そうなんだ」
「でも、新人だからと言って、甘えは許さないぞという雰囲気だったね。なんだか大変なところに来たみたいだ」
Gが呟くように言った。短い間でも感じたことは、二人ともが同じようだった。
「ああ、浮かれてられないね」
Gも、真顔で答えた。
「うん」
「でも、きっと大丈夫だよ」
Gが言う。
「そうかな」
もう一人のGが、半信半疑で応じた。
「そうさ。そうに決まっている」
自分を励さないではいられないような調子だった。
「だったらいいけどね」
「そうだよね。ま、なんとかなるだろうささ」
少なくとも二人のGのうちの一人は、楽天的なたちのようだった。
「そうだね。そうあってほしいね」
「ああ。そうに決まっているさ」
そう言い交わしながら、二人ともが不安を隠せないでいたのだった。
そんなふうに初対面の挨拶を交わしていた時に、背後から女性の声がした。高い声だったが、耳障りで不快なというものではなかった。それよりも、どこかクールな響きが含まれているようだった。
「二人ともようこそ」
Gが振り返って見ると、若い女性で、痩せていたが、日に焼けて浅黒くなった顔の中の目が大きく開かれていて、こちらを見つめていた。
「やあ」
Gが言い、
「よろしく」
もう一人のGも言った。
「こちらこそ。よろしくお願いしますね」
助手だという彼女も、途中入社してからまだ2年も経っていないとのことだった。しばらくして、彼女は仕事に戻って行った。まだやることがあるのだ。
「ともかく、僕らは今日はこれで解放だね」
Gが心からホッとしたように言った。
「ああ」
「明日からが大変そうだけどね」
「まあね」
「じゃあよければ、まだ早いけど、ビールを1杯どう?」
Gが言った。
「うん、いいね」
Gが応じた。
程なくして、二人は近所の小さな店に入り、カウンターの前に席に座った。そして、グラスを合わせた。
「じゃあ、よろしく」
「こちらこそ」
「ふうーっ。うまいね」
「ああ。なんだか大丈夫なような気がしてきた」
「そうだね。ビールさえ飲めばね」
「ああ。ビールさえあれあば、なんとかなる」
*
それからは、二人のGは住まいも比較的近いこともあったせいか、互いをよく訪ね合い、話をし、そしてよく飲んだ。職場の愚痴も構わず口にした。定職に就くのは二人ともが初めてのことだったのだ。しかも、職場は年の離れた先輩が多く、なんとなく気詰まりだった。時々、助手の彼女も加わった。ただ、彼女の趣味は登山で、二人のGとは無縁のものだったから、その機会は少なかった。
それに、二人には、料理以外にも共通することがあった。イタリア料理のGは短歌を作っていたし、フランス料理のGは詩を書いていた。Gの短歌はもはや、素人の域を超えているようだった。新聞に載るは短歌誌の宣伝のところには、Gの名をよく目にしたのだ。それからしばらくして、洒落た装丁の歌集が届いた。
Gはもう一人のGの書いたものを読むと、俳句をやったらいいんじゃないかしらと言った。それはたぶん、その頃Gが書いていた詩は日常的な言葉を饒舌に並べ立てるようなものだったし(その時の気分を表すには疾走感が大事のような気がしていた)、それに対しもう一人のGの作るものはやや古風でたおやかな万葉調の和歌だったのだ。
時々、短歌や俳句のことについて話すこともあった。
「この頃の短歌には、日常語を使ったものが多いね」
「ああ、確かに。そうだね」
「だったら、散文詩や川柳を書けばいいんじゃないのかな」
「ああ。まあ、短歌には、俳句のように川柳に当たるものがないからね」
「なるほど。そうなんだね」
「ああ」
「多様性の時代の始まりってことかな」
「まあね。そうかもね。でも、あなただってごくふつうの日常語を使って書いているでしょう」
「そうだね、しかも長い。でも、散文詩だからね、一応」
「ねえ、まだ早いけど、一杯やるのはどう?」
「いいね」
店に入ると、二人はグラスを合わせた。
「あの子がいたらいいのにね」
Gが言うと、
「そうだね」
もう一人のGが答えた。
「でもいないね」
「確かにね」
「なんだかつまらないね」
「まあね。ビールをもう一杯どう?」
「いいね」
「これで、なんとか凌げるんじゃないか?」
「まあね」
「でもね……?」
「うん。でもね……」
*
やがて数年が経つと、イタリア料理のGは母校に移って行った。それで、住まいも遠くなった。しかし、それからもごくたまにだったが、二人は会うことをやめなかった。
その頃には、Gはすでにイタリア料理界で一目置かれる存在になっていた。もう一方のGはさほど変わらないままだった。なんとかやってはきたものの、パッとしない。何をやっても、中途半端のようだった。それで、なんだか一人だけ取り残されたような気がすることがあったのだ。Gのことを羨ましいと思う気持ちもなかったわけではなかったが、それでも一旦顔を合わせたらそのことは全く気にならなかった。二人ともが、つゆほども気にしていないようだった。
さらに時が経って(時が経つのは本当に早い)、Gが彼らの業界で頂点と目される賞を獲得した時も、Gは心から祝福した。Gも屈託なくそれを受け入れた。
その時は、もう一人の同僚だった女性と3人で、祝賀会のようなものを開いた。会場の手配も日程の調整も、すべて彼女がやってくれた。当日、2人と会うのはいつしか5年とか10年振り、あるいはそれ以上だったかもしれないくらいになっていた。それでも、顔を合わせたら、それまでに過ぎ去っていた夥しい時間はあっという間に消え失せて、不安と希望に満ちていながらもすっきりと晴れ渡った青空を見ることの多かったあの頃に戻った。皆が年も取っていたし、職場も違っていたが、三人の気持ちは昔のままだった。Gはいい気分だった。それから、三人で中華街の台湾料理を堪能したのだった。
それで思い出したのか、彼女が突然言った。
「そう言えば、カラオケにも行ったわよね」
「ああ。嫌がっている奴がいて大変だった」
「そうそう」
「そうだね。1度だけね」
Gも思い出したのだった。あんまり嬉しい思い出ではなかったが。
*
「せっかくここまで来たんだから、1曲くらい歌いなさいよ」
「そうだよ」「そうだね。でも、やっぱり遠慮しとくよ」
「どうしてさ」
「いいかげん男らしく、覚悟を決めて歌いなさい」
珍しく、有無を言わせないような、キッパリとした言い方だった。
「そうだ。そうだ」
もう酔いが回っているようだったGが、はやし立てた。
で、Gは、仕方なく歌うことにした。流行りの歌は、下手さがバレるような気がしたので、子守唄を歌うことにした。時々、浴室で歌うことがあったのだ。それに、新しいものは教室の中で十分だと感じていた。「島原の子守唄」だったような気がする。もしかしたら「五木の子守唄」だったかもしれない。二人におだてられて、ついもう1曲歌ったのだろうか。
若い頃を思い出すと、こんなこともある。若いというのは、恥ずかしさや後悔を超えることができる時代なのだ。それにしても、後から思い出すことといえば、愚かしいことばかりのような気がするのは、どうしてだろう。(前半終わり。後半に続きます)
2025.06.08
FANTASY 37 新年度直前臨時増刊号・2「デザイン事務所シリーズ第2部 もう一つパイロット版」
デザイン事務所の日常と探求 もう一つパイロット版(後編)
*
すると、今度はCが不意に切り出した。なんだか暗い表情を浮かべている。もしかして、また?とAは心配になった。
「課題が出ると、どこから手をつけていいのか、わからなくなるんです」
Cが、切り出したのだった。
「どういうこと?」
Aが、ちょっと安心しながら訊いた。なんと言ったって、あの時のような辛いことではないらしい。
「好きな住宅やインテリアのデザインはあるんです。だけど、……」
「うん」
「いざ自分でデザインしようとすると、何から手をつけていいものか、わからなくなってしまうんです」
「なるほどね」
Aは、在職時にずっと慣れ親しんできた悩みを久しぶりに聞いて、うなづいた。
「自分の好きなようにデザインするだけじゃダメですよね?」
Cが、また呟くように訊いた。
「まあ、課題のテーマに沿ってなくっちゃね」
「ええ。それに、オリジナリティーも、ですよね?」
Aは、ああやっぱりねと思いながら、訊き返したのだった。
「ところで、お前さんは好きなデザインや憧れるような日常の生活があるんだよな?」
「はい」
「じゃあ、課題に対してもそれを大事にして取り組めばいいんじゃないか」
「はあ。それじゃあつまらないものになりそうです」
「どうして?」
「だって、私の憧れる生活は、他の多くの人とあんまり変わらないし平凡なんですもの」
「もっとシンプルに考えてみるのさ」
Aはできるだけさりげない口調で言おうとした。彼女や彼らは、急ぎすぎているのだ。すぐにオリジナルなものを作り出さなくてはいけないという思い、半ば強迫観念のようなものに囚われているのだ。それは、たぶん教員の側に大半の責任がある、とAは考えていた。彼らは、知らず知らずのうちに、自身の優位性を示そうとして、必要以上に複雑な表現で言ったり、むづかしいことを要求するのだ。だから、彼はよけいに理念じゃなくて、まずは小さな種であっても自分自身の思いから出発するのがいいと伝えよう、と考えるようになっていたのだった。それを育てることで、大きな木に育つのだ。
「え、どういうことですか?」
「お前さんたちは、なんだか理念ばかりが先行しているように思うんだよな」
「えっ?」
Cがなんのことだというふうな顔をした。
「課題で示された住まい手の行動を、具体的に想像してみたらいいんじゃないのかね。性格やら嗜好なんかを含めてね」
「たとえばどんなふうに?」
「簡単なことだよ。それだって、まずは自分や自分が知っている人のことを思い出すといい」
「えっ?」
「お前さんは、食事も勉強も何もかもたいていのことはテーブルの上でやると言っていたよね」
「ええ」
「だったら、テーブルはどんなものがいい?」
「ちょっと大きめのほうがいいかな」
「そうだよね」
「でも、当たり前すぎませんか?」
「そんなことはないさ。当たり前ということは、多くの人が大事だと思うってことだろ?」
「ええ、確かに。他には?」
「ちょっとしたもの、たとえばティッシュだとか雑誌だとか、を置いておけると便利かも」
「じゃあ、テーブルの下に一枚板を取り付けて、棚のように使うっていうのは?」
「あ、いいですね」
「よく、新聞やらテレビのリモコンやらを置いておくスペースとして作ることがあるよ」
「へえ」
「俺なら、それを少し奥に入れるほうがいいと思うね」
「えっ、どうしてですか?」
「目に入りにくいし、膝もぶつかりにくい」
「なるほど」
「そんなふうに1日の生活を想像しながら、少しずつ自分らしい工夫をしていけばいいんじゃないか」
「ええ、他にはどんな?」
「それはご自分で。課題の住まい手が自分の年齢と違うような場合は、自分が知っている似たような年齢の人たちを思い浮かべながら、考えるのもいいかもね」
「はい」
「ともかく、あまり抽象的にならないようにするのがいい、と思うね。なんといっても、具体的な経験から始めるのがいい。君たちは、理念がずいぶん好きなようだけどね」
「ええ、確かに。でもそれでいいんですかね?」
「えっ?」
「コンセプトはって、必ず訊かれるんですよね」
「まあね。でも、それはできた後から考えればいいんじゃないか」
「ふーん。でも、課題の途中でも聞かれるし、どんなコンセプトで始めたのかと聞かれることもありますよ。いいんですか?」
「構いやしないさ。その時は、時々の想いを伝えておけばいいし、必要なら、なんとなく初めからそういう思いもありましたぐらいでどうだい?だって、発表の時のコンセプトといっても、自分の案を説明するためのものだろ?」
「ええ」
「だったら、なんの問題もないんじゃないか」
「ああ、そうか。そうですよね」
Cが、少し安心したように言った。
「始めは、ただの思いつきでいいさ。始める取っ掛かりにすぎないんだから」
「はあ?」
「それを育てていけばいいのさ。少しずつね。その過程では、時々の想いを伝えればいい」
「じゃあ、出発点と終点が違った方向になったとしても、いいんですよね」
「ああ。全然かまわない」
「はい」
Cの顔が少し明るくなったようだった。
「それから、なんだか決まり事のようなことってありますよね?」
「なんだい。例えば?」
「リビングルームにはソファを置かなくちゃいけない、とか」
「ああ。ソファは置かない代わりに、こんなふうに過ごしますということが示すことができればいいんじゃないかと思うけどね」
「でも、必ず置くようにと言われた場合には?」
「うーむ。たいてい、そう言われるよな。それでも置かないというのが認められないのなら、コンパクトなソファベッドをおいて、来客用にも使えるようにするとか」
「臨機応変?」
「そう、臨機応変に。やりながら考えるんだよ」
「はい」
「ま、他にもいろいろあるけどね」
「はあ」
*
その時ドアを叩く音がして、誰かが入ってきようだった。誰かとみれば、Bだった。ずいぶんご無沙汰だったし、予想もしていなかったけれど、折良くやって来てくれた、とAは思った。
「こんにちは」
Bが声をかけると、Aもすぐに応じた。
「おお、こんにちは」
「お久しぶりです」
「やあ、ようこそ。今日はどうして?」
「たまたま、時間がちょっとできたんです。ずっと、来なくちゃと思っていたんですが、なかなか……」
「そうなんだ」
「でも、あんまり時間がないので、お昼ご飯用にお惣菜を買ってきました」
「えっ?」
「カフェに、お惣菜というのはどうかとも思ったんですけどね。時間があんまりないんです」
「ふーん。そうなんだ」
「ずっとご無沙汰していたので、今日こそと思ったんです」
「へえ。ありがとう」
そんなやりとりをしていると、片付けを終えたCがやって来て挨拶をした。
「こんにちは」
「あ、この人は、いまうちで働いてくれているCさん。インテリアを勉強している学生だよ」
「よろしくお願いします」
「こんにちは。よろしく」
ひととおり挨拶が済むと、AがCに言った。
「じゃあ、この人のお昼ご飯用のお惣菜を用意してくれるかな」
「はい。わかりました」
そう言って、Cはカウンターの中へ入って行った。
「よく来てくれたけど、そんなに時間がない?」
「ええ。はい」
*
「これでいいですか?」
しばらくして、Cがトレイにお惣菜とお茶と箸を載せて持って来た。
「……」
「……」
それを見た2人ともが、黙ってしまった。
「えっ、嫌だ。どうかしましたか?」
Cが訊いた。
「……」
「うーむ」
「おいしそうに見えるかい?」
Aが言った。
「ええ、まあ。買って来たお惣菜ですから」
「まあ、そうだけれど」
「なんか間違いましたか、私?」
「同じものでも、できるだけおいしそうに食べたいよね?」
「ええ」
「としたら、もうちょっと工夫ができるかもね」
状況を察したBが付け加えた。
「えっ?」
Cはすっかり困惑しているようだった。
「ちょっと待ってね。そのくらいの時間はあるでしょう?」
「ええ」
そう答えたBは、Aが離れた後、Cに何か話しかけているようだった。
「さっき、Aさんに聞いたんだけど……」
うまくいきそうだと、Aは思った。
*
「待たせたね」
Aは、お惣菜をもともと入っていた容器からお皿に移し替えたものを、運んで来た。
「ありがとうございます」
Bが礼を言いながら、箸を取った。
「へえ」
Cが、ちょっと驚いたような表情をしていた。
「どう?」
「おいしそうです」
「さっきより?」
「ええ。うんと」
「よかった。」
「同じものだけどね。それでも、器に盛り付けただけで違うということだよね?」
「はい」
「それに、それ以上に、供する人の気持ちが伝わって嬉しいということじゃないかな」
「はい」
「同じものでも、おいしく食べてもらおうという気持ちがあるかどうかってことだね」
「ああ、そうなんですね。確かにそうだ」
「インテリアもこれと同じことかも」
「えっ、どういうことですか?」
「人をもてなす心が必要だということかな」
「喜ばせたり、驚かせたりね」
「美の神は細部に宿るというけど、それと同じことかもしれない」
「ま、気持ちだけじゃどうにもならないってこともあるけどね」
「ふーん。確かに」
「でも、気持ちがなければ始まらない」
「ええ。そうですね」
Cが答えた。
「何事もね」
「それに、さっき言いかけたことだけれど、もしかして、きみがもうデザインの専門家のつもりでいたいのなら、歴史的な視点が不可欠だろうけどね」
Aが思い出して切り出すと、
「そんなにむづかしく言わなくても、課題と似たような条件で作られてきたものを真似することから始めるのもいいかもしれないですよね。それから、当時と今を比較しながらね。歴史的な視点で振り返りながら、これからの時代にとって相応しいものはって考えてもいいね」
Bが補足するように言った後、すぐに続けた。
「でもね」
「でもねって?」
「まあ、そういう歴史的視点は最も大事なものの一つだと思うけれど、そうしたものは、もっと後からでもいいんじゃないかって気がしますね」
「そうね」
「はあ、なるほど」
Cが呟いた。
*
「じゃあ、これで失礼します」
Bが言うと、Cが少し大きな声で言った。
「また来てくださいね」
「ああ、また話せたらいいけどね。……」
そう言うと、Bは急いで店を出て行き、振り向くことなく声をかけた。
「あ、これからもしっかりやってね」
「ありがとうよ。でも頑張れるかなあ」
Aがそう応えると、
「いや、……」
Bが振り返りながら言ったが、Aにはよく聞こえなかった。
(終わり)
2025.03.31
FANTASY 36 新年度直前臨時増刊号「デザイン事務所シリーズ第2部 もう一つパイロット版」
デザイン事務所の日常と探求 もう一つパイロット版(前編)
*
このところの天気はいかにも春に近づく頃にふさわしく、安定しなかった。好天続きだった冬に比べると、違いがよりいっそう明確になったようだった。先人が言ったように、春に3日の晴れなし(あるいは、三寒四温か。とすれば、まだ冬だったのか)。
Aが一時体調を崩して、何日ぶり家に店を開けた時、予想以上にお客の数は少なかった。天気のこともあるには違いないが、やっぱり、不定期に開け閉めしたら、てきめんに悪影響がでるのだ。これに限らず、たいていのことが習慣というか定期的であることが肝心なのだということを、改めて思い知らされたようだった。。
そこでランチの客があっという間にいなくなった後、Aがぽつりと言った。
「こないだ、読者がいないようなブログをどうして書き続けるんですか、と聞いたことがあったろ?」
「えっ」
「言ったよな?」
Aが、また訊いた。すると、Cがムキになったように反応した。
「誰も読まないなんて言いませんよう」
するとAが、
「そうだったか?でも、なぜ、書いているんですか、と訊いたよな?」
それをやり過ごすかのように、繰り返し訊き直したのだ。
「ええ。自分も何かできるということを証明したい、というようなことでしたよね」
今度はCも、素直に応じた。
「ああ、確かにそう言った。でもな、……」
「でも?」
今度はCが訊いた。と、Aは直接答えることはせずに、
「ああ」
軽く肯定するように言ったのだった。
「どうしたんですか、違うんですか?」
「違うというわけじゃないが、正確じゃなかった」
と、Cが、
「どういうことですか?」
畳み掛けるように訊いた。
「確かに、誰かが喜んでくれると嬉しい、それはそうなんだけれど、どうも一番は自分が嬉しいと思いたいみたいなんだよ」
Aが恥じるかのように言うと、
「なあんだ、そんなことですか」
Cが拍子抜けしたかのように言ったのだ。
「なあんだ、とはなんだよ」
Aが言うと、
「だって、そんなこと、当たり前じゃないですか」
Cは、あっけらかんと言い放った。それにかまわずAが、
「もしかしたら、名誉欲なのかと思ったんだよ」
自身に言い聞かせるかのように言うと、
「はい」
と、Cは素直に応じた。
「そうじゃないんだと思いたいけど、自分が嬉しいと思いたいというのは、誰かが楽しんでくれているということを実感したい、ということでもあるわけだけれど、もっとありていに言うなら誰かに褒められたい、認められたいというのがやっぱりいちばんのようなんだよ」
「へえ、そうなんですか?」
Cがふーんとでも言うように、言った。
「ああ、恥ずかしいけどね。こないだ気付かされたんだよ」
「しごく当たり前のような気がしますけどね」
「ま、そうだろうよ。若ければそうさ」
「はい」
「年をとってみなくちゃわからない」
「へえ」
「俺も、かつてはそう思っていたんだけどね」
「ふーん」
「まあ、気にすることはないさ」
「……」
*
Aはある時、確かに改めて気づかされたような気がした出来事があったのだ。そのことを思い出したのだった。
このところずっと、カフェ以外で人と会うことが減っていることはすでに自覚していた。新しく体験するということがない、いや、残念な体験は日々事欠かないのに、新しくて嬉しい経験というものがなかなかないのだ。たとえば、手元にメールはまだ届くが、ほとんどはAmazonやらなにやら、通販サイトのものだ。そのほかのものは滅多にない。
届いたメールの中に、珍しくふだんとは違うアドレス、懐かしいアドレスのメールがあった。元の職場の同僚からのものだった。どうしたのかと思いながら開いてみると、彼が2人の共通の先輩とメールをやり取りした時に、久しぶりに会食でもしようということになったというので、その誘いを寄こしてくれたのだった。
その先輩というのは、2人にとっての元の上司で、Aもごく稀にメールをしていた。賀状の交換をした時には気候が良くなったら一緒にお寺にも行こうと誘われていたのが、ふっつりと途絶えたままになっていた。ある時に、体調を崩されているようですという話を聞いたのだったが、ちょうどほぼ時期を同じくして、Aも体調が芳しくない時があった。
最寄りの駅からはバスも出ていてお店のすぐ前に停留所があるということだったが、歩いても10分足らずというので歩いて行くことにした。急ぐこともない、十分に時間的な余裕はあるし、気持ちを落ち着かせるためにもそうするのが良さそうだった。何しろ、もう何年も会っていないのだ。
旧道の両脇にはお店が立ち並んでいたが、駅から遠ざかるにつれてだんだんその数が減って行った。たぶん利便性の面で不利なのだろう。この頃はなんでも、便利で効率的であることが求められるのだ。さらに歩みを進めて行くと、2階建ての和風の建物に敷設された看板が見えた。和食店だったのだが、いかにも新しそうで、趣があるとは言い難かった。しかし、気取らない普段使いの店では、そうしたことが求められるのかもしれない。
Aが着いたのは開店時刻の5時ちょうどだったが、暖簾はもう掛かっていたので、引き戸を開けて店に入ることにした。すると、すぐに「いらっしゃいませ」という声がかかった。Aが予約してある旨を告げると、奥の席に通された。ちょっと残念な気がしたのは、狭いのはいいとしても、新しくてきれいだがいかにも新建材を使ったピカピカの作りに見えたし、おまけに明るすぎるようだった。
Aはとりあえず手前の席に座ることにして、奥側の席を先輩の席とするよう、すでに置かれていた箸や手塩皿を並べ替えることにした。並べ替えたところで、後ろからこんにちはという声がかかった。今日の席を設けてくれた後輩だ。彼は、Aよりも少し年下で2年ほど遅れてやってきたのだったが、まだ元の職場に在籍している。
「お、お早いですね。お久しぶりです」
後輩が言った。
「やあ。お久しぶり。元気そうだね」
と、Aも応じた。
「ええ、まあ。でも、そうでもなかったんですけどね」
「ふーん。相変わらず忙しいの?」
Aが訊いた。彼はいつも忙しそうにしていたのだ。
「ええ。今も会議に出なくてはいけませんから」
「へえ」
「色々と変わりつつあります」
彼が少しばかり残念そうに言った。
「うん」
「親睦会も、別々にやるようになりました」
「ふーん」
「一つの学科が、場所も違うようになったので、独自にやりたいとい言い始めたんです」
「ああ」
そうなることは、Aにもなんとなく予想がついていたことだった。遠くの身内より近くの他人、というわけだ。残念なような気もしたが、何れにしてももう彼とは関係のないことだった。
それから間もなくして、扉が開く音がして、懐かしい声が聞こえた。大きくはないけれど、太い声だ。
「よお。こんばんは。待たせたね」
振り向くと、ニット帽をかぶった先輩がいた。在職中は白衣かスーツ姿だったから、Aはちょっと不思議な気がした。
「こんばんは」
「お久しぶりです。奥へどうぞ」
「お元気そうですね」
「いやそうでもないよ」
「はい。なんとなくは聞いていました」
「君はどう?」
「実は、僕もあんまり」
ちょうど同じ頃、Aも体調が万全でなく、連絡することができなかったのだ。
「へえ。君は」
「やっぱり先輩方と同じです。短い間ですが入院しました」
こんなふうに会話はいたってスムーズに進んだが、歳をとると経験することはたいてい同じようだった。どうしてだか、若い頃は考えもしなかったようなことを経験するようになるのだ。
それからは、思い出話が続いた。
夏休みの終わりのころ、伊豆の山中の施設で「リトリート」と称する2泊3日の合宿があった。
その時にも歌ったのが、頌栄541番。
「僕はね、この頃どういうわけか頌栄451番を歌うようになった」
Aが言うと、
「いや、541番ですね」
と、すかさず訂正された。
「あ、そうだった」
「よく覚えているんだよ、彼は。おんなじだね」
すかさず、先輩が言った。
おんなじというのは、大先輩というか元の学長だったが、恐ろしく記憶力が良くて、時々食事を共にしたりすると、必ず「あの時は……」、「何年にはこんなことが……」等々、自身が成したことをよく聞かされたのだった。
そのびっしりと並べられた予定にがんじがらめにされて辛かった合宿から戻ると、必ず大相撲を男4人で見た。ちょうど、そう言う時期だったのだ。そしてたわいのない話をしながら、当然のことながら中には愚痴めいたものもあったがそうして、ストレスを発散させていたのだ。その職場は、当時には珍しく女性たちが牛耳っていた(ま、それを束ねていたのは元の学長だったが、それでもなかなか苦労したらしい)。そのこともあったかもしれない。
それから、話は現在の職場のありように移った。
「忙しくなりましたね」
まだ現役で働いている後輩が言った。
「まあ、そうだろうね」
先輩が言った。
「昔は4学科が協力していたからね」
Aも続いた。
「ええ」
「さっきも話していたんですが、親睦会も別々にやるようになりました」
後輩が言った。
「そう」
先輩が、さもありなんといったように応じた。彼もたぶん予見していたのだろう、それきり黙った。彼は退職する時に、もうこことは関係ない、どうなろうと気にしないよ、どうすることもできないしね、と言っていたのだ。組織改革に伴い生まれた新しい学部が、やがて分かれて、それでもしばらくの間あった緩やかな横のつながりが今や消えつつあるのだった。
「残念ですけどね」
その時、Aは不意にその分岐点となった会議を思い出したのだった。 そして、我知らず気色ばんだのだった。
「あの時は、無茶苦茶な会議の連続だった」
最初は静かに切り出した。
「ええ」
その際には、後輩もAと同じような対応をしていたのだ。
「一旦決まったことを蒸し返し、のらりくらりと玉虫の結論に持ち込む、その後会議を何回か重ねて最終的には、結局自分のいいようにしたんだ。卑劣で狡猾なやり方だった。ま、自分のところは安泰となってよかったに違いないだろうけど。許したくないね。顔を合わせるのだって嫌だ」
Aが一気に言うと、2人ともが黙った。彼らはそのことに与していたわけではなかったが、その独立した学科の出身、所属だった。
「……」
「……」
それからAは不意に我に返った。どうしたことだろう。これほどまでに、怒りを抱えていたとは。他の2人は、意に介さないように振る舞った。
おかげで、また元の楽しい会話に戻ることができた。次々に出てくる料理の中にはAが苦手なものもあったが、最後の方に出てきたコハダの鮨は小ぶりで美しく、おいしかった。
「今度、お寺にでも行こう。最近は、たいていお寺巡りの日々だよ」
先輩が言った。
「ええ」
「はい」
Aも後輩も、同じように答えた。
「お一人で?」
Aが訊いた。いかにも彼らしいという気もしたけれど、にわかには信じ難い気もした。以前は、よく夫婦で車で旅行していた様子を聞いていたのだった。
「ああ。1人がいいよ」
「寂しくないですか」
「ああ、全然。もう気になることはなにもない」
先輩は、さっぱりとした口調で言ったのだった。
「それは、きっと成し遂げたっていう気持ちがあるからでしょうね?」
Aは、にわかには信じられない気持ちと羨ましい気持ちがないまぜになったような気分で、訊いた。
「そんなことはないよ」
「職場のことやら、研究やら、海外での活動やら。きっと、誰かのために役に立つことができたという実感があるせいじゃないですか?」
彼は、発展途上国の貧しい農民のために、キノコの栽培技術を教える取り組みをした。
「いやいや。そんなことはないよ」
「あるに決まっている。だってそうでしょう?」
Aは自身のことを思いながら、言った。少し酔っていたのかもしれなかった。すると、先輩はまたさらりと言ったのだ。
「いや、みんな自分のためにやっていたことだよ」
在職時の時から変わらない言い方だった。
それからも、またしばらく楽しい会話が続いた。
翌朝、Aはなんとなく昨晩のことを思い出し、反省しながら起きてみると、ちょっと飲みすぎたようだった。そして、頭と額の境目辺りが痛かった。きっと、罰なのだと思った。
Aは2人に謝罪のメールを送ったが、2人ともから、気にしないでください、人間だもの、という返信が送られてきた。
それから、Aは不意に気づいた。結局のところ、昨晩のことは当時も今も自身が1個の人間として自立していないということなのだ。
そんなことがあって、Aは自分から話す気になったのだった。繕うことのない、本当に思っている気持ちを正直に話すのがいいような気がした。そうしないと、平穏な気持ちにはなれないし、先日の会合の時のようにいつか爆発してしまいそうな気がしたのだ。
(続きます)
2025.03.30
FANTASY 35 「デザイン事務所シリーズ第2部 パイロット版」
はじめてみないことには、先へ進めない。
デザイン事務所の日常と探求 パイロット版(後編)
*
Cがまたカフェにやってくるようになってから、しばらくの間は、2人ともがなんとなくよそよそしいというか、話すことといえば当たり障りのないものだけだった。それまでのことをやっぱりお互いに意識していて、Aは努めてなんでもない風を装おうとしたが、実際には腫れ物に触るような心地だった。そんなある日、
「この前はすみませんでした」
Cがうつむいたまま、小さな声で切り出した。
「え、なんのこと?」
Aはハッとしたが、とぼけて言った。
「養子にしてくださいって、言った時のことです」
「ああ」
なんといえば言えばいいのかわからないまま、Aは曖昧に返事をした。
「どうかしてたんです」
「そうか」
「ずっとひとりぼっちなんだと思ったら、怖くなって……」
Cはそう言うと、また黙った。
「ああ」
それから、Cは小さいけれどしっかりした声で
「でも、一人じゃない」
と言うと、Aの顔を見てはっきりと宣言したのだった。
「周りに助けてくれる人がいる、ってことがわかったんです」
「そうなのか」
Aはほっとしながらも、未だ戸惑うような気持ちだった。
「ええ。だから安心してください」
Cがきっぱり言うと、Aはなぜか、驚いたかのように間の抜けた返事をした。
「えっ」
するとCは、Aの目をしっかりと見ながら、宣言したのだった。
「もう、養子にしてくださいって、言いませんから」
「うん」
Aは安心したものの、ちょっと寂しい気がしたようだったが、それでも、またそう言われるのも困ると思うと、ふっと笑って、軽いため息をついた。何しろ、こうした状況に慣れていなくて、どういうふうに対応すれば良いのか、全くわからなかったのだ。今まで何をしてきたのだろうと思うと、
「やれやれ」
とつい口に出た。すかさず、これを聞きつけた Cが、訊いた。
「えっ?」
「なんでもないよ。お前さんのことじゃない」
Aは、あわててそう言うと、また軽くため息をついた。
Aは、Cが帰った後も一人店に残って細々とした仕事を片付けると時々、ターンテーブルにレコードを載せてから、とっておきのスコッチを一杯やるようになっていた。その日は、16年もののラガーヴリンかグレンリベットの18年のどちらにしようか迷ったけれど、まろやかなグレンリベットをこれまた滅多に使うことがなくなっていたバカラのグラスに注ぐと、冷えた水を少しだけ足した。
静かなピアノ・トリオのライブ演奏を聴きながら、その日のこと、それからこれまでのことを思った。やっぱり、小さく笑って、ため息をついた。歳をとったものの、その時間に見合うだけ成長し、成熟したとは言い難い。人も、手をかけないと古びるだけで、上等のウィスキーやチーズのようには成熟できないのだ。
*
AとCはすっかり以前の関係に戻ったようだった。カフェも、なんとなく明るい雰囲気が増したようだった。
それ以来、AとCは店が暇なときに、デザインの話をするようになった。事務所は相変わらず仕事が来ないままだったし、カフェの方は逆に結構お客が入っていたので、カフェの営業日を1日増やしたのだ。そのため、Cが事務所に来る機会がほとんど無くなったのだ。その代わりに、カフェでデザインについての話をするようになったというわけだった。なんと言っても、もともとCはデザインの勉強をしたいと言って、やってきたのだったのだ。
昼の忙しさが落ち着いてお客がほとんどいなくなった頃、Cが独り言のように言った。
「やっぱり違うなあ。どうしてなのかなあ」
「えっ?」
聞きつけたAが応じた。すると、Cが訊いた。
「事務所もそうですけど、お店の棚に脚があるのはどうしてですか?」
「ああ、よく気がついたね。確かに目に見えるところの棚は基本的には脚付きだよな」
「はい。でも、ふだん見慣れているのは脚がない気がするんですけど」
Cがさらに言う。
「そうだね。ふつうは台輪という長い帯状の板が張られているね」
「へえ。どうして?」
Cはさらに興味を持ったようだった。不思議そうに言った。
「第1には、床と開閉部分の間を確保するためだね。これは脚も同じ」
「はあ」
「そうしないと扉や引き出しが床とこすれたり、場合によっては引っかかって開かなくなる時もある。それに、足をぶつけたり、カーペットが敷けなくなったりすることだって」
「じゃあどうして、台輪をつけずに脚をつけたんですか?」
Cが訊いたが、Aはこれを好ましく思った。今時の若者の多くは答えを求めるだけで、理由を知ろうとはしない。それで、逆に訊くことにした。
「なぜだと思う?」
すぐに答えを教えるというのではなく、まだ自覚されていないCの考えを引き出そうとしたのだ。そうすることが教育的だと思っていたのだったが、もしかしたら、断言するだけの自信がないだけということかもしれない。
「さあ?」
「見たときの印象は?」
「うーん。脚付きの方が、軽やかかな」
Cが恐る恐るという感じで答えた。
「うん。そうだろう?一方、台輪の方は安定感があると言えるかもね」
「はい。でもみんなは軽やかさよりも安定感が好きってことなのかなあ?」
「どう思う?」
Aは、さらに訊く。
「そうじゃない、というか軽快さが好きな人も多いと思うけどなあ」
「そうだよな。でも、脚付きは少ない」
「うーん」
「その他には、床が見える面積が広いほど広がり感が出る」
「そうなんですね。いいことばかりのようですけど……。でも、少ないですよね」
「なぜだと思う?」
「えーっと……。あ、掃除がしにくいとか?」
「そうそう、それだよ。少なくともそれが一つ、大きいと思うんだよな」
「はい」
Cが、嬉しそうにうなづいた。少なくとも、そんなことなら、早く教えてくださいよとは言わなかった。
そこで、Aはまた別のことについて話しはじめた。
「ついでに言えば、家具の上の方にも横長の板があるね。あれは幕板というんだけどね」
「はい」
「あれもない方がスッキリ見えると思うんだよな」
「ええ」
「でも、ほとんどが幕板をつける」
「やっぱり掃除?」
Cも、自分の考えを口にすることを躊躇わなくなったようだった。
「面倒なことはできるだけ少ない方がいい、ってことだな」
「まあ、そうですかね」
「でも、気持ち良さはどうなんだ、ってことも考えて欲しいね」
「はい」
「ただね、いい面があれば悪いこともあるというのが物事の一般的な性質だから、どっちを取るかってことだけどね」
Aは、断定的になることを恐れて、急いで付け加えた。
「ええ。楽だけどつまらないか、手間がかかるけど楽しいってことですか?」
Cがまた訊く。
「まあね。そのバランスのどの辺りで折り合うかということだろうと思うがね」
「はい」
「たいていのことには、絶対という正解はないんじゃないか?たとえば、幕板の場合は。高さを低くするとか、少し奥の方につけるとか、工夫の仕方はいろいろありそうだけれどね」
「はい」
「そうすると、バランスで判断するとか、長所と短所のどちらを優先するかということで決めるってことになるよね」
「ええ」
「だから、どっちが正しいってことでもないんだよね。人によっては、煮え切らない態度だと言うかもしれないけどね」
「はい」
「だから自分の好きなことを明確にして、それを大事にすることが重要と思うんだよな」
「はい。そうですね」
「そうさ。お前さんはまだ若いしね」
「ええ」
Cがあっさり認めたが、Aは、Cがもうおばさんですなどと言わないところが好ましいと思った。彼がまだ勤めていた頃には、そういう言い方をたくさん聞いていたのだ。しかし、口に出すことはしなかった。
「そうだよ。ただ、頑なにならないように気をつけなくちゃいけない」
Aは、できるだけあかるい口調になるよう努めた。
「はい」
「ま、頑張りなさいよ」
「はい」
ちょうどその時に、お客から声がかかった。切り上げどきだ。Aは話が長くなり始めると、説経めくことを自覚していたのだ。それで、客の方に返事をすると、Cの方を向いて言った。
「そう、そう。それが一番」
「わかりました」
Cも素直に答えた。
*
また別のある日、店じまいの片付けをしている時に、Cが問いかけた。
「センセイは退職してからも、事務所をやったり、ブログを書いたりするのはどうして?」
「ああ、そのことね。実は長いこと自分でもよくわかっていなかった」
Aが正直に答えた。ある時は、卒業生にまだやってんのと呆れられたこともあったし、書くものに対してはほとんど何の反応もないのに、なぜ続けているのか自分でもよくわからなかったのだ。すると、
「えっ、そうなんですか?」
Cは、驚いたようだった。
「そう。でもね、こないだようやくわかった気がした」
Aは、その時のことを思い出しながら、言った。
「へえ。どうして?」
「インターネットである出版社が、書いたものを講評してくれるというのを見て、応募してみたんだよ」
「ふーん」
「ああ。しばらくして、返ってきた」
「はい」
「開けてみると、甘口の講評と自費出版へ誘うようなことが書いてあった」
「へえ、そうだったんだ」
「でも、甘口でも、あらためて読んだらそれなりに役に立った。やっぱり、他者の目が大事なんだ」
「はい。それで?」
Cが促した。
「翌日に、電話がかかってきて、何のために書いているのかとか、コンテストには応募しているのかとを聞いて、まあこっちはおざなりだったけどね、それから自費出版のことを匂わせた、というかかなりはっきり口にしたんだ」
「はい。それで?」
「コンテストに応募してもかすりもしないということと、誰も面白いと思ってくれないようなものを自費出版するなんて考えられない、と言った」
「はあ」
Cは、よくわからいと言うように応じた。
「すると、是非頑張ってくださいと言いながら、あっさり切られた」
「へえ」
「その時、思ったんだよ。なんだか悔しいなと。なんとか見返してやりたいなと。今思い返すならば、なんだか子供っぽいような気もするけどね……。ともかくも、それでわかったんだ、ああ俺にもできることがある……、一つくらいは取り柄があることを証明したいんだなって。自分で確認、と言うか確信できればいいんだけれど、それは自分ではわからないからね。変だと思うだろ?」
「いえ。なるほど、そうだったんですね」
その時に感じたことを、改めて思い起こした。
「もしかしたら、ただ誰かに認めてもらいたいというだけのことなのかもしれない……」
Aはそこで言葉を切って、しばらくしてからまた続けた。
「ま、いずれにしてもお前さんたちにはわからないだろうけどね」
Aが諦めたような口ぶりだった。するとCが、
「えっ、わかりますよう」
と、ややふくれるように反論したのだった。
「たぶん、わからないね。だって、お前さんくらいの歳の時は、なんだってできる、手に入れられるような気がしてるだろ?」
Aはそれまで、傲慢とも言えるほどに自身の可能性を信じているように振る舞う若者を
たくさん見てきたのだ。
「そんなことはありませんよ。逆に、何にもできないかもと思っていることが多いかも」
Cが、予想していなかったことを口にした。
「ああ。そうなのか。そういえば少し前に、悟り世代なんて言われたことがあったな。今でも、あんまり希望が持てるような社会じゃないしね」
Aは、自説に固執することなく、すんなり同意した。確かに、一口に若さといっても、いろいろな若さがあるのだ。ちょっと考えればわかるようなことでも、怠けているうちにいつの間にか、定型化し、硬直化した考え方が染み付いていたのかもしれない。こうしたことは、きっと他にもあるのだろう。うまく対応できるだろうか。むづかしいような気がした。気をつけなければいけない、と自戒した。
「まあ、そうですかね」
Cがボソッと呟くように応じた。
「大人たちはわがままで自分の事しか考えていないようだし、政治家も同じ、というかもっとひどい気がする」
Aが言うと、Cが続けた。
「だから、広い範囲で考えるのはむづかしい気がするんです。自分にできることは少なそうだし、なら、自分のまわりの小さな世界の中で、楽しく暮らせればいいかなって、……」
「そうなんだね」
「ええ。ちょっとつまらない気もするけど」
「まあね」
「はい。仕方ないんです」
「ああ。でもね、そんなに捨てたもんじゃないかもしれないよ」
Aが、励ますように明るいい調子で言った。
「そうですかねえ」
Cが、相変わらず自信が持てずに疑うように言った。
「ああ、そうさ」
「そうかなあ」
「ま、やってみるしかないのだろうよ」
「うーん」
「若いし、ま、失敗したって、たいていはどうってことないさ」
Aは反省を込めて言った(こちらは、残念ながら、まあ自信があった)。
「そうかなあ」
「そうさ。それに、何と言っても、きみはまだ若いしね。失敗を恐れるには若すぎるくらいだ」
Aはなんとはなしにそう言ったつもりだったが、若さへの羨望を含んでいたかもしれなかった。
「そうですね。じゅうぶん若いし、始まったばかりですからね」
Cは、今度もあっさりと認めたし、しかも若さを強調するかのようでもあった。自信を鼓舞しようとしたのかもしれない。
「そうだよ」
Aは拍子抜けすると同時に、ちょっと苦いものを感じたが、今度も素直に同意した。Aは、かつては老成することに憧れているつもりだったが、いざ自分が歳をとってみると若さを羨ましく思うようになったことをはっきり自覚していたのだ。人は失ってはじめてわかることがある、という証の一つだ。
「確かに、……」
と言いかけて一度言葉を飲み込んだ後、続けた。
「ま、頑張りなさいよ」
「はい。好きなことに打ち込むように、ですね」
Cは、先回りするように応じた。
「そうそう。それがいいよ」
安心したAが言い、
「はい。わかりました」
Cが素直に答えた。以前と変わらないやり取りだったが、つながりが少しだけ深まったようだった。しかし、気持ちが移ろうのは、何も女性だけに限ったことではない。多くのことが儚く、危うさを秘めているのだ。
Aは、家に帰ってからも、時々レコード盤をかけた。CDよりもラジオよりも、その方が落ち着くような気がするのだった。こうした時には、特に古い音楽を好んでかけた。たとえば、ナット・キング・コールのようなジャズのスタンダードナンバー。歌を歌らしく歌う、歌詞の意味とリズムを大事にして、言葉を捻じ曲げたり押しつぶしたりしないで歌われていた、たぶん、そうした時代の歌だ(あるいは、ただの幻想かもしれないが)。Aは、彼が活躍していた時代に聴いていたというわけではなかったが、なぜか懐かしい気がして、心に染み入るように感じていたのだった。そして、年をとるに連れて、なぜかその思いはますます強くなった。それで、その夜もターンテーブルの上にレコード盤を乗せ、針を下ろした。ただ、時々外してしまうようになったことが問題だ。
*
そのうちに、Aが退職した時に「皆が集まれる場所があればいいですね」と言っていたBが、時々ランチにやってくるようになった。カフェのある街には週1回来るだけだし、遅くまで授業がある。しかも遠くに住んでいるので、夜はなかなか会う機会がない。それで、なんとか調整がついた時に寄るようになったというわけだった。Aは、これをCへのデザインについて考えるための機会にしようと思い立ったのだった。何と言っても、Bは様々な場面で実務を経験してきた現役のデザイナーなのだ。きっと得るものは多いはずだ、と思っていた。
(パイロット版・完 さて、命運は如何に)
2025.02.09
FANTASY 34 「デザイン事務所シリーズ第2部 パイロット版」
はじめてみないことには、先へ進めない。
デザイン事務所の日常と探求 パイロット版(前編)
*
Aのカフェは、Cがいなくなった後も客足が減ることもなくまあまあの入りが続いていたが、なんとか一人でもこなせるくらいだった。それでも、たまに手が足りないような時には、階上に住む学生のDが手伝ってくれた。不器用そうに見えて、今時の若者らしく要領がいいというのか、人当たりがよかった。それで、お客の評判も悪くなかった。
しかし、Cがいなくなってからというもの、Aはなぜか気が抜けたような気がしてぼんやりとすることがあった。Gが入ってきても気がつかない時さえあったのだった。
「よおっ」
いつものように声をかけながら、Gが入ってくる。
「……」
しかし、Aは無言で、何やら思いにふけっているようだ。
「よおってばよ」
「……」
Aはまだ、ぼんやりして無言のままだ。
「こんにちは」
GがAの前にやってきて、大きな声で呼びかけた。
「おっ、いらっしゃい」
やっと気づいたAが顔を上げて、言う。
「いったいどうしちまったんだよ、ぼおっとして」
「そうか、すまん」
「この頃、多いよ。ま、いいけどさ」
「ああ。何にする?」
「うん。……」
そんなことがよくあった。
おまけに、Aが退屈しのぎに見ていた英国製のミステリードラマでは、身につまされるような場面が出てきてひやりとすることがあった。例えば、主人公に対して、こんな言葉が投げかけられた。
「あなたは、なんでも複雑にする。思考回路が普通じゃないのよ」
あるいはまた、
「依存症でも、行動障害でも、なんでも、あなたみたいな人は”どん底”にたどり着くの。あなたのような人には耐え難いはずよね。あなたは、人に助けを求めることができない。……。他の人とまともに触れ合ったことがないのね。……。私は、あなたみたいにはなりたくない」
そして、主人公は独り言つのだった。
「私は、人生を掴み損ねていたんだ。夢の中で全てが終わってしまっていた……」
そんなふうだったから、見ないわけにはいかなかったし、見終わった後は、楽しい気分とは言えなかった。ただ、幸か不幸か、このドラマはわずか2話で終了した。
Aは大晦日に久しぶりにブルックナーの第9番を聴こうと思いたち(ベートヴェンは、その前に何回か聴いていた)、CDをかけると音飛びがした。しかも、一ヶ所だけじゃない。傷がついていたのかと思って、取り出して見てもそれらしきものはなかった。どうしたことかと思いながらも念のために、盤面を放射状に拭いてみた。そうすると、音飛びはしなくなった。たぶん傷というより、曇っていたのに違いなかった。何と言っても、長い間聴いていなかったのだ。まあ、機械や盤面に大きな問題がなくてよかった。
さらに、元日にクライバーのニューイヤ・コンサートを見ようとしたら、結局探せなかった。実は、ブルックナーの第9番の前にはヘンデルのメサイアを聴こうとして探したのだったが、こちらも見つけられなかった(それが、翌日にはすぐに目につくところにあったのだ)。この頃は、こういうことが多すぎる。Aはやれやれと呟き、それから、いなくなってしまったCのことを思い出した。
Aは、ため息をつくと、思わず知らず、すぐに苦い笑いがこぼれた。そして、自戒のためにこの気分を書き留めておこうと思い、分ち書きにして、詩のようなものをこしらえた。
過ぎしこの一年を思い出してみようとしたら
大きな ため息が出た
この先いったいどうなるのだろう
自問するが 答えは見つからない
の度に フッと笑い
ため息をつく
気がつけば いつものこと
日々変わるところがない
我知らず漏らす 独り笑いとため息
このセットこそが 我が日常の友
書きつけると、Aはまた、小さく笑った。
年が明け、朝早くラジオをつけると、狂言が。滅多に耳にすることがないのに、正月はこうした狂言や謡曲をはじめとする邦楽がよくかかる。いかにも日本らしい雰囲気を作り出す。Aも、なぜか古き良き時代の日本を思い出した。実際には、具体的な場面を思い出したというわけではなかったから、ただのイメージに過ぎなかった。
しかし、一歩外に出るとその思いは、たちまちのうちに消え去った。イメージではなく、現実の世界に引き戻されたのだ。外はよく晴れて、雲ひとつないような天候で、しかも暖かかったが、あちこちに干してある洗濯物が目についた。仕方がないという面もあるのだろうが、ちょっと興ざめしたような気分になった。
*
Cがいなくなってからも長く続いた暑かった夏が去り、ようやくやってきた秋もあっという間に過ぎて、寒い冬になり、まだ春には遠いという頃、そろそろ営業時間が終わる時に、ドアの開く音がした。
カウンターの中の小さなスツールにぼんやりと座っていたAが、目を向けた。そこにはCが立っていたのだった。半分 開いたドアの ノブを握ったまま、入って来ようとはせず、動かないようだった。
「やあ。いらっしゃい。どうした?入ってこいよ」
驚いたAは、できるだけさりげなく言わなくてはと考えながら、声をかけた。でも、うまく言えなかった。それでも、Cが中に入ってきた。
欧米だったら、カウンターから飛び出て行って、抱きしめておでこにキスをするところだったろうが、Aはそうはしなかった。というか、できなかった。Aはもともと、素直に感情を表すことができるようなタイプじゃなかったし、娘か孫のような気がしていたのだったが、確信が持てなかったのだ(彼は、子供がいたことはなかった)。天井の方を見上げながら、そっと、できるだけ力を入れないようにして、軽く抱きしめた。
するとCが、顔を上げると、
「お腹すいた」
と言あい、にっこりした。
「あっ」
そう言うと、Aはすぐにカウンターの中に駆け込んだ。
Aはためらうことなく、パスタを作ることにした。Cが事務所で初めて食べたのが、パスタだった。今はまだアサリの季節ではなかったから、イワシのパスタを作ることにした。シチリア名物だ。シチリアには行ったことがなかったし、生のイワシもなかったから、オイルサーディンの缶詰を使うことにした、これならいつでも用意してある。お湯を沸かして麺を茹でるくらいの時間でできてしまう。しかも、うまい。それに、いまの季節だってイタリアンパセリはいつも用意してあるのだ。
Aはピカピカに磨き上げたアルミのフライ、パンの中で炒まったオイルサーディンの中に、茹で汁と醤油と輪切りにした小ネギを入れると香ばしい香りが立ち上った。そして茹で上がったパスタと和えると、素早く皿に盛った。
「さあ、どうぞ。レモンを絞って、熱いうちに召し上がれ」
Aが言うと、Cが、
「わあ。おいしそう。いただきまーす」
と、屈託なく言った。そして、
「おいしい」
と、つぶやくように言ったのだった。
「よかった。よくきてくれた」
Aはそれを聞くと、ホッとしたように、小さな声でぶっきらぼうに言った。
「はい」
そう言うとCは、やがてポツリポツリと少しずつ、これまでのことを話し始めた。
「こないだは、困らせてしまってごめんなさい」
Cがうつむいたまま言い、それから顔を上げてAを見つめた。
「すんだことだ。気にするなよ」
すんなり答えた。これはAがいつも思っていることだった。必ずしも前向きに考えてばかりのことではなかったが、過ぎたことはしかたがない。なんとかできるのは、これからのことだ、と学生たちによく言っていたことだった(事実そうしたものだし、まあそう言うしかなかった)。
「わたし、どうかしていたんです」
「ああ」
「本当に一人ぼっちになってしまったんだ、と思っていたんです」
Cがしみじみと噛みしめるように、思い出すように、言った。
「ああ。そうだな」
Aも小さく応じて、視線を店の奥へやった。
「だから、つい……」
「うん」
「でも、そうじゃないことがわかったんです」
「ああ」
「おば夫婦も、私のことを気にしてくれていたんです」
Cは、自分に言い聞かせるように、はっきりと言った。
「ああ」
「ただ、あの子のことがあったので、私と話す時間がなかったんです」
「うん。そうだね」
「それなのに、わたし、どうかしていたんです」
「ああ。それで、何があった?」
Aが、促すように言うと、
「ある日、おばが訪ねて来てくれたんです。私は音がしたような気がしたんですけど、降りて行くのが面倒で、自分の部屋に座ったままだったんです。すると、下から私を呼ぶ声がしたんです。でも誰だかわからなかった。それから、階段を上ってくる音がして、怖かったんですけど、わたしもうどうでもいい気がして。ドアを叩く音がして、おばさんが入ってきたんです」
Cが、一気に言った。
「どうしたの?電気もつけないで?暗い中で……?」
驚いたおばが聞いても、Cは答えずに黙ったままだった。
「……」
「大丈夫?悪かったわね。話をすることもできずに」
今度は、弱々しい声で、申し訳なさそうに言った。
「……」
それでも、Cは黙ったままだった。
「ずっと気になっていたんだけどね」
おばは、不登校の息子のことや施設に入った母親、すなわちCにとっての祖母のことで手一杯だったのだ。Cも、初めの頃はよく訪ねていたのだが、認知症のせいで辛く当たることに耐えられなくなったこともあって、このところはすっかり遠ざかっていたのだった。
「……」
「一人で辛かったでしょう?」
おばが、つぶやくように言った。
「……」
「ごめんね」
「……」
それからCは、たまらずわっと泣き出すとおばの胸に飛び込みしがみつくと、おばはしっかりと抱きしめた。
登校拒否の子供は、心配した友達が何回も訪ねてきてくれたおかげでわだかまりも溶けて、つい最近になって登校するようになった。今ではなんでもなかったように通っていて、新しい友だちも増えたということだった。そのため、母親であるおばや父親のおじはようやく安心することができるようになり、心ならずもCをほったらかしにしてしまっていたことを思ったのだった。それまでも、店が終わってからしばらく待ってみたり、朝夕に2階を訪ねてみたりしたということだった。
そんなことがあって、Cも固く閉ざしていた心を開くようになり、だんだん元の姿に戻っていったようだった。
「それは何よりだった」
Aは安心して、遠くを見るようにして言った。
「ええ」
「よかった」
「ありがとうございます」
「それじゃあ、これからどうする?」
Aが、大きな声で訊いた。
「……」
「どうしたい?」
「もしよければ、……」
遠慮がちに、Cが言う。
「ああ。もしよければ、なんだい?」
Aがこの機を逃さないように、促した。
「えーっと」
「遠慮せずに言ってごらんよ」
「はい」
「さあ、どうぞ」
「また、ここで働かせてください」
Cが、つぶやくような、小さな声で言った。
「ああ。いいとも、もちろんさ」
Aが無理に一呼吸置いて言うと、Cが続けて訊いた。
「デザイン事務所の方も?」
「ああ」
「仕事はないけどね。当然、アルバイト代の方もね」
「ええ」
「じゃあ、そういうことで……」
「よろしくお願いします」
「ああ、よろしくね」
「はい!よろしくお願いします」
今度は、元気一杯の声だった。そしてAを見ると、にっこり笑った。Aも視線をそらすことなく笑った。ずいぶん久しぶりのことだった。
(後編に続く)
2025.02.02
クリスマス特別編 FANTASY 33 「プチとうんと昔の猫やねずみたちのお話(β版)」

皆さんもよくごぞんじのように、今でも世界は争いに満ちています。減るどころか、ますます増えているかのようですね。プチのまわりでも同じです。猫同士の諍いだってあるし、昔から因縁のあるネズミとのいがみ合いも未だに絶えることがありません。
知っている人もいるかもしれませんが、プチは少し前に、たまたま知り合ってやさしく接してくれた町に住むお兄さんと一緒に見た「トムとジェリー」が好きでしたから、ねずみのジェリーのような友だちがいればいいのにと、願っていたのでしたが、残念ながら当分の間それは叶いそうにありませんでした。

まわりを見わたしてみても、強いものが弱いものを押さえつけて、ますます力を増していくばかりのようでした。それに、プチだって少し前には生きるために悪さをしたことがなかったわけではありませんでした。
しかし、やさしくしてくれたお兄さんやアオたちに接するうちに、次第に、どうしてみながおだやかで平和に暮らすことができないのだろう、と考えるようになったのでした。
そんなある時、プチは、おばあさんから聞いた話を思い出しました。

うんと昔、地球上にまだ森と海しかなかった頃、人々はなんとか生き延びようと必死でしたが、なかなかうまくいきませんでした。いちばんは食べるものが不足していたためでした。米や麦、それに豆類などの穀物の種が消えてしまったせいですね。これを見ていた天上の神さまたちは、そのことに心を痛めていました。というのも、この原因となった出来事には、一部の神さまが関係していたのです。そこで、遠くまで飛ぶことのできる生き物を地上に送って、穀物の種を届けさせることにしたのでした。神さまたちは、さっそく鳥たちを呼び寄せて、言いました。

「おまえたちは、毎日毎日植物の種をついばんでいるのだったな?」
「はい」
鳥たちが答えると、神さまが、さらに問いかけました。
「そして遠くまで飛んで、運ぶこともできるのだな?」
「ええ。もちろん」
鳥たちはすぐに、いかにも当然というように答えました。
「それでは、地球までひとっ飛びして、種を届けてはくれまいか?」
今度は、神さまがいつもとは違った口調で言ったのでした。
「はい。わかりました」
鳥たちが勇んで答えると、神さまは、
「よし」
と、うなづいてから、言いました。いつもの厳かな口調でしたが、少し安心したようでもありました。
「それでは、わたしたちはなんの種を運べばよいのでしょう?」
鳥たちが、たずねました。
「穀物の種だ」
「はい」
「地球上の人間たちが、食べるものがなくて困っているのだよ」
神さまは、このことをたいへん気にしているようでした。
「はあ」
鳥たちは思いがけない答えに驚いて、つい頓狂な声を出したのでしたが、なぜ神さまたちが遠く離れた地上の人間たちのことを心配するのかわからなかったのですね。それでもかまうことなく、神さまたちは、厳かに命じました。
「だから、おまえたちは地上に穀物の種を運んで、一晩のうちに実らせるのだ」
「はい」
「それでは、さっそく米や小麦、豆などの種を集めて、すぐに地球に届けておくれ」
神さまたちは、またいつもと違って命じるのではなく、頼み込むような言い方をしたのでした。
「わかりました」
そんな神さまたちの姿を見たことがなかった鳥たちは、これはきっとよほど重大なことに違いないと思って、即座に答えたのでした。
「頼んだぞ」
神さまたちが口々に、言いました。

そうして、鳥たちは大急ぎであちこちから種を集めてくると、ただちに地上へ向かいました。地球に到着すると、四方八方に分かれて飛んでいき、すぐに種をまきました。それから、神さまに教わったとおりにおまじない「スィターリ、フォーリモ」を唱えると、一夜のうちに米や小麦、大麦、それに数種の豆が生えてきて、たくさんの実をつけたのです。

翌朝、これを見た人々の驚きと喜びは、いうまでもありません。豊かに実った穀物を目にして喜ぶ人々の姿を見届けた鳥たちは安堵し、すぐにまた天上界に帰っていきました。

人々は、それらから種を取ることを知り、米や麦などの穀物を育てることを覚えたのです。
それからというもの、人々は食べるものにこと欠く事はほとんどなくなりました(それから長い時間がたった今、たくさんの食べ物が捨てられる一方で、またしても食べるものがなくて困っている人がいるのですが、いったいこれはどうしたことでしょうね)。

しかし、その時に地球に向かったものがほかにもいたのです。もうわかった人もいるかもしれません。ねずみですね。ねずみたちは、初めは少なかったのですが、すぐに増えて、あっという間に穀物のほとんどを食べ尽くすようになってしまいました(ねずみ算という言葉あるくらいです)。そのせいで、人々はまた食べるものの不足におびえるようになったのです。
これを知った神さまたちは相談して、すぐにまた別の動物を呼び寄せて、地球に送り込むことにしたのでした。さて、なんでしょうね。みなさんもよく知っていますよ。そう、プチの祖先の猫です。

猫たちは、一生懸命にねずみを捕まえたのでしたが、それでも一掃することはできませんでした。なにしろ、ねずみたちはたくさんいましたからね。それに、猫だっていい猫ばかりとは限りません。中には神さまの言うことを聞かずに、なまける猫もいたことでしょうね。実際、それまでにも、自分勝手なふるまいをしたために、神さまたちに天上から放り出されたものもいたのですから。
それで、神さまたちは、もう一度、猫たちに命じました。今度は、ねずみを一匹残らず退治するまでは地球上にとどまるように、と。このせいで、猫とねずみの戦いは、世界のいたるところで、今でも続いています。
*

また別のある時、プチは思い切ってアオに訊いたことがありました。何といっても、ジェリーのような友だちが欲しかったものですから。
「ねえ、アオ。ぼくたち猫とねずみたちは、どうして仲よくなれないのかな?」
すると、アオが言いました。
「これは、前におじいさんに聞いた話だけどね」
「うん」
「ある時、一匹の猫がねずみに持ちかけたんだ」
「うん。なんて?」

「ねずみさん、もう争うことはやめにしよう」
「うん。いいね」
プチは、思わず言いました。
「ねずみは答えた。それはいいですね」
アオが続けました。
「うん」
「そこで、猫が言った。きみたちは、安心して食べ物を探しに出てきていいよ。もう、じゃまはしないから」
「うん。うん」
「これを聞いたねずみたちは喜んで、言ったんだよ。ありがとうございます。わたしたちも、もうあなたをからかったりしません、って」
「うん。ああよかった」
プチは、すっかり安心して言ったのでしたが、するとアオがすぐに続けて言ったのでした。
「それから、猫がさらに言ったんだ」
「なんて?」
「ただね、食べ物を探しに出かけるときは、必ず私のヒゲのすぐ前を通るようにして、撫でてください」

「へえ。どうしてなんだろう?」
「どうしてだろうね?どうしてだと思う?ともかく、それを聞いたねずみたちは、もう一度みなで相談した上で受け入れることにした。簡単なことだったし、何しろ長い長い争いにくたびれていたからね」
「うん」
「でもね、一匹の若いねずみが言ったんだよ」
「うん。それで、なんて?」
「でも、これは罠かもしれませんよ。だって、ちょっとうますぎる話だもの、とね」
「ああ」
「それで結局、ねずみたちは、猫に伝えることにしたんだ」
「なんて?」

「それはありがたい話ですが、あなたにとってはいいことでも、わたしたちにはいいことがありません、って」
「えっ、どうしてさ?」
プチは、不思議に思って訊きました。するとアオが言ったのは、
「その猫は、目の前を通るねずみたちを捕まえるつもりだったのさ」
それで、プチもわかりました。そうなったらその猫は、ネズミを捕まえるのに、もう追いかけることもしなくていいのですから。
「ああ。ずる賢い猫だったんだね」
プチが、がっかりした様子で言いました。
「ああ。だから、ねずみたちはぼくたち猫のことを信じないのさ」
「うん。でも仲良くしたいな」
プチが言うと、アオが遠くを見上げながらつぶやきました。
「ああ」
「できるかな?」
プチが、やっぱり、つぶやくように言いました。
「ああ」
アオは、また同じように短く答えました。
「できるよね?」
プチは、少し不安になりながらも、期待をこめるように言いました。すると、

「できるさ。ぼくたちが望むならばね。そして、ちゃんと約束を守るならね」
今度は、アオがきっぱりと言ったのでした。
プチは、この時のことをしっかりと考えて暮らしていかなければと思ったのでしたが、今でも忘れずに心に留めています。
実は、はじめのところで少し書いたように、プチもこれまで悪さをしたことがなかったわけではありませんでした。プチがもっと小さかった頃には、人を騙して魚を得ようとしたことがあったのです。それは、体の弱いおばさんに食べさせるためだったのでしたけれど。あとからそのことを知ったおばあさんは、たいそう心配したのでした。
幸い、その時に知り合った町のお兄さんのおかげで、過ちに気づいて、お兄さんが紹介してくれたアオやその仲間たちをはじめとするおおくの友だちと過ごすうちに、次第に元の素直な子猫に戻ったのでした。それで、おばあさんももう心配しなくてよくなりました。もっとも、別の心配をすることが時々あるようですが。

そしてプチは、今度ねずみに会ったら、思い切って言ってみよう、と決めたのでした。
「ねえ、ねずみさん。そろそろ仲よくしませんか。なんの条件もなしです。約束を守って、争いをせずに、ただ仲よくするだけです」
仲よくなれたらいいですね。
(おしまい)
あとがき
読んでくれた人には、ありがとう。
小さな物語を、何と言ってもクリスマスですから(でも、思っていた以上に短かった)。
気がつけば、またしても掲載前の2・3日で仕上げることになってしまいました(だから、β版。これは紛れもなく、続けてやることのできない怠け者のせいですね)。
特に、絵が問題。うまく描けないから写真を下書きに使えるiPadでと思ってやってみようとしたら、なおうまくいかない(結局、1枚だけ)。ま、絵だけに限りませんが……(憧れるだけで、適性に欠けるのかも)。
もしも読んでくれた人がいたなら、どうぞ良いお年をお迎えください。
読者、できれば編集者やご意見番役もいてくれたなら、ありがたいのですが。
責任を押し付けるようなことはしませんので、どうぞぜひ気楽にご意見をこちらまでお知らせください。
2024.12.24
新企画日曜版再延長戦 FANTASY 32 「デザイン事務所とカフェの仕事と推理」17
デザイン事務所とカフェの仕事と推理 第17回
25
それからどのくらい経ったのか、ある時Cが、不意にやってきた。AはCがまた戻ってきたことに安心する一方で、何事かと思って身構えた(何しろ、こういうことには慣れていなくて疎いのだった。
「こんにちは」
Cが言った。
「やあ。こないだは悪かった。ごめん」
Aが、謝罪で応じた。
「ええ、それはもういいんです」
Cが言う。
「えっ?ああ」
Aは、言葉を失ったようだった。すると、
「あのー、ちょっと話してもいいですか?」
さらに少しだけ真剣な表情になったCが、言った。語尾は伸ばさないかった。
「いいよ。もちろん。どうしたんだい」
Aが、心配げに答えた。
「お願いがあるんですが」
Cが、抑揚のない調子で言った。
「ああ、そうだったのか。何だい。言ってごらんよ」
Aがそう言うと、
「……」
Cがなぜか、黙ってしまった。
「どうした。遠慮なくどうぞ」
「……」
「さあ」
Aが促した。するとCは、
「あのー、わたしを養子にしてください」
と、言ったのだった。
「えっ」
Aは驚いて、今度こそ息を呑んだ。
「だから、わたしをセンセイの養子にしてくれませんか?」
Cがもう一度、今度ははっきりと言った。
「えっ?」
Aは、なおも訳がわからないまま、問い返すように声を上げた。すると、
「もう、言いました……」
と言い残して、Cは出て行った。
Aは、
「ああ」
と呟いただけで、しばらくの間は、何が起こったのかよくわからなかった。
そんなことがあった後、しばらくAとCの関係はぎこちなくなった。Aはできるだけ平常心のままでいることを心がけたし、Cも平静でいようとしたようだった。
それからまた少し時間が経った時、Cが切り出した。
「あのー、こないだのことですが」
「えっ」
Aは、先日のことを思い出して、うろたえた。
「だから、この間話したことです」
「ああ」
「考えてもらえましたか?」
「ああ」
Aはなんと答えていいものかわからずに、生返事を繰り返すばかりだった。すると、Cはイラついたように、さらに問い詰めた。
「それで、返事は?」
「ちょっと無理じゃないか?いくらなんでも……」
Aが、しどろもどろの様子で言った。
「えっ。どうして、ですか?」
「だって、当たり前だろ。考えて見てごらんよ」
Aはなんと言っていいかわからなかったが、なんとか答えた。
「考えました」
「いくらなんでも、年が違いすぎるだろう」
「いくつですか?」
「えっ」
「だから、いくつ?」
「50ほど。ということは半世紀ほどだな」
そう言いながら、不思議なことに、Aはしみじみと感じ入った。
「だからなんなんです?別に結婚してください、って言っているわけでもないし」
Cは、いとも簡単そうに言う。
「えっ」
Aはまた、現実に引き戻された。
「だからなんなんですか?それがどうしたっていうんですか?」
Cが、たたみかけるように言った。
「でもねえ……」
Aは、相変わらず煮え切らないままだった。
「ちゃんとしてください」
「……」
「本当に真剣に考えましたか?」
なんだか小学4年生が、担任の先生に怒られているようだった。
「……」
「あのね、センセイの好きなカザルスは、80歳を超えてから、二十歳になるかならないかの娘と結婚しました」
「えっ?」
「二人は、とっても幸せに暮らしたんです」
「ああ……」
「二人はとっても幸せに暮らしたんですよ。だから、わたしをセンセイの養子にしてください。別に、結婚しましょう、と言っているんじゃないですよ」
Cがたたみかけるように言った。Aはますますどぎまぎしたが、なんと言うべきかわからなかった。
「……」
「いったい、なんなんですか?黙り込んで」
Cが問いただした。すっかり興奮して、イライラしているようだ。Aはに気圧されるばかりのようだった。
「……」
「私には、もう誰もいないんです……」
Cが、今度は急に、小さく呟いた。
「よしわかった」
Aは、Cの剣幕と、か細い頼りなげな声の谷間に飲み込まれたかのように言った。
「ありがとうございます」
Cが安心したように言うと、Aは慌てて付け加えた。
「ちょっと早まるんじゃない」
「えっ」
「だから、いくらなんでもすぐに養子にするというのは無理だろ?」
「どうしてですか?」
Cが、今度は落ち着いた口調で訊いた。
「どうしてって……。だからね。少し時間を置くことにしよう」
「でも……」
「1年後も君が同じ君が同じ考えだったら、もう一度考えることにしたらどうだろう?」
「……」
「どうした?君の気持ちをじゅうぶんに汲んだつもりだ」
「……」
「じゃあ、この話は無しだ」
「わかりました」
「よし。わかってくれてよかった。そうすることにしよう」
「……」
Cは、また黙り込んだ。そして、出て行った。
Aは、困惑するばかりだった。
Aは、もちろん結婚するなどは論外で(カザルスとはとても違いすぎた)、養子にすることだって簡単にはいかない。自分がカザルスやもう一人のパブロのようだったのなら結婚するというのも魅力的なような気がしなくもなかったけれど、それは残念ながら無理なことだった(第1、妻帯者なのだ、妻が年老いた両親お世話をするために遠くへ行ってからもうずいぶん経ったととはいえ)。
彼女も一時的な気の迷いに違いない、とも思った。それでも、本当に彼女の気持ちが変わらなかったなら、養子に迎えてもいいかもしれないという思いがちらりと頭の隅をかすめることがないわけじゃなかった。
なぜ、こんなことになった?。Aは自分に問いかけた。自分には距離感がわからないのかもしれない。近づきすぎるか、遠ざかるか。その中間がない。すなわち、ちょうどいい距離を保てないのだ。そうだとすれば、いい関係を作り出すことはできない。Aには子供がいなかった。そのせいで、子供の気持ちを察するという経験もなかった。そのことが、自分を甘やかし、大人にすることを妨げたのだとAは思うことがあったのだ。
結局は、Cもやがて離れていくかもしれない。いや、もう離れていってしまったかもしれなかった。
Aは、大人になれず、わがままな自由さの中で、表層だけを見て年をとってきたのだ、と思うのだった。何が本質で、大事なことか、ということよりも目に見える景色の美しさ、形態の魅力に拘泥してきたのだった。
流れるままにやってきたのだ。そして、結局、自身では何も作り出すことができなかった。与えることもしなかった。やれやれ。Aは大きくため息をついた。
それから、何日かはふだんの日常と変わるところはなかった。Aは安心したような、不安なような気持ちで過ごした。そして、Cがまた、ふっつりと姿を見せなくなった。
今度は長かった。Aは、Cがもう戻ってこないかもしれないような気がした。
Aはどうすることもできず、半ば事務的に仕事をこなし、家へ帰ると時々映画を観た。
Aは映画が好きだったが、イギリスびいきだったにも関わらず、なぜかフランス映画を好んだ。これまでのベスト2は、『男と女』と『冒険者たち』だ。3番目は時々変わる。『アメリカの夜』(フランス)、『フォローミー』(イギリス)、『八月の鯨』(アメリカ)、等々。
Cが現れなくなってしばらくたった頃、アラン・ドロンが亡くなったというニュースが届いた時、Aは『冒険者たち』を観ることにした。久しぶりのことだった。以前は、毎年夏になると観ていたのだった。冬は『男と女』。それが、いつの頃なのからかだんだん観なくなった。たぶん、集中力が続かなくなってきたのだ(特にスクリーンじゃなく、テレビの画面で見るようになってから)。初めて観たのは中学生の時、あるいは高校生になりたての頃だったが、それが今や主人公の倍ほどの歳になったということもあるのかもしれない。
『冒険者たち』には、ドロンとジョアンナ・シムカスが、コンゴ沖に沈んだ宝石を発見する直前に釣りをしている場面がある。
シムカスの演じるレティシアは、ドロンにお金を手したらどうすると訊かれた時、海に浮かぶ家を買うと答える。正確には要塞だが、そこを改装し、創作はするが、発表はしないと言うのだ。さらに、一人で住むのかと訊かれて、2人(ドロンとリノ・ヴァンチュラ)とも大歓迎すると答える。
その時、魚がかかり、引き上げるとハタだった。そして、レティシアは、
「ハタはひとりで生きている。長い人生を」
と言う。
そして財宝を発見し引き揚げた後、操舵室でヴァンチュラと2人になったレティシアは、沈んでいく夕日を眺めながら、
「帰ったら、アトリエを買うのかい?」
と訊かれて、
「いいえ、あなたと暮らすわ」
と答えるのだ。ドロンより年長で、しかも風采の上がらないヴァンチュラに対して。
Aは、切ない気持ちになりながらも、ああ、やっぱりいいなあと思うのだ。
Aは、シャワーを浴びるとき、決まって賛美歌が口を突いて出るのに気づいて、苦笑いした。若い頃に、職場で覚えたのだったが、それは必ずしもいい思い出とは言えなかった。他の宗教もたぶんそうかもしれないが、ある種の押し付けがましさが苦痛だったのだ。
そして、それは今も変わらない。宗教に近づくよりは、ますます違和感を覚えるようになったのだ。いまの世界の状況を見れば、そうならざるを得ないような気がするのだ。
それでも、Aは歌うのをやめようとはしなかった。『頌栄451番』。短いし、忘れることもない。何か、拠り所になるようなものを欲しいと思っていたのだろうか。
Aは、Cのことを時々思い出して、後悔すると同時に寂しい気持ちになったが、その頻度はだんだん少なくなるようだった。
しかし、心の中にぽっかりと穴が空いたような気持ちは、ずっと変わらないままだった。
(第1部完)
あとがき
わざわざお断りするまでもない気がしますが、もう夏休みもとうに終わったし、こちらは終わりそうにないし……。と、いうことで2部構成とすることにして、第1部をひとまず終了します(第2部があるかどうかはわかりませんが)。
あんまり進歩はなかったけれど(おまけに、最後の方はいかにも急拵えで、ちょっとバタバタした感じは否めませんでした)、主題が少しずつ定まってきたような気がするのは、まあよかった。
読んでくれた人(感想は届いたことはないけど、もしかしたらいるのか?)には 、御礼申し上げます。よくぞ、辛抱してくださいました。ありがとうございました。
急募!
結局、何の反応もありませんでした(残念)。
ともあれ、今年も、「絵本大賞」に応募しようと思います。
昨年は、「まだやってんの?」と呆れられましたが、石の上にも3年。
もう一つの小説(第1作)の読者、できれば編集者、ご意見番役も、いてくれたなら、ありがたいのですが。
責任を押し付けるようなことはしませんので、どうぞぜひ気楽にご意見をこちらまでお知らせください。
2024.10.01
新企画日曜版延長戦 FANTASY 31 「デザイン事務所とカフェの仕事と推理」16
デザイン事務所とカフェの仕事と推理 第16回
23
カフェの方はだんだん落ち着いてきたし、カウンターの中のAの姿も様になってきたようだった。客足に、リズムのようなものがあることもわかった。
AとCの小さな衝突も相変わらずあったが、大事に至るようなことはなかった。Cがプイと店を飛び出していっても、たいていは翌日には戻ってきた。何事もなかったかのようだった。Aは、それがCのたいしたところだと感心し、同時に救われていることを自覚していた。
ひと段落したCが、Aの方を見るでもなく言った。
「事務所の仕事は来ませんねえ」
「ああ」
Aも、グラスを拭く手を休めることなく答える。気持ちはグラスに集中しているようだ。
「カフェの方は順調なのに……」
Cが、さらに続けた。
「順調なのかな?」
Aが訝るように、呟くように言った。
「ええ。どっちが本業かわからないくらい」
「もしかして、不満なのかな?」
「いいえ。こっちも面白くなってきた」
実のところ、Aも同じように感じていたのだった。それがいいんだか悪いんだか、そんなことを思った。
「事務所の方の仕事がないのは、どうしてだと思う?」
一呼吸置いて、今度はAガグラスを置きふきんをしまうと、Cの方に向き直って訊いたのだった。
「さあ」
Cがわかならないなあという顔をしたのは、遠慮したのだろうか。
「たぶん、当然なんだよ」
Aが言った。
「どうして?」
「なんでも、そうなんだよ」
「えっ?」
「結局、魅力がないってことなんだよな」
Aがわかっているというふうに、少し自嘲気味に言ったのだった。
「どうしてそう思うんですか?」
Cが、不思議そうに訊く。
「デザインだけじゃなく、ホームページも、教えられて始めたインスタグラムも、ほとんど誰も見ない」
Aがつぶやくように言った。
「えっ、なんですか?」
「ああ、インスタグラムのフォロワーというのか、あの数なんかは、カフェの改装を手伝ってくれたうんと若い知人の足元にも及ばない」
「はい。でも悪くない気がしますけどねえ」
Cが言った。励ましてやろうという気持ちだったのだろうか。
「まあね。でも、人が面白いと思うものとは違うんだね」
Aはこのことをずっと感じていたのだった。周りの知人たちの手になるものより格別優れているとは思わなかったが、とくに劣っているわけでもないし、中にはまあいいものもあると自負していたのだったが、反応はなかった。
「そうかなあ」
「ああ、俺の感覚がね」
Aはそう呟くと、元気を出そうという気持ちで、
「さあ、お茶の時間にしよう」
と言った。
「ええ。そうしましょう。落ち込んだ時にはおいしいものが一番」
Cが応じた。どうやら、Aの口癖が伝染ったらしい。
「何にする?」
「センセイは?」
Cは、相変わらず今でも、Aのことをセンセイと呼ぶ(もしかしたら、確信犯かもしれない)。この時は咎めようという気にもならなかった。
「久しぶりに、ココアを飲みたくなった」
Aは、ココアは甘くして飲むのが好きだったが、暑い季節には口にすることはなかった。それが、なぜだか急に、甘くて優しい味が恋しい気がしたのだ。
「あ、いいですねえ。わたしもココアにしよう」
Cも応じた。Aは同席する人が同じものを頼むと、よりいっそう連帯感のようなものを感じることがたまにあったが、この時がまさにそうだった。
それから、Aはミルクを取り出し、小さな黄色のホーローのミルクパンで温め始めた。
そして、もう一つ小さな温め用の陶製の飴色をした鍋に2人分のココアの粉を入れると、温まったミルクを少し注ぎ、ゆっくりと練り始めた。ココアを飲むには少し時間と手間がかかる。その間に、気持ちも少しずつ落ち着いてきた。
「さあ、できたぞ」
「おいしい。ココアってこんなにおいしかったんですね」
Cが言うと、Aも応じた。
「ああ。心を込めて作ったしね」
「何ですかあ?でも、心もあったまるような気がする」
Cが言った。
「そうだろ?」
と言うと、
「ココアのせいですね」
Cが笑った。素敵な笑顔だった。
と、Aがポツリと呟くように言った。
「でもね、俺はデザインに向いてないような気がするんだよ」
「えっ、どうしてですかあ?」
Cが、驚いて訊いた。
「根が怠け者だからね、詰めも甘いし」
Aが答えた。自覚していてもなかなか治らないのだ。
「うーん、そうかなあ。やっぱり、それはあるかも」
Cは、驚くふうでもなくそう言ったのだった。
「えっ?」
Aは、Cの思いがけない言いように、一瞬怯むような気がした(見透かされていたのか)。
「いえ、他にも何かあるんですか?」
Cが、からかうかのように、さらにたたみかける。
「デザインは基本的にはシンプル、足すより、引くもんだよね。少なくとも、近代以降のデザインの考え方は、概ねそうだと思う」
Aが気を取り戻して、続けた。
「ええ」
「お前さんも知っているミース、ジャスパー・モリソン、佐藤卓など、皆そうだね」
「はい」
「好きなデザイナーはたいていそうだ」
「ええ。そうかも」
「わかっちゃいるんだけどね。でもいざ自分でやろうとすると、心ならずも、俺は足す派のようなんだよ」
Aは、そう言わなければいけないことが残念だったが、長年の癖は簡単には変えられないのだ。
すると、
「はあ、でもあんがい好きなんだけどなあ」
Cが独り言のように、でもAに聞こえるように呟いた。
「えっ、何が?」
そう言われると、ちょっとどきっとして気になった。
「センセイのデザイン」
今度は、はっきりと言った。
「それはどうも。でもね、センセイはいい加減、やめてくれ」
いちおうそうは言ったものの、もはや悪い気はしなかった。何度注意しても直らなかったが、Aもだんだん慣れてきて、マスターなどと呼ばれるよりはよほどいいという気がしていたのだ。
「はい」
「で?」
「えっ?」
「どこが好きなんだよ?」
Aが訊いた。やっぱり気になるのだった。
「あ、事務所のデザインだって、ここのインテリアだって、ちょっと安っちいと言えばそうだけど、貧乏たらしくはありません。それに、片付きすぎてショウルームのようになってもないし……。落ち着くし、案外いいと思うけどな。それにホームページに載ってるものだって」
Cが、説明した。
「へえ。ありがとうよ。お前さんくらいのもんだね、そんなことを言ってくれるのは」
ホームページまで見てくれているとは思いもしなかった(何しろ、読者はほとんどいないのだ)。
「いえ、いえ」
Cが言ったが、Aにはそれが急に大人びて見えたようだった。
「これからしばらくは、カフェの営業時間を増やしたほうがいいのかもな?」
Aが自分に言い聞かせようとしたものか、あるいはCに相談しようとしたのか、ポツリと呟いた。
24
数ヶ月ほども経った頃だったか、昼時以外にやって来るお客もだんだん増えて、次第に安定してきた。食事のためでなく、お茶の時間を楽しむのだ。
そうしたお客の要望に応えようと考えていたAが、Cに訊いた。
「ねえ、アップルパイは好きかい?」
「もちろん。美味しいですよねえ」
「そうだろ、これからは特に美味しくなる」
「ええ」
「だからね、アップルパイを店でも出したいんだけどな?」
「はい、いいですね。あのパン屋さんのですか?」
Cはなにも考えないで、訊いた。
「ああ、そうきたか?」
Aがちょっとがっかりして、言った。
「でも、届けてくれるのかな?わたしは、もうちょっとリンゴがたくさん入っているほうがいいけどな」
「実はね、アップルパイは店で作ったものを出したい」
「えっ、そうなんですか?センセイ、できるんですか?」
「俺はね、きちんと計量して作るなんてことは、どうもだめなんだよ」
「あら、そうなんですか?」
「お前さんは、お菓子を作るんだったよな?」
「ええ、まあ」
「だから、お前さんにつくって欲しい」
「えっ、無理!ダメダメ!」
Cは大きく手を振って、言下に断った。
「そうか?きっとうまいと思うんだけどな」
「……」
「しようがないな。だったら諦めるしかないな?」
「……」
「どうした?」
「それも……」
「なんだよ?」
「だから、諦めるのもどうかなって…」
「だったら、やってみてくれよ」
「でも……」
「どうした?」
「それも……」
「なんだよ?だったら、言うなよ」
Aは落胆して、小さく言ったのだった。
「……」
それから数日後、Cが勢いよくドアを開けて入ってきた。手には紙袋を下げていた。
ちょうどテーブルの上を綺麗に並べ替えていたAのところへやって来ると、紙袋を持ち上げて見せて言ったのだった。
「ジャーン」
「なんだよ?」
アップルパイへの取り組みを断られたせいで、意気消沈したAがちょっとばかり投げやりな口調になった。
「さあ、なんでしょう?」
Cが、焦らすように訊く。
「なんなんだよ?」
今度は少しイラついた言い方だ。このところは、なんだか心がざわつくようで落ち着かない日々が続いていたが、その日はCのあかるい口調がそれに輪をかけた。
「なんだと思います?」
「わからないよ……」
「わかりませんか?」
Cがわざと怒ったように、訊いた。語尾は伸ばさなかった。Aも、
「ああ」
と、素っ気なく答えるだけだ。
「これです」
Cはがまんできないとばかりに、取り出してみせた。
「おうっ!」
Aは声を上げた。Cがアップルパイを作って、持ってきたのだった。
「どうですか?」
「いいねえ」
思わず笑みが漏れた。
「食べてみてください?」
「うん。うまいよ。……」
そう言うと、Aは黙ってしまったのだ。
「どうしました?」
Cが、心配そうに訊く。
「うーん……」
Aは、上の方をにらんだままだ。
「どうしたんですか?」
Cがもう一度訊くと、Aはようやく口を開いた。
「ちょっとね……」
「はあ?」
Cは、いったいどうしたっていうんだろう、と訝った。
「俺の思っていたイメージと、ちょっと違う……」
Aは,なぜそんなことを言ったのか、自分でもわからなかった。
「はい……」
Cは、すっかりがっかりしてしまったようだった。
「もっと外側がパリッとした感じのものがいいんだよ」
Aは、Cが初めて作ったことをすっかり忘れていた。ずっと最高のアップルパイを期待していたが、そのせいで、Cのアップルパイに対する感想も厳しくなったのだ。
「はあ?」
Cは、戸惑い、呆れて、だんだん腹が立ってきた(せっかく頑張って作ってきたのに……)。
「なんだよ?」
「わたしは、しっとりしているのが好きなんですけど……」
「だから、お前さんお好みじゃなくてさ?」
「……」
Cが無言のまま、Aを睨みつけた。
「どうした?」
「……」
「なんだよ?」
Aは、Cとの対立に戸惑いながら、言うのだった。
「……」
Cは、相変わらず無言のまま俯くと、答えようとはしなかった。そして、顔を上げるとしばらく遠くを見るような目でAを見つめた。
その日は、ずっとぎくしゃくしたまま、過ぎていった。
翌日から、Cがぱったりと姿をあらわさなくなった。
Aは後になって、Cがアップルパイを作ったのは初めてだったことを思い出した(大事なことは、いつも後から気づくのだ)。なぜ、もっと素直に喜びを表して、感謝の気持ちを伝えられなかったのかと悔やんだが、もはや遅かった。
時々、思いがけずもきつい言い方で、Cを叱るようになっていた。Aは、もともと人との付き合い方に慣れることがなかったが、Cとの関係にはすっかり慣れたような気がして、まるで自分の子供か親しい姪のように近づきすぎたのかもしれない。
少し前までは、彼と若者の立場の違いが多少の齟齬は帳消しにしてくれていた。そのことを、Aは忘れていたのだ。そうした立場ではない1対1の関係となると、そうはいかない。
AはCのことを好ましく思っていたのだったが、孫と言ってもいいほど年が違っていたし、おまけに実際には孫はおろか子供もいなかったので、その気持ちも付き合い方も自分の気持ちも、皆目分かっていなかったのだ。
急募!
いちおう最終日ですが、何の反応もありません(うーむ)。
今年も、「絵本大賞」に応募しようと思います。
昨年は、「まだやってんの?」と呆れられましたが、石の上にも3年。
そこで、このコーナーに掲載したうちのどれを応募するのがいいか、皆様のご意見を頂戴したいと思います。
もう一つの小説の読者も(できれば編集者、ご意見番役を引き受けてもらえるとありがたいのですが)。
責任を押し付けるようなことはしませんので、どうぞ気楽にご意見を。こちらまでお知らせください。
なお応募の都合上、9月末日までの早いうちに頂戴できれば助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
2024.09.30
新企画日曜版 FANTASY 30 「デザイン事務所とカフェの仕事と推理」15
デザイン事務所とカフェの仕事と推理 第15回
20
Aは店に着くと、まずドアや窓を開け放つ。休みの間に淀んだ空気を追い出し、新しい空気を入れるのだ。そして、店内の清掃に取り掛かる。といっても、だいたいは営業を終えたその日のうちに済ませてあるので、床をざっと掃き、カウンターとテーブルを拭き、椅子やメニュー等をもう一度並べなおすくらいだ。そして、窓のガラスを磨くと、最後は店の前の掃除だ。ホウキとチリトリをもって、店の前に立ち、ゆっくりと眺め回す。そして、あたりを掃き清めた後、もう一度眺め回して汚れがないことを確認する。暑い季節には、打ち水をすることもある。それから、よしっと小さく声に出して、店の中に入る。もう一度店の中をひとしきり眺めて、問題がないことを確認するともう一度、よしっと自分に言い聞かせて小さくうなづく。それから開店時間ぴったりに開店の札をかけるのだ。
Aは掃除が好きなわけでも、得意なわけでもない。きちんと整えられて、掃除が行き届いた空間が快適なことは知っているし、自分のアパートに帰るたびに、片付けなくちゃとか、もう少し綺麗にしなければと思うのだが、なかなか実行することができないままだ。最近はようやくクイックルワイパーで毎日床を拭くことが定着してきたが、文字通り四角い部屋を丸く掃くのだ(正確にいうなら、ものが多いせいで不整形だが)。ものを動かして拭くことは滅多にない。
こうしたことを通して感じることは、才能があるとかないと言う時まず一番は「続ける」能力だということだ。掃除はやろうと思えば誰でもできる。続けていれば、まあまあの掃除はできるようになるだろう。経験を積むうちにいろいろと工夫もするから、さらに上手にできるようになる。しかし、それを実際に続けて実践できる人ばかりではない。他のことでも同じではないか。ただ、できるということと一流の腕になることは当然違うから、続けた先に一流になれるかどうかと言う時に初めて、才能の有無ということが問題になるのだろうと考えるようになった。
そんな彼が店の掃除に精を出すのは、客商売をするものにとっては当たり前のことというようなものだが、新鮮な気持ちと環境とでお客を迎えるためなのだ。ある探偵小説の中で、「夕方の、開けたてのバーが好きだ」と言った男がいたことを思い出しながら(あいにく、Aのカフェは夕方になると閉めるのだが)、実践する。
美しい空間が美しい人々を呼び寄せるわけじゃない。そこに現れるもてなしの心が、心優しい人々を招き入れるのだ。そう考えて、Aは毎朝、毎夕掃除に取り組むことにしている。彼にとって、それは決してたやすいことではなかったが。
営業が終わると、二人で乾杯をする。無事に終わったことを確認し、祝うのだ。Aはまずはビールを飲み、Cは紅茶だが、それからグラスや食器を洗い、鍋やコンロもシミが残らないようにピカピカにした。遅くならないいうちにCを帰すと、もう1杯飲むこともあった。そして、最後に残った椅子をあげてから、床に掃除機をかけて綺麗にする。
Aは、掃除の時間は営業時間に比べると、意外に大きな割合を占めている事に気づいていた。たまには疲れてサボろうという気になることもあったが、なんとか思い直して取り掛かるだった。なんといっても、こうした基本的なことを欠かさず続けることが、毎日のカフェの運営を可能にすると思い定めてのことだ。それに、慣れれば大して苦にならない。むしろ、やめるのが惜しい気がしてくるのだ。
もちろん、他の店との競争を生き抜くためには、料理や飲み物、あるいはインテリア等々の独自の特徴を打ち出すことも重要に違いないが、まずは必要なこと、すなわち清潔で凛とした空気を保つことを欠かさずに続ける日々を重ねることこそがいちばんなのだ。Aは自分が怠け者であることを知っていたから、日々の手続きや手順といった、いわば日課をていねいにこなすことをとくに心がけているのだ。これこそがやがて生活を充実させ、豊かにするだろうと思っていた。このため、確認のためのチェックリストを用意していた。ただ、店でできることがなぜ家でできないのだろうと自問することがよくあったが、よくわからなかった。結局、責任感の問題なのだろうか。
21
Aに話したことで少し気持ちが軽くなったのか、そのあとのCは元の調子に戻ったように見えた。
カウンターの中に立っていると、そのつもりがなくてもお客の話が聞こえてくる。Aは、ふだんは注意をそらすようにしているが、時々気になって聞くことがあった。
「それって、どういうこと?」
少し大きくなった声が聞こえた。声のした方をちらりと見やると、若い男の2人連れだった。
「うーん。なんと言えばいいのか…。ほら、彼の世界観がね」
もう一人の方が応じた。
「うん。独特というか、ね」
「むづかしいよね」
「ちょっとわからないところがあるよね」
「うん。だから魅力的ってこともある」
「ミステリアス?」
「謎めいていてね」
「ああ、そうだね」
「でも、説明できないんだよね。あの世界観」
「うん」
なんだか堂々巡りしているばかりのような気がして、Aはどっちがどっちだかわからなくなってきた。彼らの使う「世界観」というのは一体どういう意味なのだろう。一般的には、世界の見方、世界に対する考え方を指すはずだが、Aはどうもそれとは違うような気がするのだ。訊いても、よくわからないのだ。それで、いつもイライラさせられることがあった。たぶん言っている当人だって、わかっていないのかもしれないのだ。でも、使っている当人たちは気にしていないし、何かを言い当てたような気になっているようなのだが。それが現実だし、今それを言い立てたところでどうにもならない、とも思った。彼らは、複雑なものがすぐれている、と考えているのかもしれない。
自分で説明できない言葉を使うというのは、わからないまま使っているということだ。これは、まずい。でも、当人はわからないということさえ気づいていないのかもしれない。いや、もしかしたら、その方が立派に聞こえると思っているのかもしれない。ともあれ今は、これに限らず、漢語やカタカナ語を使いたがって(時にはわざわざ言い換えて)、言葉を大事にしないようなのだ(大切なものだとは思っていないのかもしれない)。ただ、災害が起きた時などに駆けつける若者を見るたびに、その気持ちの尊さや行動力に感心するのだけれど、そのふたつの違いの大きさに戸惑うこともあった。
かつては若い人たちとの付き合いを楽しんでいた、というか刺激が受ける部分があったAだったが、最近はすっかりそういうことがなくなった。まず、会う機会がなくなってしまった。多くの若者の振る舞いや考え方との差異がとても大きいと感じるようになってきたのだ。会う機会といえば、減ったのは若者とのことだけじゃない。もともと人付き合いをこまめにやるということがなかったせいで、今や人と会って話をする機会がほとんどない(カフェのカウンターの中では別だが)。これが年をとるということなのだろう。
そんなことを思っているうちに、Aは人に何かを説明しようとするとき、つい先人の言葉を引用してしまうことを思い出した。例えば、こんな具合だ。
「人生は短いから、『やりたい事をやんなさい。後で後悔しなさんな。やりたい事やんなさい。グラスのふちに唇をつけたらとことん、一滴残らず飲み干しなさい。後で戻ってきても、もう雫は残っていない。今のうちに飲みつくしなさい』と言った日本の作家がいるよ。元は、オーストリアの医師で劇作家のもののようだけどね」
これはどうしたことか。まあ、自分が言うより、先人たちの方がずっと的確に言い当ててくれるということには違いないが。これは、とりもなおさず自分に自信がないということの表れではないか。いやそれよりも自分自身がない、ということなのかもしれない。それはまずい。そう思って、これではわからないままむづかしい言葉を使いたがる若者と変わらないなと、苦い思いを飲み込んだ。
22
ある時、ちょうど客が引けた時、Aはずっと気になっていたことを思い切って言うことにした。とくにたいしたことというわけじゃなかったので、なぜそいうことになったのか。
「なあ。お前さん、話す時に語尾を伸ばすだろ?」
「えっ、そうですかあ?」
Cはなんのことかというような口調で訊き返した。
「ほら、やっぱり」
「あらまあ。でもそんなに変ですかあ?」
全く気にしていないようだった。
「変だろ?」
「どうしてですかあ?」
「なんだか、調子が狂うんだよ」
「でも今まで誰もそんなことは言いませんでしたよう」
Aは、そんなことはあるはずがないという気持ちと、俺は人が気にしないような事が気になるたちなのかもと思いながら訊いた。
「そうなのか?」
「はい」
「でも、俺は気になるんだよ」
「はあ」
「なんだか、はぐらかされているような気がするんだよ」
だんだん、イライラしてくるのがわかった。たぶん、Cとの付き合いに慣れるにつれて、遠慮や気遣いがなくなってきているのだ。それにどうしたことか、Aはこのところ、意に反して邪悪な言葉や悪いことが起きる場面が、不意に脳裏をよぎる時があったのだ。
「へえ。でも考えすぎじゃないですか」
Cは、いかにもつまらないことを言うという調子で言い捨てた。
「ともかくも、俺は嫌なんだよ」
「ふーん。そうなんですかあ?」
「ああ。だからやめてくれ」
「何をですかあ?」
Cも、同じような気持ちになってきているようだった。
「それだよ。今の口調」
「えっ?」
「さっきも語尾を伸ばしたろう?」
「そうでしたあ?」
「そうだよ。今もそうだ」
「はあ。いけませんかあ?」
「だから、やめてくれ」
「だから、何をですかあ?」
次第に意地の張り合いのようになってきたが、2人とも気づいているのか、いないのか、何れにせよやめようとしなかった。
「だから、それだよ」
「はあーい」
「わかったのか?」
さらに強い口調になった。
「ええ」
「ほんとうか?」
「わかりましたあ」
わざと語尾を伸ばした口調で言うと、店の外へ出て行った。
その日は、それきり戻って来なかった。
Aは、Cと小さな衝突をすることが増えていることに、なんとなく気づいていた。
子供扱いしすぎたのか。あるいはまた、ついぞんざいな対応をしたせいか。あるいは、恐れていたように、慣れ過ぎてしまったのかもしれなかった。
急募!
未だ、何の反応もないのですが……。
今年も、「絵本大賞」に応募しようと思います。
昨年は、「まだやってんの?」と呆れられましたが、石の上にも3年。
そこで、このコーナーに掲載したうちのどれを応募するのがいいか、皆様のご意見を頂戴したいと思います。
もう一つの小説の読者も(できれば編集者、ご意見番役を引き受けてもらえるとありがたいのですが)。
責任を押し付けるようなことはしませんので、どうぞ気楽にご意見を。こちらまでお知らせください。
なお応募の都合上、9月末日までの早いうちに頂戴できれば助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
2024.09.29
新企画日曜版延長戦 FANTASY 29 「デザイン事務所とカフェの仕事と推理」14
デザイン事務所とカフェの仕事と推理 第14回
それからは、Aは時々、Cのおばあさんの様子を尋ねるようにした。それがいいことかどうかはわからなかったが、他に思いつかなかった。おばあさんのことを気にかけているのがCや叔母夫婦だけじゃないこと、他にも側にいることを知らせるようにした方がいい気がしたのだ(何と言っても、AはCの近くにいる時間が多かった)。そうすることで、Cの気持ちが少しでも和らぐならばいい、と思ってのことだった。
ある日、客足が引いて暇になった時、Aはいつものように、Cに声をかけた。
「おばあちゃんとはどうだい?時々会っているのかい?」
「ええ、はい」
Cが答えたが、いつものような快活な口調ではなく、少しためらったようでもあった。Aはちょっと気になったが、まあ話題が話題だし、仕方がないのだろうと思い直して訊いた。
「具合はどう?」
「相変わらずですけど、でも少しマシになってきたかな……」
「それは良かった」
「ええ。ありがとう……」
と言った後、しばらく黙り込んだかと思ったら、わっと泣き出したのだった。
すっかり驚いたAは、なんと声をかけていいものかわからずに、オロオロするばかりだった。ただ、見ているしかなかった。慣れていなかったのだ。それからしばらくして、Cが問わず語りに話し始めた。
「おばあちゃんが家にいなくなって、寂しい……」
小さな声だった。
「ああ」
「家に帰っても、もう誰もいないんです……」
「ああ」
「家に帰っても、真っ暗なんです」
「ああ。おばさんたちはどうした?」
「おばさんたちは、よくしてくれています」
「それは良かった」
「でも、今は店が終わると、すぐに帰ってしまうんです……」
「どうしたんだい?何かあったのか?」
「はい、子どものことがあって……」
「うん」
「学校に行きたがらなくなったと言うんです……」
おば夫婦も、問題を抱えていないわけじゃなかったのだ。これまで、Cはそのことを話さなかったし、感じさせるようなそぶりもなかった。逆に、それだけ澱のように心の底に積もっていったのだろう。Aもそのことに気づかなかった。
「そうだったのか?」
「だから、その前は、お店が終わったあとも話しを聞いてくれたり、時々はおばあちゃんも一緒に、5人で食事もしたりしていたんです」
Cは、遠くの方を見るように言った。
「ああ」
「それが、おばは早く帰らなくちゃいけないし、おじも片付けが終わるとすぐに……」
「ああ」
おば夫婦に子どもの問題が起きる前は、いつもとはいかなかったけれど、おばたちはCのそばにいた。男の子を含めた5人が家族のように時間を共にすることが少なからずあったのだ。それが、おばあちゃんが施設に入るのとほぼ同時に、すべて一変してしまったのだった。
お店が終わると、おばは、
「悪いわね、帰るわね」
と言って足早に去り、おじも片付けを早々にすませて、
「俺も帰るよ。じゃあ」
と、これまた家路へと急ぐのだ。
二人が帰ってしまうと、Cだけが家に残される。Cの帰りがもう少し遅くなると、その二人さえいない。シャッターの降りた店の奥の、暗くてひっそりと静まり返った部屋に入らなければならないのだ。誰もいなくなってしまった部屋にただ一人、いなければならないのだ。寂しさが募り、どうしていいのかわからずに、孤独な時間をたった一人で耐え、やり過ごさなければならなかった。やがて自分自身のことさえ、見失ってしまいそうになるのだ。まだ二十歳になるかならないかという若い女の子にとって、過酷で無慈悲な時間だ。
「おばあちゃんが家にいなくなって、わたし、寂しい……」
Cがもう一度呟いたが、Aはどうしていいかわからないまま、黙っているしかなかった。「ああ。寂しいよな」
Aは、Cのわずかに震える小さな肩を見ながら、ぼそっと応じるのが精一杯だった。
それから、Cは意を決したように、
「ごめんなさい。今日はもう帰ってもいいですか?」
と言うと、返事を待たずに帰って行った。
それで、Aは、少し早いが、店を閉めることにした。そして、カウンターに座って、Cの話しを思い返した。まだ真っ暗というのではなかったが、人気のない静かな空間で一人じっと座っていると、自分には何もできそうにないことがいかにも役立たずの人間であることの証明という思いがしてきて、寂しかった。
急募!
未だ、何の反応もないのですが……。
今年も、「絵本大賞」に応募しようと思います。
昨年は、「まだやってんの?」と呆れられましたが、石の上にも3年。
そこで、このコーナーに掲載したうちのどれを応募するのがいいか、皆様のご意見を頂戴したいと思います。
もう一つの小説の読者(できれば編集者、ご意見番役を務めてもらえるとありがたいのですが)も。
責任を押し付けるようなことはしませんので、どうぞ気楽にご意見を。こちらまでお知らせください。
なお応募の都合上、9月末日までの早いうちに頂戴できれば助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
2024.09.24
新企画日曜版延長戦 FANTASY 28 「デザイン事務所とカフェの仕事と推理」13
デザイン事務所とカフェの仕事と推理 第13回
18
Aは、歳をとるにつれて、自分と周囲の関係は安定すると思っていた。ところが、どうしたことか、今更ながら人の付き合い方に戸惑うことが増えている気がした。それで、ただでさえ少なかった付き合いがさらに少なくなるようだった。とくに若い人との関係がそうだった。
Aはすでに十分すぎるほどに年を取っていたと思っていたし、その通りだったが、何一つ成し遂げたものがないことを自覚していた。事務所の看板を掲げた住宅のデザインはもちろん、デザインの分野等のいくつか、あるいは詩や小説にも関心を持ち、自分でもやってみたいと取り組んではみたけれど、どれもが中途半端なまま終わった。うまくできず、人を楽しませたり喜ばせたりと言うことはもちろん、本人でさえも達成感を味わったものはなにひとつなかったのだ。おまけに人との接触もなくありつつある。Aは時々、不意に、
「俺はどうなるのだろう」
と独り言が口をついて出ることがあった。確かに年は取ったが、成熟したとは言い難かった。人間も手をかけてやらないと古びるだけで、熟成した上等のチーズのようにはならないのだ。
その一方で、職を得て、これまでなんとか暮らすことができただけでも、できすぎた幸運というものであることについても思い返すようになった。それが、周りの人々に恵まれた結果だということもすでに自覚するようになっていた。だから、これからは自分にできる限りのことを精一杯やろう、と思い定めるしかなかったのだった。
19
ある日のこと、営業を終えていつものように乾杯していた時、
「じつは、おばあちゃんが…」
唐突に、Cが深刻な顔で切り出した。以前のようにおばあさんがとは言わなかった。Aは、このことが気になった。
「ん、おばあちゃんが、どうした?」
思わずどうしたことかと思って、身構えながら訊いた。Cは、しばらく黙ったままだったが、そのあとで言ったのだった。
「おばあちゃんが…、変なんです」
珍しく、思い詰めたような言い方だった。
「何があったんだい?」
Aはさらに心配になって訊いた。
「時々、わたしのことを責めるようになったんです」
「うん」
「今までそんなことはなかったのに……」
「うん」
はじめて見るCのその様子に、Aは聞き役に徹するのがいいと思った。
「ふだんはとってもやさしいおばあちゃんなんです…」
「うん、それで?」
「あんたは、恩知らずだと言うんです……」
「えっ?」
「じつはわたし、おばあちゃんに育てられたんです」
思いがけないことだった。
Cの家は八百屋だから、Aもときどき買い物に出かける。そこでは、40代くらいの男女が働いていたので、すっかりCの両親だと思っていた。ところが違っていたのだ。彼らは亡くなった母親の妹夫婦だと言うのだった。彼らはCとおばあちゃんと一緒に暮らしているわけではなく、店を開けるために、毎日通ってくるのだ、ということだった。
「おばあちゃんは、亡くなった父のお母さんなんです…」
「うん」
「ふだんは、とってもやさしいおばあちゃんなんです…」
Cが言葉を詰まらせた。
「うん、それで?」
「わたしをひどい勢いで罵るんです」
「えっ」
「あんたは、恩知らずだと言うんです」
「えっ?」
「でも、ある時はとっても優しいし、元気だった時と変わらない…」
「えっ?そうか……(認知症か)」
Aには覚えがあった。認知症になると、それまで思いもよらなかったような言葉を口にするようになることがあるのだ。Aも経験したことがあったのだ。その時に言われたのは、それを解決するには、引き受けるしか方法はないと言うことだった。
「あんたは、恩知らずだと言うんです…」
Cはもう一度小さく呟くように言った。
「そうなのか」
「はい」
目元には涙が一筋、流れたようだった。
「たいへんだな。わかるよ」
Aは、気づかないふりをして言った。
「えっ?」
「まあね、似たようなことを知っている」
「はい。でも、ふだんはとってもやさしいんです」
「ああ。病気なんだよ」
「どうなっちゃうんだろう」
Cがか細い声でつぶやくように言った。今までの明るい姿からはとても想像もつかないほど頼りなさげだった。
「しようがないんだ……」
そう言ったあと後ろを向くと、大丈夫とAは自分に言い聞かせるように呟くと、思い切るように明るい声で言った。
「さあ、なんか食べよう。作るよ。何がいい?」
Aが訊いた。おいしいものを食べれば、元気になる。他の方法は知らなかった。
「やさしい彩りのパスタがいいな。今日のような雨の上がった夏の午後に合うような」
と、Cがほんの少しだけ、元気を取り戻したように答えた。
「そうだね。それじゃあ仰せの通りにいたしましょう」
ちょっと大げさに腰を折って、言った。すると、Cは泣き笑いのような顔をした。そして、
「お願いします」
Cが背中で言った。語尾を伸ばさなかった。そう言うのを聞きながら、Aは足早にキッチンに向かった。
で、トマトとブロッコリーのペペロンチーノにしたけれど、案外よかった。色合いも、梅雨明けを控えた晴れた日のランチのぴったりな気がした。出来上がるとすぐに盛り付けて、香りのいいオリーブオイルを垂らして、テーブルに運んだ。とにかくスピードが大事。スパゲティは熱いうちに食べることが肝心。そうじゃないと美味しくないのだ。Aは、今日のような日には特にそうだ、という気がした。
「できたよ」
「わあ、美味しそう。綺麗な色ですね」
Cが小さく、驚きの声を上げた。
「そうだね。初夏のテーブルにぴったりだろう?」
「ええ」
「さあ、どうぞ召し上がれ」
「あ、おいしい」
Cが小さく笑った。いっときのものかもしれないけれど、美味しいものの効果があった。
食べながら、Cはおばあさんとの生活について、もう一度話し始めた。初めてのことだった。それまでもいろいろと話すことはあったが、それは学校のことや好きなことについてがほとんどで、おばあさんとの私生活のことは時々それにほんの少し混じるくらいだった。彼女が家族のことについて話すことは、これまでほとんどなかったのだ。
おばあさんが体調を崩してからしばらくは、Cが自分で世話をしていたようだった。若い彼女にとって、それはたやすいことではなかった。学校もあるし、アルバイトもしなければならなかった。これを見かねた叔母夫婦がソーシャルワーカーと相談して、幸い空きが出たという地域の施設(嫌な言葉だ。人がまるでモノか何かのようだ)があって、そこに入ることになった。
3分の1ほども食べ進めた頃だったろうか、Cが切り出した。
「あんたは、恩知らずだと言うんです…」
これで3度目だ。先ほどと同じ言い方だったが、さらに声は小さくなっていた。おばあさんの口から出た言葉が、よほど堪えたのだ。まあ、無理もないことだ。
「うん」
Aは、うなづくことしかできなかった。
「これからどうすればいいんだろう…」
Cがつぶやくように、小さな声で言った。
「うん」
「これからわたし、どうなるんだろう…」
Cがまた、不安そうに、震えるような小さな声だった。
Aはなんと言っていいものか、わからなかった。うんと言うしかなかった。何か有効な助言をしたかったが、思いついたものは何もなかったのだ。若い女性との話に慣れていないこともあったかもしれない。いい年なのに、何も有益な経験はしてこなかった、ということに改めて気づくしかなかった。
「でもね、それまでは幸せだったんだろう?」
「ええ」
「よくしてくれていたんだよな?」
「はい」
「じゃあ、そのことを思いながら、おばあさんと接するのがいいんじゃないか?」
「そうなんでしょうか?」
「おばあさんは病気なんだ。残念だけど、すぐには治らない。だから、受け入れるしかないんだよ」
Aは自分に言い聞かせるようだった。
「ええ」
「いつか、よくなるかもしれない。もしかしたらこのままかもしれない」
「はい」
「でも、好転するかもしれない。そう思って、接するしかないんじゃないのかな?」
「ええ」
「おばあさんがしてくれたことに感謝しながらね」
「ええ。そうですね。そうするしかないですよね。それがいいですね。そうします」
Cが一気に言った。自分の心と頭に染み込ませようとするかのようだった。
それがなんであれ、まずは対象を愛する心あってこそなのだ(Aは、最近になって、そう思うようになったのだった)。
急募!
未だ、何の反応もないのですが……。
今年も、「絵本大賞」に応募しようと思います。
昨年は、「まだやってんの?」と呆れられましたが、石の上にも3年。
そこで、このコーナーに掲載したうちのどれを応募するのがいいか、皆様のご意見を頂戴したいと思います。
もう一つの小説の読者(できれば編集者、ご意見番役を務めてもらえるとありがたいのですが)も。
責任を押し付けるようなことはしませんので、どうぞ気楽にご意見を。こちらまでお知らせください。
なお応募の都合上、9月末日までの早いうちに頂戴できれば助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
2024.09.23
新企画日曜版 FANTASY 27 「デザイン事務所とカフェの仕事と推理」12
デザイン事務所とカフェの仕事と推理 第12回
17
ある日、忙しかったお昼時が過ぎてようやく落ち着いた頃のことだった。
「ちょっと、お姉さん」
と呼びかける声が聞こえた。
「……」
「そこのお姉さん、注文をいいかな」
「誰のことでしょうね?。だいたい、わたしはお姉さんじゃないし」
Cが言った。なんだか機嫌が良くないようだ。
「他にいないだろ?お前さんのことに決まっている」
客の方が続けた。
「お姉さんなんかじゃありません。じゃあ、わたしはおじいさんて呼べばいいんですか」
「そうとんがりなさんなよ」
また、客が言った。
「とんがってなんかいません」
Cがむくれながら、言う。
「参ったな、なんだかえらく機嫌が悪いね」
お客も、仕方がないという感じで返すしかなかった。
Aが助け舟を出したものかどうか思っていたその時、
「じゃあ、パスタって呼ぶのがいいか?」
隣の客が言ったのだった。
「えっ?」
Cはすっかり困惑しているようだ。
「最近、パスタが作れるようになったんだろ?」
「ええ、まあそうですけど」
「じゃあ、いいじゃないか?」
「嫌ですよう。第一、注文かどうかもわからなくなるし」
少しだけ機嫌が直ったようだった。
「あ、そういうこともあるか。まあいいじゃないか、あんがい楽しいんじゃないかな?。おーい、パスタ、パスタ頼むよなんて」
「呼んでいるのか、注文しているのか。もしかしたら、パスタ一皿なのか、二つなのかわからなくなることもありそうだぜ」
「じゃあ、パスタちゃん、パスタをひとつって言うのか?」
「嫌ですってば。どっちも、嫌ですっ!」
Cが言ったが、お客の方が上手のようだった。Cをからかって、楽しんでいるのだ。
その様子を見かねたのか、それともさらにからかってやろうというのか、また少し離れたところに座っていた他の客から声がかかった。
「お嬢さん、あれは誰の絵?」
「わたしの絵です」
「えっ?わたしのえ?お嬢さんは、のえっていうのかえ?」
「違います。あの絵は、わたしの」
「だから、のえはわたし?のえが名前なんだろ?」
また始まった。
「違いますよう、あの絵はわたしが描いたんですって言ったんです」
「へえ」
「でも、たいしたもんだね、ちょっとシャガールに似てるような……」
「そうですかあ。嬉しい。わたし、シャガールが好きなんです」
褒められて、Cの機嫌がすっかり直った。確かに、時々気むづかしくなる時があるようだが、やっぱり若い女の子ってことか。
「やっぱりね。他には?」
「マチスも好きです」
すっかり気分が良くなったようで、楽し気に答えた。
「へえ。じゃあ、これからは画伯と呼ぶことにしようか。でもちょっと大げさだから、の絵ちゃんということでどうだい?」
画家の名前を持ち出したお客が訊くと、
「お、いいね。ノエちゃんで行こうよ。お嬢さんとかは堅苦しくていやだし、お嬢というのもなんだかね」
周りからも、次々に声がかかった。
「そうだね」
「えっ?」
Cは、すっかり困惑しているようだったが、怒っているふうではなかった。
「いいじゃないか、それとも画伯がいいかい?」
「もう、どうでもいいです」
Cが、あきれたように言って、その場を離れた。客たちはその後もしばらく声を掛け合っていた。
「じゃあ、の絵ちゃん、ノエちゃんでいこう」
「そうだな」
「いいね」
ひょんなことから、店でのCの愛称が決まった。
ひとまず、騒ぎは無事に収束したようだった。
まあ、終わりよければすべてよしとしてもいいようなものだが、その後でAは、念のためにもう一度、Cにカフェが客商売であることとデザインの仕事だって何だって、変わらないことを、思い出させることにした。
「今日も、最初はお客の言ったことにムッとしてたよな?」
Aが言う。
「ええ、まあ」
Cは、不承不承認めた。
「お客のいうことにいちいちカリカリしないように、って言ったことがあったろ?」
「えっ。そうでしたかあ?」
Cはとぼけて言う。
「Gが同じように言った時だよ。まあ、気に障ったかもしれないけど」
Aは、分かっているだろという気持ちだった。
「ああ。そうでした」
「お客だって悪気はないんだよ。たいていは、ちょっとからかってみたいだけなのさ」
「そうかなあ?」
Cが、わからないというように言った。
「そうだよ。特にお前さんのような若い娘に対してはね」
「そうですかあ?」
「ああ、そうさ」
「そうかなあ?」
「あんまりそういう機会もないから、面白がってからかいたくなるんだよ」
「へえ」
「でもね、デザインの仕事も似たようなもんだよ」
「そうなんですか?」
「そうさ。だからまあ、あんまり怒りなさんなよ」
「だって」
Cは、まだ不満げのようだ。
「お客相手は、こちらの思うようにはいかないんだから」
Aが続けた。
「そういうものなんですかねえ?」
「ああ。デザインの仕事だって何だって、変わらないさ」
「ふーん」
「昨日いいと言っていたからその気でいると、今日になったら気に入らないから変えてくれと言われることなんかしょっちゅうだよ」
「へえ?」
「まあ、ちょっとくらい腹が立つことがあってもぐっと飲み込んで、お客の気持ちになってみることだね。そうすると、たいてい腹も立たない」
Aは、自分は必ずしもそうすることができるわけじゃないことを自覚していたが、ま真理は真理だ、と思って言った。お客ばかりじゃない、相手のあることはみなそうなのだ。それが正当なものか理不尽なものだあるかに関わらず、彼らには彼らなりに理由があるものなのだ。
「わかりました」
Cも、素直にうなづいた。そして、決まり悪そうに笑った。もうわかっているようだったので、Aはくどくどと言う必要はなかった。なかなかむづかしいもんだなと思いながらも、ひとまずほっとしたのだった。
だが、その後でCがふっと顔を曇らせたようだったことに、Aは気づかなかった。
一方、偶然に決まった愛称については、はじめこそ嫌がっていたCも、慣れたのか、それとも案外気に入ったものか、ノエちゃーんと声がかかると、はあーいなんて答えている。まあ、Aには若い女の子の気持ちはわかりようがなかった。
急募!
未だ、何の反応もないのですが……。
今年も、「絵本大賞」に応募しようと思います。
昨年は、「まだやってんの?」と呆れられましたが、石の上にも3年。
そこで、このコーナーに掲載したうちのどれを応募するのがいいか、皆様のご意見を頂戴したいと思います。
もう一つの小説の読者(できれば編集者、ご意見番役を務めてもらえるとありがたいのですが)も。
責任を押し付けるようなことはしませんので、どうぞ気楽にご意見を。こちらまでお知らせください。
なお応募の都合上、9月末日までの早いうちに頂戴できれば助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
2024.09.22
新企画日曜版再延長戦 FANTASY 26 「デザイン事務所とカフェの仕事と推理」11
デザイン事務所とカフェの仕事と推理 第11回
16
カフェに、いつものようにGがやってきた。しかし、今日はいつもより遅いようだった。Gはたいてい本日のパスタを頼む。
「やあ、いらっしゃい。本日のパスタでいいかい?」
Aが訊いたが、確認のためというより、まあ挨拶がわりだ。するとGが、小さくうなづいた。
「ああ」
本日のパスタは夏の茄子を使った「ノルマ」だ。いつの間にか、もう7月なのだ。「ノルマ」はシチリアの名物料理で、揚げ焼きにした茄子(本来は揚げるようだが、揚げものをしないAは揚げ焼きにする)とトマトのソースのパスタだ。19世紀初頭のイタリアシチリア出身の作曲家ヴィンチェンツォ・ベッリーニのオペラ『ノルマ』が名前の由来で、優れたものを指すのだという(Aの作る「ノルマ」が、優れたものかどうかはわからなかったが)。今日はショートパスタのフジッリを使うことにした。
食べ終わったGが「ごちそうさま」と言ったきり軽口も叩かず、何やら考え込んでいる風だった。あのおしゃべり好きのGが、黙ったままとは。いったい、どうしたというのだろう?何かあったのだろうか。気になったAは声をかけた。
「やあ。どうした?」
「うん?」
Gは心ここに在らずという様子で、生返事をした。さらに心配になったAはGの正面のところに行くと、顔を見ながらもう一度訊いた。
「いったい、どうしたんだい?」
「えっ?」
Gが顔を上げたが、そう言っただけだった。
「ずっと黙り込むなんて珍しいじゃないか。なにか心配ごとでもあるのか?」
「ああ」
相変わらず、生返事をするばかりだった。
「どうした?」
「うん」
「で、何かあったのか?」
何度か押し問答が続いた後で、ようやく言った。
「実は、いなくなった」
「えっ?」
「いなくなった」
「誰が?」
「猫」
「えっ?」
「だから、猫がね」
「何だって?マジかよ?」
心配して損したとばかりに、Aが思わず毒づいた。
「猫だよ」
Gがなおも繰り返した。
「なんだよ。心配したのに」
Aは、すっかり拍子抜けしまったようだ。
「でも、本当なんだ。一緒にいなくなった」
Gは、いつになく混乱しているようだった。
「そうなのか?それで、誰と?」
「だから、猫と一緒に」
「だから、誰がだよ?」
妻か、子供か、それとも看護婦なのか、Aはまた心配になって訊いたのだった。
「犬だよ」
「なんだよ。心配したのに」
またまた、拍子抜けした。でも、Aはそう言った後で気づいたのだったが、人も犬も猫も、家族のような存在である限り変わらないのだ。
「でも、本当なんだ。犬と猫が一緒にいなくなった」
「ふーん」
「なんだよ。冷たいね。俺にとっては、一大事なんだよ」
「ああ、それで何があったんだよ?」
「それが、さっぱりわからない。急にいなくなった」
「最後に見たのは?」
「昨日の夜。それから俺は定例の会合に出かけたんだけどね」
「ふーん」
「それで、今朝散歩に連れて行こうとしたら、いなくなっていたんだよ」
「うん」
「心当たりはないのか?奥方や子供は見ていないのか?」
「ああ、妻は今実家にいる。子供も一緒だ」
「えっ?何かあったのか」
「実はちょっとした諍いがあって、数ヶ月ほど前から実家に帰っているんだ。それで、俺が猫と犬の世話をすることになったんだ。妻が知ったらおおごとだ。ますます分が悪くなる」
Gが、ちょっと気まづそうに言った。
「ふーん。それじゃあ、奥方の方が心配じゃないか?」
Aが驚いて訊く。
「いや、たいしたことじゃないんだよ」
こちらの方は、さして気にしていないというふうだった。
「そうなのか?」
「ああ。妻もわかっている。ちょっと俺を困らせようという魂胆なのさ。前にもあった」
「そうなのか」
Aは数ヶ月にもなるというのにかと思ったが、こうしたことは人それぞれだからと思い直して、理由は訊かないことにした。事情はわからないが、まあたぶん、さほど心配することはないのだろう。
「うん。面目ない。あ、お前さんが探してくれないか。前に似たようなことをやったことがあったろ?」
Gが、いいことを思いついたとばかりに、明るい声で訊いたのだ。
これを聞きつけたのか、Cが水の入ったサーバーを持ってやってきた。
「お水のお代わりはいかがですか?」
「ああ、もらうよ」
Gが言って、一息ついた。AはCの方を見ると、声をかけた。
「お前さん、猫も、犬も好きですって言っていたよな?」
「ええ、言いましたけど。それが何か?」
Cが、腑に落ちない様子で訊いた。
「犬と猫との付き合い方の違いは、なんだい?」
「『犬は人につき、猫は家につく』、って言いますね」
Cが、こともなげに答えた。
「ああ、そうだった」
Aが、言った。
「なんだよ?」
Gが割り込んだ。その時、Aは思うところがあって、Cをこの場から遠ざけることにした。
「悪いが、他の席も水が足りているか、見てきてくれないか」
Cは離れがたい様子だったが、Aに促されて立ち去ったが、その時に首を少し傾けて振り向くとこう言ったのだった。
「猫は、連れ出せませんよ」
Cが渋々といった感じで離れて行くと、Aはまた質問を続けた。
「それで、犬と猫の世話は誰がしていた?」
「妻だよ。それが何か関係があるのか?」
「それで、奥方はどうだい?不満じゃなかった?」
「ああ、確かに。たまには散歩に連れて行きなさいよとか、いろいろ言われていた」
「うん。で、どうした、たまには手伝っていたのか?」
「いや、あんまり得意じゃないしね。でもまあ、そうしたもんじゃないか?。ほら、俺は知っての通り、忙しいからね」
「確かにね。でも、奥方はそう思ってはいなかったかもしれないぜ」
「脅かすなよ」
「あのね、この際だから言っておくと、お前さんの仕事は時間が来れば終わりだけど、家事はそうはいかないんだよ」
「なんだよ。それが、今回のことと関係がありそうなのか?」
「たぶんね。そのことも諍いの原因の一つだったんじゃないのか?」
「ああ、まあね」
それから、Aはさらに踏み込んで訊いた。
「立ち入ったことを訊くけど、寝室は同じなのかい?それとも別寝なのか?」
「えっ。それが何か関係があるのか?」
Gが、ちょっと気色ばんだようだった。
「いや、別にお前さんの私生活を覗こうというわけじゃないよ」
Aが、付け加えた。
「じゃあ、どういうことだよ?」
「わが国では、だいたい子供が生まれた後は半数以上が夫婦別寝になる、と言った建築家がいたんだよ」
「そういうものなのか?」
「まあ、そうしたもんじゃないか?。俺はよく知らないけどね」
「なんだよ。だから、それが今回のことと関係があるのか?」
「まあね。話したくないなら、無理には訊かない。別に知りたくもない。第一、お前さんが持ち込んできた話だしね」
「いや、そう言うなよ。確かに、寝室は別だよ」
「やっぱりね」
「やっぱり?それで何かわかったのか?」
「寝室は少し離れている?」
「ああ。生活のリズムが全然違うもんでね。音が漏れて起こすことのないようにしている」
「うん。なるほどね」
「なんだよ?」
「だいたいわかった気がするよ」
「そうなのか?で、どこにいるんだ?」
「知りたいのか?」
Aが、訊く。
「知りたいのかって、当たり前じゃないか。だから、藁にもすがる思いでここにきたんじゃないか」
Gが、たまらず言った。Aは、初めから話すつもりできたんだと思った。あんまり嬉しい話じゃないから、なかなか話せなかったんだろうと、Gの気持ちを想像して同情したが、もう少しからかいたくなった。で、言った。
「そうなのか?俺は藁なのか?」
「そんなつもりじゃないよ。焦らさないで、早く教えてくれよ」
Gが急かした。Aは、からかうのはこのくらいにしておこうと思って、自分の推理を開陳することにした。
「猫は、お前さんの家にいるよ」
と、Aが言った。
「だから、いなくなったって言っただろ?」
Gががっかりして、怒ったような口調になった。
「目に入らないだけだよ」
Aが軽く受け流して言う。
「えっ。さっぱりわからない」
Gは、ますます混乱したようだった。
「奥方の寝室を探してみなよ」
「そうなのか。でも、餌はどうなんだ?」
「奥方の実家は、そんなに遠くなかったよな?」
「ああ」
「当然、自宅の鍵も持っている」
「ああ、そうだったのか」
Gがようやく思い当たったようだった。
「で、犬は?」
「簡単なことじゃないか。実家だよ」
「なるほど、そうか」
Gは安心したようにそう言うと、そそくさと帰っていった。
後日、Gがお菓子とお酒を持って店にやってきた。
「どうしてわかったんだよ?」
「ああ。Cが言ったろ、『犬は人に付き、猫は家に付く』って。犬は旅行に連れて行くことができるけど、猫はそうはいかない。環境の変化を嫌うそうだからね」
「なるほどね。そうか。となると、お菓子は小さすぎたか?」
「それにね、自慢じゃないが俺はね、人には好かれないが、犬や猫には案外好かれるんだよ。だから、言えた義理じゃないが、お前さんももう少し他者の心理を学んだ方がいいね。ま、内科医でよかったよ」
「どういうことだよ」
Gは、ちょっとムキになって言った。
「精神科医だったら、と思ったんだよ。あ、そうでもないか。内科医だって、問診が重要だろ?だいたい、今度の騒ぎだって、お前さんが奥方の気持ちを理解していなかったことにある」
Aが言った。教師が、聞き分けのない学生に対する時の口調のようだった。
「面目ない」
Gが、うつむきながら言った。
「もう少し、人の身になってみろってことだね。俺だって偉そうには言えないけどね」
「ああ、そうだな。これからはそうするよ。あのおばさんにも、もう少し優しく接することにするよ」
Gが今度は、素直に同意した。
「ああ。そうするのがいいね」
そんなふうな小さな騒動も混じりながら、カフェの日常がだんだん定まっていくようだった。
急募!
未だ、何の反応もないのですが……。
今年も、「絵本大賞」に応募しようと思います。
昨年は、「まだやってんの?」と呆れられましたが、石の上にも3年。
そこで、このコーナーに掲載したうちのどれを応募するのがいいか、皆様のご意見を頂戴したいと思います。
責任を押し付けるようなことはしませんので、どうぞ気楽にご意見を。こちらまでお知らせください。
なお応募の都合上、9月末日までの早いうちに頂戴できれば助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
2024.09.17
新企画日曜版延長戦 FANTASY 25 「デザイン事務所とカフェの仕事と推理」10
デザイン事務所とカフェの仕事と推理 第10回
15
そして、5月も終わろうかというある日の昼下がり、カフェは料理教室に早変わりした。
まず、茹でたパスタとバターを混ぜただけのものにパルミジャーノ・レッジャーノをたっぷりかけただけの、「スパゲティ・アル・ブッロ」から始めることにした。
茹で方さえ覚えればいい。熱いうちにバターを絡めてよく混ぜ、チーズをおろしてかけるだけで十分いおいしいはずだ(Aは、昔これをよく作って食べていた。これを知ったのは、伊丹十三の『ヨーロッパ退屈日記』のはずだが、お金がない身には心強い味方だったのだ。上にかけるチーズも、紙缶に入った粉チーズしかなかった頃だ)。
「一番簡単なスパゲッテイ、いや今時はパスタというのか?」
「はい、どういうものなんですか?」
「イタリアの盛り蕎麦と言ったところだね、スパゲッティ・アル・ブッロ」
「へえ。どんなものなのかしら?」
「さあ、やってみよう」
「はい」
「まず、パスタ用の鍋にお湯をたっぷり沸かそう。お湯は多いほうがいい」
「はい」
「沸くまでの間に、スパゲティとバターと、チーズとお皿の用意をしておこう」
「はい」
スパゲティを200グラムほどと、バターケース、そして皿を2枚出した。それからパルミジャーノ・レッジャーノの塊とチーズおろし器も。
「沸きました」
「それじゃ、塩を一掴みほども入れて。教科書にはお湯の10%と書いてあるよ」
「入れました」
「それじゃスパゲティを入れよう。はじめはくっつかないようにかき回したら、あとは火を少し弱めて静かに茹でればいい」
「茹で時間は?」
「好みだけれど、表示時間より少し短いくらいがいいかも。よく1分前と言うけどね。メーカーによっても違うから、実際に噛んで試す方がいい」
「はい。セットしました」
「ついでに、チーズもたっぷりおろしておこう。そして、お皿も温めよう。スパゲティに限らず、温かいものは温かい器にが原則だ。お鍋の湯気を当てれば温まるよ」
「ああ、そうか」
「当意即妙。臨機応変。特に、スパゲティの場合は、時間との勝負なんだからね」
「わかりました。あ、もうすぐです」
「じゃあ、一本噛んでみて」
「はい」
「どう?アルデンテという言葉は知っているだろ?」
「はい。ちょっと固すぎるかも、と思います」
Cは忙しく手を動かしているせいか、それとも緊張しているためか、語尾を伸ばさなかった。
「じゃあ、もう少し待とう」
「はい。……。あ、ちょうどいいかも」
「それじゃ、皿に盛り付けよう。トングで取って」
「はい」
「次は、すぐにバターを入れてかき混ぜる。お湯を捨てて空になった鍋の中でやる人もいるようだけれど」
「こうですね」
「うまいね」
「少し高くなるように、盛り付けるのがいいんですよね」
「そう。よく知っているじゃないか」
「毎日見てますから」
「あ、そうか。最後にたっぷり、チーズを振りかけて」
「できました」
「さあ、食べよう」
「はい」
「どう?」
「おいしいです。本当においしい。すごーい」
「君がつくったんだ。スパゲッティ・アル・ブッロ。バターであえたスパゲッティ」
「はい。教わりながらですけど」
「これでもう、一人で作れるだろう」
「ええ。なんだか嬉しい」
Cは笑いながら言った。Aには、目の端に光るものが見えたような気がした。
「うん。『おいしいものを食べていれば、きっといつか幸せがやってくる』、と言った作家がいたようだよ」
「へえ、そうなんだ。たしかに、そうかも」
「ついでに言うと、丁寧に作ること。そうすると美しい味の料理になる。出来上がりをイメージしながら作ることも大事だね。盛り付けは、ならないうちは、あらかじめスケッチしておくといい。あ、お前さんは絵を描くんだったよね。ちょっと余計だったかもしれないね。でも、他の人のものを見て参考にするおくことも大事だよね。これは絵でも、デザインにおいても同じだと思うがね」
「ええ」
やけに素直だ。
「さてと、もう疲れたかい?」
「いえ。大丈夫ですけど」
「それじゃ、もう一人分作ってみるか?」
「ええ。なにを作ります?」
「こんども、同じように簡単なオイル系のものを作ろう」
「はい、何を?」
「君がここで初めて食べたやつ。あさりのスパゲティ、スパゲッティ・ボンゴレ・ビアンコ」
「へえ」
「用意するものは、さっきと同じように、1人前としてスパゲッティ100グラム、塩、ニンニク、赤唐辛子、アサリ、オリーブオイル2種、白ワイン、イタリアンパセリ、レモン」
「そんなに多くないですね、よかった。オリーブオイルを2種類用意するのは、どうして?」
Cも積極的になってきたようだ。
「炒め用と、風味付け用だね」
「へえ、そうなんですね」
「さあ、やってみようか」
「はい。まずお湯を沸かします」
「そうそう。その間に、アサリをこすり洗いしておこう。それから、ニンニクとイタリアンパセリをみじん切り、レモンはくし切りにしよう」
「はい」
Cは、あさりを丁寧にこすり洗いした後、イタリアンパセリとレモンも洗った。まな板をセットし、切る準備に入った。刻んだ材料を入れておくための小さなボウルも用意している。Aが調理するときのことをよく観察していたようだ。
「いいねえ。あ、木製のまな板はあらかじめ水で濡らしておくほうがいい。そうすると、匂いがつきにくくなるよ」
「なるほど」
Cはそう言いながら、刻み始めた。ゆっくりだけれど、綺麗に刻まれている。それから、小さなボウルに移した。そして包丁をさっと洗い、ペーパータオルで拭くと、レモンを切り、同じような手順で最後ににんにくを刻んだ。匂いが移ることを考えているようだ。筋がいい。
「いいね。お湯はどうだい?」
「はい、湧きました。これからパスタを入れます」
「よし。塩も忘れないでね」
「はい。でも、塩を入れるのはどうして?」
「そばやうどんとは違って、パスタには塩が入っていないんだよ」
「へえ、そうなんだ。入れました」
「入れたら、次は、フライパンにオリーブオイル、こっちは香りの少ないピュアオリーブオイルだよ、これを入れたら、火をつけよう」
「はい。火加減は?」
「弱火だね。焦がさないないようにね。にんにくと、それから唐辛子を入れて香りが立ってきたら、白ワインとアサリを入れて蓋をしよう。そしたら火を強くして、アサリの口が開くまで待つ」
「はい」
「音がしているだろ。アサリが開いている音だよ」
「ああ、そうだ。聞こえます」
「それじゃ蓋を取って、火を弱くして。それからちょっと上等の香りのいいエキストラ・ヴァージン・オリーブオイルを少々かけまわす。それから、フライパンを揺すって、油と水分を一体化させるんだ。いわゆる乳化というやつだね」
「はい。けっこう忙しいんですね」
「そう、さっきも言ったけど、パスタは時間の勝負だからね」
「ええ」
「そろそろ、パスタの茹で具合がいい頃だと思うけど。どうだい?」
「あ、もうようさそうです。」
「じゃあ、フライパンの中にトングで移して」
「はい。ヒョイっと」
「ざっとあえて」
「はい」
「じゃあ盛り付けよう。捻るようにして盛るといい、らしいよ」
Aはそのことを知っているが、不器用なせいでうまくできない。
「はい」
茹でている途中で温めておいた皿の上に、きれいに盛り付けられたボンゴレ・ビアンコが現れた。さすがに絵を描くだけのことはある、とAは感心した。
「いいね。少し残ったパセリをかけると、もっと美味しそうに見えていいかも」
「ええ、そうですね」
「さ、食べてみて」
「おいしい。さっきのものより、料理したって気分です」
「よかった。じゃあ、少し俺にもくれよ」
と言って小皿に取り分け、レモンを絞った。
「あ、レモンがあったんだ」
Cが気づいて、言った。
「たいていの料理書には、レモンをかけるとは書いてないような気がするけど、俺はレモンをかけた方がさっぱりするようで好きなんだよ。パエリアの時のようにね」
「なるほどね。わたしもちょっとかけてみようかな」
「どうだい?」
「おいしい。わたしは酸っぱいのが好きなので、こっちの方が好きかも」
「ね。じゃあ今回は、ここまでにしよう」
「はい。次はなんですか?」
「もうしばらくは、パスタを作ることにしよう。飽きたんじゃなければね」
「はい。飽きたりしません。なんだか嬉しい。おばあさんにも作ってあげよう」
次回は、カルボナーラを作ることにした。簡単だし、人気もあるから店でも出している。
その次は、基本のトマトソースとボロネーゼソース。パスタはこのくらいでいいだろう。あとは、応用すればいいのだ。
そんな風にして、しばらく料理教室が続いた。Aは、Cが料理に対する興味を持ち始めたことに気づき、しかも飲み込みが早いことに感心した。
急募!
今年も、「絵本大賞」に応募しようと思います。
昨年は、「まだやってんの?」と呆れられましたが、石の上にも3年。
そこで、このコーナーに掲載したうちのどれを応募するのがいいか、皆様のご意見を頂戴したいと思います。
責任を押し付けるようなことはしませんので、どうぞ気楽にご意見を。こちらまでお知らせください。
なお応募の都合上、9月末日までの早いうちに頂戴できれば助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
2024.09.16
新企画日曜版 FANTASY 24 「デザイン事務所とカフェの仕事と推理」09
デザイン事務所とカフェの仕事と推理 第9回
14
Hのところの家賃の値上げ攻勢は、さらに強まっているということだった。家賃の賃上げの阻止の交渉は、なかなか困難な状況が続いているようだった。Hにとって、値上げは困る。さりとて、移転というわけにもいかない。行くべき場所のあてはないし、ようやく常連客がつき、経営的にも安定してきたところなのだ。Hの前はどういうわけか長続きせず、何度か店名が変わった。Hが店主となってはじめて、やっと続くようになったのだった。それなのに、窮地に追い込まれてしまっているのだ。理不尽と言ったとしても、今のこの社会情勢では仕方がないのかもしれない。
AのところはいちおうEがオーナーだったから、今のところ直接的な影響が及ぶようなことはなかったが、いずれ直面する時があるかもしれない。何と言っても、不景気は何年も続いていて長引くばかりだったし、Eも歳なのだからないとは言えない。おまけに、彼に無理を強いるわけにはいかないのだ。
カフェの営業はだんだん軌道に乗ってきた。いつも満席というわけではないが、客足は安定していた。夜はやらないのかというリクエストもあるくらいで、評判も悪くないようだった。そのことは嬉しかったし、夜の営業のことも考えるべきかもしれないとも思った。
ただそれよりも、Aはずっと料理するばかりであることが、次第に負担に感じられる時があった。お客とおしゃべりすることさえできないのだ。俺は料理人になりたくてカフェを始めたというわけじゃない、という思いがだんだん強くなってきたのだ。夜の営業のことも大事かもしれないが、その前にこの状況をなんとかしなくてはいけない。それが先だ。それでなくては、続けられなくなりそうだった。
では、どうするか。新しい料理人を雇うのが最も簡単だが、それはできそうになかった。何より経済が許さないし、店の中の雰囲気のこともある。新しい料理人に加わってもらうことで、いろいろな関係が変わるのも嫌な気がした。とすれば、……。Aはあることを思いつき、さっそく翌日に試してみることにしようと思った。
開店前、Cがやってくると、Aは挨拶もそこそこに、切り出した。
「ところで、お前さんは、料理はできるのかい?」
「えっ?」
Cが、なにごとかと思って、聞き返した。
「だから、料理はできるのかなあって?」
「どうしたんですかあ?」
「料理ができるのなら、ちょっと楽になるかなあ、と思ってさ。俺も年だからね」
「ああ、そうかあ」
「で、どうよ?」
「ええっと、実は……」
Cが俯いた。
「うん?」
「……」
「なるほど、あんまり得意じゃないってことだな?」
「ええ、まあ」
「でも、お菓子はつくるんだよな?」
「はい」
「料理は好きじゃないのか?」
「ええ、まあ。と言うか、ええっと、しません」
Cは、小さな声で言った。
「そうなんだ」
「だいたい、おばあさんが作ってくれていたし……。おばあさんは、料理がとっても上手だったんです」
「よし、わかった」
「ごめんなさい」
「いいさ。気にするな」
「はい」
それで終わり、というわけではなかった。
「ところで、店が休みの日に少し時間を取れる時があるかい?」
さらに、Aが訊いたのだ。
「えっ?なんですかあ?」
Cがまだ続くのかというように、訊き返した。
「特訓するのさ」
Aが考えていたことを切り出した。
「えっ。なんの?」
驚いたCが言う。
「決まってるだろ、料理だよ」
「えっ。どうして?」
「嫌かい?」
「いやあ……」
「嫌なら、無理にとは言わないよ」
「いや、嫌じゃないんですが、できるかなあって思って」
Cが少し不安そうに答えた。
「できるさ」
Aはきっぱり言った。
「そうかなあ?」
「そうとも。舌を持っている限り大丈夫さ」
今度は、励ますように言った。
「舌?」
Cがまた、なんのことかわからずに訊いた。
「そう、舌。味がわかる舌だよ」
「そうなんですか?」
「おまけに、……」
Aは、一呼吸置いた。
「おまけに、なんですかあ?」
気になったCが、急かすように訊いた。
「おまけに、食べるのが大好きだ。そうだろ?」
「ええ、はい」
Cの顔がパッと明るくなった。そして、頬が赤くなったようだった。
「なら、心配ない。すぐ上手くなるよ」
「はい」
Cはあかるい子だったし、およそ悩みとは無縁のよう見えた。しかしAはこのところ、それだけじゃなさそうな気がなんとなくするようになっていたのだ。
AとCは、さっそく日にちと時間を相談して決めた。
急募!
今年も、「絵本大賞」に応募しようと思います。
昨年は、「まだやってんの?」と呆れられましたが、石の上にも3年。
そこで、このコーナーに掲載したうちのどれを応募するのがいいか、皆様のご意見を頂戴したいと思います。
責任を押し付けるようなことはしませんので、どうぞ気楽にご意見を。こちらまでお知らせください。
なお応募の都合上、9月末日までの早いうちに頂戴できれば助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
2024.09.15
新企画日曜版延長戦 FANTASY 23 「デザイン事務所とカフェの仕事と推理」08
デザイン事務所とカフェの仕事と推理 第8回
何年か前に住人と台所に焦点を当てた番組を見ていた時、出演していたとある老建築家が、歳を取ったら面倒くさいことが楽しいと言ったのだったか、それともあえて面倒にするのが楽しむコツと言ったのだったかは忘れたが、そうしたことを言った。
Aは、その時はそういうものかと思っただけだった。正直に言うなら、今だってそんな境地には至らず、できれば、面倒なことは可能な限り避けたい、と思う。
それでも、そうすることが必要な時がある、そうした方がいい場合があるのだ、ということはわかったような気がするのだった。
Aはしばらくの間、海が見えるところで育ったせいもあって、海を見ながら暮らしたいと願っている。歳をとるにつれて、その思いは強くなるようだった。ただ、うんと小さい時から海を見ながら育ったわけではなかったから、海というよりも大量の水を見たいと言う方がいいのかもしれない。しかし実際は、彼の住む小さなアパートから見えるのは、少しの緑と遠くの住宅の灯りが見えるだけだった。ただ、視界が遮られないのがせめてもの救いだ。だから、テーブルの上に水盤に見立てた小さな鉢を置いたり、ガラスの器に花を生けたりしている。
Aは最近になって、どうしてもっと早くに、自分の家を手に入れなかったのか、と思うことがよくある。それにはそれなりに訳があって、彼は若い頃、住宅は国や自治体が貸す方式がいいと考えていた。彼が敬愛する教授たちも皆、そう言っていた。そのために、家を所有しようとは考えなかった(後になって知ったのだが、教授たちは皆、自分の家を所有していたのだった。理屈とは別に、少なくとも我が国においては、借家はいつでも借りられるというわけではないことを、Aはずいぶんと後になって知った。きっと、彼らはそのことを知っていたのに違いない。それなら、どうして早く教えてくれなかったのか?当たり前過ぎた、ということなのだろうか)。もはや遅きに失するようだけれど、このことを後悔する時がある。それで、時々スケッチをする事もあったが、最近はそれも遠ざかったままだ。
Aが自分の家が欲しいというその理由の一つには、ものを捨てることができないということがある。ビンや缶でさえも取っておく。美しいと思ってのことというのももちろんだが、何かに使えるのではないかということも少なからずある。ボールペンの芯だって、簡単には捨てられないのだ。資源ごみとして金属部分とプラスティックの部分に分けなければならないのではないかと思って取っておくのだ。捨てるものをすぐに決めればいいものを、つい後回して、ものが溜まっていく。溜まるさらにとおっくうになって、さらに後回しになる。
Aは自身のそうした嗜好や性格をよしとしたわけではなかったが、簡単には変えられるものでもなかった。だから、つい溜まってしまったものをしっかり収納して、しかも見苦しくないような空間で暮らしたいというのが、Aの願いだった。
使われることのないまま、しかも安い物、間に合わせのもので埋めつくされると、目も当てられない。Aは適度に趣味の良い空間の中で暮らすことを願っていたが、果たせないままだ。ウィリアム・モリスが言うように高価であることとと趣味の良さは比例しないと思いたいけれど、かならずしもはそうはいかないことも多いのが現実だ。
Aの場合、それはとりもなおさず、ものが多いということだし、捨てられないで溜め込んでしまうということだ。CDなんかでも、同じ曲でも違う演奏者によるものを何枚も買ったりする。しかし、あるものに的を絞った収集家というのではない。それでも、例えばシリーズものは全て揃えなければ気が済まない。欠けることを嫌うのだ。もしかしたら、自身が欠けたところばかりだからということがあるのかもしれない。しかも、さらに悪いことには、それを徹底することも、体系化するというのでもないのだ。
この結果、出現するのは、聴きもしないしめったに観ることもないものがたくさん含まれた不完全なコレクションによるものの多さと収納スペースの狭さなのだった。捨てることができればいいけれど、捨てられないならこれを収納できる空間を備えた自分自身の住まいが欲しい、と思うようになったのだった。
床の上にものを置かないこと、このことが部屋をすっきり見せる。床が見える割合が大きいほど片付いて見える。Aはこのことを知っているけれど、実践できないのだ。知っていることと実践することとは、まったく別のことだ。はっきりいうなら、Aは実践する能力に欠けていたのだ。
翌朝、Aは5時に起床した。もう少し寝ていたいところだが、年を取ってからは、一度目が覚めたらなかなか眠れない。それで、顔を洗うと、Gに言われたように血圧を測って記録する。それから、小さなライカを持って散歩に出かけるのだ。散歩のコースは決まっていて、必ず海が見える場所に行く。そこから見えるのは、遠くに小さく見えるだけの海なのだが、それでも海は海だ。先日は、そこで初めて言葉を交わした。
その日は少し早めの散歩に出た。
何日か前に草が刈り取られて、すっきりしたけれど誰もいない小さな公園で、一人の女性に声をかけられた。
「おはようございます。写真ですか?」
その時、Aは子供用の滑り台の上に上って、遠くに見える海を眺め、写真を撮っていたのだった。振り向くと帽子を被り、杖を手にした女性が立っていた。
滑り台から下りて、もう一度挨拶をし、改めて見ると、僕よりも少し年上だろうか(夫が80歳を超えているので……、と言っていた)。上品な女性だった。
「いい写真が撮れましたか?」
彼女が、もう一度訊いた。
「いえ、僕のは散歩に来たという証拠写真のようなものですから」
Aが答えると、そこから会話が始まった。
医者に言われて毎日5000歩を日課としていて、自宅からここまで来るとちょうど3000歩くらいになるらしい。残りの2000歩は、夜に家の周りを歩くという。元々は二人で一緒に散歩していたのが、夫が歩くのがゆっくりになったので、朝は別々になったということだった(何しろ主婦の朝は忙しいので)。
思いがけずいろいろな話題が続いて、目の前に見える海のこと、雲のことから美術館や音楽会のことも。その他諸々を含めて、30分ほども話しただろうか。途中からはもう一人、小さな犬を連れたご婦人が加わった。初めてのことだった。珍しくも、楽しいひと時だった。
それからAは二人を残して、もう一つの海を見ることのできる場所へ。しばらく眺めて写真を撮ると、さらにいつもの散歩コースを辿って行った。しばらく歩いていると、反対側の歩道に先の方に二人の女性が見えた。小さな犬もいるようだった。それで少し歩を早めて近づくと、やっぱり先ほどの二人だった。
「良い一日をお過ごしください」
と、声をかけた。
すると向こうからも、
「あなたこそ」
という声が返ってきた。
おかげでAは、もう良い一日だ、と思った。
Aはほぼ同じコースを、順番を変えたり、曲がる場所を変えたりしながら歩くのだが、海も街の景色も一瞬たりとて同じ瞬間はない。だから、何かしら気づくことがあり(ただの不注意なだけだったのかもしれないが)、退屈だと思ったことはなかった。路傍の草や小さな花、家々の庭に咲いている花を見るのも楽しみの一つだ。今は、色々な花が咲き始めた時だ。そして、驚きやら喜びやら、何かを感じるたびに写真を撮る(ただ、Aはそれらのほとんどの名前を知らないことが残念だった。名前を知っているだけで、どれほど豊かな気分になることだろう)。もうすぐ芙蓉が咲き始めるだろう。この花も、時刻によって花びらの開き方や色を変えるようだ。
また、Aはかつてのように新聞の隅々まで読むことをしなくなり、最近ではほとんど眺めるだけのような読み方になってしまった。その代わりに訃報欄の年齢を見るようになったし、人物を取り上げた記事ならばその人物の年齢が気になるのだ。たいていは、その数が自身のそれよりも上のことが多いけれど、たいして変わらないこともままある。だから、少しずつものを整理しよう、本当に大事なものだけに囲まれた空間にしようと願っているのだけれど、なかなかうまくいかない。しかし、いつまでもそうも言って先延ばしにしてはいられないのだ。
Aはこれまでずっと、何とはなしに「遠慮」する暮らし方をしてきたような気がしていた。誰かに気を使tたり、慮ったりすることが多く、周りになんと思われようと気にしない、かまわないという強い気持ちになることができなかったのだ(もちろん、時には頑固なところもないわけじゃなかったが)。Aは、それは結局は自分に自信がなかった、ということでもあるだろうと思った(もしかしたら、自分自身に遠慮していた、ということかもしれない)。
もともと小さい頃から、争い事を好まない質でもあった。ただ臆病なだけだったかもしれないが、積極的に付き合いを求める質でもなかった。後になって聞いたことだが、幼稚園の頃は行くふりをして藁小積みに隠れていたり、長じてもしばらく不登校の時期があったらしい(Aは記憶力が乏しく、元素記号を暗記するようなことは大の苦手だった。生活についても同様で、特に高校生の頃までのことはほとんど覚えていなかった)。無遠慮な幼い子供たち(いや、今やこれは子供たちに限らない。子供ならまだしも、いい年をした大人にもたくさんいるのだ)を羨ましいと思うこともあったが、彼らとは違う年齢の自分が同じようにするわけにはいかないということも承知していた。
だから、なんとなく我慢しながら、やり過ごすこともままあったのだ。それが、彼自身の性格を捻じ曲げているところが少なからずある、ということも何となくわかるようになっていた。たとえば、一旦相手が去るようなことがあれば、その理由がなんであれ、わかってもわからなくても追いかけるようなことはしなかった。むしろ、関係をすっぱりと断ち切ってしまうのだ。その方が、想いを残していたとしても、楽になれるような気がしていたのだ。そのために、受け身でいることにも、すっかり慣れてしまった。ただし、受け身でいる限りは、その他大勢、あるいは番外となることを覚悟しなければならない。Aが退職した時、多くの人との関係が消滅し、付き合いはうんと少なくなった。
だから、Aは生活の中にCが現れたことを嬉しく思っていたが、同時に同じ轍を踏むのではないかと恐れた。
それやこれやが、Aを少なくとも愛すべき人間とはかけ離れたものとしたのだ。自分が蒔いた種であるとはいえ、それを残念に思うことがあった。
そのせいで、Aは一人で過ごすことを好むようになり、誰にも気を使わずに本を読み、音楽を楽しむようになった。なんにせよ、救いは見つけられるものだ(それが一時的なものであるにせよ)。とはいえ、失うものもある。たぶん、たいていのことは得失の両方があるが、それが必ずしも相半ばするというものでもないのだろう、と考えるようになっていた。
急募!
今年も、「絵本大賞」に応募しようと思います。
昨年は、「まだやってんの?」と呆れられましたが、石の上にも3年。
そこで、このコーナーに掲載したうちのどれを応募するのがいいか、皆様のご意見を頂戴したいと思います。
責任を押し付けるようなことはしませんので、どうぞ気楽にご意見を。こちらまでお知らせください。
なお応募の都合上、9月末日までの早いうちに頂戴できれば助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
2024.09.09
新企画日曜版 FANTASY 22 「デザイン事務所とカフェの仕事と推理」07
デザイン事務所とカフェの仕事と推理 第7回
13
そうして、慌ただしい最初の1週間が過ぎていった。
明日は、開店以来のはじめての日曜だ。開店前のひと月ほどは何かと忙しかったから、久しぶりの休日だ(さらにその前は、毎日が日曜のようなものだった)。
Aは、まだ明るさをたっぷり残し、正面から夕日を受けた建物が一際鮮やかな黄金色に光り、全体を黄昏色に染め上げられた初夏の夕暮れの町並みと空をきれいだなあと見やりながら(Aは、夏のこの時間帯の光景がことのほか好きだった)、そんな気持ちを何ヶ月ぶりかで思い出し、決まった仕事があるというのはこういう利点もあるのだと、改めて思い知った。自由業や無職では、こういうわけにはいかない。オンとオフの切り替えが、どうしてもむづかしいのだ。
いや、本当なら、仕事がなくても、時間を定めて、例えば事務所の中を整理して、家具や道具などをピカピカに磨き立てればいいいのだ。自分を鍛え上げればいいのだ。そうやって、自分できちんと管理できるといいのだが、あいにくAはそういうタイプじゃなかった(これが何事とも中途半端になってしまう原因の一つだ、ということを自覚してはいたのだが)。
Aが家に帰っても、誰も待っている人はいない。たぶん、蟻の子一匹さえもいない(最近になって、Aは小さな蜘蛛を1匹見つけた。たまにしか見ないのだが、名前をつけようと思った。しかし、名前をつけるのはなかなかむづかしい)。ただ、なぜか埃がすぐ積もる。一人でいることにはさほど困らないが、埃には手を焼いている。そのことに驚きあきれながら、俺は誇り多き男なのだと洒落てみて自らを慰めているが、家の中がすっきりしないことにほとほと困りきっているのだ。
映画『八月の鯨』の中で、90歳のリリアン・ギッシュは、
「どうして埃がたまるのかしら」
そうつぶやきながら、大きく目を見開きながらゆっくりと手を動かす。さらに、洗濯物を干し、花を摘み、「どうして…」と言いながらも家の中をきれいに保つために、手を動かし続けるのだ。Aは、この場面を思い出すたびに、俺もそうしなくっちゃと思うのだったが。掃除が下手、というかどこからどう手をつければいいのか、まったくわからなくなってしまう(たぶん、まず手を動かす前に考えてしまうせいなのだ。そしてわからなくなって、やめてしまう)。
Aが帰る家に、妻はいない。というか、正確に言うなら、妻はいるにはいるのだが、もう長い間遠く離れたままだ。実家で、年取った両親の面倒を見ているのだ。いつの間にか、そんな歳になってしまったのだ。そして、自身にもいろいろな不具合を生じるようになった。
そんなこともあってAは、生活にちょっとした変化が必要だという気がしていた。そこで、家に常時接続のインターネット環境を曲がりなりにも整えたのだ。と言っても、特別の工事をしたわけではなく、ルーターをコンセントに繋いだだけのものだが(これがどの程度のものかは、実はよくわからなかった)。
このため、いちおうは動画も気兼ねなく楽しめるようになった。Aは、お試しのつもりがいつの間にかあるショッピングサイトの会員になっていたのを、まあ便利だからそのままにしていた。それで、そこが会員に無料で提供するビデオ配信を気兼ねなく見ることができるようになったのだった。
これはこれで楽しいのだが、退職して自由時間が増えたら大画面で映画を堪能しようと思って、映画のDVDやら頼んでBS放送を録画してもらったものを溜め込んでいたのに、そのせいで時間が取れなくなってしまった。なかなか計画通りにはいかないものだ。
いやそれより、いざその年になってみると体力と気力が追いつかなくなってしまったのだ。暗い中で、2時間集中することがむづかしくなったのだった。それで、映画は本当に好きなものをごくたまに観るだけになり、その代わりに英国のミステリードラマを中心に見るようになったというわけだった。そのため、近々買い換えるつもりでいた大きなスクリーンとプロジェクターも、いつの間にかもはや不要のように思えてきていた。映画は、昼にディスプレイで観るのがいいかもしれない。気分は半減するが、観ないよりましだ。Aは時々、そう思うのだった。
始めるのに遅すぎることはないというのはよく言われることだが、やっぱりできる時にできることをやるのがいいのだろう。
そうした事情があって、愛読していたミステリーのシリーズをそのサイトがドラマ化されたると、ずっと見るようになった。原作者もプロデューサーに名を連ねていたが、アメリカ製ドラマには珍しく(?)、1話が10回ほどのシリーズで完結する(Aはこれを楽しむというより、むしろ焦れったく感じるようになった。たぶん、せっかちになっているのだろう)。
主人公の刑事が相棒と車でラスベガスに向かう場面。当然、音楽がかかっている。相棒が訊く。
「これ、誰のアルバム?」
「ソニー・ロリンズとマイルス・デイビスの『バグス・グルーブ』」
「いいね。曲名は?」
「『ドキシー』、ソニーの作だ」
「詳しいね」
「ちょっとね」
「最近の音楽は?」
「昔ので手一杯だ」
Aも思わずうなづき、声を出した。全く同感なのだった。こういう時は、スコッチを1杯やることもある。本当ならバーボンをと言うのがいいのかもしれないが、あいにくAはバーボンが苦手で、好んで飲みたいとは思わなかったのだ(香りのせいだろうか)。飲むのは、ごく普通のブレンデッドのものだ。
かつてはシングルモルトじゃなければなどと粋がって飲んでいた時期もあったが、たいして違いがわかっていたわけじゃない。恩師が、時々古いバーに連れて行ってくれたりした、ふだん飲むのはこれで十分と言っていたのが『フェイマス・グラウス』だったことを思い出して以来、それに倣うことにしたのだった。日本酒でも、食事の時は結局これが一番と言って飲んだのは昔からある銘柄のもののようだった。京都の旧家の出身である彼は、口も肥えていたし、経済的にも恵まれていたようだったから、飲もうと思えば、シングルモルトでもなんでも飲めたはずだった。
主人公の刑事とAはほぼ同年齢らしかったが、テレビの中では、小説の中の彼がいつも遅れてやってくる(ま、これは初めからそうだったから、しようがない)。ただAが、自身と大きく違うところでうらやましいと思ったのは、彼は、かつて担当した事件が映画化された際に映画会社から入った謝金をもとに、ロスアンジェルスの街を見下ろす丘(崖)の上に、ガラス張りの家を建て(相棒は、「あんなところに住む人間がいるとは?」とからかうのだが)、そこにマッキントッシュ製のアンプやマランツ製のアナログ・プレーヤー、幅広のトールボーイタイプのスピーカー(Ohm WalshというNYのメーカー製らしい)などで、主にジャズを聴くのだ。なんという題のものだったか、主人公はアート・ペッパーを好んでいるということが書いてあった気がする。
Aは、ある時からレコードを1枚、寝る前に必ず聴くことにしよう、と決めた。別に、ロスのタフな刑事を真似しようというわけじゃない。1日の終わりを静かに過ごすのにいかにもふさわしい気がしたのだ。何と言ってもレコードは、CDやラジオ等と比べると手間がかかる。レコードを袋から取り出し、丁寧に拭き、ターンテーブルに載せてから、もう一度ホコリを払う(日頃から盤面を磨いておくことも欠かせない)。それから、慎重に針を降ろすのだ。
レコードを聴くという行為においては、その手間を惜しまず丁寧にやることが何やら儀式めいて、心を平穏にしてくれるような気がしたのだ。
そして、その最初の1枚を何にするか少し迷ったけれど、結局ミケランジェリが弾くドビュッシーの『映像Ⅰ・Ⅱ』を聴くことにした。これがよかったのか、それともそうではなかったのか。ミケランジェロが紡ぎ出す美しい音の連なりは、内側に沈潜するばかりのように聴こえたのだ。
やがてA面が終わり、盤をひっくり返すとしばらくしてぷつっ、ぷつっというのが聞こえた。一旦停止して取り出し、磨き直して再び針を下ろしたが、やっぱり変わらなかった。傷が入っていたのだ(いったいどうしたのだろうか。乱暴に取り扱ったことはないはずなのに。酔っ払って聞いていたのか)。さすがにこれを、傷があるのもまた好ましい、とは言えない。
時に冷徹の人、時に、テクニックはあるけれど、音楽に欠けるとも評されたアルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ。ピアニストは、普通は自分が弾く楽器を選べない。コンサート会場に設置されているピアノを弾くしかないのだ(何と言っても大きいし、重い)。ミケランジェリは、そのピアノ(スタインウェイ社製)をコンサートのたびに運ばせたらしい。そして、ある時からは専属の日本人の調律師を帯同するようになったという。その調律師によれば、初めて自宅の練習用の小さなアップライトのピアノを調律した時の状態はひどくて、よくこれであんなに繊細な弾き方ができるものだ驚いたらしい。ミケランジェリはまた、他の誰もが気づかないようなピアノの異常を見逃さなかったともいう。
こちらも自身に厳しかったスヴャトスラフ・リヒテルも同様だったということだが、彼のピアノはヤマハ製だったようだ(彼のミケランジェリ評は、テクニックは完璧だけれど、冷たいというものだったが)。Aは、そんなミケランジェリの徹底ぶり、ほとんど音楽に殉じるといってもいいくらいの音楽への取り組み方を素晴らしいとも思い、感動したのだった。そして、羨ましく思ったのだったが、それこそがAに欠けていたことだったのだ。
おまけに、思いがけなく気づくこともあった。たとえば、ディーリアスはビーチャム盤のCDが最初だと思っていたら、マリナーのLPがあったのだ。これは記憶力のせいか、あるいは聴き込むことをしなかったせいなのか。ともあれ聞いてみたら、LP盤で聴くマリナーの演奏はビーチャムやバルビローリのCDに比べると、ほんの少しだけ流麗すぎるような気がした。
Aはディーリアスのほかヴォーン・ウイリアムズもよく聴くようになった(イギリスのメロディは、耳に馴染むようだった)。CD棚を片付けていたら、『ヴォーン・ウィリアムズ管弦楽曲集』があったのだ(片付けるといいことがあるし、ものは動かさないままだと隠れて見えなくなってしまうことがある)。CDには、有名な「グリーン・スリーヴス」も入っていた。Aは、ディーリアスみたいに聴けるかもと思って(何と言っても、「グリーン・スリーヴス」なのだから)、取り出しておくことにした。
ある朝、聴いてみると、予想した通り、いやそれ以上に良かった。
ディーリアスは心地よいけれど音が気持ちに任せて流れていくような気がするのに対して、こちらはもう少し構築的のようだ(何と言っても、正規の音楽教育を受けている)。ウィリアムズは20世紀に入ろうかという頃に王立音楽大学で学んだとは言え、イングランドの伝統的な民謡を採取した人だから、彼の管弦楽曲は耳になじみやすい。Aは、そういえば英国の国民的な作曲家エルガーも幼い頃から楽器の手ほどきを受けていたとはいえ、正式に音楽の高等教育を受けたわけではないようだ、ということを思い出した。
Aは、ディーリアスやエルガーの音楽を聴くことを好んでいた。我流はややもするとある癖をおびて、それが気になることもあるけれど、ディーリアスやエルガーはそれを感じさせない、というか嫌じゃないのだ。形式張った堅苦しさというものと無縁のせいだろうか。それで、朝か昼の早い時間に聴くことが多い。
Aはそうやっていくつかの夜を過ごすうちに、夜に聴くレコードは、ピアノソナタなど単一楽器か、多くてもせいぜい2つくらいの楽器による演奏で、しかも音の綺麗なものが好ましい気がしたのだ。もとより夜には大きな音が出せないということもあるが、それよりもその日がどんなに雑駁なまま過ごした1日だったとしても心を穏やかにして1日を閉じるためには、音の振幅が大きくてダイナミックなものやリズミカルなものよりも、静かなものがいいような気がするのだ(ま、沈潜しすぎる危険もないではなかったが)。
それでも、たまにパブロ・カザルスが弾くバッハの無伴奏チェロのような音楽も聴きたくなることがあった(日常の生活を振り返って、もう一度志を新たにするということが必要だと思うことがあるのだ)。それらはヘンデルのような愉悦感のある音楽を好むAの嗜好とは異なっていたけれど。ともかくも、寝る前にレコードを1枚聴く、それがAの新しい習慣になりつつあった。
急募!
今年も、「絵本大賞」に応募しようと思います。
昨年は、「まだやってんの?」と呆れられましたが、石の上にも3年。
そこで、このコーナーに掲載したうちのどれを応募するのがいいか、皆様のご意見を頂戴したいと思います。
責任を押し付けるようなことはしませんので、どうぞ気楽にご意見を。こちらまでお知らせください。
なお応募の都合上、9月末日までに頂戴できれば助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
2024.09.08
新企画日曜版延長戦 FANTASY 21 「デザイン事務所とカフェの仕事と推理」06
デザイン事務所とカフェの仕事と推理 第6回
12
その後もしばらくの間は、カフェの方は相変わらず忙しかったが、だんだん落ち着いてきた。客足も開店当初ほどではないし、物珍しさだけでやってきたお客の多くは来なくなる。慣れてきたことも大きい。AとCの連携も、いくらかはスムーズになったようだった。
初めは、お客を目の前にしてもなかなか会話は弾まなかった。たいていは、注文をさばくのに忙しくてそれどころじゃなかったし、少し時間が取れたとしても、やっぱり気になって余裕がなかった。それで、挨拶や天気の話がひとしきり終わると、そのあとはなかなか続かなかった。しかし、やがて常連客と呼べそうな客も少しずつ増えてきた。
ランチタイムも終わりかけた頃に、Gが入ってきた。
「参った、参った」
と呟きながら、カウンターに腰掛けた。
「どうした?」
Aが水の入ったグラスを差し出しながら訊く。
「おばちゃんが、なかなか帰ってくれないんだよ」
「へえ」
「どこも悪くないよって何回説明しても、いやきっとここが悪いんじゃないですか、て言って聞かないんだよ」
「ふーん」
「きっと、インターネットやら雑誌やらを見て、自分もこの症状に違いないと思うんだね」
「困ったね」
「困るよ。そうした、聞きかじりの耳学問にはまったおばちゃんが増えているんだよ」
「へえ。おばちゃんたちだけなのか、おじちゃんたちは?」
「おばちゃんたちだけ、おじちゃんたちは、たいていだめだね」
「どうして?」
「医者に頼ろうとするばかりだね」
「へえ、なるほどね。そういうものかね」
「ああ、男はね、どうもね……」
それから、急に思い出しように、
「ああ、喉が乾いた」
と言い、グラスの水を一気に飲み干すと、ふーっと息をついてようやく落ち着いたようだった。
Gは近所で個人の内科クリニックをやっている。Aももう10年以上も通っていて、まあ主治医と言っていいのかもしれない。坊主頭に、楕円形の細い金属製フレームの眼鏡をかけている(初めて見たときから、ほとんど変わっていないように見えるのはどうしたことだろう)。年齢はAとあんまり変わらないようだ、もしかしたら、少し年下かもしれない。
生真面目だが、ちょっと調子者のところもあるようで、いつだったかAが自転車に乗っていて怪我をした時は、
「スマホなんかをイジリながら、乗ってたんじゃないの?」
などど言ったりした。またある時、肋骨の下の痛みがずっと引かずに、周りの友人たちもいろいろ病気を抱えているようだと言うと、まあなんでもないと思うがねなどと言ってエコーで診ながら、
「まあ70の壁は越えたけど、次は80の壁だね」
などとのんきなことを口にしたりもした。お調子者の割にはまあ口はあんまりうまくないが、柔和な物腰のせいか、けっこう流行っているようだ(もしかしたら、あんがい腕もいいのかもしれない)。
「お腹もすいたな」
Gが言うと、
「何を食べる?」
とAが訊く。
「ええっと、今日のパスタ・ランチは何?」
「菜の花のペペロンチーノだね」
「お、いいね。でも、ニンニクは減らしてくれよな」
「ああ。医者も客商売だからね。それに最近のニンニクは、あんまり臭わないようだけどね」
だいぶ呼吸もわかってきたようだった。
そこに、ドアが開き、もう一人男の客が入って来た。Cが、
「いらっしゃいませー」
と大きな声をかけると、Gもそちらの方に向き直って、おっと手を挙げて挨拶をする。
お客は、Gのクリニックの入るビルの1階にある中華料理店のオーナー・シェフのHだった。彼も、時々やってくるようになった口だ。Gは、律儀にも2つの店を交互に利用している。毎日中華料理というのは、さすがに自分の年にはきついと言いながら。Hもそれを知っていて、受け入れているようだ。
Hがカウンターの前に座ると、Cがグラスに入った水を運んできた。同時に、カウンターの中のAが言った。
「やあ。いらっしゃい」
「どうも」
Hが小さな声で答える。
「なんか、元気がないね。アルバイトの娘が来なくなったとか、なんか悪いことがあったか?」
Gが茶々を入れてきた。
「ああ。ちょっとね」
「どうした?」
Gがさらに訊く。
「何にする?」
Aも訊いた。
「コーヒーをもらおうか」
「へえ、食事じゃないのか?」
Aが訊いた。Hは、昼は自分で作ったものは食べないと言う。ずっと、人のために料理し続けているからだ、その気持ちもわかるような気がした。Aが作る量とは、段違いに違うのだ。
「ああ。食欲がないんだよ」
Hが、小さな声で言った。
「ふーん。何があった?」
Aが心配そうに訊く。
Hはしばらく黙っていたが、
「家賃がね」
小さな声で、切り出した。
「家賃がどうした?上がりそうなのか?」
「ちょっとね。こないだ大家が食事に来てくれたんだけど、その時にどうしたことか家賃の話が出たんだ。悪い予感がしたんだよ。ボソボソと色々な例を並べ立てた挙げく、『で、上げなくちゃいけなくなるかも』と言うんだよ。参ったよ」
Hが一気にそう言った。
「そうなのか?」
Aが心配そうに言った。
「うちみたいなところでは、結構こたえるんだよ」
また、小さな声に戻った。
「わかるよ」
「ああ」
「どうした?」
食べるのに集中していたのか、おとなしかったGが訊いてきた。
「お前さんのところには、関係ないだろうけどね」
Hはちょっと拗ねたように言った。
「そうなのか?」
「そうだよ」
「どうしてだよ?」
Gがなおも訊いたが、Hは黙ったままだった。
「わかるよ」
Aが助け舟を出した。Hは、
「ありがとうよ」
と言うと、目の前のコーヒーを一気に飲み干した。そして、出て行った。
「いったい何があったんだ?」
Gが訊いた。
「お前さんたちのビルは、駅に近いだろ?」
「まあね」
「だから、たぶん、少しずつ需要が増えてきているんだよ」
「そうなのか?」
GやHの入るビルは、駅から少し離れているものの、駅側の歩行者道路に面している。だから、新規に開店する店も少しずつ増えている。多くの人が、それまでの関係よりもわずかの損得で動くようになってきたのだ。時代とともに人情も変化したということもあるだろうが、長引く不況のせいで経済も厳しさを増して来ているのだ。何しろ、このところは尋常じゃない物価高が続いている。
「ところで、お姉ちゃんは元気なのかい?」
Gは雰囲気を変えようとでもしたのか、Cの方に向かっておどけた調子で声をかけた。
Cは、黙ったままだ。どうやら、お気に召さないらしい。
「ねえ?どうなの?
なおも訊いた。
「ええ。おかげさまで。お姉ちゃんじゃ、ありませんけど」
ようやくCが、Gの方を見ることなく言った。
「おっと、こわいね。Aにこき使われれて、疲れてんじゃないの?」
またしても、Gがおちゃらかして言う。場の雰囲気を読まないのか、それとも生来のものか……。でも、どこか生真面目さを隠せないようでぎごちないところがあった。それが、余計に気障りにするのかもしれなかった。
「いいえ。そんなことはありませんよ」
「元気の出るような彼氏はいないの?」
「おかげさまで」
Cはちょっと投げやりな風に、どちらとも取れるような曖昧な返事をした。
「ふーん。そう?」
Cは、唇の端を少し上げてにっこり笑っただけで、もはや何も言わなかった。彼女は、にっこり笑って無視するという技をすでに身につけていたようだった。Aは感心しながらも、これがカフェを始めてからのことか、それ以前からのことか、あるいは天性のものかはわからなかった。
しばらくすると、食後のコーヒーを飲み終えたGが席を立った。やがて、客がいなくなり、店の中が静かになった。AとCだけになった。
「あんがいきびしいんだなあ」
Aが切り出した。
「えっ?何がですかあ?」
Cは、何のことかという調子で訊き返した。
「いや、あんがい冷たくあしらうこともできるんだなあ、と思ったのさ」
「なんのことですか?」
Cがちょっとふくれたように言った。
「Gに対した時のことだよ」
Aが言う。
「どうかしましたか?」
「最初はムッとして、そのあとは無視していただろ?」
「えっ?」
「とぼけなくてもいいよ。見え見えだったから」
「やっぱり?」
「そうさ」
「あら嫌だ。Gさん気を悪くしていましたあ?」
Cが、あんまり気にするふうでもなく言った。
「まあ、それは大丈夫だけどね」
「そうですかあ?」
「たぶん、気づいていなんじゃないかな。気がついたとしても、あいつはああ見えて、あんがい人がいいんだよ」
「ふーん?」
「そうさ」
「よかった」
やっぱり、どうでもいいような調子でCが言った。
「でもね、これからは気をつけような」
「はあ」
「何と言っても、客商売だからね。まあ、あんまりカリカリしないことだね」
Aは、これでおしまいというように言った。
「はい」
Cも、今度は素直にうなづいた。
それから二人は顔を見合わせて、笑った。
読んでくれて、ありがとう。
次回に続きます。
急募!
今年も「絵本大賞」に応募しようと思います。
昨年は、「まだやってんの?」と呆れられましたが、石の上にも3年。
そこで、このコーナーに掲載したうちのどれを応募するのがいいか、皆様のご意見を頂戴したいと思います。
責任を押し付けるようなことはしませんので、どうぞ気楽にご意見をこちらまでお知らせください。
なお応募の都合上、9月末日までに頂戴できれば助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
2024.09.02
新企画日曜版 FANTASY 20 「デザイン事務所とカフェの仕事と推理」05
デザイン事務所とカフェの仕事と推理 第5回
9
当日は、少し霞んでいたが、いい天気だった。とはいえ、初夏の朝の空気はまだひんやりとしていた。開店時刻は10時の予定だ。AとCは2時間前に集合しようと約束していたが、Aは3時間以上も前に着いていた。カウンターの中に入り、辺りをなんども見回した。うなづくと、もう一度グラスを手にして磨いた。そして、カウンターやテーブルの上にメニュー表を並べ始めた。それが済むと今度は、緑色の黒板にチョークで、本日のメニューと書き、続いて下に2重線を引いた。
すると、まもなくして、ドアが開く音がして、
「おはようございまーす」
という例の間延びした調子の挨拶とともに、Cが入ってきた(いつものことながら、この間延びした言い方が気になったが、今日はそれをどうこう言っている場合じゃない)。ともあれ、彼女も待ちきれなかったのだ。
「やあ。おはよう」
Aが、少し弾んだ調子で声をかけた。久しぶりにワクワクする気持ちを、抑えられないのだ。
「早いですねえ」
Cが、短い質問で返した。
「ああ。そちらこそ」
「よく眠れなかったんです」
あの能天気に見えるCが眠れなかったとは。ちゃんと本気で取り組もうとしていることがわかったようで、Aはちょっと嬉しかった。
「そうか。俺もだよ」
「えっ、センセイも?」
と言い、この時にやりとしたように見えたのはAの気のせいだったのだろうか、さらに続けた。
「なんだか、遠足の前みたいな気がしちゃって」
「ああ。この歳になってもね」
「えっ?」
「あ、半世紀ほども違うけどね」
Aはあわてて付け加えた。これまで、年の差を感じることももちろんあったが、気にならない時も少なからずあったのだ。
Cは軽くうなづくと、何やら抱えてきていた手提げ袋から半分ほど取り出して見せた。
「あ、これを」
「なんだい?」
Aは思わず覗き込むようにしながら、尋ねた。
「なんだと思います?」
Cが焦らした。なんだか嬉しそうだ。
「うーむ?」
Aは、首を傾げて考え込んだ。
「ジャーン!」
Cが、待ちきれないというように、取り出した。
彼女が手にしていたのは、店名入りのTシャツだったのだ。
「おお!」
「どうですか?」
「いいねえ。いったい、どうしたんだい?」
「文化祭の時に、作ったことがあったんで、やってみたんです」
思えば、彼女はほんの数年前までは高校生だったのだ。Aはこのことに気づいて、改めて驚く気持ちを隠せなかった。一呼吸置いて、
「ああ、そうなんだ」
ようやく言った。
「じゃあ、さっそく着替えてきてください」
彼女はジャケットの下に、もう着込んでいた。
それから、さらに昨晩焼いたというクッキーも持って来ていた。きっと、紅茶に合うに違いない。コーヒーにも。
彼はさっそく着替えてくると、書きかけの黒板にメニューの続きを勢いよく書きつけた、もちろんCのクッキーも。その間、Cはグラスに小さな花を生けて、カウンターやテーブルの上に置いた。
いよいよ、開店の時刻が近づいてきた。
さあ、まもなく開店中の札をかける時間だ。Aは、高ぶる気持ちが湧き上がってくるのを感じた。心臓が早打ちするようでもあった。そこで、大きく深呼吸をした。
それからドアの方を見ると、誰かが背中を向けて立っていた。視線が遮られてはっきりとは見えなかったが、男性のようだった。
10
元同僚だったBか、上階の学生のDか、前オーナーのEか、あるいは顔なじみの町の住人か。それとも……、知らない新しい客かもしれない。Aは、期待と不安を抱えながら、こんなに早くから誰だろうと思いながら、近づいて行った。なんと言っても、もしかしたら開店を待つ、カフェ最初のお客かもしれないのだ。
と、男が不意に、向こうを向いたまま言った。
「準備の方はどうだ?」
すぐにわかった。声の主は、Eだった。前のオーナー兼大家だ。そして、こちらの方を向くと、
「やあ」
と、ぶっきらぼうに言うと、不器用に笑った。
「やあ、驚いたな」
Aも笑顔で応じた。
「そうか?」
「きてくれて嬉しいよ。もうふるさとに帰ったとばかり思っていた。どうしたのさ?」
Eはここを閉める時、電車で2時間ほどのところのふるさとに帰って、畑仕事をやるつもりだと言っていたのだ。
「まあね、ちょっと気になったもんだからね」
「そうだね。やっぱりね、気になるよね?」
「ちょっとね」
Eがぼそっと呟いた。すっぱりと忘れてしまうというわけにはいかないことが、照れくさかったのかもしれない。何しろ何10年もここで店をやってきたのだ。簡単に忘れられるわけもないし、気にならないわけがない。いい時ばかりではなかっただろうし、特に晩年は流行っていたとは言い難かった(開店休業のような日も、少なからずあったのだ)。いろいろと去来するものがあったはずだ。
「まあ、中にどうぞ。入って見てくれよ」
Aは、Eの背中を押すようにして、中に入った。
「おお。こりゃ、たまげたな」
Eは小さく声をあげた。無理もない。良し悪しは別にしても、以前の姿はほとんど残っていないのだ。
「どう思う?」
Aが訊く。自分では悪くないと思っていたが、人がどう思うかはわからない。自分の家なならまだしも、お客相手の店なのだからなおさら気になった。
「悪くないね、いいんじゃないか」
Eが、今度は少し大きな声で言った。
「そう?」
Aは今日初めて、少しだけホッとした。自分ではまあ悪くないと思っていても、人がどう思うかが大事なのだ、ここは家じゃなくてカフェなのだ。
「前とはすっかり変わったようだけどな」
Eがまたぼそっと言った。暗くて古めかしい喫茶店から、明るくてこざっぱりとしたカフェに変わったのだ。
「そうだね。悪いかなとは思ったんだが」
「何を言う。かまいやしないさ」
「ありがとう。安心したよ」
Aは、そのことを気にしていたのだ。内装のこともだが、Eの気持ちのことが気がかりだった。
「でも、プレイヤーやアンプ、それにスピーカーはそのままなんだな」
「ああ。そりゃあね」
それから、安心したように笑顔で、Eの方に向き直って訊いた。
「さて、何を飲む?」
「ビールをいいか?」
Eが言った。
「もちろん」
「乾杯しなくちゃいけないからね」
「ああ。そうしよう」
Aは、棚からぴかぴかに輝いている磨き立てのグラスを2つ取り出すと、ビール瓶の王冠を開け、少し傾けてゆっくりと注ぎ始めた。朝から飲むのは気が引けたけれど、今日は特別だ、かまうことはない。ビールの注ぎ方は色々あるようだが、Aはふだんから英国のパブの方式を採用することにしていた。一回注いだ後少し休ませてから、さらにもう一度ゆっくりと注いでいく。
「いよいよだな」
Eが言った。
「ああ、そうだ。さあ、乾杯しよう」
そう言って、きれいに泡立った黄金色に輝くグラスを掲げた。
「うまい」
「うまいね」
「邪魔はしたくなかったんだけどね」
一口飲んだEが、言った。
「邪魔だなんて、とんでもない。よく来てくれてた」
Aもすかさず応じた。
「ところで、準備は万端か?」
Eが改めて訊いた。なんだか急に年取ったような声だった。安心したせいか、それともいよいよ店が自分の手を離れたことを実感したのかもしれない。
「まあまあというところかな。それより、ちょっとドキドキしているけどね」
Aが答える。
「ま、初めてのことだからね?」
「そうだね」
「でも、心配することはなさそうだな?」
Eが励ますように、そして自分にも言い聞かせるように言った。
「だといいけどね」
「大丈夫だよ」
Eは店の中の全体を見渡すと、もう一度小さくうなづいた。色々な思いを飲み込むかのようだった。
その時、ドアが開く音がした。2番目、いや最初の正規のお客がやって来たのだ。
「いらっしゃいませー」
Cが、間延びするのことない、元気な声で迎え入れた。
「じゃあ、これで帰るよ。勘定してくれ、いくらだ」
グラスをぐいっと空けてから、聞いた。
「いいよ。何しろ、初めてのお客だからね」
「いいのか?」
「もちろんさ。また来てくれ」
「ああ。じゃあ、今日は甘えておくよ」
「ああ」
「じゃあな、また。あ、見送りはいいよ」
振り向くことなくゆっくりと出ていくEを目で見送った後で、カウンターに目をやると、封筒が置いてあった。筆で大きくA様とある。開けてみると、お祝いと書いた袋と手紙らしいものが入っていた。
頑張れよ。
手伝いが必要な時はいつでも言ってくれ(特に、オーディオの機嫌が悪い時には)。
とあった。Aは、やれやれと呟き、手紙と祝儀袋を手にしたまま上を見上げた。
「いらっしゃいませ。お決まりですか?何になさいますか?」
Cが淀みなく訊いた。
「コーヒーをもらおうか」
お客が言った。
「承知しました」
ごく自然に言うのが、Aにも聞こえた。練習でもしていたのだろうか。それとも若い人にとってはなんでもないことなのだろうか。
最初のお客の注文はコーヒーだった。Cがすぐさま、コーヒー一杯でーす、と声をかけてきた。Aが、初めてお客に出すコーヒーだ。緊張したが、失敗はしなかった(たぶん)。
「ありがとうございましたあ」
Cが、元気な声で2人目のお客を送り出して、戻る時に目が合った。
Cが近寄ってきて、言った。
「おじいさん、来てくれましたね」
Aは、おじいさんかと思ったが、その思いは押さえ込むことにして訊いた。
「ああ。でもどうして、声をかけなかった?」
「お邪魔かなあなんて、思って」
Cが、からかうように言う。
「なんでだい?そんなことはないさ」
Aも意外だとでもいうように応じた。
「そうですかあ?」
また、間延びした言い方に戻っていた。そのうちに、注意するのがいいかもと思った(少なくとも、店の中では。でもお客に対しては、どうなのだろう?)。
「お前さんも、よく知っていたんだろう?」
「ええ、まあ」
「だったら、どうしてさ?」
「でも、しみじみ語り合っているようでしたもん。小娘の入り込む余地はない、って感じでした」
Cは、今度は真面目なのかからかっているのか、わからないような口調だった。
「そうなのか?」
「はい」
「ま、彼もいろいろ思うところがあっただろうからね」
Aは、自分に言い聞かせるように言った。
「そうですね」
Cが、今度は神妙にうなづいた。
「また来るさ」
Aは、そう願いながら言った。
「ええ」
Cもまた、自分に言い聞かせるようだった。
11
昼が近づくにつれ、お客がだんだん増えて来た。
はじめてみたら、見るとやるとは大違いだった。二人とも、ずっとてんてこ舞いだった。コーヒー、紅茶にビールといった飲み物だけじゃなく、パスタやオムライスそれにサンドイッチの食べ物のメニューの全部が出た。しかも、後から考えると至極あたりまえのことながら、一つずつではなくいっぺんに注文がくるのだ。料理は予想以上に時間がかかった。それも当然。Aはそれまで、複数の料理をいっぺんに作ったことなどなかったのだ。
それに、メニューは一応ふだんから作り慣れているものばかりだったが、全部を完璧に覚えているわけじゃないし、その都度味が多少違ったところで気にすることはなかった(何しろ、素人料理人なのだ。おまけにAは、昔から暗記するのがだの苦手だった)。ただ、ここで作るものはお客に出すのだ。
そうなったからには、しようがない。無い袖は触れない(?)のだからと急遽黒板に、料理は少し時間がかかることがあります、と付け加えることにした。お店をやるのに甘えていると言われるかもしれないが、できないことはできないと潔く書くほうがお客に足して誠実であるような気がしたのだ。何と言っても、まだアマチュアの料理人なのだから(このあたりのことは、これから少しずつプロになっていけばいいと思っていた。それが受け入れないなら、それはしようがないと、覚悟を決めた)。
その後も、二人でやっとなんとかこなせるほどのお客が入り続けた。本当はそれほどでもない数なのかもしれないが、慣れない二人はうろたえ、慌てふためくばかりだったのだ。
お昼時の忙しさが一段落した後、遅い昼食を取ることができたのは、3時に近かった。
「この調子だとパンクしちゃいますよう」
Cがちょっとおどけたような口調で言った。冗談だったろうが、案外本音のようでもあった。何か手段を講じる必要があるのかもしれない。でも、とりあえずは、笑ってごまかすことにした。明日の心配よりは、まずは今日を乗り切ることが先だ。Aは、できるだけ深刻にならないよう気をつけながら、言った。
「そうだよなあ。でも、まあご祝儀がわりってことじゃないかな?」
「そうですかね?」
「たぶん、いつまでも続きやしないさ」
「ほんとに?」
「ああ。きっと、ビギナーズ・ラックというやつだよ」
自分を安心させるように言ったが、それは不安なことでもあった。
「それはそれで、また困っちゃいますけどね」
Cは、意外に冷静だった。
「確かに。それは困る」
Aも同意して、そしてふたりは顔を見合わせて笑った。
「さあ、もう少しだ。頑張ろう」
「そうしましょう」
少し短くなった夕方の部は、さすがに食事の注文は減ったが、そのあとも客足は途絶えることがなかった。
最後の客を送り出すと、二人でささやかな祝杯をあげた。
「やっと終わったね」
「やっと始まりましたね」
「ああ。今日はありがとう。疲れなかったか?」
「まあ、若いですから。誰かさんとは違って、ね」
Cが軽口を叩いた。緊張が解けたのだ。
「でも、明日からはもっとメニューを絞った方がいいかな?」
「ええ。そうしましょう」
「さあ、乾杯」
と声をかけ、カップとグラスを合わせた。Cは紅茶、Aはビールという妙な組み合わせだったが、特別の日のビールは、格別だった。
カフェでの新しい生活の第1日目が、終わったのだ。
読んでくれて、ありがとう。
次回に続きます。
2024.09.01
新企画日曜版 FANTASY 19 「デザイン事務所とカフェの仕事と推理」04
デザイン事務所とカフェの仕事と推理 第4回
5
Cが帰っていった後、Aは彼女の話を思い出した。下の店を引き継ぐ、そのことを考え始めると、下の主人の意向を確かめる前から、身体中を血が勢いよく流れていくのがはっきりとわかるようだった。久しく感じたことのない感覚だった。
事務所の看板を掲げたところまではよかったけれど、今までデザインの仕事はほとんどなかったのだ。だからAは、Cがその話をした時から、すぐにリストを作り始めた。なまけ者のくせに、妙に素早い時がある(この辺りが、お調子者でもあることを示しているようだ)。手元にあったプリントの裏に(まっさらの紙よりも、この方が筆が進むのだ)、太字の青の消せるボールペンでさっと、「カフェが備えるべき空間条件」と書き付けると、すぐに続けて書き始めた。はやる心をなだめて、ゆっくりと丁寧に書こうと心がけた。何事も、焦ってはいけない。急いては事を仕損じる、のだ。
空間以外のことも書いたせいで、あっという間に条件(というか、願望だったが)は1ダースを超えたが、思いつくままに書いたので、並び方はバラバラで前後に関連性はなかった。このことは気にしなかった。まずは、視覚化することが大事だ(人の頭はそんなに立派にできていないと聞いていたし、少なくとも彼自身の頭については確かだった)。検討したり推敲するのは、その後でいい(Aは、これを二人の小説家と一人の文化人類学者から学んだ)。

Aは、ひとまずここでボールペンを置いて、眺めてみた。それから、カスクート、鯖サンドに2重線を書き入れて消した。やっぱり、足したがる性格らしい。
Aは、その後自宅に戻ってもじっとしていられず、パソコンでまとめなおしはじめた。今度は、相互に関係を考慮してまとめた。
新しいカフェが備えるべき条件
01. 立って飲めるスペースも欲しい。立ち飲みのコーナーがあれば、そこにいるときの自由性が
格段に増す
02. 歩道にテーブルと椅子を出したい →無理なら、歩道を店の中に引き込む。カフェのファ
サードの大部分を全面開放できるようにする
03. カウンターの一隅には、小さな囲炉裏を据えつけよう →冬は火を眺められるし、炭火料理
ができる素朴な材料、デザインでもいいが、全体は素朴になりすぎないこと
04. 安価でも本物を使い、偽物は避ける。ビニルレザーやプリント合板の類は極力使わないこと
→使うなら、ビニルはビニルらしく、フォーマイカはフォーマイカらしい使い方を
05. できるだけ、既存のものを活用すること →必要に応じて手を加える
06. いわゆる尖ったデザインはしない。品書き等のデザインは少し凝ったものに
07. くつろげること。ただし適度な緊張感がある空間であること。飲み物はちゃんとしたものを
出す(はじめは種類は少なくても良い)
08. 音楽を楽しむ空間とすること。音だけではなく、視覚的にも(オーディオ装置やレコードの
ディスプレイ)。本も読めたらいい
09. 音楽は、特にジャンルにはこだわらないが、時間帯に合わせて、馴染みやすいものを
→例えば朝はバッハやヘンデルそれにモーツァルトなんかの軽いもの、昼はチーフタンズや
少し遅くなると10ccや後期のロキシー・ミュージックなんかもいいかもしれない
→レコードの入手がむづかしそう。CDも導入? →著作権料は?
10. カウンターの上には、お客が注文した料理や飲み物以外は載せない。
→ボトルや大皿料理が並んでいるのも魅力的だが、気をつけないとすぐにものでいっぱいに
なる
11. 食べ物のメニューも最初は少なくてよい。まずはパスタの類からはじめよう(オイル系、ト
マト系、和風?)
→いっぺんには作れないし、余り物が出るのも困る(無駄が出ないことを心がけること)
12. 飲み物はちゃんとしたものを出す(はじめは種類は少なくても良い)。コーヒーは豆から挽
いていれる
13. 料理も飲み物も、極力自然に近い材料を使う。人工的な添加物は避ける
14. 作り置きのできるデザートも欲しいが、Cに練習してもらう?(彼女にも責任がある!)
15. 初めから完璧を目指さない(アマチュアであることを自覚すること)
16. 営業許可取得のための準備をする
17. はじめは週3回くらい?
Aはその後、料理のレシピ本を手にすることが多くなったような気がした。もともと料理は好きだったし、苦痛だと思ったこともなかった。料理をしているときは、他のことを忘れることができたのだ。ともあれ、今回はお客のために作ることになる。自分のための料理なら、もう何度も作っているからレシピ本を見る必要はないのかもしれないけれど、もともと覚えることが不得手なAはよく忘れることがあるのだ。しかも、見ているとたいてい新しい発見があるものだ(こうしたことがあると、料理に限らず楽しい。だから、人は学び続けるのだろう)。
もしかしたら、デザイン事務所がクッキング・スタジオの事務所のようになるかもしれない。だから、まずは料理よりも空間のデザインから始めることにしたのだ。でも、そうなったら、それはそれでいいことにしよう、と思った。そのうちに、デザインの依頼もやってくるだろう。
そして、初めから完璧を目指さない(アマチュアであることを自覚すること。ただし、接客だけは甘えない)と書くことも忘れなかったのは、長い経験から嫌というほどわかっていたからだ。人は何かを始めようとする時、ややもすると初めから張り切り過ぎたりハードルを上げすぎたりすることになりがちだ(例えば、、物理学の場合、初歩的な入門書ではなく本格的な学術書に手を出してしまう。料理だって、いきなり本格的なフランス料理に挑戦しようとするのだ。そうすると、途中で疲れてしまい、結局は長続きしない場合が多いのだ。
また、申請書類の作成や講習などといった営業許可取得のためのあんまり楽しいとは言えない仕事もある(たいていの仕事は、こうしたいわば影の仕事が大半なのだから、これを軽く見るわけにはいかない)。楽しい面を見ないと続けられないが、そうではない部分もきちんと見ておかないと、結局は挫折することになりかねない。
6
想像することは楽しいことだが、それだけでは先に進まない。何しろ、時間がたっぷり残されているわけじゃない。資金だって同様だ。それで、Aは、彼にしては珍しく思い切って下の喫茶店に行くことにした。そして、訊いたのだった。それも単刀直入に。返ってきたのはやっぱり、やめるつもりだという簡潔な答えだった。Aは残念なような気もしたが、一方で新しい気力が湧き上がるのを感じた。なんにせよ、わかれば胸のつかえは下りるのだ。
「どうしてやめることに?」
「ま、いろいろさ」
Eが言う。
「そうだろうね」
いろいろの中身は容易に想像がつく。例えば、儲からない、体力的にきつくなくなった(何と言っても、もう年なのだ)、あるいは飽きてしまった等々、挙げればきりがない。それは、Aにとっても同様なのだ。
「で、やめた後はどうする?」
「なんとでもなるさ。一人なもんだからね、気ままに暮らすさ」
そう言った後で、Eが訊いた。
「ところで、お前さんの事務所の方はどうなんだい?」
「ま、ご想像の通りさ」
「流行っていない。そうだね?」
Eが、ずばりと核心をついた。
「ああ」
Aは素直に答えた。隠す必要はなかった。
そして、しばし考えるような間があいた。そして、彼の口から意外な言葉が飛び出した。
「だったら、この店を引き継ぐつもりはないかい?」
「えっ?」
「そっちは本業とは別の収入があれば、楽になる。こっちは家賃が入れば、生活の助けになる。お互い、悪い話じゃない。そうだろう?」
「ま、そうだろうね」
Aが答えた。お客が入ればということだが……(しかも事務所が本業と呼べるかどうか怪しいが、こちらの方も同様だ)。
「じゃ、決まりだな?」
Eが、短く言った。
「ああ。でも、俺にできるかね?」
なぜだか、すんなり口に出た。
「なんとかなるだろう?安くしておくよ」
Eが言い、Aが応じた。
「ああ、ありがとう。頼むよ」
もう、決まったようだった。
Aはすぐに営業許可を得るための手続きを調べ、講習を受けて無事に許可を取得することができた。
そんなふうにして、AとCはカフェを始めることになったのだった。これといった展望もないまま、だ。今までどおりだ、これまでと何も変わらない、Aはそう思った。
Aは計画を立てるのは好きだが、これまでたいていのことは計画とは無関係に、成り行き任せでやってきたような気がしていた。それはとりもなおさず、多くの人の助けがあってのことだった(最近になって、Aはそのことを強く思うようになっていた)。
7
カフェを引き継ぐことが決まると(まだ口約束の段階だったが)、Aはすぐに事務所に戻って、お気に入りのファーバーカステル製の木軸のシャープペンシルを手にすると、黄色のトレーシングペーパーを広げて内装のスケッチを始めた。
頭にはまず、時間のことがあった。いつまでやれるものかわからなかった(あの鮨屋が辞めた年齢の時に、Aは始めようとしているのだ)。お金のことも、考えないわけにはいかない。家賃だけが先に出て行くという状況は、極力短かくしなければならない。それに、何より時間をかけすぎると、飽きてしまいそうなのが怖かったのだ(それまでに、同様の失敗を何度となく繰り返してきていたのだ)。
内装は、いくらなんでもあのままというわけにはいかない。もう少しすっきりとした内装にして、家具ももう少し軽快なものにするほうがいいだろう(古いソファと椅子は諦めるべきかもしれない)。ただ、モダンになりすぎないようにしなければならない。ショールームのようなシャープな空間は、束の間見るにはいいかもしれないが、くつろぐのには向かない。カフェは、飲み物だけでなく音楽や本、そしておしゃべりをゆっくりと楽しむための場所であってほしいのだ。
コンロの前のカウンターは少し広くして、いわば厨房から外に出したシェフズテーブルのようなものにするのはどうだろう、と思った。お客は多くないだろうから、話しながら作ったものを出せればいいのではという気がしたのだ。
でもお金の余裕はないから、DIYでやるしかないだろう。とすれば、モダンになりすぎることはない。これで、たくさんある心配の種のうちの一つは消えた気がした。でも、あいにくAには本格的なDIYの経験がなかった。ただ、あるものでなんとかするというのが信条だったから、その癖だけは身についていたが、例えば端材とブロックを組み合わせて棚を作るといった類のものにすぎなかった。しかし、これが過ぎると、とたんに貧乏くさくなってみみっちい感じがしてしまう(質素なのはちっともかまわないが、みみっちいのは嫌だった)。DIYのことは、頭ではわかっても、体がついていかないという事情もあった。おまけに、箱を作ろうと釘をまっすぐ打とうとしても、曲がってしまう。昔から不器用な質なのだ。
だから、大まかなスケッチを作ると、すぐに手配に取り掛かることにした。
幸い、少し前に古いマンションを手に入れたところで、今は自身で改装中という若い知人Fのことを思い出した。彼に相談してみよう。きっと、なんとかなるだろう。
で、さっそく相談してみたところ、彼は5年ほど勤めていた建築事務所をちょうど辞めたばかりで、経済的なこともあるので改装はストップしているところだという。マンションを買ったのはローンが組めるようにと、事務所を辞める直前だったらしい。Aは、Fが若いのに計画的なことに感心した(自分が若い時とはずいぶん違う、いや今の自分よりも堅実かもしれない)。話をすると、快諾してくれた。手伝ってくれそうな人についても、探しますよ、と言ってくれたのだった。好意に甘えるのは心苦しいような気もしたが、背に腹は代えられない。話はとんとん拍子に進み、数日後に始めることになった。
8
まずは、壁紙をはがすことから始めた。はじめは皆がなんとなく恐る恐るという感じでやっていたのだが、失敗してもいいからと言って、思い切ってやることにした。すると、次第にペースが上がってきた。剥がしてみると下地が傷んでいるところも少なからずあった。何しろ古いのだから、しかたがない。出たとこ勝負でやっていくしかない。痛んでいるところは一応補強して、さらにパテで手当をした。それから窓枠や作り付け家具との取り合いの部分に養生テープを貼って、白いペンキを塗り始めた(白い壁はややもすれば単調になりやすいが、たいていは七難を隠してくれる)。細かいことまでは決めていなかったが、やりながら相談して、巾木も廻り縁も天井もスイッチパネル類も含めてすべて白く塗ることにしてみようということになった。時間も節約できるだろうし、ちょっと新しい感じが出るかもしれない。これだけで最初の1日が終わった。
食器棚をはじめとする既存の棚類も、今回はペイントし直すだけで済ませることにした(一部は扉をつけて、統一性を持たせることにすればいい。なんとかごまかせるだろう)。そのほか必要な棚は、穴あきの支柱を立てて腕木で合板製の棚板を支えるようにした。一部をテーブルのように大きく広げたカウンターは、卓上いろりを落とし込めるようにしたものを積層合板を重ねて作った。本当なら無垢の1枚板がいいことはわかっていたが、とても経済が追いつかない。それからひとつだけ置くことにした四人がけのテーブルは、既成の天板を再利用することにして、新しくスチールの足をつけることにした。
道路側に置く二人がけのテーブルと椅子は、ひとまず安い既製品を2組ほど買って乗り切ることにした。そして、床は本当ならば、木製の板を張りたかったけれど、経済とメンテナンス(そして、歩道との連続性)のことを考えて、モルタルを塗って済ませることにした(ただそれだけだとつまらないから、目地を入れた)。
電気工事やガス、水回りの工事は手に余るので、できるだけいじらないようにして、それでも必要のある時は専門の業者に頼らざるを得なかった。
そんなふうにして4日ほど作業は続いた。最終日の夕方、カウンターが取り付けられた時には、一斉に歓声が上がった。一応、完成したのだ。冷蔵庫から瓶ビールとグラス、食品庫からナッツとチーズを持ってきて、再び養生シートを被せたカウンターの上に並べた(開店時にシミのあるカウンターでは、具合が悪い)。そして、ビールを注いだグラスを高く掲げて乾杯した。皆が笑顔になった。
食器やカトラリーは、とりあえずは手持ちのものに加えて、少しだけ合羽橋で似たようなものを買い揃えることにした。もともとカジュアルなカフェになるはずだから、食器を統一する必要はないし、むしろ違うものが少し混じる方が楽しいだろう。いずれにせよ、まずそんなにいっぺんに出すことはないだろうと思って、Aは思わず独り笑いをした。
飲み物や料理については、帰宅後に考えてみたが、何しろ時間が不足していることに加え、経験もないことから、まずは飲み物はコーヒー、紅茶、そしてビール。食べ物はパスタとオムライス、それから近所のパン屋から買ってくるバゲットを使ったカスクートをいくつか、サバサンドもいいかもしれないと思ったが、サンドイッチにとどめることにした(やっぱり、足したくなる性格なのだと、今度は苦笑いした)。
突貫工事の末、ようやく小さな看板、というか名札のようなものを取り付けるところまできたのだった。一刻も早く取り付けたい気持ちもあったが、これは翌日早いうちに取り付けることにした。Aは別に験を担ぐという気持ちはなかったけれど、新しいお店、新しい生活は、朝の清潔な空気の中で、始めるのがふさわしい気がしたのだ。
次の朝、AとCが最後の仕上げに取り組んだ。Aが訊く。
「ここでいいか?曲がってないか?」
「もうちょっと右でーす。少し左をあげてみて。いいでーす」
Cが大きな声で答えた。
そして、しっかり、取り付けた。
二人で、少し離れたところから見てみる。
「どう?」
Aが訊くと、Cがすかさず答えた。
「完璧でーす」
「そうか?」
「ま、ほんの少しだけ、ひいき目ですが」
と言って、Cはにっこり笑って見せた。確かにそうかもしれない。でも、気にしない。
「ようやくだね」
「はい」
いよいよ明日からだ。
「はい」
「ここまで、よくやってくれたね。ありがとう」
Aは照れ臭かったが、思っていたことを口にした。
「いいえ」
Cも珍しく神妙に応えた。
「がんばるぞ」
思わず口をついた。
「はい。がんばります」
Cも続いた。語尾は伸ばさなかった。
それから、中に入ると、予習を兼ねてパスタを作って、Cとふたりで食べた。まあ、悪くない。まあまあの出来だ。お客に出しても、文句は言われないだろう。
さあ、いよいよ開店だ。
ようやく、準備が整ったのだ。Cが帰ると、Aはもう一度店内を見回して、うんとうなづいた。それから、レコードプレイヤーによく手入れされたレコード盤をていねいにセットすると、正面になるようにカウンターに座りなおし、耳を傾けた。いい気分だった。
読んでくれて、ありがとう。
次回に続きます。
2024.08.25
新企画日曜版 FANTASY 18 「デザイン事務所とカフェの仕事と推理」03
デザイン事務所とカフェの仕事と推理 第3回
4
「おはようございまーす」
いつものようにCが、間延びしたあいさつとともに入ってきた。
「やあ。こんにちは。おはようじゃないよ。こんにちはだ」
「でもまだお昼前ですよ、もうすぐお昼だけど。それにその日で初めて会った時は、みんなおはようと言いますよ」
「何度言ったら、わかるんだい?朝と言ったってもう遅いし、第一初めて会ったからといって時間にかかわらずおはようございますと言うのは、水商売の人たちだよ。ここは、お店でも芸能事務所でもないんだから」
Cがやってくるようになってからもう何日目になるのか、毎回同じような場面が繰り返される(もしかしたらCには、スペイン人の血でも入っているのか?)。そのあとで、Aはここもお客次第だし、収入が不安定なのは変わらないな、と思って何やら冷たいものを感じたのだったが。
「ごめんなさい。わかりました」
その日は、殊勝にもCはそう答えた。それでAも、
「わかったのなら、それでいい。今後気をつけるように」
この会話を終わりにするべく言った。
すると、
「はい。……。あ、お腹減った」
間髪を入れずに、Cがあっけらかんとした調子で言ったのだった。Aは、威厳を持って言ったつもりだったが、どうやらそうではなかったようだ。
「えっ?なんか言った?」
「いえ。なんでもありません」
「いや、なんか聞こえた」
「言いませんよう」
「いや、言った」
「言ってませんてば」
「お腹減った、と言ったろう?」
「いやだ、聞こえちゃいました?」
「しっかり聞こえたよ」
「すいません」
「お腹が減っているのか?」
「ええ」
「朝ごはんは?」
「実は、食べていません」
Cが、今度はちょっと恥ずかしそうに、言った。起きたのが遅かったのだ。
「ま、聞いてしまったからしようがない。なんか作ろう」
Aは、やれやれと思いながら言った。若者は、どうしてこうなのだろう?
「やったあ。でも本当に?」
Cは軽い歓声を上げたが、すぐに疑い深そうに聞いたのだった。
「ああ、どうして?」
Aは、なんのことだかすぐにはわからなかった。
「だって、お昼ご飯のことは空耳だったのかなあって、思いはじめていましたから」
Cが、皮肉っぽく言った(こういうところは、容赦がない)。
「そうかね?」
「だって、ずっと出なかったもん」
Cが、くったくのない少女のように言ったのだった。
「悪かったね。今日は作るよ」
思い出したように、Aが応じた。
「ええ。期待してまーす」
また、語尾を伸ばして言った。
「おちゃらかすんじゃないよ」
Aは、つい言うのだった(やっぱり、年寄りにありがちな説教好きからは逃れられないということなのかもしれない)。
「ごめんなさい」
Cが言ったが、どのくらい本気なのかはわからなかった。
で、冷蔵庫を覗いたけれど、当然のことながらあんまりたいした材料は入ってない。しかし、その脇のシンクには、ちょうど塩抜きしていたアサリが置いてあった(昼は、このところはパスタを作ることが多いのだ)。大きな鍋とアルミのフライパンも用意してある。そして、ワインも(Aは、どうやらイタリア人になりつつあるようなのだ)。もちろん、ビールだってあるが。
「アサリは大丈夫?」
大きな声で聞いた。
「はーい。大丈夫でーす」
やっぱり大きな声だったが、相変わらず語尾を伸ばした返事が返ってきた。Aは、やれやれ(そのうちに、それとなく注意してやるか)、と呟いた。
で、ボンゴレ・ビアンコを作ることにした。
これを作るのは、たいしてむづかしくはない。ただ、フライパンでじっくり炒めたニンニクと赤唐辛子の中にアサリを加えて白ワインで蒸し煮にする。さらにパセリを加えたら、これと茹で上がったスパゲティを和えればいいだけだ(パスタは炒めるのではありません、和えるのですと、あのイタリアンの人気シェフも言っている)。その後で、ちょっと上等のエキストラ・ヴァージン・オイルをかけ回す。そして、刻んだイタリアンパセリの余りを少々足してやる。これで、香りとうまさがぐんと上がる。料理の腕は、ほとんどいらない。そうだ、イタリアンパセリはここで栽培することにしよう(うまく育つかどうかはわからないが)、とAは不意に思いついて、にやりとした。
出来上がったパスタを盛り付けた皿を事務所の方に運んだ。パスタはなんといっても、熱いうちに食べるのが肝心なのだから。
「さあ、どうぞ」
机の上に乗せると、Cは、
「わあ」
と大げさに驚いて見せると、
「いただきまーす」
と言うや否や、すぐさまフォークをくるくると器用に使って食べ始めた。Aは、人が嬉しそうに食べる姿を見るのは悪くない、と思った。
「おいしい!これって、本当にセンセイがつくったんですか?」
「ああ。でも、センセイは勘弁してくれって言ったろう?」
「そうでした。ごめんなさい」
「わかればよろしい」
Aがもったいぶったような口調で言った(もしかしたら、センセイになったような気分だったのかもしれない)。
「はい」
今日のCは、やけに素直だ。でも…と言わないのは、パスタのせいだろうか、そんなに期待していたのかと、Aはちょっと悪かったかという気がしてきた(まあ、ただお腹が空いていただけかもしれないが)。
「じゃあ、これからはそうしてください」
「はい。でもこれ、お店で出すことにしませんか」
Cが唐突に言った。
「えっ?」
Aはびっくりして、思わず知らず頓狂な声をあげた。
「はい。だから、お店で出しましょうよ」
「どこで出すって?」
「お店ですよ」
「えっ。でも、お店なんてどこにもないだろう?」
「だから、お店を始めるんですよ」
Cが、またまた突拍子も無いことを言い出した(やれやれだ。これも、今時の子の特徴なのなのだろうか?)。
「なんだって?」
思わず、またしても大きな声になった。
「だから、お店をやりましょうよ。お店で出しましょう。だって、おいしいもの。これ、けっこういいですよー……」
相変わらず語尾を伸ばして、そう言いながら、Cはフォークを器用に操って食べ続けた。
「でも、どこでさ?」
Aがもう一度訊いた。興味が少しだけ湧いたが、抑えようと努めた。
「この下で」
Cが、こともなげに答えた。
「えっ、どこだって?」
Aは今度こそ正真正銘驚いて、大きな声を出したのだった。
「だから、この下ですってば。あらいやだ、センセイったら、耳が悪いんですか?それとも、やっぱり年のせいかしら?」
「そんなことはありません。でも、この下にはもうお店がある。知らないのか?ま、ちょっと冴えないかもしれないけど、もっと冴えないおじさんがやってる。それに、何度も言うように、センセイはいい加減やめなさい。学校の先生と生徒じゃないし。だいたい、先生と呼ぶのは、本当に尊敬しているか、逆に皮肉を込めたものか、あるいはなんと呼べばいいかわからなくてとりあえずお茶を濁す時くらいのもんだ」
「はい。でも、大丈夫なんです、センセイ」
まったく聞いていたものかどうかわかりやしなかった。でも、それより何より気になって、Aは改めて訊いたのだ。
「どういうことだよ?」
Aが問いただすと、Cが言ったのだった。
「こないだ、聞いたんですよ」
Aの言うことはほとんど、聞いてなかったようだったが。
「何をさ?」
「はい。下のお店のおじいさんが、もうやめるかもって言ったんです」
Cが下のお店に行ったことがあるなんていうのは、意外だった。しかも、店主と話をしていたとは(まあ、Cは人当たりは悪くないが。あ、今おじいさんと言ったのか。たしかにAよりも少し年上のはずだが)。なんと言ったって、下の店は古めかしくて冴えない喫茶店以外の何ものでもない。近頃はやりの、レトロ喫茶や古民家カフェなんて言葉が似合うようなところじゃない。Cのような若い女の子が行くはずもないようなところなのだ。
「えっ?そうなのか?」
寝耳に水だったから、Aはあわてて訊いた。
「そうですよ」
「そんな年だったか?」
「ええ」
Cはこともなげに言ったあと、文字通り大急ぎで取って付けた。
「でも、年の取り方は、人それぞれですよ。センセイはまだ若いから、大丈夫」
「えっ(そうなのか)?でも、さっきから言っているように、センセイはやめてください」
Aはさっきは年寄り扱いされたばかりだと思いながらも、悪い気はしなかった。
「はい」
Cが、今度は素直に答えた(まあ、いつまで続くかはわからない)。
下の店の主のEはたしかにAよりは年上だが、実際のところそんなには違わないはずだった。でも、ということならば、自分が思っている以上に、自分も周りから見れば年取っているってことなのだろう(そう思うとAは、ついため息をついた。そして、やれやれとひとりごちたのだった)。そろそろ、本当にやりたいこと、できること(やりたくてもできないことがあることも、もうわかる年だ)をやる最後の機会かもしれない。
昔、通っていた鮨屋の主人が70歳になる頃に店を閉めると言った時のことを思い出した。
銀座の名店で修行したという彼の握る鮨は、小ぶりで上品な姿をしていて、うまかった。しかし、彼には跡継ぎがいなかった。それで、元気なうちにしばらく前から始めた趣味に専念したいと言うのだった(新しい趣味は、陶芸だった)。正直なところ、当時のAにはその気持ちがわからなかったが、今はよくわかるような気がした。何と言っても、陶芸は手を使う仕事だし、それが形となって眼の前に現れるのだ。そして、気に入ったならばいつまでも残しておくことができる。
鮨も似ていると言えば似ていると言えなくもないが、いくら美しくても食べられてしまえば、跡形もなくなってしまう。その瞬間の喜びだけでは、人は満足できないのかもしれない。
ただ、目の前のお客が喜んでくれるのを見ることができるという喜びについてはどうなのだろう。今のAには、こちらの方が断然大きいような気がしたのだった(ただの想像に過ぎなかったが)。
読んでくれて、ありがとう。
次回に続きます。
2024.08.18
新企画日曜版 FANTASY 17 「デザイン事務所とカフェの仕事と推理」02
デザイン事務所とカフェの仕事と推理 第2回
3
だから、所員は所長であるAだけだった。だが、しばらくしてからは暇を持て余した(たぶん。そうじゃなかったら遊びに来たりはしない)大学2年生だという女の子のCが、時々やってくるようになった。彼女は近所の八百屋の娘で、近くの大学のデザイン学科に通っているということだった。求人もしないのに、なぜかやってくるようになったのだ。Aは今でも、Cが初めて事務所にやってきたときのことは忘れない。
事務所をはじめて半年ほど経って、チラシを配ったり、いちおうちゃんとした看板を掲げることをようやく済ませた頃のことだった。それまではクチコミに頼るだけだったから、とにかく早く手をあげることだけはしておかないと、何もしないままになりそうだと思ってのことだった。しかし、それがどうして彼女の目にとまることになったのか……。
老朽化して木目の浮き出た階段を踏みしめて、ミシミシと唸らせながら登ってくる音は、ふだんとは違う響きが聞こえた。靴音は男のもののような気がした、というかハイヒールのようなものではなかった。しかし、奥の方へ進むことはなく、事務所の扉のところで止まった。お、ちゃんと看板を掲げてから初めての依頼者だ。これは幸先がいいぞ。案外やっていけるかも。さあ、どんな仕事がやってくるのか。Aはワクワクしながら待ったが、同時になにやらざわつくようでもあった。なんでも、初めてというのは特別な感じがして、期待と不安が入り混じるのだ。
すぐに、扉をノックする音が聞こえた。トントントン。3連打だ。いいぞ、と思った。Aは、よく日本のテレビドラマなんかで出てくるような、トン、トンという妙に間延びした2連打のノックが嫌いだった。なんだか貧乏くさい気がするのだ。でも、こういうことを気にすること自体が、似たようなものかもしれない。しかもある時、贔屓の英国製のドラマで、若い刑事がトン、トンと2連打のノックをする場面を目にしたのだった(ま、こういうこともある)。
なんであれ他所から借りてくるなら、まずはしっかりその基本形のまま借りて欲しいのだ。そうじゃなかったら、たいていの場合、なんだか中途半端でみすぼらしい感じがしてしまう。変形させて、成長させるのはその後だ、とAは思っていたのだ(果たして、ノックの響きに成長があるのかどうかは、不明だが)。
「どうぞ」
Aは、期待を隠せないまま、返事をした。ちょっと上ずっていたかもしれない。
「失礼しまーす」
ちょっと間のびしたあかるい声とともに現れたのは、Tシャツにジャケット、そして太めのジーンズに白のコンバースを履いた女の子だった。頭には、コットンのキャスケット、背中にはリュックを背負っている。後ろで縛った黒い髪が肩までかかり、輝くのが見えた。
「(おっと」)
やってきたのは仕事の依頼ではなくて、暇を持て余している(に違いない)若い女の子だったのだ。
「(えっ?)」
Aは古希を迎えたばかりだが、一般に言われるような、酸いも甘いも嚙み分けるような懐の深さや寛容さと言ったものとは、未だ無縁のままだ(もちろん、憧れがないわけではないのだが、残念ながら身につかないようだった)。でも、どうしたことか、このところは一気に年取ったような気分になることがよくある。この時も、まさにそんな気がした。
「おはようございまーす」
妙に語尾を伸ばすのは、いかにも今時の女の子だ。Aは、これが馴染めなかった。
「やあ。おはようございます」
まいったなーという気分をなんとか隠して、挨拶を返した。
「Cと言います。約束もなしで、ごめんなさい」
いちおう、礼儀はわきまえているようだ。
「で、どういうご用件でしょう?まさかインテリアデザインの依頼じゃ、ないでしょう?」
もうすっかりがっかりしていたが、Aもいちおう、丁寧な口調で尋ねた。
「はい、もちろん」
最初の訪問者は、悪びれる様子もなく、そう言ったのだった。Cという名前らしい女の子らしかった。
「じゃあ、何の御用でしょう?」
仕方なく、訊いた。すると、間髪を入れずに返ってきた返事は、
「ここで、働かせてください」
というものだった。
「えっ?」
Aは思わず知らず、上ずった声が出た。本当にびっくりしたのだった。
「わたし、いま学校で住宅のデザインの勉強をしているのですが、授業だけじゃつまらない気がして……」
Cが話し始めると、Aが口を挟んだ。
「ふーん。ま、学校というのはたいてい、そうしたものじゃないのかね?」
ちょっと意地悪な言い方だった。Aは経験上、学校という場所は学ぶものの気持ち次第ということを知っていたのだ。
「そうかもしれませんが、でもわたし、実際の現場で経験してみたいんです。ちょうど春休みだし」
「えっ?」
また、バカみたいに繰り返した。
「デザイン事務所で、デザインの実務を学べたらいいなあって」
「ふーむ。それはいい心がけだけどね」
「だったら、決まりですね。よろしくお願いします」
ぺこりと頭を下げたが、今度は語尾を伸ばさなかった。
「えっ?」
Aはさらに間の抜けた声で、また繰り返し、あわてて付け加えた。
「ちょっと待って」
なんだかすっかり相手のペースになってしまっている。これはいけないと、Aはかろうじて一呼吸おいた。
「えっ、どうしてですか。何か問題あります?」
Cというらしい女の子が、たたみかけるように訊いた。
「どうしてって、ねえ。そりゃあ、あるでしょう?」
「えっ?」
「それなら、もっといい事務所があるでしょ?」
「たとえば、どんな?」
Cが、間髪を入れずに、のんびりした調子で重ねて訊いてきた。
「例えば、きみが好きなデザインをしているようなところ、とか」
「ええ。なるほど」
「だいたい、きみはデザインの実務をと言ったけど、うちにはほとんどないよ」
全くないと言う方が正確だったかもしれないが、Aはそれじゃなんとなく格好がつかない気がしたのだった。
「そうなんですか?」
「それに、こないだなんか、棚のことで相談したいことがあると言うから、棚をデザインして、新しく作るのかと思って出かけたら、この棚が邪魔なんだけど捨てた方がいいかしら、なんて聞かれたくらいなんだから」
自慢するようなことではなかったが、つい力が入ってしまった。
「へえ。そうなんですか。でも、考えようによっては、それもデザインのひとつですよね?」
どうやら、機転はきくようだった。
「ま、全く無関係とは言わないけれど……。時には、犬の散歩の依頼だってある」
ちょっと押され気味のAが続けた。そして、さらに付け加えて言った。
「まったく、うちがデザイン事務所だということはすっかり忘れているのに、暇だということはしっかりわかっているようだ」
しかし、声は次第に小さくなった。おっといけない。初めて会った人に愚痴ってしまっている。しかも若い女の子にだ。Aはますます困惑し、混乱するばかりだった。
「へえ、面白そう。私、犬は好きだから、任せてください。それで、他には?」
さらに、たたみ込んでくる。これでは、どっちが諭しているのかわからないというものだ。
「猫の世話だってあるよ」
Aがヤケクソ気味に言ってから、急いで付け加えた。
「いや、だから、仕事があって、それに、ちゃんと給料を払ってくれるようなところとか」
「なるほど。たしかに、そうかもしれませんね」
ようやく、話が噛み合い始めたようだった。
「そうだろう?なら、そうしたほうがいいね」
「でも」
「でも、って?」
またまた、驚いた(わかったようだったのに、どうしたことなのか)。なんだか、すっかり相手のペースに乗せられて、自分を見失ってしまっているような気がした。きっと、対面でのお客の応対に慣れていないせいだ、これも貧すれば鈍するということなのだろうか。どうしたことか、Aは頭の片隅で急に反省し始めた。これが、さらに形勢を不利にしたようだった。
「でも、わたし、この近くじゃなければ困るんです」
少し、真剣な口調だった。
「えっ?そうなの?」
Aは、またバカみたいな反応をしてしまった。
「そうなんです」
「それでも、他にあるだろう?」
とは言ったものの、あんまり詮索しても悪いと思って、この時は、Aはそれ以上のことは訊かなかった。しばらく、間が空いた。
「じゃあ、ぜひよろしくお願いします」
Cは、今度こそもう決まりだと言わんばかりに、宣言したのだった。その勢いにすっかり飲み込まれたのか、Aがそれに釣られるように言ったのは、自分でも思いもしないものだった。
「そう?いいのか?給料はうんと少ないよ。見てのとおり、事務所ははじめたばかりだし、ようやく看板を出したところだからね。さっきも言ったように、今のところまともな仕事はない。これからだって、怪しいもんだ。だから払えたとしても、文字通り雀の涙。それもただの1滴の時だってあるかもしれない。まあ、時々お昼ご飯くらいは作ってあげてもいい」
なぜ、こんなことを口走ってしまったのか、Aにはわからないままだが、やっぱりCのあかるい積極性に気圧されてしまったのかもしれない(やれやれ)。
「えっ、そうなんですか?やったあ、ラッキー!」
なんとも能天気な女の子だった。まあ、これが若いということなのかもしれない、Aは心の中で呟いた。そして、ほんの少し羨ましくなった。
ともかくも、そうして事務所は晴れて(?)、二人体制となったのだった。そして、それ以来Aは、相変わらず噛み合わうことのないCとの会話に翻弄されている。
読んでくれて、ありがとう。
次回に続きます。
2024.08.11
新企画日曜版 FANTASY 16 「デザイン事務所とカフェの仕事と推理」01
デザイン事務所とカフェの仕事と推理
前書き
月例増刊号は、しばらくの間、日曜版として週1回の連載を試みようと思います。数年前に2つ目の小説をと書きかけてそのまま中断していたものを、修正しつつ書き継いでみようというわけです(ちょっと無謀?)。完成したら掲載しようなどとと言っていたら、いつになるかわからない。これこそ、見切り発車するしかない。それに、うまくいかなくても、誰も困らない。ということで、長期連載に挑戦(中・長編小説なのです)、というわけです。必要なら、書き直せばいいだけだ、と開き直りながら(第一、読む人がいるかもわからない。と、言いながらこうして前書きを書いているというのもちょっと……)。
ミステリーが好きなので、本来ならばハードボイルド系をと言いたいところですが、とても無理(僕は、引くのが苦手で、それよりも足す方がまだしも、という気がする)。ならば、楽しい読み物をと思って、いわゆるコージーミステリー、軽いミステリー仕立てののんびりとした日常の話をと思って書き始めたのですが、何しろ長いものは2回目なので、ミステリーに不可欠な事件が起こらず、どこへ行くのかわかなないまま収集がつかなくなって、中断するに至ったのでしたが。さて、今回はどうなるか。果たして、無事(?)事件は起こるのか。はたまた、別の展開になるのか。まあ、やってみなくちゃわからない。
タイトルは、『ヴァイオリン職人の探求と推理』や『ビール職人の醸造と推理』などから拝借しました。新聞小説が1日あたりほぼ原稿用紙2.5枚分1000字というから、日曜を除いた1週間分だとすると6000字ということになる。とりあえず週1回、おおよそこのあたりを目安に、掲載することから始めてみようと思います。何事も中途半端になりがちな生活と性格を鍛え直す練習になればいいのですが。
デザイン事務所とカフェの仕事と推理
1
タオルにたっぷりお湯を含ませた後、しっかり絞って顔を覆うとたちまち温かな湿気が広がって、肌に染み入るようだった。久しぶりに気持ちがよかった。Aは長い間、この感覚を忘れていた。勤め始めてからしばらくすると手間を惜しんで、電気シェーバーを使うようになっていたのだった。そして、シェービングクリームを手にとって頬に塗りつけると、恐る恐るカミソリを頬に添わせながら動かした。何も起きなかった。
Aが髭を伸ばし始めたのは、退職した後しばらくしてのことだった。それからもうひと月ほどにもなるだろうか。うんと若い時にも試みたことはあったけれど(貧相な見かけを隠せればと思ってのことだった。重厚な大人っぽい見かけに憧れたのだ)、生やしてみると薄くてみすぼらしいので、すぐに剃ってしまった。
今度は白いものが目立つだけで、薄くてみすぼらしいことには違いがなかったが、でも伸ばし続けていた。というか、髭のことなどどうでもいいような気がして、剃る気力がなくなっていたのだ。洋服についても同じで、清潔でさえあれば着た切り雀のように見えても気にしなかった。たぶん、新しくなった生活に馴染めず、生きる力を失いかけていたのかもしれない。でも、もう剃ることにしよう。そろそろ気分を変えてもいい頃合いだ。そもそも、髭で環境の変化を乗り切ろうとしたというのは、いかにも志が貧しい気がする。しかし、何であれ、気分を変えなくちゃいけない。
2
Aが長年勤めた職場を離れるときに、いっしょに働いていたBが、「これからも、皆が集まれるような場所があるといいですね」と言ったことが、始まりだった。彼は、Aよりも一回り以上若い上に、冒険心がある起業家タイプの人間だ。やりたいことがあれば、すぐに実行に移す。自分でデザイン事務所とカフェを運営している。でも、儲けようとか大きくしようとか、野心というのかガツガツしたところがない。それが、経営者としていいことかどうかはわからないが、だから気が合ったかもしれない。その時Aは、とくに新しいことを始めようという気はなかったけれど(何しろ筋金入りの怠け者を自認しているのだ)、集まる場所があるというのはちょっと魅力的に響いた。それにもうひとつ、大量の本や雑誌、そしてCDやDVDの収納場所を一刻も早く確保しなければいけないという事情もあった。
で、とりあえず部屋を借りることにした。と言っても、たいした場所じゃない。借りられたのは郊外の街にある、再開発が終わりかけている駅に通じた幹線道路沿いの商店街(というのか、歩道に面してところどころに3層から5層くらいのビルが建っており、今でもごくゆっくりその数を増やしているが、その間を木造の古い店や民家が埋めている)。不思議なことに、反対側の駅に近い方はそれでも、新しい店やビルが建設されていた)。つまり、新しい場所は、今のところシャッター通り化をかろうじて免れているものの、駅前の再開発からは取り残された幹線道路沿いのモルタル壁の建物の2階にあった。二室続きの広い方で、12畳ほどの細長い部屋だ。ここをボロ隠しのために、壁紙を剥がして白く塗って、ありあわせの家具を運び込んだ。キッチンとトイレは隣室と共同。駐車場ももちろんない。
チャコール・ブラックから赤に塗り替えた古いミニを停めることができないのは、残念だった(雨の日のことを考えると、正直なところちょっと辛い気もした)。でも、家賃のことを考えると、贅沢は言えない(何しろ、収入源はといえば、わずかな年金だ。しかも、物価は上がる一方なので、気分はますます暗くなるばかりだ)。ま、自宅から歩いて通えない距離じゃないし、健康のためと思えば我慢できないこともない。それに、雨の日は休めばいいのだ。仕事じゃないのだから、と前向きに考えることにした(なんと言っても前向きが一番、ということを身につけなければいけない)。隣人は近所の大学に通う男子学生で、本人によれば、今時珍しく、6年生だという。
1階は古びた喫茶店だ。このあたりの店の中でさえ、くたびれ加減は際立っている。とても、カフェと呼べるようなものじゃない。Aよりも少し年上のくたびれた主人(マスターと言うのだろうか)が、一人でやっている。昼間でも薄暗くて、四人掛けの小振りのくたびれたデコラ張りのテーブルとビニルレザーの椅子が2組、そして5人ほどが座れるカウンターがあるだけ。天井には、大きなシーリングファンがついている。ただ、古いけれど、タンノイの大きなスピーカーとラックスの真空管アンプ、そしてヤマハのレコード・プレヤーが置いてある(どうしたことか、何れもがAが若い頃に憧れた往年の名機のようだったが、これをちゃんと鳴らすには相当の腕が要りそうだった)。ただし、CDプレーヤーは見当たらなかった。インターネット配信やサブスクリプションなんていうものは、論外。どうやら、こちらも時代から取り残された口のようだ。
それでもAは、時々この音(JBLよりも柔らかい響きで音楽を聴かせて、好ましい気がしていた)を聴きたくなって、降りて行くことがある。そして、ここから少し行ったところには郵便局がある。実は、これもけっこう重宝している。というのも、Aは田舎の施設で一人で暮らす恩義のある人に毎日ハガキを出す。外に出ることのできないその人のために、その季節季節の木々や花々、そして野草の写真を撮って送るのだ。
さて、そこで何をやるかが問題だった。元々は本やCDの保管というか書斎のようなものとして使い、時々は集会のための場所として利用できればいいというつもりだった。それでもよかったのだけれど、ちょっと芸がない気がしてきた。というより、しばらくしてわかったことは、実際のところは思ったより人が集まらなかったのだ。考えてみると、これは至極当然のことだ。人にはそれぞれに生活があるし、忙しいのだ。誰もがAのように暇というわけじゃない(Aが気づくのは、こんなふうにたいていずっと後になってからだ)。場所があることは大事だが、それだけでは不十分で、出かけたくなるような何か他の魅力が不可欠なのだ。それが、主の魅力でもいいわけだが、残念ながらAの場合はそうではなかった。
で、しばらくしてデザイン事務所の看板を掲げたのだった。とは言っても、建築やインテリアの仕事はほとんどなく、もっぱら近所の建物のトラブルの相談が時々あるくらいだった(予想通りで、まあそんなに期待していたわけじゃなかったが、ちょっと寂しい気がしていた)。そのほか、たまには床屋のポスターや洋装店のセールのチラシのデザインもやった(小さな街では、こうした洋装店の類を時々見かけるが、売れている様子はないのにどうして潰れないのかは、Aにとっていまだに謎だ)。時には、犬の散歩を頼まれることだってある(「どうせ暇なんでしょ?」という具合だ。まあ確かに、じゅうぶん暇があることには違いがなかった)。
先日などは、カーペットを交換しなくちゃいけなくなったからというので、新しくするカーペットの選定の相談だろうかと思って出かけてみると、そうではなかった。なんと、カーペットの交換の間、犬(カーペットを齧ってダメにした張本人だ)を散歩に連れていってちょうだい、という依頼だった。まあ、暇だったこともあるし、妙齢の女性ににっこり微笑まれながら頼まれたら、断ることはできない。で、引き受けて、散歩に出た。主導権は犬の方にあるような散歩だった。
読んでくれて、ありがとう。
次回に続きます。
2024.08.04
月例増刊夏休み特別号・2 FANTASY 15 「プチとツキの夏休み」
プチとツキの夏休み

プチは、西の遠く離れたところに住む、いとこのツキを訪ねるために、泊りがけの小旅行に出かけることになりました。プチが何日か家を開けるのは、初めてのことなのです(いろいろな事情で、帰るのが遅くなったことはありましたけれど)。途中で何が待っているかわからない、ちょっとした冒険旅行です。
ツキは、プチと同い年。偶然にも同じ年の同じ日に生まれました(もちろん、場所は比較的近かったのですが、同じではありませんでしたけれど。もしかしたら生まれた時刻も同じ頃だったかもしれません)。そのせいか、初めて会った時から、すぐに仲良しになりました。
プチがツキと出会った頃、ツキはちょっと変わった子ねこでした。あんまり自分から口を開くことはほとんどありませんでしたし、話し始めたとしても、言葉がうまく出てこなかったり、突然話題が別の所に飛んだりして、聞いている方は理解することも大変でした。だから、周りの猫たちや近所の人たちのほとんどが、次第にもう相手にしようとはしませんでした。

でも、プチは辛抱強くはなしを聞いて、ツキが言おうとしていることや彼のことをわかろうとしたのです。それがツキにとってはとても嬉しいことでしたし、プチにとってもツキはだいじな仲間でした。というか、双子の兄弟のようだったというのが近いかもしれませんね。プチもお母さんとお父さんを亡くしばかりだったし、周りには友達もいないし、話し相手といえばおばあさんだけでしたからね。
しかし、それからしばらくして、ツキが家族といっょに遠くへ引っ越して行ったので、それからずっと会うこともできませんでした。それが、おじさん、つまりツキのお父さんから手紙が届いて、ツキが会いたがっているので遊びに来ないかという誘いでした。プチも、同じ気持ちでしたが、おばあさんのことが気になって出かけられませんでした。ある時に、このことをアオに話したら、ぜひ行くといいと言ってくれたのでした。だから、プチはこの小旅行を楽しみにしているのです。
その間、体の弱いおばあさんはどうするのでしょうか。プチももちろんそのことが一番心配しでしたが、大丈夫。アオとその仲間たちが協力して面倒を見てくれることになっているのです。アオたちが山の家に行って泊まったってかまわないよと言ってくれたのですが、おばあさんがせっかくだから、アオたちの海のそばの洞窟に行ってみたいというので、連れて行ってくれることになったのです。なんと言っても、おばあさんも外に出るのはうんと昔のこと以来ですから、プチと同じほど、もしかしたらそれ以上に楽しみにしているようなのです。

プチは、道すがら、いろいろなところでたくさんの猫たちと会いました。アオや街で悪さをしてプチたちと戦ったあとは仲良くなったあの黒猫の仲間たちがたくさんいましたから、行く先々で彼らが待ってくれていましたし、みな歓迎してくれたのです。おかげで、プチは長い道のりも苦にならず、楽しく進むことができたのでした。何と言っても新しい友だちができるのは嬉しいことでしたから。


海沿いの道から山の方へ続く道に入ると、あたりは田んぼが広がっていました。稲の背ももうずいぶん高くなって、たくさんの穂をつけているようでした。プチは、まっすぐの道をさらに進んでいきます。どのくらい歩いたのか、喉が渇いたので水を飲み、しばらく休憩した後、さらに歩きます。初めて目にすした、まだ鮮やかな緑色をした稲穂が風に揺れるのを見ていると、なんてきれいなんだろうと思うのでした。
時々、地図を確かめながら、いよいよツキの住む家が近づいていることがわかると、思わず足早になるのでした。まっすぐの道をさらに歩いて行くと、遠くの方で手を振ったり、跳ねたりする猫が見えました。あ、ツキだ。きっとツキに違いない。

そこでプチも大きく手を振り、大声でツキの名前を呼ぶと、一目散に走り出しました。次第に、ツキの姿が大きくなってきました。さらに近づくと、ツキも走り寄ってきました。そして、お互いに飛びつくようにして、しっかりと抱き合ったのでした。

「やあ、ツキ。元気だったかい?」
「ああ、……」
ツキは短く答えて、何か言おうとするのですが、うまく言葉が出てきません。昔からそうだったのです。言いたいことはあるのに、うまく言葉が出てこないことがあるのです。
「ねえ、ツキ。あわてなくていいよ。時間はたっぷりあるんだからね」
「ああ、ありがとう」
ツキは、にっこり笑います。初めてあったときもそうだった。プチは、いつも辛抱強く聞いてくれたのでしたから。
「じゃ、じゃあ、家の中へ、ど、どうぞ」
「ああ。おじさんは元気かい?」
「う、うん。元気だよ」

中へ入ると、満面の笑顔のおじさんが待っていました。
「やあ、プチ。よく来たね。疲れただろう?」
「はい、いえ。手紙をありがとうございました」
そう言いながら、一息入れたプチはあたり見まわしました。決して贅沢ではないけれど、さっぱりと片付いていて気持ちの良さそうな家でした。ツキは、おとうさんとふたりで暮らしています。おかあさんは、ある時にふいに出て行ってしまったということでした(プチは、ある時におばあさんに聞いたのですが、どうしてかはわかりませんでした)。
それから、お茶とお菓子を食べながら話していると、すっかり昔のとおりの気持ちになったのです。

翌朝、プチはツキといっしょに散歩に出かけました。朝の空気が清々しく、葉っぱに残った夜露が陽の光を浴びててきらきらと輝き、緑が風にそよいでいます。時折り強く吹く風が、プチとツキの頬を撫でていきます。
「きれいだねえ!気持ちがいいねえ!」
「あ、ああ。いっ、いつまでも、見ることができたら、いいのにね……」
「えっ。どうしたの?なにかあったのかい?」
「あ、ああ。で、でもね……」
「うん?」
「あ、あのね、この田んぼも取り上げられてしまうかもしれないんだよ。村の大人の人たちが、そう言っていたんだ」

ツキが言うのには、この村に住むひとりのお金持ちが、村の人たちに、田んぼを耕す機械を買うためにたくさんのお金を貸していました。その利子が高くて、村の人たちは利子を払うのが精一杯だったのです。それで、その高利貸しは、時々ニヤリとしながら
「そろそろ、お金を返してもらえませんかな」
と言うのでした。
「ちょっ…、ちょっとお待ちください。今はとても無理です」
貧乏な村の人たちは、いつもこう言うしかなったのですが。すると、お金持ちはすかさず、
「じゃあ、田んぼをいただきましょうかな」
決まって、こう言ったのでした。
「そんな、それは困ります……」
村人たちは、弱々しくいうのでしたが。
「こっちだって、困るんだよ」
そう言われると、返す言葉もなく、
「……」
だまりこむしかなかったのです。
「それじゃあ、こうしましょう。誰か村の娘を嫁に出す気はありませんか。そうしたら、借金のことはすっかり忘れることにしましょう」
お金持ちは、急に優しくなった声で言います。
「ええっ……」
村の人たちは、思いもかけない申し出に驚きました。
「あなたがたも田んぼを失わなくていいし、私も助かる」
「それはいくらなんでも……」
「じゃあ、やっぱり田んぼで払ってもらうしかありませんな」
今度は、強い口調でした。そう言われた村の人たちは、困り果てて、
「今しばらく、お待ちください」
と言うのがやっとでした。
そんな話を聞いて、プチも悲しい気持ちになったのですが、その期限がもう間もなくだっていうのでした。
「む、村の人たちをなんとか、助けてやれないかな?」
「ああ」
「ねえ。プチ。む、村の人たちはとってもいい人たちなんだよ。ぼ、ぼくのことも気にかけてくれているんだ」
ツキが言うと、プチは何かを思いついたように、
「ねえ、ツキ。きみは工作が得意だったよね?」
と言いました。
「うん、まあね」
「それに、細かいことまできちんと考えることも」
「うん」
それから、プチとツキは家に帰るとおとうさんに話をして、村人たちの代表に来てもらうことにしました。それから、カカシと娘たちの綺麗な洋服を借りることにしました。大まかな作戦を伝えると、村人たちは半信半疑でしたが、すぐに用意してくれました。

そして、その晩、プチはツキといっしょに細かい計画をたてた後、カカシにきれいな洋服を着せることにしたのです。もちろん、頭にはツバの大きな帽子をかぶせるようにするのを忘れませんでした。
「これなら、きっとだいじょうぶだね?」
「う、うん。き、きっとうまくいくよ!」
プチとツキは、顔を見合わせて、にっこり笑ったのでした。
翌朝、また村人の代表者たちに来てもらうと、プチは言いました。
「あの強欲な、高利貸しに伝えてください」
「なんと?」
「花嫁候補が決まりました、と。お昼に、連れて行きますからと」
「えっ?そんなものはいないのに?」
村人たちはびっくりして、声をあげました。
「ええ、このカカシを見てください。遠くから見ると、きっと若い娘のように見えるに違いありません」
「ああ、確かに」
ようやく、納得したのでした。
それから、プチとツキは、もう一度作戦を伝えました。今度は細かいところまで、全部をです。
プチとツキは村人の代表者たちといっしょに、綺麗な洋服を着て大きな帽子をかぶった花嫁候補をつれて、ごうつくなお金持ちの屋敷にの近くまでやって来ました。
「さあ、高利貸しに伝えてきてください。少し離れたところに花嫁候補がいます、と」
プチが、言います。
「ああ」
「さ、作戦のことを忘れないでね」
今度は、ツキが念を押しました。
「ああ、わかっているさ、ツキ」
村人の代表たちも、よくわかっていました。
しばらくすると、村人と証文を持ったお金持ちが門の近くまで出て来ました。
「あそこに、あなたの花嫁の候補がいますよ。見えますか?」
「ああ。でもどうしてここまで来ない?」
「村の娘たちは、みな恥ずかしがり屋ですからね」
「ああ、そうか」
「それでは、証文をこちらに」
「ああ。でも、やっぱりすぐに、娘をここまでつれて来てもらえるとありがたいのだがね?」
「いえいえ、とっても恥ずかしがり屋なものですから。とくに、あの娘はね」
「そうか。なら、しかたあるまい」
「おわかりになってくださって、よかった。さ、証文をこちらへ」
「ああ。これだ。確かめればいい」
「確かに」
「それでは、約束通り、今度こそつれて来てもらおうか」
「ええ。でもそれよりも、あなたが迎えに行かれたらどうでしょう。娘は、あそこで待たせますから」
「どうしてだ?」
「あなたのやさしさが、娘にも伝わるに違いありません。きっと、好ましく思うことでしょう」
「ああ。確かに、そうだな」
ごうつくなお金持ちは、自分のことを良く思われたいと思っていましたから、すぐに承諾したのでした。
「それでは、しばらくお待ちください。くれぐれも焦らないで。何と言っても恥ずかしがりの娘のことゆえ」
「ああ」
気もそぞろで、返事をしました。
「娘に伝えたら、合図をいたしますから」
「ああ、わかった」

それから、村人はプチやツキたちが待っているところに戻ると、お金持ちに聞こえないように小さく言いました。
「うまくいったぞ」
「証文は破ってしまいましょう」
「ああ」
証文を破り捨ててにっこりすると、お金持ちの方を振り返ると、大声で言いました。

「さあ、どうぞ。おいでください」
そう言うと、花嫁候補の娘を残して立ち去りました。それを見たお金持ちは、はやる気持ちを抑えきれずに、急ぎ足で花嫁のところをめざしたのですが……。

それから、プチとツキ、そして村人たちには、悔しそうな声を上げて地団駄を踏むお金持ちの姿が見えたのでした。
強欲なお金持ちは、
「してやられてしまったな。まあ、しようがない。お前さんを連れて帰ることにしようか」
とつぶやいたのでした。それから、
「少しは我が家も、賑やかになるだろうからな……」
と話しかけながら、着飾ったカカシを抱えて戻って行きました。

こうして、田んぼを手放さなくてよくなって、美しい景色を守ることができた後も、しばらくプチはツキと楽しい時間を過ごしました。

「じゃあね」
プチが言うと、ツキが
「うん」
おじさんに肩を抱かれたツキが、うなづきます。
「またね。今度は。僕の山の家に来てね。おばあさんも待っているからね」
「うん。またね」
「絶対だよ」
「あ、ああ」
「ツキもおじさんも元気でね。じゃあね。待っているからね。必ずだよ」

それから、プチは来た道を戻って、ずっと遠くの山の家をめざしました。途中で振り返ると、ツキがまだ手を振っているのが見えました。
おしまい。
*
あとがき
夏休みの頃でもあることだし(ま、僕にはほとんど関係ありませんが。それどころか、日曜祝日だって平日と変わりませんけど)、久しぶりにプチのお話を、と思いついたのでした。もう、誰もおぼえていないかもしれませんけど。実は、『天空に……』が即日設計で終わったのも、このせいでした。飽きっぽいし、集中力がないということもありますが(小さい頃からそうだったようなので、筋金入り)。
ともあれ、意気込んだ割には、なんだか代わり映えがしないようなので、挿絵のタッチを変えてみることにしました(サインペンを使いました。せめてもの工夫)。今回もやっぱり、見切り発車っぽいようですけど。
それにしても、読みたくなる(と思える)ようなお話を書くというのはむづかしい。
最後まで読んでくれて、ありがとう。
2024.07.28
月例増刊夏休み特別号・1 FANTASY 14 「天空に浮かぶ石柱と床」
天空に浮かぶ石柱と床
*
その時、セイはビルの中の広い室内に横たわっていた。目が覚めたような気がしたので、薄く目をあけてみると、周りはすべて白一色の光景が目に入った。床も壁も天井もすべてが白い面に囲まれた中に、ベッドがたくさん並んでいた。ベッドもまた白いシーツと白いカバーに覆われて、その中にはたくさんの人々が横たわっているようだった。立っている人や歩き回るものは、誰もいない。そしてもちろん、誰一人として声を出すものもいなかった。まるで、セイ以外の全員が、じっと眠ったままのようだ。ただわずかに聞こえているのは、ミサ曲のような音楽だけだった。それも耳を澄ませると、ようやく聴こえるような、ごく小さな音だった。
音楽に聴き入るうちに、自然に目を閉じると、また眠り込んだようだった。いったいどのくらい経ったのか、再び薄く目を開けた時、ひとりの女性が立っているのが見えた。
その女性は澄んだ瞳で、セイをじっと見て、
「さあ、どうぞこっちへいらっしゃい」
と、やわらかな口調で声をかけたのだった。
「えっ?」
セイは、何がなんだかわからず、思わず訊いた。しかし、自分の声がまるで知らない人の声であるかのようだった。
「目を覚ましたばかりのあなたよ。さあ、起きて、こっちへいらっしゃいな」
女性は、もう一度やさしくいざなうのだった。
「ええ。はい」
抗うすべはないようだった。セイは、その目と声に吸い込まれるように自然と起き上がり、一歩を踏み出した。まるで、地に足がつかず、浮いているような、ふわふわとした感じがした。
「さあ、ついていらっしゃい」
今度は、もはやためらうことなくついてくることを確信したような口調だった。
「はい」
「こっちよ」
その人は、手で進むべき方向を指し示した。
「はい」
「さあ」
その声に誘われるまま、セイはついて行った。なんだか頭がぼんやりしたままだし、周りの様子もよくわからなかった。うんと長い階段を上って行ったような気がするが、相変わらず、全身が浮いたような感じのままだった。いったい、どのくらい上ったのだろうか。でも、不思議なことに、疲れた気はまったくしなかった。
「さあ、着いたわ」
女性が、言った。
「どうぞ、見てご覧なさい」
その声に促されるように、
「はい」
と答えたセイは、恐る恐る顔を上げて、目をあけた。
*
すると、どこまでも広がる青空に薄い雲がたなびく天空に石柱が何本も立ち並び、その上には間をあけて、1本ごとに小さくて平たい薄い石の板が載っている光景が眼前に広がっていたのだった。それぞれの床には明るい光が差して、白く輝いていた。ただ、どうしたことかそのうちのいくつかは、光が当たっていないところもあるようだった。光の当たっているところのところどころには、一枚の布でできたような白い奇妙な服を着た人が一人ずつ立っていた。そこには手すりも何もなく、ちょっとでも揺れたり、バランスを失ったりすると、たちまち真っ逆さまに落下してしまうのではないかと心配になったが、立っている人はまるで気にしていないかのようだった。
「さあ、こっちへいらっしゃい」
そのうちの一人が、声をかけた。ここまで案内してきた女性はいつの間にかいなくなっていて、他には誰も見あたらなかったので、声をかけられたのは、このセイのはずだった。
「えっ?」
驚いて、セイは思わず呟いた。
「さあ、どうぞ。早くこっちへ来るといい」
「……」
今度は、声が出なかった。細い石柱の上に乗った狭くて薄い石の床を見ると、足がすくむ思いがしたのだ。
「何も怖がることはないんだから」
やさしい声で、諭すような声が聞こえた。
「……」
返事をしなければいけないと思いながらも、言うべき言葉が見つからなかった。
「ただ、足を踏み出すだけでいいんだ」
いかにも簡単で、心配することは何もないというように、言うのだった。
「めまいがします」
他に言うべきことを知らず、ようやく正直に打ち明けた。
「高いところが苦手なのですか?」
「ええ。はい」
恥ずかしい気もしたが、改めて足元がふらつくようだったので、仕方なくうなづいた。
「じゃあ、目を閉じて想像すればいいんですよ」
それで万事解決とでもいうように、さらりとこともなげに言うのだった。
「何を?」
「雲の上の楽園ですよ」
「楽園?」
「ああ、楽園デス。何もむづかしいことじゃないでしょう?」
「……」
「そう、いつも光に満ちていて、穏やかで静かな場所です」
「……」
いろいろなことが頭をよぎったが、声は出なかった。
「ストレスも苦しみも何もないところですよ。たぶん、これまであなたが直面してきたようなことは、ここでは一切感じなくて良くなるんです」
「誰でもが……?」
ようやく、セイは小さな声で聞いた。
「……」
「そうじゃないんですね?」
そう呟くと、これまでのことが急に思い出された。必ずしも、順風満帆というわけではなかった。その一方で、人にも幸運にも恵まれた。ただ、そのことに甘えて、結局、好意や運を生かすことができなかった。何事に対しても、きちんと向き合い、真剣に取り組み続けることができなかったのだ。それに、胸を張って誇れるような人間になれたわけでもなかった。
つかの間、過去のことを振り返っていると、
「とにかく、こちらへ来ればいいんデス」
ともう一度、誘う声がした。
セイは、無言のまま、またそっと薄く目を開けてみた。やっぱり変わることなく、石柱と薄い床がいくつも立ち並び、その多くが白く輝いていた。さらに強いめまいを感じて、思わず倒れそうになった。なんとか、踏みとどまろうとして遠くを見やると、ちょうど一本の石柱の床に当たっていた光が消えていくのが見えた。
「(これ以上は、いられない。いてはいけない)」
もう少しでも長くいたなら、思わず知らず、誘われるままに足を踏み出してしまいそうな気がしたし、あるいはその前につい足を滑らせてしまかもしれないと思ったのだ。
それで、再び目を閉じたまま後ろを振り向くと、一目散に走り出した。
「お待ちなさい!」
後ろの方で呼び戻す声がしたようだったが、かまわず走り続けた。もし一瞬でも走るのをやめて立ち止まってしまえば、もう前へは進めず、先ほどの場所へ戻ってしまいそうで、怖くなったのだ。
「さあ、戻って来るんデス!何も怖れることはないんだ!ただ、楽園が待っているだけなんデスから!」
さらに呼ぶ声が続いたが、セイはなんとかこれを振り切ろうと加速した。
どこをどう走ったのか、今となってはまったく覚えていない。たくさんの人々がベッドに横たわっていた、あの白くて大きい部屋を通り抜けたのかどうかも定かではなかった。何もかもが遠い出来事で、もはや何も思い出すことができなかった。ただ、床を踏む足の感覚は少しずつ感じられるようになった気がした。
やがて人の気配がしたような気がして、目を覚ますと、やはり白い壁と天井に囲まれた一室の中のベッドにいた。用心深くあたりを見回すと、ベッドは一つだけのようだった。
*
「ようやく目が覚めたのね?」
という女の人の声がした。セイの背中を冷たいものが一筋、流れるのがわかった。
「(また⁉︎)」
そう思って、無言のままでいたら、再び気持ちがすくんだ。それから、もう一度、
「ご気分はいかがですか?」
と尋ねられたのだった。以前と同じくやさしい口調だったが、今度は有無を言わせないような感じはしなかった。それで、こわごわ目を開けて声のする方を見ると、白衣を着た女の人が立っていた。セイはビクッとしたのだったが、彼女は目が合うと、にっこりと微笑みかけたのだった。
「ええ。なんだか不思議な気がします」
セイは、少し安心して、正直に答えた。
「もう何時間も、ずっと眠り込んでいましたからね」
無理もないと、慰めるように言うのだった。
「そうなんですか?」
「ええ。でも、もう大丈夫よ。少しずつ、元に戻りますから、安心していいですよ」
白衣の女の人はそう言うと、再びにっこりして、部屋を出て行った。
*
セイはそれからしばらくそのまま起きていたが、少しずつ自分の身体の重みや温もりの感触が戻ってきたような気がした。それで安堵したのか、やがてまた眠りに落ちたようだった。夢の中で、木を植えている修道僧のような黒衣を着た人を見たような気がした。それでセイは、自分もりんごの木を植えよう、もはや十分に成熟した果実を収穫することは望めないにしても、育て続けなければならないと思ったのだ(怠け癖を完全に払拭することも、たぶんできないだろうけれど)。
**
あとがき
今回は、以前に書いた夢で見たことを元に、少し「奇妙な味」になるようなものをと、試みました。手を替え品を替えて、極めて数少ない読者の関心を少しでも惹くことができれば、と思ってのことですが、さて首尾は?
それにしても、いつまで経っても相変わらず、即日設計風のままというのは、どうしたことか。たぶん、他のものに取り掛かって、一旦そちらに関心が移ってしまえば、今度はそのことばかりという風になってしまうようなのです。さしずめ今なら、〇〇発達障害とかなんとか、病名をつけられてしまいそうです(やれやれ)。
それで、もう掲載してしまおうと思います。
月例増刊夏休み特別号・1 FANTASY 14 「天空に浮かぶ石柱と床」
天空に浮かぶ石柱と床
*
その時、セイはビルの中の広い室内に横たわっていた。目が覚めたような気がしたので、薄く目をあけてみると、周りはすべて白一色の光景が目に入った。床も壁も天井もすべてが白い面に囲まれた中に、ベッドがたくさん並んでいた。ベッドもまた白いシーツと白いカバーに覆われて、その中にはたくさんの人々が横たわっているようだった。立っている人や歩き回るものは、誰もいない。そしてもちろん、誰一人として声を出すものもいなかった。まるで、セイ以外の全員が、じっと眠ったままのようだ。ただわずかに聞こえているのは、ミサ曲のような音楽だけだった。それも耳を澄ませると、ようやく聴こえるような、ごく小さな音だった。
音楽に聴き入るうちに、自然に目を閉じると、また眠り込んだようだった。いったいどのくらい経ったのか、再び薄く目を開けた時、ひとりの女性が立っているのが見えた。
その女性は澄んだ瞳で、セイをじっと見て、
「さあ、どうぞこっちへいらっしゃい」
と、やわらかな口調で声をかけたのだった。
「えっ?」
セイは、何がなんだかわからず、思わず訊いた。しかし、自分の声がまるで知らない人の声であるかのようだった。
「目を覚ましたばかりのあなたよ。さあ、起きて、こっちへいらっしゃいな」
女性は、もう一度やさしくいざなうのだった。
「ええ。はい」
抗うすべはないようだった。セイは、その目と声に吸い込まれるように自然と起き上がり、一歩を踏み出した。まるで、地に足がつかず、浮いているような、ふわふわとした感じがした。
「さあ、ついていらっしゃい」
今度は、もはやためらうことなくついてくることを確信したような口調だった。
「はい」
「こっちよ」
その人は、手で進むべき方向を指し示した。
「はい」
「さあ」
その声に誘われるまま、セイはついて行った。なんだか頭がぼんやりしたままだし、周りの様子もよくわからなかった。うんと長い階段を上って行ったような気がするが、相変わらず、全身が浮いたような感じのままだった。いったい、どのくらい上ったのだろうか。でも、不思議なことに、疲れた気はまったくしなかった。
「さあ、着いたわ」
女性が、言った。
「どうぞ、見てご覧なさい」
その声に促されるように、
「はい」
と答えたセイは、恐る恐る顔を上げて、目をあけた。
*
すると、どこまでも広がる青空に薄い雲がたなびく天空に石柱が何本も立ち並び、その上には間をあけて、1本ごとに小さくて平たい薄い石の板が載っている光景が眼前に広がっていたのだった。それぞれの床には明るい光が差して、白く輝いていた。ただ、どうしたことかそのうちのいくつかは、光が当たっていないところもあるようだった。光の当たっているところのところどころには、一枚の布でできたような白い奇妙な服を着た人が一人ずつ立っていた。そこには手すりも何もなく、ちょっとでも揺れたり、バランスを失ったりすると、たちまち真っ逆さまに落下してしまうのではないかと心配になったが、立っている人はまるで気にしていないかのようだった。
「さあ、こっちへいらっしゃい」
そのうちの一人が、声をかけた。ここまで案内してきた女性はいつの間にかいなくなっていて、他には誰も見あたらなかったので、声をかけられたのは、このセイのはずだった。
「えっ?」
驚いて、セイは思わず呟いた。
「さあ、どうぞ。早くこっちへ来るといい」
「……」
今度は、声が出なかった。細い石柱の上に乗った狭くて薄い石の床を見ると、足がすくむ思いがしたのだ。
「何も怖がることはないんだから」
やさしい声で、諭すような声が聞こえた。
「……」
返事をしなければいけないと思いながらも、言うべき言葉が見つからなかった。
「ただ、足を踏み出すだけでいいんだ」
いかにも簡単で、心配することは何もないというように、言うのだった。
「めまいがします」
他に言うべきことを知らず、ようやく正直に打ち明けた。
「高いところが苦手なのですか?」
「ええ。はい」
恥ずかしい気もしたが、改めて足元がふらつくようだったので、仕方なくうなづいた。
「じゃあ、目を閉じて想像すればいいんですよ」
それで万事解決とでもいうように、さらりとこともなげに言うのだった。
「何を?」
「雲の上の楽園ですよ」
「楽園?」
「ああ、楽園デス。何もむづかしいことじゃないでしょう?」
「……」
「そう、いつも光に満ちていて、穏やかで静かな場所です」
「……」
いろいろなことが頭をよぎったが、声は出なかった。
「ストレスも苦しみも何もないところですよ。たぶん、これまであなたが直面してきたようなことは、ここでは一切感じなくて良くなるんです」
「誰でもが……?」
ようやく、セイは小さな声で聞いた。
「……」
「そうじゃないんですね?」
そう呟くと、これまでのことが急に思い出された。必ずしも、順風満帆というわけではなかった。その一方で、人にも幸運にも恵まれた。ただ、そのことに甘えて、結局、好意や運を生かすことができなかった。何事に対しても、きちんと向き合い、真剣に取り組み続けることができなかったのだ。それに、胸を張って誇れるような人間になれたわけでもなかった。
つかの間、過去のことを振り返っていると、
「とにかく、こちらへ来ればいいんデス」
ともう一度、誘う声がした。
セイは、無言のまま、またそっと薄く目を開けてみた。やっぱり変わることなく、石柱と薄い床がいくつも立ち並び、その多くが白く輝いていた。さらに強いめまいを感じて、思わず倒れそうになった。なんとか、踏みとどまろうとして遠くを見やると、ちょうど一本の石柱の床に当たっていた光が消えていくのが見えた。
「(これ以上は、いられない。いてはいけない)」
もう少しでも長くいたなら、思わず知らず、誘われるままに足を踏み出してしまいそうな気がしたし、あるいはその前につい足を滑らせてしまかもしれないと思ったのだ。
それで、再び目を閉じたまま後ろを振り向くと、一目散に走り出した。
「お待ちなさい!」
後ろの方で呼び戻す声がしたようだったが、かまわず走り続けた。もし一瞬でも走るのをやめて立ち止まってしまえば、もう前へは進めず、先ほどの場所へ戻ってしまいそうで、怖くなったのだ。
「さあ、戻って来るんデス!何も怖れることはないんだ!ただ、楽園が待っているだけなんデスから!」
さらに呼ぶ声が続いたが、セイはなんとかこれを振り切ろうと加速した。
どこをどう走ったのか、今となってはまったく覚えていない。たくさんの人々がベッドに横たわっていた、あの白くて大きい部屋を通り抜けたのかどうかも定かではなかった。何もかもが遠い出来事で、もはや何も思い出すことができなかった。ただ、床を踏む足の感覚は少しずつ感じられるようになった気がした。
やがて人の気配がしたような気がして、目を覚ますと、やはり白い壁と天井に囲まれた一室の中のベッドにいた。用心深くあたりを見回すと、ベッドは一つだけのようだった。
*
「ようやく目が覚めたのね?」
という女の人の声がした。セイの背中を冷たいものが一筋、流れるのがわかった。
「(また⁉︎)」
そう思って、無言のままでいたら、再び気持ちがすくんだ。それから、もう一度、
「ご気分はいかがですか?」
と尋ねられたのだった。以前と同じくやさしい口調だったが、今度は有無を言わせないような感じはしなかった。それで、こわごわ目を開けて声のする方を見ると、白衣を着た女の人が立っていた。セイはビクッとしたのだったが、彼女は目が合うと、にっこりと微笑みかけたのだった。
「ええ。なんだか不思議な気がします」
セイは、少し安心して、正直に答えた。
「もう何時間も、ずっと眠り込んでいましたからね」
無理もないと、慰めるように言うのだった。
「そうなんですか?」
「ええ。でも、もう大丈夫よ。少しずつ、元に戻りますから、安心していいですよ」
白衣の女の人はそう言うと、再びにっこりして、部屋を出て行った。
*
セイはそれからしばらくそのまま起きていたが、少しずつ自分の身体の重みや温もりの感触が戻ってきたような気がした。それで安堵したのか、やがてまた眠りに落ちたようだった。夢の中で、木を植えている修道僧のような黒衣を着た人を見たような気がした。それでセイは、自分もりんごの木を植えよう、もはや十分に成熟した果実を収穫することは望めないにしても、育て続けなければならないと思ったのだ(怠け癖を完全に払拭することも、たぶんできないだろうけれど)。
**
あとがき
今回は、以前に書いた夢で見たことを元に、少し「奇妙な味」になるようなものをと、試みました。手を替え品を替えて、極めて数少ない読者の関心を少しでも惹くことができれば、と思ってのことですが、さて首尾は?
それにしても、いつまで経っても相変わらず、即日設計風のままというのは、どうしたことか。たぶん、他のものに取り掛かって、一旦そちらに関心が移ってしまえば、今度はそのことばかりという風になってしまうようなのです。さしずめ今なら、〇〇発達障害とかなんとか、病名をつけられてしまいそうです(やれやれ)。
それで、もう掲載してしまおうと思います。
月例増刊号 FANTASY 13 「ひとりだけのエクソダス 光3部作完結編」
ひとりだけのエクソダス
まえがき
もう6月も今日で終わり。ということは、1年の半分が終わってしまったということだ。なんと早いことか。驚くばかりですが、だからと言って、これといった何かをしたわけじゃない。こうした自分にも改めて驚くのですが、これは呆れると言わなければないけませんね。
呆れているばかりでも仕方がないので、月例増刊号のファンタジーを掲載します。一応、これで完結です。楽しんでくれる人がいるといいのですが。
ひとりだけのエクソダス
きみたちも また
寂しい夜を耐えただろうか
今宵借りもののラジオから流れてくる
東京放送もうねっている
----『新鮮な日々』の一節
*
その夜は、いつものバーの、いつもの席に座っていた。
「いよいよだね」
僕は切り出した。
「ええ」
Iが答える。
「寂しくなるな」
正直に言う。
「そうね」
「ああ」
「でも、いろいろな経験をすることができました。ありがとう」
「こちらこそ。おかげで、楽しかったよ」
「祖父の故郷での、あっという間の一年でした」
「ああ、早いよねえ。でもね、脅かすようで悪いけど、年取るともっと早くなるよ」
また、余計なことを言った(悪い癖だ)。
「そうかしら?」
不思議そうに言う。それも無理からぬことだ。まだ若くて、無限の可能性を信じられる頃なのだ。
「ああ、そうとも。人生は短いから、『やりたい事やんなさい。後で後悔しなさんな。やりたい事やんなさい。グラスのふちに唇つけたらとことん、一滴残らず飲み干しなさい。後で戻ってきても、もう雫は残っていない。今のうちに飲みつくしなさい』と言った日本の作家がいるよ」
「へえ。誰ですか?」
「開高健。博識で、釣りやグルメ紀行でも有名だけれど早くに亡くなってしまった。この言葉の元は、オーストリアの医師で劇作家のもののようだけどね。アルトゥール・シュニッツラー、いくつか、有名な映画の原作もある」
「そうなんですね。覚えておきます」
「うん。多才な人がたくさんいるんだね」
「ええ」
「……」
「ところで、どうしてこんなに親切にしてくれたのかしら?」
彼女が不思議そうに訊いた。
「バンクーバーが懐かしかったしね」
僕は笑い話にするつもりで答えた。
「えっ⁉︎」
「K もいなくなった……」
また、余計なことを言ってしまった。
「はい」
「実はね、うんとむかしに、僕がそんなふうにしてもらったことがあったんだよ」
こうなったら、本当のことを話して雰囲気を変えるしかない、と思い定めて言った。
「そうなの?」
「ああ」
僕は、うんと昔のフランクフルトの夜のことを思い出したのだった。思えば、なんとも珍しくて、しかも本当に素敵な体験だった。
初めてのドイツ。バウハウスを巡る旅だった。
「バウハウスは知っているよね?」
「ええ」
「ずっとバウハウスを巡ろうと思っていて、それがようやく実現したんだ」
「ワイマール、デッサウ、そしてベルリンね」
「ああ。よく知っているね」
「いちおう、デザインの勉強もしましたから」
「そうなんだ」
「はい」
「それで、とくに行きたかったのはデッサウだよ。ヴァルター・グロピウス、2代目の校長でもだった彼が設計した校舎がある。グロピウスは、20世紀の建築家の4大巨匠の一人でもあるよ。ま、後の3人と比べると、忘れられがちだけどね。バウハウスを象徴するアイコン、と言っていいと思う。これを見た時は、とても感動したことを今でも覚えているよ」
「へえ」
「君も知っているように、バウハウスは世界中のデザインを教える学校のモデルとなった。僕が通った学校もそのひとつだった」
まだ出来たての学校で、若い教員たちを中心に、バウハウスと同じように理想と希望に溢れていた。
「そうなんですね」
「それから、その後でフランクフルトへ行ったんだよ。短い滞在だったけれど、見たかった美術館がいくつかあったからね」
「ええ」
「フランクフルトに着いた時はもう遅かったし、地元らしい食事を楽しみたかったけれど、食べる所の手配までは気が回っていなかった(たいてい、こうしたものだ)。そこで、ホテルのフロントで訊いて、フランクフルトらしいレストランを教えてもらって、出かけたんだよ」
「はい」
「店は、さほど苦労することもなく見つかったよ。特に気取った様子もなかったので、安心したんだ。ドアを開け、中に入ると、満員であることがすぐにわかった。テーブルは全て埋まっていて、入り込む余地はなかった。それで、ちょっと呆然として立ち尽くしたんだ」
「あら、大変だわ」
Iが言った。僕は、改めてその時の場面を、つい昨日のことのように思い出したのだった。不意に、込み上げるものがあった。
その時、しばらく呆然とする外国人の僕を見て、
「どうしたんだい?」
声をかけてくれた人がいたのだった。
「フランクフルトらしい食事をしたいと思ったんですが……、遅かったようです……」
「そうなんだ。じゃあここに座ればいい」
それぞれ、黄色と黒のセーターを着た夫婦らしい中年のカップルが言ってくれたのだった。2人ともが、なんとなく抱いていたドイツの中年のイメージとは異なって、痩身だった(だから、はじめは愛想がいいという感じはしなかった)。
「ありがとうございます。でも、いいんですか?お邪魔じゃありませんか?」
僕は、思いがけない親切に驚いた。
「もちろん。いいからおかけなさい」
にっこり笑って、空いた席を示してくれた。
「ありがとうございます」
「ところで、どこから来たんだい?」
「オックスフォードからなんです。しばらく滞在しているんですが、元は日本から」
「そうなのかい。ようこそ、フランクフルトへ」
そして、食べるべきフランクフルトの名物料理も勧めてくれた。もちろん、陶製の器に入った、あのお酒も。
「まずは、リンゴ酒、アプフェルヴァインから。お酒が飲めるならね」
夫のハンスが笑いながら言う。口ひげにはもう、白いものが混じっていた。
「はい」
「それから、リップヒェンね。塩漬けにした豚肉を茹でたものに、ザワークラウトを添えた料理よ」
すかさず今度は、妻のブリギッテが教えてくれた。ハンスはこの近くで貿易会社を経営していて、彼らはこれを食べるために久しぶりにこの店に来たということだった。
「それで、僕は無事にフランクフルト名物の料理を楽しむことができた」
「よかったわ。親切な人がいて、幸運だったのね」
Iも驚いて、そして安心したように言った。
「うん。でもそれだけじゃなかったんだ」
「何があったの?」
心配そうに訊いた。
「ハンスとブリギッテに翌日のことを話すと、彼が言ったんだよ。『じゃあ下見をしておかなくちゃね』って」
「えっ?なんですって?」
心底、驚いたようだった。
「時間がないなら、効率よく回らなくてはいけないからね、と言うんだ」
「そうなの?」
それで、
「ええ。でも、もう時間がないんです、と答えると、『じゃあこれから行こう』と言って、僕を外に連れ出したんだ」
「それで?」
「外には黒い大きなベンツが停まっていた」
「それで、どうなったの?」
「そして、案内してくれた。フランクフルトで見るべきところを。それから、ホテルまで送り届けてくれたんだ」
「ワオ!アンビリーバブル!すごいわ」
「ああ。今から思うと、ちょっと無防備だったような気もするけどね」
「ええ!」
「そんなことがあったからね」
「へえ。信じられないくらい親切な人がいたのね」
「ああ。確かに、そういうことがあった。それで、自分もできることをしようと思ったんだよ」
「じゃあ、私もハンスとブリギッテに感謝しなくちゃあね」
「うん、そうかもね」
それから、ハンスとブリギッテとはメールをしたり、クリスマスにはプレゼントを交換したりしていたのだけれど、ハンスが突然亡くなってからは、次第に疎遠になった。ブリギッテは英語が不得意で、ハンスにもう少し英語を勉強したほうがいいねと言われていたそうだ。そういえば、僕も同じことを言われたことを思い出した。
「オックスフォードにいるにしちゃね」
思えば、僕はそれだけじゃなく、その時々で、ずいぶん親切にしてくれた人たちがいたのだ。
「僕は、恵まれていたんだね。ハンスとブリギッテの他にもいたからね」
「へえ」
「だから、自分にもできることをって、思ったんだよ」
「ええ」
*
Iが帰国してからは、また元の生活に戻った。ちょっと味気ない毎日だ。例のバーにも、あんまり行かなくなった。時々、K やIのことを思い出す。Iからは、今でもたまにメールが届く。仕事も順調のようだし、おばあさんともいつでも話せるようになったということだった。めでたいことだ。メールがもう少し多く届くようになればいいと思うけれど、たぶん忙しいのに違いないから、それもなかなかむづかしい。今は慣れ親しんだところで暮らし、何より親しい人に囲まれているのだから、それも仕方がないことだ。そうして、異国でのことも、懐かしさを残しつつ、次第に忘れていくのかもしれない、と考えたりすることもある。
それで、思うことがあって、久しぶりにバーに出かけてみることにした。開店時刻に合わせて少し早めに出て、ジャケットを着てネクタイを締めて行くことにした。
そのバーは、決して都会的でもないし、しゃれているわけじゃない、それどころか質素と言う方がいいくらいだけれど、負けず劣らず凛とした空気が漂っている(少なくとも、開けたての時は)。
少し早くついたが、店内は明るかったし、ドアを押してみるとすんなり開いた。で、中に入ると、予想通り客はまだ誰もいない。開けたての清潔な空気は損なわれていない。
「こんにちは」
「やあ。いらっしゃい。ずいぶん久しぶりですね」
「ああ。ちょっとね」
いつもと同じ、特に変わったところもない挨拶だ。
でも、なんとなくいつもと雰囲気が違っていた。流れていた音楽のせいだ。
「おや、レゲエだね。珍しいね。ジミー・クリフ」
「ええ。ちょっと元気が出るような曲にしようと思って。お客はいないし、外はまだ明るいようだから。景気付けに、ね」
「たしかにね」
「ジャズの方が良ければ、変えますよ。でも、嫌いじゃないでしょ?」
「ああ、もちろん」
それどころか、……。この歳になって、来し方を振り返ることがある。たいてい恥ずかしくなるようなことばかりだ。でも、この曲を聴くと、そんな自分がさらに恥ずかしくて情けなくなって、前を向かなくては、という気になるのだ。
「そういえば、Iさんはどうしているんでしょうね?」
店主が言った。
「ああ、元気にやっているようだよ」
僕が答えた。
「なら、良かった」
安心したように言う。
「うん」
「でも、さびしいですね」
「ああ」
「あの娘がドアを開けて入ってくると、とたんに雰囲気がパッと明るくなりましたものね」
「うん」
「華やかな雰囲気がありました」
「そうだね」
「日本語は流暢だったけれど、なんだか日本人離れしていましたね」
「4分の1ほど、フランス人らしいよ」
「ああ、そうなんですね。なるほどね」
「父親の母親がフランス系ということだった。だから、家では、英語の他にフランス語や日本語で話す時もあった、と言ってた」
「へえ、やっぱりね」
「そのおばあさんともようやく話せるようになって、喜んでいるみたいだ」
「日本に居た時は、なかなか話せなかったようだけど。何しろ、僕よりも年上のおばあさんだから、コンピュータやスマートフォンは得意じゃないらしい」
「ええ」
そんな話をしているうちに、『ハーダー・ゼイ・カム』はすぐに終わった。
「ついでに、ボブ・マーリーはどうでしょう?」
そういって、レコード盤を取り出した。
「おっ、今日はレコードなんだね?CDじゃなくて?」
「ええ」
「『エクソダス』」
「ええ」
「いいね」
「元気が出そうでしょう?」
「うん」
「明るい歌詞というわけじゃないんですけどね」
「そうだね。こうやって聴いていると、僕なんかはジャズよりもロックやポップスの方が相性がいいみたいだ」
「そうなんですか?」
「大雑把に言えば、ロックは直接的だし、それに対してジャズはある種知的な操作が加わって、内省的なところがあるような気がするんだけどね。例外もあるだろうけれど」
「うーむ。確かにね。でも、ジャズでも、このところまたビバップが戻ってきているようですよ」
と、教えてくれた。こういうことを教えてくれる人がいるのはありがたい。偏狭さから逃れることができるはずだから。
そんな話をしていたら、タイトル曲の『エクソダス』がかかった。その時ふいに、思ったのだ。
(「旅に出よう」)
そうだ、そうしよう、そうするのだ。いやそうしなければいけない。
で、言った。
「そろそろ退散するよ。ごちそうさま。どうもありがとう」
「えっ、もうですか?」
店主が言った。
「ああ、誰かと会う前にね、帰るのが良さそうだ。ちょうどいい潮時だよ。ありがとう」
「あ、はい。また、よろしくお願いします。ありがとうございました」
「それじゃ、また」
僕は、外に出た。街には、まだ夕日の残照が残っている頃だった。
その夜、僕は、不思議なあかるさのあるフォレのレクイエムを聞きながら、トランクに荷物を詰めた。
*
その時に、うんと昔に作った詩を思い出した。もう何十年も前のものだ。それが手元に残っていた。その時のように、前を向くなければいけない。
『ぼくたちがながい夜を旅するとき』。
それは、ちょっと長い、というかそうとうに長い。渡辺武信や泉谷明に憧れていた頃のものだ。たぶん、直接的な影響を受けているだろうと思う。たしかに若かった、少なくとも今よりは。
引用してみることにしよう。ちょっと長いし、おまけにこの話には関係ない部分が多いけれど、誰かが文句を言ってくる心配は皆無なのだ(ま、「ぎゃっ」と叫ぶかもしれないけれど)。1行さえあればいいと思ったりもするけれど、この際、全部を載せても問題はない。日の目をみる可能性を与えることにしよう。
*
ぼくたちがながい夜を旅するとき
1
膨らみ過ぎた都会の幻影が あらゆる記憶を捨ててぼくたちを襲い
ぽっかりと口を開けた闇の切り口から いくつもの夜があらわれてくる
かすかに光りを放ちながら溶け出る鉛の渦が
音もなく拡がりつづけている
次々にめぐってくる夜にやさしく罠をしかけるのは
きみの唇だ やわらかなきみの髪だ
複雑にからみあい もつれあった夜々は
きみのしたによってほどかれて
新しい夢を編み込んだ一枚の毛布となって
ぼくたちを包み込む
が しかし
まぶたを閉じるならば
都市の重たい鼓動が
ほのぐらい血管を逆流する
2
ぼくたちは まず
小さな部屋で ささやかな宴を張ること
から 始めよう
もういちど
都市を
ぼくたちの手の中に
獲り戻すために
明るい電灯の下でかかげられたワイングラスの中で
光りをはね返し
ゆらゆらと ゆらめいているぼくたちの海
で キッド船長のように
勇ましく
宝捜しをつづけることができるだろうか
いつまで
帰っていく場所のない ぼくたち
は いったい
何処へいけばいいのか
いつも
問いは
遠い彼方に消える
3
テレビを消し 灯を消し
すべてを消してみても
決して消しきれない
ぼくたちの記憶
いつでも 闇は
不安のかたちをすることを やめない
しかし
闇の中で眼を開け
おたがいの眼差しの中に宿ったひとすじの光り
のうちに
輝く海を見つけ出せ
4
悪い時代なのかもしれない
けれど
もはや誰も止めるな
ぼくはどこまでも行くのだ
暮れていく街
暮れていく海
暮れていくやつはみんな勝手に暮れていけ
そんな感傷は 激しい波にくれてやる
やぶれかけた帆船は完全に沈めてしまい
虹のしぶきの光る海へ行くのだ
激しく夢見ること
それだけが 僕たちの持ちうる武器だ
脆弱なやさしさよりは
くるしい暴力を!
激しく夢見ることで
悲しみを断ち切れ!
*
それから、ドアを開けて外に出ると、鍵を閉めた。頭の中には、あの「エクソダス」が鳴っていた。もはや、アパートの1室で宴を張ることはないけれど、光る海を求めて行くことにするのだ。今なお、どこかにあるかもしれない「海」を見に。
**
あとがき
ちょっと気取ってつけてみた『光3部作』は、一応これでおしまいです。
思いがけず、もう少しで半世紀も前になろうかという時に作った詩(?)も載せることになった。まだ若い頃に読み返したときは「きゃー」と言って、すぐに放り出したい気になった。しかし、歳をとってから恐る恐る読んでみたら(やっぱり愛着はあるのだ)、案外悪くない気がした。というか、かつての自分が愛おしいような気持ちになるのだ。でも、これは、全然成長していないし、成熟とは縁遠いままだということですね。(うーむ)。
ちょっと長くて余計なところもあるけれど。長い間ほとんど人の目に触れなかったのだから、日の目を見せてやる、というのも悪くない(?)。
冒頭の1節も同様。
「私の耳は貝の殻 海の響きをなつかしむ」というところだろうか(うーむ)。やっぱり、歳のせい?
おまけに、ほぼひと月ほども手を入れること怠っていたために、またもや見切り発車でした(やれやれ)。
読んでくれて、どうもありがとう。
2024.06.30
月例増刊号 FANTASY 12 「緑の葉を抜ける光 光3部作第2弾」
緑の葉を抜ける光
*
Kがいなくなってしまってからは、ずっと心にぽっかりと穴が空いたようだった。なんだか自分一人だけで、砂漠かジャングルのようなところに取り残されたような気分になったのだ。
別にそれほど頻繁に会っていたというわけじゃないし、とくに最近は年に数回くらいしか会うことがなくなっていた。だから、物理的にはそんなに変わったというわけじゃない。しかも、最後の方のKの様子は明らかに変だった。自己否定や自己憐憫が端々に現れて、ちょっと辛い時もあった。
それなのに、彼が僕の前から消えると、二度と手に入れることができないものを失ったような気がしていたのだ。もしかしたら彼が、僕自身の中にあるそうした部分を代替してくれていたのかもしれない。だからたぶん、自分はそうしたことからしばらく遠ざかることができていたのでは、と思ったりすることもある……。
でも、もしかしたら、いくらかでもその穴を埋めることができるかもしれない。今は、そんな気がしている。少なくとも、しばらくの間はあかるい気分になることができる。まあ、もしかしたらまた……、という不安がないわけじゃないけれど。でも、先のことを案じてばかりいるのもつまらない。
*
ある晴れた日曜日、気分転換のためにいつもとは少し違う道を試してみようとした散歩の途中で、思いのほか歩く距離が長くなって、道沿いにあった小さな公園のベンチで、ぼんやりと空を眺めていた。いかにも春らしい柔らかな青空に一つだけぽっかりと浮かんだ雲が、ゆっくりと形を変えながら流れていくのだ。その時、足元につまづきかけた人がいた。
「Oh, very sorry !」
外国人の女性のようだった。
「OK. That’s my fault. 大丈夫?僕が足を伸ばしていたのが悪かった。ごめんなさい」
咄嗟に言って、顔を上げた。と、
「Oh. こんにちは! 覚えていますか?」
その人は、そう言ったのだ。
驚いて、もう一度よく見てみると、ひと月ほど前に、海辺の鄙びたバーで偶然隣り合わせた日系カナダ人女性のIだった。その彼女と、ばったり出くわしたのだった。
「もちろん ! どうしたの?」
「道に迷ったようなんです。それで、ちょっとぼんやりしてしまって……」
視線をそらして、恥ずかしそうに言った。
「ふーん。でも、また会えてよかった」
ぼくは、驚いたけれど、なんだかとても幸運なような気がした。率直にいえば、再会したことが嬉しかったのだ。
「私も!あなたは、今日は何を?」
彼女が訊いた。
「散歩の途中だよ。退屈しのぎにやっている。で、君は?」
僕はそう答えて、訊き返した。
「町の探検、かな。ふつうは自転車なんですが、今日は、ゆっくり歩いてみようと思って。でも、道に迷いました」
「そうなんだね。あれから、どうしてた?日本での生活にはもう、慣れたのかな?」
「まあ、少しずつ……。なかなか、簡単じゃありませんね」
「ああ、確かにね」
言葉も思うようには通じず、文化も習慣も何もかも異なる国で暮らす、というのは簡単じゃない。
「実は、あの後で、あのバーにも何回か行ったんです」
と、Iが言った。予想もしなかったことだった。
「へえ」
「でも、会えませんでした」
「ああ。それは、悪いことをしたね。実は、僕もしばらく行っていないんだよ……」
「そうなんですね」
「ああ、いろいろあってね。ところで、君はいま、すごく急いでいるの?」
「いいえ」
「じゃあ、よかったら桜を見に行ってみないか?」
あんまり期待しないで、訊いてみた。期待しすぎるのは、問題だ。そうした時の答えは、だいたい想像がつくのだ。
すると、Iの顔がパッと輝いた、ような気がした。 そして、
「ええ、ぜひ。私も、とても見たかったんです」
と言ったのだった。
ぼくは、ちょっと驚いたけれど、それで、近くでまだ満開の桜が見ることができて、しかもあんまり人の多くなそうな場所へ行くことにした。一つだけ、よく知っている場所があったのだ。それほど遠くじゃない。歩いて行けるところだ。それで、海沿いの道をゆっくり歩いて行くことにした。
「ホームシックにはならない?」
歩きながら、訊いた。
「少しだけ、かな。いつもは忙しいから、あんまりそういうことはないけど、お休みの日はちょっと寂しいです」
この時ばかりは、まさに異国でゆきくれた人のように、沈んだ声で答えた。
「ああ。そうだね。誰だって、寂しくなる」
僕も相槌を打つ。
「ええ、そうですね。ありがとう」
「この辺りは海といっても、グランヴィルの景色とはずいぶん違うものね」
「ええ。でも、あんがい好きです」
彼女が言ったのだった。
「へえ。どうして?」
「まず、海。海には変わりがありません。そして、素朴な気がします」
「ああ。なるほど。確かにね」
「そう……。でも時々、おばあさんが恋しいです。父と母はメールやチャットで話せるけれど、まだおばあさんとは、話せていない」
今度は、ほんとうに寂しそうで、まるでおばあさんに甘える年頃の少女のようだった。
「ああ、そうなんだね」
「ええ。でも、もうすぐ話せそうです」
また、元のあかるい口調に戻った。
「それはよかった。きっと、おばあさんも喜ぶね」
「はい。とっても、楽しみにしてるんです」
彼女が言い、僕もなんだかすっかり安心した気分だった。
しばらくすると、桜の咲いている場所に着いた。ここは、久しぶりだ。小さな公園だけれど、それでも桜の木は何本もあって、じゅうぶんに見応えがある。
「さあ、着いた。桜を見るのは、ここだ」
そう言いながら、ちょっとばかり複雑な気分になった。ずっと前に、Kたちとここで花見をしたことがあったのだ。
「おお。なんて綺麗なんでしょう」
Iが声をあげた。まだ、満開の時を過ぎてはいなかったのだ。
「気に入ってくれたようだね。よかった」
僕は、ホッとして言った。
「ええ、とっても。ありがとう。ああ、これが、日本の桜なのね⁉︎」
ずっとこの時を待っていた、というかのようだ。
「そう、でも、バンクーバーにも桜はあるんだよね?」
僕は、少し訝りながら訊いた。
「ええ。スタンレーパークとか、街のあちらこちらに。日本からの贈り物です」
「ああ、そうだった。確か、最初は横浜や神戸からだったんだよね?」
「ええ、そうです」
「それでも、日本の桜は格別?」
「ええ。やっぱり、元々の場所で見る方が、ずっと素敵」
「ということは、これも地産地消、かな?」
僕は、Iと初めて出会った海辺のバーでのやり取りを思い出しながら言った。
「そうですね」
Iが笑った。
「日本ではね、お花見といって、家族や友人たちと集まって、食事やお酒と一緒に、桜を楽しむ習慣があるんだよ」
僕が説明した。と、彼女は、
「へえ。私も、ぜひやってみたいわ」
と言ったのだ。
「でも、桜の季節は短いからね。もうすぐ終わる」
「そうですね」
「残念だけどね」
「ええ。ほんとうに残念。来年か、再来年か。また今度ですね」
「ああ。帰国しても、またいつか来ればいい」
「はい。そうですね。ぜひ、そうしたいわ。でも、今はこの桜を楽しむことにしましょう」
と、Iが言った。たしかにそうなのだ。明日のことよりも今日、今この時を大事にしなければならない時があるのだ。
「ああ。そうしよう」
それからしばらくの間、黙ったまま、桜を眺めていた。時々口にした言葉といえば、「綺麗だね」、「はい」、「とても美しいわ」、「いいねえ」、「ええ」、「ほんとにね」、くらい。
「実はね、この隣が、Kが働いていた場所だよ」
思わず、口をついて出たのだった。
「はい。そうなんですね。彼は元気?」
「いや、それがね……」
言わないでおいたほうがよかった、という思いがよぎった。でも、もう遅い。一度口を飛び出た言葉は、もう飲み込めないのだ。
「何かあったんですか?」
彼女が訊いた。
「ああ。いなくなってしまった……」
と、答えるしかなかった。
「えっ。どうしたんですか?」
「消えてしまったんだよ」
「消えた?なぜ?どこに?」
心配そうに訊く。
「それがわからない」
もどかしかった。
「はい……」
「連絡も取れないし、目の前からいなくなってしまったんだよ」
「どうして?」
「……」
何も言うことがなかった。
それで、しばらくの間、沈黙が続いた。
「君さえよければ、そのうちに、ゆっくり話せるような時があったら話すことにしよう」
僕が言った。話題を変えたかったのだ。
「ええ。そうしましょう。もし、迷惑じゃないのなら」
彼女が応じた。
「とんでもない。君の方こそ?」
「助かります!」
すっかり元の姿に戻ったようだったのが、救いのように思えた。
「それはよかった。もともと暇だしね。それに、近くに友達もいない。Kも消えてしまったのでね……」
また、言ってしまった。
「ええ。残念ね」
「ああ」
それから、また咲き誇る桜を眺めた。今度は無言のままだった。
しばらくの間、眺めていたその後で、メールアドレスを交換し、近いうちにまた会うことを約束して別れた。
帰りながら、Iとまた会えたことは嬉しかったが、K のことを思い出すと、また辛くなった。
*
それから何日か過ぎた頃、僕は久しぶりにバーのカウンターの前に座っていた。まだ、お客は誰もいない。バーは、開けたての凜とした空気に満ちていた。この雰囲気が好きなのだ。背筋が伸びるような気がする。それは、鄙びたバーでも変わらない。いつでも、どこでも変わるところがない。
あの日と同じ壁から3つ目の席に陣取って、壁側の席には荷物を置いた。今日は、ここを空けておかなければならない。カウンターの向こうの店主兼バーテンダーに小さく声をかけて、スコッチに少しだけ水を足したものを頼んだ。
「お久しぶりです」
「ああ。いろいろあってね。来れなかった」
「ええ。今日は、ハイボールじゃないんですね?」
「うん。ちょっとね」
「このスコッチの飲み方は、Kさんでしたよね?」
「そうだね」
「そういえば、このところKさんも見ませんけど?」
彼が言った。はっきりと訊くわけではないが、明らかに知りたがっているようだ。
「ああ。それなんだよ……」
ちょっと困ったけれど、仕方がない。
「はい?」
「いなくなっちまった」
「えっ?」
「姿を消してしまったんだよ」
「へえ。何かあったんですか?」
「それが、さっぱりわからない」
また、同じようなことを繰り返さなければならなかった。
ちょうどその時、バーのドアが開く音がして、Iが入って来るのが見えた。今日は、白いTシャツの上に薄手のジャケットを羽織って、下はやっぱり細い黒のジーンズだ。
「やあ、いらっしゃい」
「こんばんは」
挨拶を交わしながら、奥の席の方にやってきた。
「こんばんは」
Iが、あかるい声で言った。
「やあ、こんばんは」
「お待たせしました?」
「僕も、ほんの少し前に来たばかりだよ」
「そう。よかった」
「元気にしてたかい?」
あの桜の日からさほど日は経っていないにのに、僕はホッとして言った。
「はい。あなたは?」
彼女も訊く。
「よかった。僕は、まあまあってとこだね」
「まあ。この間はありがとう。あなたのおかげでとってもいい経験ができました」
「どういたしまして」
僕が言うと、彼女は隣に座って、小さな鞄を壁際の椅子の上に置いた。今日は、うるさい若者もいないし、まだ早いせいで常連の老人たちもいなかった。
「あら。今日はクラシックがかかっているのね」
Iが気づいて、言った。
「ああ、小澤征爾が亡くなったようなんだ」
「ええ。残念ね」
「ああ。小澤は知ってる?」
「ええ、まあ。セイジ・オザワはトロント響の専任だったことがあるから……。名前は小さい頃からよく聞かされていたわ」
「ああ、そうだった。海外で活躍する日本人指揮者の草分けだった」
「そう。それに、バンクーバー響にはカズヨシ・アキヤマがいたのよ」
「へえ。そうなんだ」
「今は、世界中のどこでも日本人指揮者が活躍しているますね」
「そうだね。ところで、君はクラシック音楽が好きなのかい?」
「ええ。クラシックだけ、というわけじゃありませんけど」
「そうなんだ」
「家では家族が皆、楽器を弾いて、それでよく合奏していたんです」
「へえ、いいね。うらやましいな。それで、君は何を弾く?」
「ヴァイオリンを少々、ね」
「ふーん」
「あなたは?」
「残念ながら、聴くだけだね。まだ小さかった頃、家にはピアノがあったけれど、弾けるようにはならなかった」
「それは、残念」
「うん。今でも、後悔している」
「どうして?」
「やっぱり、自分で弾かないで、音楽を楽しむと言ってもね。なんだかね」
「そうなんですか。でも、どうして?」
「怠け者なんだね。それにね……」
「何?」
「きっと、何に対しても中途半端な性格のようなんだね」
そう言いながら、まるでKのようだと思った。彼がいなくなってから、なんだか急に似てきたようだ。でも、余計なことを言うのは、いいことじゃない。
「そう?」
「それで、君はどういったものを弾くのが好きなんだい?」
話題を変えようとして、訊いた。
「やっぱり、バッハかしら……、ね」
ちょっと考えてから、言った。
「やっぱりね。バッハはいいよね。特別だ。Kも好きだった。フランクも気に入っていたようだった……」
「あら。わたしもフランクのソナタは好きよ。あなたは?」
「フランクのものは、いくつかCDを持っているよ。昔は、バッハやモーツァルトが好きだった。でも、今はあんあまり高尚じゃないものが好きなようだという気がしている」
僕の喋りたがりは、治らないようだ。
「コショー?ペッパー?」
「いや、コウショウ。あんまりハイブロウなものより、もう少し柔らかいものが好きなようなんだ」
「なるほど。たとえば?」
「バッハよりもヘンデル。モーツァルトよりもシューベルトやブラームスと言えば、わかるかな?」
「うーん。はい、なんとなくだけど。でも、わたしもヘンデルは好き。合奏協奏曲は、家族と一緒に弾いたことがある」
「指揮者になる前のブリュッヘンの弾く『木管のためのソナタ全集』もいいよ。休日の朝にぴったり、と思うけどね」
「へえ。聴いたことがないな」
「じゃあ、今度貸してあげよう。気に入るかもしれない」
「楽しみだわ。ぜひ、お願いします」
そう彼女が言ったのが、嬉しい気がした。
僕はこれまでずっと、バッハとモーツァルトが一番好き、と思っていた。もちろん、それは今でもそうだけれど、もしかしたらバッハよりもヘンデル、モーツァルトよりシューベルトが好きなのかもしれないと思うようになったのだ。それに、シューマンもブラームスも、メンデルスゾーンも。バッハと同時代のヘンデルは別にして、皆ロマン派と呼ばれる人たちだ。ヘンデルも、構成の緻密さというよりも、愉悦感や寂寥感といった感覚の方が優っているような気もする。バッハやモーツァルトにも愉悦感に満たされたものはたくさんあるけれど、それらの奥にはもっと別のもの、哀しみや厳しいものが隠されているような気がするのだ。それが、ちょっときついように感じる時があるのだ。
思えばこれは、自分の性向をよく示している気がする。構成や精神性といったものよりも叙情(というか、もしかしたら情緒というべきか)、全体よりも部分のほうを気に入るのだ。なぜなのか、わからないけれど、ちょっと残念な気がしないでもない。それは、全体を把握する力や仕組みを理解する力が不足しているということなのかもしれない。いや、それもあるには違いないけれど、構造や構成よりも感覚的で情緒的なのが第一なのだ。それは、クラシック音楽だけじゃなく、ポップスやロック、そしてジャズでも変わらない。確かに、考える力は不足しているのかもしれないと思う。ポップスやロック、それにジャズの時でも変わらない。
「で、クラシック以外は?聴かない?」
「もちろんちがうわ。当然、ポップスやロックも聴く」
当たり前でしょ、というように言った。
「あ、そういえば、ニール・ヤング、ザ・バンド、それにラッシュのようなちょっと知的な歌詞と難解で複雑なプログレなど。カナダ出身のロックスターはたくさんいるね。それに、ジョニ・ミッチェルも忘れてはいけない」
「ええ。でも、残念ながらそのいずれもが、おばあさんの時代のアイコンね」
彼女が笑いながら、言った。
「うーん。そうか。新しいものは知らないんだ」
改めて自分の年を思い知らされた気になったけれど、実際そうなののだからしかたがない。
「私も、日本のグループのことはよく知らないし、正直に言うと、カナダのグループもそうなの」
と彼女が言った。慰めようとしてくれていたのかもしれない。
「そうなんだ。じゃあ、なにを聴いていた?」
「ジョニ・ミッチェルは好きよ。でも、ちょっと恥ずかしいけれど……、まだ幼かった頃は、ガールズバンドや女性のスターをよく聴いていた。主にアメリカね、ちょっと古いもの。例えば、ジョーン・ジェット、シンディ・ローパーなどね。懐かしいわ」
彼女は、ちょっと微笑んで、遠くを見るように顔を上げて言った。少女時代を思い出したのかもしれない。でも、たいして昔じゃない。僕なんかに言わせれば、ほんの少し前っていうところだ。それでも懐かしいのだろう。
「へえ、なるほどね。でも、それもおばあさん、とは言わないけれど、お母さんくらいのものじゃないか?」
今度は、僕が訊いた。
「ええ。そうね。大学に入った頃からは、もうほとんど聴かなくなったけど」
「ふーん。そうなんだね。でも、なんとなくわかるような気がする。でも、黒づくめのファッションは?」
「ああ、あれね。初めてここに来た時に、着ていたもののことね?」
「そうそう。てっきり、ハード・ロッカーかと思った、それもヘビーメタル系の」
「ふだんはあんまり、あんな格好はしないけど。きっと、それは祖母の影響ね」
「えっ?ところで、おばあさんとはもう話せたかい?」
「いいえ。まだなの。父がちょっと忙しいようなの。でも、もうすぐね」
「それはよかった」
「彼女は若い頃は、フランソワーズ・アルディやマリアンヌ・フェイスフルが好きだったみたい。とくに、イギリス人のマリアンヌのほうね。彼女を真似た、黒づくめの服装の写真を見たことがある」
やっぱり、フランス系カナダ人というせいだろうか。
「なるほどね。それはたぶん、アラン・ドロンと共演した映画だ」
「そうなの?でも、祖父はフランソワーズの方が好きだったみたい……」
「ふーん」
「彼は、亡くなる前に白状したのよ。他に誰か会いたかった人がいるかって訊いた時に、『フランソワーズ・アルディ、かっこよかったな』、と言ったの」
「へえ。やっぱり、映画みたいだ」
そう言いながら、『みなさん、さようなら』は、たしかカナダじゃなかったか、と思った。
「確かに、そうよね。そんな話は、全くしなかったのに。祖父のことは、ずっと堅物だと思っていた……」
「ああ。でも、案外そんなものかもね。誰に対しても、全部を話すわけじゃない」
不意に、またKのことを思い出した。
「そうね。でも、よかったわ……」
Iが言った。きっと、彼女も祖父のことを思い出していたのに違いない。
それからしばらく話をした。そして、遅くならないうちに帰ることにした。何にでも潮時というものがある。
そして、何日か経ったあと、僕は思い切ってIにメールしてみることにした。
「終わりかけの桜の下で、もう一度ピクニックはどう?お花見だよ?」
すぐに返事が来た。
「うれしいわ。ぜひ、そうしましょう」
まあ、あんまり興味はないだろうと思っていたのに。少々大人びた外国人とは言っても、何しろまだ、20代の若い女の子なのだから。
*
で、またあの場所で会うことになったのだ。このあいだの公園で待ち合わせをして、お昼ご飯を持ち寄っての、ちょっとしたピクニックだ。
僕は行楽弁当の定番を作った。鮭とかつぶしと梅干、彼女のためにカニカマ(バンクーバーで食べたカニが、美味しかったことを思い出したのだ)とツナマヨのおにぎりに、卵焼き、牛肉のしぐれ煮などを詰めた。彩りのために、スナップエンドウやトマトを添えることにした。彼女は、ローストビーフを挟んだカスクートと、見た目も鮮やかなシーザーサラダを作って来た。
とくに、ローストビーフは絶品だった。僕が知っているローストビーフといえば、ビュッフェ形式の時に出てくるものだったが、大抵は薄切りで、しかもパサついていた。それが、ジューシーで厚さもあって、いかにも肉を食べていることが感じられた。
残念ながら、桜の花はほとんど散ってしまって、もうほとんど葉桜と言っていいくらいになっていたから、周りには誰もいなかったけれど、それでも日本風にブルーシート(さすがに、緋毛氈は無理というものだ)を敷き、座ることにした。念のために、彼女が楽なようにと折りたたみの小さな椅子も用意したのだったが、
「ありがとう。でも、必要ないわ」
と、言われた。本当は楽じゃないのかもしれないけれど、あくまでも、日本風を楽しみたいのだろう。
ほんとうに、楽しかった。彼女も喜んでいたみたいだった。時々、2人顔を合わせて、にっこりした。それから、また桜を見た。目が合うと、彼女が微笑んだ。素敵な笑顔だ。笑顔を見るのは嬉しいことだ。
満開の桜が美しいのはもちろんだけれど、わずかに残った花もまた、なかなか風情があっていいものだ。
その時、ほとんど緑の葉ばかりになった木々の間から一筋の光が差し込んで、彼女の顔を照らした。続いて、僕の顔も。
「あっ、眩しい」
彼女が言う。
「あっ、僕もだ」
それからも、時々会うことになった。年甲斐もなく、なんだかあかるい気分になった。単調な生活に少し彩りが添えられたようで、久しぶりに楽しいと思える日々が戻って来た気がしたのだった。しかも、何であれ避けようとするのではなく、いったん受け入れて、それから前に進むということを教えられたのだ。
ただ、Iは1年も経たないうちに、帰国するのだ。そのことはもう、わかっている。今の僕は、彼女にとっての日本での父親みたいな役割だ。年からいえば、祖父と言う方がふさわしいかもしれないけれど。ともあれ、その役割を楽しんでいるのだけれど、本当の父親はもっと若くて、背が高いくてかっこいい。それに比べるとこちらはちょっと貧相、背も低いし、足も短い。ま、しかたがないことだ。戻ったら、すぐに忘れるのかもしれない。ま、これもしかたがない。
その役割も、やがて終わる。始まりがある限り、終わりもまたある。ま、それもしようのないことだ。それでも、きちんと引き受けることができるようにならなければならない。しばらくの間ともに過ごした時間を通じて、彼女が教えてくれたように。そして、前に進むのだ。
前に。前に、進まなくてはならない。先のことを思い患っていても、いいことはないのだから。
**
あとがき
今回は、前回の続編。前回のものは、見切り発車(ま、いつもそうしたものだけれど)だったし、ファンタジーとはいいにくかった。それで、続きを書くことにしたのですが……。さて、首尾はどうだったか。一応、来月の臨時増刊号での第3部完結編をめざして、取り組もうと思ってはいるのですが……(ちょっと気取って、「光3部作」)。
月末の予定が不明なので、少し早く掲載します。それに、読み返せば、色々と思うところが出てきて手を入れたくなるのですが、それではいつまでたっても終わらない。それだけじゃなくて、そうし続けていると、いっそう冗長になるばかりのようなのです。
何れにしても、まあ、読む人はほとんどいないでしょうけど……(この間は、「私たち(若い人)は、長い文章は読みませんから」、と言われた。映画やドラマでさえ、倍速にして見るらしい。忙しいんですね)。
2024.05.26
読んでくれて、どうもありがとう。
月例増刊号 FANTASY 11 「罰を受ける日」
「暮しが仕事 仕事が暮し」
「確かなものを作りたかったら、確かな暮らしをせよ」ー 河井寛次郎
罰を受ける日
桜は遅かったけれど、辺りはすっかり春めいてきて、もはや夏日を通り越して真夏日というところがあるらしい。変なことは、気象だけにとどまらない。地球上の異常は、いったい、いつまで続くのだろう。
最近は、人と会うことがほとんど無くなった。コロナ禍を経験して以来、外出することがすっかり減ってしまって、それが今でもずっと続いている。とくに、若い人と会うことがなくなった。何より、働く環境を始め、生活を取り巻く環境が大きく変ったことがあるに違いない。そして、お互いに、と言うよりはこちらが一方的に歳を取り過ぎたことのせいが、大きいのかもしれない。まあ、それも仕方がないことだ。
もとより、若さに対する信仰があったわけではない。それどころか、早く老成することに憧れていた(いまから思えば、たぶん、若者としての自分が他者に受け入れてもらえそうにないことを感じ取っていたためなのだ)。
また、ハタチを超えたばかりかというくらいの若者が「もうおばさんなので」とか「もう若くないから」とかいうのを聞くと腹立たしいようで、「馬鹿言うんじゃない」と叱りつけたいような気分になったくらいだった。それでも、年を取っていざ老年期に入ると、若さがまぶしく思えてくることがあるし、羨ましくなることもある。若い人たちが自分たちの世界のことで忙しくて、年寄りとつき合う時間が無くなるというのは、さもありなんという気にもなる。
*
そのとき、僕たちは海辺の小さな町の古いバーのカウンターの隅に座って、久しぶりに飲んでいた。
僕はハイボール、Kはシングルモルトに水を少しだけ入れたものを。Kは最初の職場を定年退職した後の第2の職場で働き始めたばかりだったし、僕はといえばずっと自由業のようなものだったけれど、周りの環境が変わって働き方について考え直さなければいけない時期だったのだ。二人ともが、そろそろ来し方行く末を考えてもいい時期でもあった(もしかしたら、少しばかり遅いのかもしれなかった)。
その日は、金曜だったせいなのか、お店にはいつになくお客がたくさんいて、にぎわっていた。ただ、ふだんとは違って若者のグループが多くて、彼らはそれぞれテーブル席のソファに陣取って大声をあげながら話しており、カウンターに座っているのは僕たちと同じかそれ以上の年恰好だけで、隣を含めていくつか空席があった。
その時に何を話していたのかは、もうほとんど忘れてしまった。ほんとうに久しぶりだったから、たぶん近況報告のようなものだったのだろう。そのせいもあってか、けっこう早いペースで飲んでいたような気がする。
音楽の聴き方が変わったことについても話をした。最近は、ラジオで聴くことが増えた。それは、いったいどうしたことだろう。新しい音楽に触れるためなのか、それとも面倒を避けるためなのだろうかか。
古い曲が新しくアレンジされて演奏されるものもよくかかる。
だから、もしかしたら、こんな話だったかもしれない。
「新しいかどうかというより、懐かしさの方が先に立つんだよね」
「ああ。どうしたことだろうね」
「一挙に、当時の時代に舞い戻るような気がする」
「そうなんだ」
「といって、当時のことを具体的に思い出すことはないのにね」
「へえ。昔のことはほとんど覚えていない、と言っていたものね」
「若い人は、新しい曲として聴くのかね」
「うーむ。どうだろうね」
「ごくたまに、なんだこれは、と思うこともないわけじゃないけれど」
「うん」
「ただ懐かしい、という気分だけなんだよ」
「へえ。そうなんだ」
「新しくCDなんか買ったことはある?」
「そういえば、ないなあ」
「僕もそうだけれど、たまに買うのは中古の古いアルバムなんだよ」
「どうしたことだろうね」
「まずいよね」
「ああ」
「生きる力が欠如し始めている、ということなのか?」
「なんだか、とってもまずい気がしてきたよ」
「うん。……」
「……」
そして、忘れられないことがある。
*
「ごめんなさい。ここ、いいかしら?」
と訊く声が聞こえたような気がした。声の方向を見ると、いつの間にか人が立っていた。暗かったし、おまけに陰になっていたが、若い女性のようだった。
「どうぞ」
Kが、素っ気なく応じた。
「ありがとう」
と言うと、その女性は、Kと壁の間の一つ空いていた席に座った。バーテンダーが、やあいらっしゃいと声をかけながらやってくると、
「何か、さっぱりとしていて軽いカクテルをお願いします」
と言った。それから、ホッとしたように、フーッとひと息吐くと、
「ここは、いつでもこんな風なのかしら?」
と、独り言とも尋ねるともつかない口調で呟いたのだった。
「ああ、今日はなかなか賑やかのようですね」
と、またKが言った。彼が見知らぬ人に応じるのは珍しいことだった。
「というと?」
若い女性は、こちらを向いて、確かめるように訊いたのだ。今度は、その姿がはっきり見えた。周りの大学生よりは、少し年上のようだった。大きな目をしていて、髪をポニーテールに結んでいた。体をピッタリ包む黒の革ジャンとジーンズ、そして同じく黒のロングブーツというかなり目立つ出で立ちだ。おまけに、姿勢がいい(残念ながら、姿勢が良ければすべて良し、というわけではないけれど)。膝の上には、金色に光る2つのCが重なる小ぶりのバッグを載せていた。
若いのに、カウンターにバッグを載せないのは好ましい、と僕は思った。うんと昔、まだ若かった頃に恩師に連れて行ってもらった老舗のバーで、カウンターに荷物を置いたお客がたしなめられたのを覚えていたのだ。荷物は床に置かれたりして汚れていることがある。これをカウンターに載せたら、他のお客が不快に思うことがあるかもしれない。だkら、荷物をおいてはいけない。肘をつくのもだめだ、と教えられた。バーは、凛とした空間の中で飲む場所なのだ。とすれば、愚痴じみた話や湿っぽい話題は似合わない。
「ふだんは、いたって静かなものだよ」
今度は、僕が答えた。
「へえ、そうなんだ」
彼女がうなづいた。訝る様子はなかった。
「上品な年寄りばかりだ」
「それで、彼らは?」
彼女が、問いただすように訊いた。
「めったに見ないね。他が空いていない限り、来ないようだけどね」
「ああ、それはよかったわ。どうもありがとう。お話を邪魔してしまいました。ごめんなさい」
そう言うと、背筋をピンと伸ばしたまま向きを変えると、携帯を眺め始めた(やっぱり、今時の若者なのだ)。
「なんでもないさ」
そう言って、僕たちはまた二人の会話に戻った。
*
「あんまり旅行することもなくなったね」
Kがポツリと言った。
「ああ。コロナがあったしね。年を取ると、いろいろむづかしいことばかりが増える」
「そうだねえ」
「たまには、美味いものを食べに出かけたいもんだねえ」
今度は、僕が言った。せめて日常のダラダラと続く閉塞感を打ち破りたい、と思いながら言った。情けないけれど、そのくらいしか思いつかなかった。
「うん」
「ところで、地産地消って言うだろう?」
思い出すことがあって、訊いた。
「ああ、言葉ばかりで、あんまり経験することはなくなったようだけどね」
「どう思う?」
「やっぱり、獲れたての新鮮なものはうまいよね」
「ああ、魚や野菜だね」
「それに、近隣の住民同士の関係が生まれる」
しばらくそんな話が続いた。
「昔、初めてカナダに行った時にね、バンクーバーだったけれど、同行した先輩が言ったんだよ」
僕はうんと若い時のことを思い出して、懐かしい気分で、言った。初めて外国旅行をした時のことだった。
「ああ」
「カナダのビールはこれが一番うまい、って」
「うん」
「でもね、それが。これを日本へ持って帰って飲んだら、全然うまくないんだ、って言うんだ。もう名前は忘れたけどね」
「なるほどね。ほら、ビールは新鮮さが大事だし、飲むときの温度もある。これは気候と大きく関わるんじゃないかね」
「うん。初めは、全然信じられなかったけどね」
「おまけに、食べ物と飲み物はその土地のもの同士を合わせるのがいいんだね。なんて言ったって、同じ水と空気の中で育ったものだらね」
「ああ」
今は運送手段が発達して、世界中のなんでもすぐに手に入る。そうした時代に慣れすぎてしまった。その代わりに失ったもののことは、すっかり忘れて。
と、その時、
「ああ、懐かしいわ」
と言う声が聞こえた気がした。隣の女性のようだった。
「えっ?」
また、反応した。
「あっ、ごめんなさい」
「いえいえ。どうしたんですか?
「私、ずっとバンクーバーに住んでいたんです」
と言うのだった。
「あらま。それはそれは」
今度は、Kが言った。
「グランヴィル・アイランドのマーケットとか、小さい頃から祖母に連れられてよく行ったから」
話をしているうちにわかったのは、どうやら、会社の研修で1年ほど滞在する予定らしかった。両親ともに日本人ということだったが、父方の祖母はカナダ人で、バンクーバーで生まれて、ずっとそこで育ったらしい。父親の転勤でカナダの内外のいろいろな場所で暮らしたこともあったようだけれど、本人が働きはじめてからは、一時ロンドンにもしばらく住んでいたことがあるらしかった。だから、もしかしたら、ここにもパブのつもりで入ったのかもしれなかった。
今や世界の住みたい都市の最上位の常連となったバンクーバーは、ある時から地産地消にこだわった街づくりをするようになったということらしかった。アリッサ・スミスとジェームズ・マッキノンの二人が著した「THE 100-MILE DIET~A YEAR OF LOCAL EATING~」という本がきっかけで、2010年前後に始まったようだ。ダイエット等のはもともと日常の飲食物という意味があるから、「100マイルダイエット」というのは、住んでいるところから100マイル(約160キロ)の範囲で獲れるものを食べようという地産地消の運動らしい。僕が訪れたのはそれより前のことだったけれども、それでもマーケットや獲れたてだという魚介類を食べさせる店もあったようだった。当たり前と言うか、それが基本という気がするけれど、それが当たり前でなくなってからもうずいぶん長い時間が経った。そのため、多くの食べ物が誰の手になるものかわからず、添加物まみれになった。
そんなことで、しばらくの間、思いもかけない時間を過ごすことになった。そして、
「じゃあ、私はこれで失礼します」
不意に、彼女が切り出した。
「ああ。なんだか質問ぜめにしたようで、悪かったね」
「いえ。こちらこそ、すっかりお邪魔してしまいました」
「おかげで、楽しかった」
「私も」
「楽しい日本での暮らしを。お元気で」
「ありがとう。また、お会いしましょう」
「ああ。ここにいるよ」
「ええ。それでは、さよなら」
彼女は、帰っていった。
*
彼女が去って、また二人だけになった。なんだか急に寂しくなって、明かりがひとつ消えたような気がした。やっぱり、ふだんは若い人、特に女性と話す機会がないせいなのだろうか。こうした彩りに欠けること、おびただしいのだ。だから、彼女が会話に加わって入る時は、つかの間、華やいだ気がしたようだった。それで、二人して、顔を見合わせると、ふっとため息をつき、黙り込んだまましばらくグラスを弄んだ。それから、
「この頃は、なんだか、自分は罰せられているような気がする時があるんだよ」
Kが唐突に、ポツリと呟いたのだった。
「えっ?」
僕は思わず訊き返した。
「自分は罰を受けているのではないか、と思うんだ」
Kがもういちど言った。今度は、少し大きな声で、はっきりと。
「いったいどうしたっていうんだい。何があった?」
僕は驚いて、訊いた。すると、Kも、
「いや、何でもないさ」
と言ったので、ああまたからかっているのかと思った。彼は、ふだんからよくそうすることがあった。しかも、自虐的と言うのか、自嘲的な言い方で。だから、そのときもそうだと思ったのだ。
「でも?」
なんとなく訊いた。
「何も起きないんだよ。何をやってもうまくいかない」
と、Kが言う。
「たとえば?」
「たとえば……」
「たとえば?」
「新しい仕事も楽しめないし、環境にも馴染めない、とか」
「それだけ?」
「自分が作った書類には、ミスプリントが目立つ、とか」
「ふーむ。他には?」
「何を書いても、反応がない」
「ああ」
「誰も読まない……」
「そうなのか?うーん」
Kは、ブログやら短い物語風のものを書いている、
「いろいろ考えて、手を変え品を変え、工夫をしてはいるんだけどね」
「うん」
「でも、なにも変わらない。誰も読まない。楽しんでいる人はいないようだし、喜ばないんだね」
「そう?」
それから、Kはテレビで見たという人たちのことを語り始めた。曰く、
無名の人の働きの偉大さ、すごさ、素晴らしさ、志の高さには驚かされることが多い。声高に主張することなく、地域の住民の思いを汲み取り、人々にとっての望ましい姿やあるべき姿を思い描き、実現すべく地道に作業を続け、取り組む。
例えば、震災後の鉄道の再開のために尽力した会社の人々。「日常を取り戻す光」のための一助にしようと労を惜しまずに取り組んで、地震からおよそ3ヶ月後に実現にこぎつけた。また、地元の高校生たちは、駅の清掃を行った。
また、日本初という難工事に取り組んだと鳶職をはじめとする職人や現場で働いた人々の奮闘ぶり。ちょうど東日本大地震と重なり、倒壊の危険を減らすために自身の命を顧みず、鉄塔に登った人たちがいたこと。
あるいは、Jリーグに参加することでコンビナート砂漠と言われた町で町おこしを図ろうと立ち上がった人々。当時のチームは、とても参加できる状況にはなかったし、しかも要件を満たすスタジアムもなかった。しかし、彼らの尽力で、チームの親会社はチーム名から会社名を外し、賛同者は増えて参加が認められたという。しかも、初年度には優勝した。
たいしたものだし、本当にえらいものだと思うけれど、自分はこうした志を持って努力した人々と全く違うのだ、と言うのだった。
「何かを成し遂げられなかった、ってことか?」
僕が訊いた。
「いや。それもないとは言わないが、いちばんはやるべき努力をして来なかったということだね」
Kが言った。
「そうなのか?」
「ああ、うまくいくかいかないかが問題じゃないんだ」
「うん」
「真剣に取り組むことができなかった。それは、ちゃんと生きて来なかったということだよ」
「じゃあ、今からやればいいじゃないか」
「ああ」
「そうすればいい」
「価値のない、とても卑小な人間のような気がするんだよ」
「過ぎたことを言っても、仕方がないよ。これからどうするかが大事さ」
「こないだは、早く目覚めてラジオをつけた時に、「愚か者」という声が聞こえたんだ。まいったね」
と言った。なんでも、若くして亡くなってしまった俳優の特集で、その中の歌詞に出て来たらしかった。さらに、
「メールには、返事さえ来ない。来るのは通販の会社だけだ」
と続けた。
「ああ、僕だって似たようなもんだ」
僕は、なんとかこの話を終わりにしようとして、言った。しかし、
「誰からも相手にされず、なんだか社会から切り離されたというか、放り出されたような気がする」
Kは、なおも続けたのだ。
「そう?でも、悪いことばかりじゃないだろう?」
「ああ。そうかも」
「そうだろう?」
「まあ、昔からそんな気もするけどね。でも、考えもしなかったような相手に、手ひどい仕打ちを受けたことも何度かある」
「えっ?」
「信じられないような裏切りも。一度ならずね……」
「ああ、それなら僕にだってある。嬉しいというわけじゃないけどね」
「うん。不当だと思うけれど、でも、彼らなりに理由があるのだろうね。盗人にも三分の理。想いは、人それぞれだから」
「……」
「やっぱり、持って生まれたものなのかね……」
と、独り言のように呟いたので、
「何?」
と聞いた。
しばらく間があいて、Kはこう言ったのだ。
「おまけに、宝くじには当たらない」
「買ったのかい?」
「いや」
「それじゃ当たるわけがない」
「前に買ったときも当たらなかった」
「……」
僕は、ほっとして、笑い出しそうになった。やっぱり、今度こそ、からかっていたんだな。しかし、Kはさらに
「年賀状にも、当選番号はなかった」
と言ったけれど、いつまでも言い続けて、何か変な感じだった。
「ああ」
僕がうなづいてから、またしばらく間が空いた。
その時、テーブル席でまた、ひときわ大きな笑い声が起こった。なんと場をわきまえない若者たちであることか。まあ、ちょっとムッとしたけれど、それでもすぐに気を取り直した。なんと言っても、若者たちなのだ。希望と自信に溢れていて、自分に悪いことなんかは起こりはしないし、ありもしない。自分に非があるなんてことは思いもしない。少なくとも僕は、私は、と思える時なのだ。世界は、夢に溢れた場所のことなのだ。確かに、若者は少々ハメを外すこともあるし、それがどうしたっていうんだ。それで、誰かに大きな迷惑をかけるというわけじゃない。仮に少しばかり不快な思いをした人があったとしても、さほど大きなことじゃない。
「彼らを見習うといいよ」
と、大きな声の方を顎で示しながら、僕は冗談のつもりで言った。
「ああ。羨ましいな。この歳になっても、自分の気持ちに正直になれない。素直に伝えることができないようなんだな」
Kが小さな声で続けた。
「……」
「受け止められてもらえないかもしれないし、誤解されるかもしれない。変な圧力をかけることになることだってあるかもしれない。力があるわけじゃないから、別に実害はない。でも、気分はね。なんと言っても、たいていの場合、だいぶ年上だからね。そんな気がしてしまうんだよ」
「そう?でも、きっと思い過ごしだよ」
「ああ、確かに。そうかもしれない。ただね、それがまた、悪い方に働く」
「そうだよ。気にしすぎるからうまくいかない」
僕は言った。
「負の連鎖ってやつかもしれない」
彼は、自分に言い聞かせるようにつぶやく。
「そうさ。だって、たいていのことが、そんなにうまくいかないのがふつうだろう?」
僕だって、いい時ばっかりじゃない。むしろ悪い時が多いくらいだ。
「ああ」
「ねえ、そうだろ?僕は君と知り合ってから、もう長いよ。これまで、ずいぶん話もしたし、一緒に出かけたりもした。それに、よく飲みもした。僕が知っている限り、君はそんなに悪いやつじゃない」
僕は言った。まあ、確かにそう思っていたのだ。
「ありがとう」
「だから大丈夫だよ」
「ああ。こんなことを言ったからと言って、別に大きな罪を犯したわけではないよ。もとより、気が小さいし、自分では人との争うことを好まないたちだと思っている。ただ、そうとは気づかずに傷つけた、または傷つけているということは大いにありそうだと思うんだよ。もとより、僕は聖人君子なんかではないのだから」
Kが、自分の心の中にずっとくすぶっているものを吐き出そうとしているかのようだった。
「もちろん。誰だってそうだよ」
僕は、他に言いようがなくて付け加えた。
「小さな嘘や裏切り、精神的な圧力だってあっただろうと思うよ。まあ、お互い様ということもあるかもしれないけれど。それから、こちらは大きな罪だな。筋金入りの怠け者ということだね。等々、挙げればきりがないよ」
「だから、それもこれも誰にもあることだよ。聖人君子じゃない限りね。そうそう、僕なんか柿ピーを一度に2袋食べてしまうことだってある」
僕は、そろそろ終わりにしたいと思って、言った。
Kがようやく笑った。それで僕はほっと一安心したけれど、
「自己憐憫が過ぎているんじゃないかという気がすることもある」
と、Kはさらに続けたのだった。
「うん」
「もう一方で、そう言う声が聞こえる気がする……」
「なら、やめればいい」
僕は、慰める代わりに、思い切って突き放すように言ったのだった。
「何を?」
「その自己憐憫ってやつを」
「うん」
「自分を哀れむことを、やめるのさ」
「やめてどうする?」
「ありのままを受け入れるんだよ」
「ああ。それで、受け入れてどうなる?」
「楽になる」
「それだけ?」
「ああ。簡単なことだろ?他に何を?」
「そう?」
「そうだよ。でも、それだけで十分じゃないか?」
「そうか?」
「そうさ。他に何を望む?」
「ああ」
「じゃあ、すぐにやめればいいんだよ」
「うん」
「新しく始めればいい」
「ありがとう」
そう言うと、彼はしばらく黙ったままだった。
たぶん、Kもそのくらいのことは、自分でもわかっているのだ。ただ、それでも、これまでの何か澱のようなものが、残っているのに違いない。長く生きれば、当然、誰にだってあることだ。人は、そうしたものを抱えながら生きるしかないのだろう。それがなんなのか、それは人によって違うだろうだろうから、言っても仕方がない気がしたのだ。だけど、つい言った。
「それが、人生というものだろう?」
「ああ」
Kは、心ここに在らずというようなふうだった。
なんだか、もうここにいても仕方がない気がした。話をしても、もはや届かない。言葉は若者たちの声とぶつかり、闇の中に吸い込まれて、ついに届くことなく、居場所を失って、宙を彷徨うだけだ。
それで、僕たちは帰ることにした。バーでは、相変わらず若者たちのうるさくて明るい笑い声が響いていた。
*
駅まで一緒に歩いた。途中で、彼はふいに、
「自分の好きにしつらえた家に住みたかったな。
結局、何にも手にすることができなかったな。
誰のせいでもなく、自分のせいだけどね」
と呟いた。そして、
「世の中には、偉い人たちがたくさんいるものだね。それに、このところはなぜか、賛美歌の451番ばかりが口をつくんだ。以前は、ほとんど声に出して歌ったことはなかったし、それにクリスチャンでもないのに」
とも。
駅に着くと、彼は改札口に向かい、僕はバスの乗り場まで歩いた。
そして、それ以来、Kとの連絡がふっつりと途絶えてしまった。メールを出しても、電話をしても、手紙を書いても返事はなかった。他の何人かに聞いても同様で、やっぱりわからなかった。彼は、突然、僕たちの前から姿を消してしまったのだ。いまでも、その行方はようとして知れない。生きているのか、どうかさえもだ。
**
あとがき
今回は、見切り発車。しばらくほったらかしのままだったのに加え、ファンタジーとはいいにくい。おまけに、少しばかり付け加え過ぎて、まだ、生煮えの感がある。ちょっと気恥ずかしい気がする。でも、代わりになるものもないし……。まあ、読む人はほとんどいないから……。
2024.04.30
読んでくれて、どうもありがとう。
緊急増刊号 FANTASY 10 「キャンディが好きだった子」(β版)

キャンディが好きだった子(β版)

君はキャンディは好きかな。あの丸いものや四角いもの、星の形をしたりしたものもある。色もいろいろだね。赤やオレンジ、黄色や緑、金色なんてものもある。たいてい、大きなガラスの瓶に入れて売られていました(今はどうなのだろう)。あのきれいで、甘いお菓子。うんと昔は小さな町にでも、子供がおこづかいで買えるキャンディをたくさん並べて、売っていた駄菓子屋さんがいくつかあったんだけどね。今はあんまり見かけなくなってしまったようです。
それに、甘いと言ったけれど、今はけっこういろいろな味があるようですよ。世界のたくさんの国で、それぞれ特徴があるんだね。日本のものは、砂糖や水飴を主原料としてるから甘い。フランスには塩バターキャラメルがあるし、修道院で作られていたという、大麦を煮詰めて作った自然な甘みを凝縮した香ばしい風味のものなんかがある。アメリカには、チョコボールやペパーミント味のものがあって、これが人気のようなのです。こんなふうに、世界中で色々なキャンディが売られているんだね。そういえば、南の島の警察の人も(もちろん、もう立派な大人ですよ)、引き出しの中の小さな缶に隠していて、時々食べているようです。
でも、子供の頃は好きだったのに、どういうわけか大人になったら食べることが少なくなってしまうもののひとつなのだね。なぜだろうね。これから話すのは、小さな子供の時からキャンディが大好きで、大人になっても変わらなかった、それどころかますます好きになった人のお話。もし、君が子供だったり、子供の時と同じように複雑じゃないものが好きなら、気に入るかもしれない。だけど、何しろ今はたくさんのものがありすぎて、みんな手の込んだものが好きのようだからね。
でも、小さいころから大人になてもずっとキャンディが好きな子供がいました。今回はそのお話です。
あ、名前がないとややこしいいので、とりあえずその子のことをアメと呼ぶことにしましょうか。

アメはうんと小さい頃から、もうキャンディが大好きだった。ある年の誕生日に、遊びに来たおばあさんからお祝いにおこづかいをもらった(おばあさんは離れたところで暮らしていたから、アメが何が欲しいのか、わからなかったんですね)。その額はといえば、キャンディが500個ほども買えるくらい。アメはお礼もそこそこに、町の商店街を目指して駆け出した。なにを買うつもりだったんだと思う?君ならどうするのでしょうね。
アメがいちもくさんに飛び込んだのは、もちろん小さなお菓子屋さんだった。

「おじさん、キャンディをください」
「おお、アメ、いらっしゃい」
「こんにちは」
「こんにちは、今日は、何にするんだい?」
「ぜんぶください」
「えっ?」
「これで買える分を、ぜんぶください」
とって、お金を見せた。
「そんなにかい?それじゃあ、500個ほども買えるよ」
「はい、ぜんぶください」
「ほんとうに?」
「もちろん。いろいろまぜてね」
「ああ、はい。わかったよ。500個もねえ」
そう言って、おじさんはいろいろな瓶から綺麗な缶に入れてくれた。
まあ、キャンディはすぐには悪くならないからね。
そして、キャンディを500個も抱えて帰ったというわけ。

「ただいまあ」
「やあ、おかえり。おや、その缶はどうしたの?」
お母さんが訊きました。
「キャンディだよ」
「そんなにたくさん?」
「おばあさんにもらったお祝いで買ったんだよ」
「へえ。おばあさんにも見せなくっちゃね」
「うん」
「じゃあ、おばあさんのところに行きましょう」
「うん、そうする」

「おばあさん、これを見て!」
「おや、どうしたっていうんだい⁉︎」
「キャンディ。おばあさんにもらったお祝いで買って来たんだよ」
「へえ、そうなのかい。それにしても、そんなにたくさん!」
「そうなんですよ。この子ったら、いくらキャンディが好きと言ったってねえ」
お母さんが呆れた顔で言った。
「そうだねえ。ところで、お前さんはいったい、どうしようっていうんだい?」
おばあさんがやさしく訊いた。
「うん。アメはね、キャンディ屋さんになるんだよ」
今度はアメが、大きな声で言った。
「えっ、お店を開くのかい?」
おばあさんはびっくりして、たずねました。
「そうだよ。でも、今じゃないよ。大きくなったらね」
「へえ、そうなのかい。じゃあ頑張らなくちゃあね」
おばあさんは、今度はホッとしたように言いました。だって、小さな子どもがお店を開くというのはむりでしょう。
「うん。世界でいちばん素敵なキャンディ屋さんだよ」
アメは、高らかに宣言したのでした(まだ10歳にもならないというのに)。

それから何回もの誕生日が過ぎ、アメもすっかり成長して、もう大人と呼んでもいいくらいの年になりました。青年となったアメは、キャンディをつくる大きな会社や販売会社、それに町の小さな駄菓子屋さんで働きました。小さい頃のキャンディ屋さんになるという夢を大きくなっても忘れずに、ずっと持ち続けていたんですね。

その後アメは、ある大きな街に住んでいました。そこにはとても広い公園があり、大きな川と海がありました。それで、この大きな街をぜひおばあさんに見てほしい、きっとよろこぶに違いないと思ったのです。だって、おばあさんが住む街には大きな公園も、大きな川も、大きな海もありませんでしたからね。
それで、おばあさんを招待して、何日かかけてゆっくりと街のあちことを案内して回りました。たいていは歩いてでしたが、時には自転車のように人がこぐタクシーに乗ることもありました(何と言っても、おばあさんも年でしたから)。そして、あるお店の前を通った時のこと。

「おや、アメ。見てごらんよ。素敵なキャンディ屋さんがあるよ」
おばあさんが言うように、ガラス越しに見えるお店の中には、いろいろな色や形のキャンディがたくさんの大きなガラス瓶に入って並んでいました。
「ああ、そうだね」
アメが小さく答えました。
「お前が小さい頃になりたいと言ったキャンディ屋さんは、きっとこんなお店だよ」
おばあさんが言いました。
「ああ、そうかな」
アメがそっけなく答えます。
「そうだよ。楽しそうじゃないか。ちょっと入ってみないかい?」
おばあさんは、ドアを開けようとしましたが、開きません。どうやら閉まっているようです。
「閉まっているようだね、残念だね」
おばあさんが、ぽつりとつぶやきました。
「そう?」
「せっかくだから、写真を撮ってもらうのはどうだい?それがいいよ」
おばあさんはそう言うと、歩いている人に写真を撮ってくれるように声をかけたのでした。
「入れないのは残念だけど、まあ写真が撮れたのだからいい、としないとね」
おばあさんは、それでもとても残念そうでした。
「入ってみたいの?」
アメが訊きました。
「ああ、だってお前が夢見ていたものだもの。ぜひ見てみたいよ」
「そんなに?」
アメがにっこりしながら、言います。
「ああ」
おばあさんが、ちいさな声で答えました。
「じゃあ、入ろう」
「えっ。でも……」

「さあ、どうぞ」
アメはポケットから鍵を取り出してドアを開けると、おばあさんを中に招き入れたのでした。
「いったいどうしたっていうんだい?」
「ようこそ、わたしのお店へ」
「おお!」
とちいさく叫ぶと、おばあさんはアメの腕の中に倒れ込んでしまいました。

アメはおばあさんをソファに座らせると、それから綺麗な缶にキャンディを詰めはじめたのでした(でも、500個はなかったようでしたが。だって、おばあさんは重くて抱えきれないでしょう)。

やがておばあさんが目を覚ますと、アメはリボンをかけた缶入りのキャンディを手渡しました。おばあさんは、もういちどアメを抱きしめました。それからアメは、おばあさんを駅まで送り、抱えるようにして電車に乗せて、おばあさんを見送ったのでした(もちろん、車掌さんにおばあさんのことを頼むのも忘れませんでしたよ)。
あとがき
今月の臨時増刊号は、久しぶりに絵本を(読んでくれる人がいるのかどうか、怪しいですけど)。
つい先日ニュースを見ていたら、大学の卒業式の場面が。彼らはコロナ禍の中で3年間を過ごし、最後の1年間はキャンパスで過ごすことができた(不幸中の幸い)。一方で、コロナ禍の最中に卒業を迎えた人たちもたくさんいたということですね。で、思い出して、大急ぎでなんとか24日に臨時増刊号を出そうとした次第です。
この時期は、色々と新しいことを始める季節ですから、ちょうどいいのではないかと思ったのです。ただ、主人公を男の子とも女の子ともわからないようにしようと思ったのですが、そのせいで絵や言葉遣いがなんだか不自然のところもあるような気がする(考えてみたら、子どもが読むわけはないから、意味がないかもしれませんけど)。
絵は、まだ色鉛筆(おまけに、黒がないまま)ですが、近いうちにiPadで書くことに挑戦してみようと思っているところ。そんなことで、題名にβ版と付記しました(もしかしたら、物語の方も、そして題名も手を入れなくてはいけないかもしれないし、α版とした方がよかったのかもしれませんが)。
まあ、一人や二人くらいは楽しんでくれる人がいてくれるのではないか、と期待していますけれど。
感想や意見が届けばいいのですが。
2024.02.24
読んでくれて、どうもありがとう。
おわりにお願い:ご意見と感想をいただけたなら助かります。
4週連続特別企画増刊号・第4弾 FANTASY 9 「穴のあいた小石のある場所」
穴のあいた小石のある場所
こじんまりとしたホテルの小さなロビーで午後の紅茶を楽しんだ後、ぼんやりと外を眺めていたら、何日ぶりかに日差しが出てきた。これは、これは。ぜひとも、散歩に出かけないわけにはいかない。
この地方は、1日のうちに四季があると言われるほど、天気が変わりやすい。しかし、この数日はずっとどんよりとした厚い雲に覆われたままだった。
このため、外の新鮮な空気を吸いたかったし、何より光を受けた村の景色を見たかったのだ。飛行機で12時間ほども離れたところまでやってきて、さらにフェリーを乗り継いで来たのだから、いかにもこの地方らしいという気もしないでもないが、厚い雲に閉ざされた景色だけ見て帰るのはいかにも残念な気がした。旅行で得た印象は誤解を生むだけ、一面しか知ることができないということはわかっていたけれど、それでもたくさんの表情を見たかったのだ。
海岸までゆっくり歩いて行くと、若者が一人、何かを探しているようだった。何か大事な物を落としたのか。例えば婚約指輪とか、何かの鍵とか。もしかしたら、ただのコインかコンタクトレンズかもしれないけれど。
「やあ」
私は思い切って、声をかけた。
「やあ」
同じように、挨拶が返って来た。
「何を探している?」
私は、近づいて行くと、ごく短く訊いた。何しろ慣れない言葉だ。
「これだよ」
右手に持った小さなものを指しながら、彼が答えた。母語のはずにも関わらず負けず劣らず短かった。
「えっ。特別の石なのか?」
さらに訊いた。
「よく見てごらんよ」
若者が今度は、諭すように言った。残念ながら、私はどうやら注意力や観察眼に欠けているようなのだ。昔からのことだ。今に始まったことじゃないのだ。
「うーん」
「ほら、小さな穴があいているだろ?」
もう一度、今度は指で指し示しながら、やさしく教えてくれた。よく見ると、あらゆる角が取れて丸くなった三角形の形をした小石は、真ん中より少し上に小さな穴が空いていた。
「ああ、ほんとだ」
これまで、丸い穴があいた小石なんて見たことがなかった。
「適度な重みがあって、ちょうどいい大きさのものを探していたんだよ」
「へえ」
「このあたりの石は、なぜか穴があいているんだ」
「そうなのか?で、何にするんだい?」
見当もつかなかった。
「釣りに使うのさ」
「へえ」
と言ったものの、どういう風に使うのかさっぱり見当がつかなかった。
「ついてくるかい?」
若者が訊いた。やっぱり短い。できるだけ節約しようとしているようだった。言葉の使いすぎはためにならない、というかのように。
「ああ、見学させてもらうよ。もしよければ」
「じゃあ、行こう」
若者が顎をしゃくって促した。私はそれに従って、ついて行った。歩いて行きながらあたりを見ると、海の上にほぼ垂直に切り立った崖の高さは様々のようだけれど、どれもその上は平らな面になっている。
彼は、海面から3mほどもありそうな切り立った崖の先端まで行くと、くたびれた帆布製のバッグの中から道具を取り出した。それは道具というほどのこともない、きわめて簡素なものだった。まずは糸、というよりは紐という方がいいくらい太かった。これにテグスをつなぎ、釣り針をつけ、先の小石の穴に通した。はあ、なるほどそうだったのか。
「これで、道具立ては完成だよ」
それから、針先には海岸で拾ってきたという小さな貝を刺した。
「えっ。竿は?」
釣り人が、擬似餌の他に一番こだわるものといえば、竿ではなかったか(しかし、すぐにと思いなおした。彼らは、遊びでやるわけではないのだ)。
「竿は使わないんだ。ここからこうやって垂らせばいいんだよ」
彼が半分身を乗り出すようにして、やって見せてくれた。
「なるほどねえ。でも、ちょっと怖いね?」
「そうだね」
「君は怖くないのかい?」
「まあ、慣れているからね。でも油断はしない」
少し厳しい口調になった。
「なるほどね」
「大波が来たら、あっという間もなくさらわれてしまう」
小さい声だったが、自分にも言い聞かせるように厳しい口調で言った後は、また穏やかな表情に戻った。
「えっ。そうなんだね」
「ああ、島のものなら、誰でも知っている」
「うん」
「あ、何かかかったようだ」
ことも無げに言った。こんなふうに静かに話す若者と会うのは久しぶりのことだった。いまでは、感情をことさら露わにするように話す若者も少なくない。このほとんど絶滅危惧種のような若者は、慣れた手つきでゆっくり紐を手繰り、引き上げてゆくと海面に30cmくらいの黒っぽい肌の魚が現れた。
「やったね」
「ああ、ベラだね。ちょっと小ぶりだけどね」
やっぱり、静かに言った。
「ふーん。これでもね」
それからしばらく釣っている間に、ベラの他にも小さな魚が何匹か釣れた。
「さあ、家に帰ろうか。おかずも釣れたことだしね」
「ああ。どうもありがとう。楽しかったよ」
「今日の晩御飯はベラだよ。君もどうだい?」
「ほんとうに?迷惑じゃないのかい?」
私は驚いて、彼のほうを見た。何しろ私は、彼らのようなヨーロッパの人間とは明らかに違うことが一眼でわかる扁平な顔をしている。どこから来たのかもしれない、旅行者風の年寄りなのだから。
「大丈夫さ。ただ、たいしたものはないよ。見ての通りの土地だからね。それでよかったら、どうぞ」
こんなに穏やかな青年が、こうも気さくにもなるのかと驚いた。その土地には、「見知らぬ人はまだ会ったことがない友人」という言い方があるらしいことは、聞いて知ってはいたけれど。私は、悪いとは思いはしたものの、甘えることにした。なんといっても、地元の人々の日常生活を垣間見れる機会は滅多にない、ましてこんなところではと思ったし、ホテルの少しばかり気取った食事にも飽きて来たところだった。
「いいのかい?ほんとうに甘えてもいいかな?」
「ああ。さあ行こう」
また、短く言った。
緩やかに壇状に連なった、石垣で囲まれた畑の間を、ポツリポツリと話しながら歩いて行った。若者は口数の多いタイプじゃなかったし、私の方には使い慣れない言葉の問題があった。少し行くと、畑の先には、軒の出のほとんどない簡素な切妻屋根が乗った石造りの家が何軒か、少し離れて建っているのが見えた。家の祖形と言いたいくらいで、美しい景色だった。ずいぶん前に、シングルモルトの銘品の宝庫、アイラ島の民家を見たときにも、同じことを感じたことがあった。
この島は、氷河期に海底が隆起してできたため、そのほとんどに石灰岩に覆われた岩盤で出来ているらしい。しかも、周りの海からはいつも強風が吹きつける。そのため、高い木は育たない。島民は何世代にもわたって、石灰岩を掘り起こし、粘土を敷き詰めた上に、岩盤を砕いて海藻を混ぜたものを重ねることで、土を作り、畑を生み出してきた。そうして作った貴重な土が強い風に飛ばされないように、石垣で囲った。ここで暮らしてきた人々の知恵と努力の結晶なのだ。こうして出来上がった畑で、ジャガイモなどを作るのだ。贅沢な野菜を植える余裕はない。何しろ、畑の面積は限られているし、さして広くもないのだ。
「ただいま」
扉を開けると、若者が大きな声で言った。家に帰るとほっとして、嬉しくなるのはどこの国でも変わらないようだった。すっかり贅沢に慣れた国でも、そうではない場所でも。
「おかえり。あら、お友達かい?」
出迎えた母親らしい女性が、なんでもないような口調で訊いた。
「ああ、海岸で会ったんだよ。日本から来たらしい」
「そうなのかい。それじゃ、こちらへどうぞ」
彼女も、息子と同じように、まったく気取ったところがなかった。
訝る様子も、ためらうこともなく、すんなりと中に通してくれた。家の中は、外観と同様に簡素な作りで、設備もごく質素なもののようだった。華美なものは一つもなかったが、それが新鮮で好ましかった。居間と食堂と台所は1室にまとめられていた。台所のコンロの上では、鍋から勢いよく湯気が出ていた。なにか茹でているのだろうか、それともその準備をしていたのかもしれない。
「今日は何が釣れた?」
奥の方から、潮風にさらされてしわがれた、男の声が聞こえた。たぶん、彼の父親なのだろう。
「ベラだよ。そのほかに小魚が」
若者が答えた。
「じゃあ、ムニエルにするか?」
父親が言った。
「いいね」
「そうしましょう」
若者と母親が、声を揃えて言った。
それから、台所の方に出てきた父親が、ちらりとこちらを見ると
「やあ。いらっしゃい」
と声をかけて、簡単な会釈をよこした。愛想はないけれど、こちらも怪しむ気配は全くなかった。調理台の前に立つと、慣れた手つきでウロコを取り、魚をさばきはじめた。それから、塩コショウをし、粉をはたき、油をひいたフライパンの中にそっと入れた。見かけによらず、繊細な手つきだった。すぐに、いい匂いが漂ってきた。母親の方は、茹で上がったじゃがいもを大量にお皿に盛ると、バターの入った器とともに目の前に置いた。まもなく、ムニエルも焼き上がり、フライパンごと運ばれてきた。父親が、お皿に取り分けてくれた。
「さあ、どうぞ。遠慮なく召し上がれ。たくさん食べてね」
母親が、にっこりと微笑みながら勧めてくれた。父親も顎でムニエルの方を示して、うなづいた。
「ありがとう」
私は短く言うと、早速ナイフとフォークを手にすると、まずはこんがりといい色に焼けたムニエルを切り分けて、口に入れた。
「うまい!」
思わず、日本語が出た。ほんとうにおいしかったのだ。素材そのものの味を久しぶりに味わったような気がした。茹で上がったじゃがいもにバターを添えただけのものも、ふだん食べているものよりも味が濃いような気がした。特に手のこんだものでもなく、まして高級なものでもない、ごく簡素な食べ物。それにもかかわらず、それは格別の味がした。すぐそばで取れた新鮮な食材を、手早く調理しただけのもの。もしかしたらそのことに加えて、作り手の気持ちも味の中に閉じ込められるのだろうか。
「それはよかった」
3人が口をそろえて、そしてにっこり微笑んだ。私も、同じように、にっこり笑った。初めて会ったばかりの人たちと、こうしてこんなにも打ち解けた気分になれることに驚いた。だいたい、私は慣れているはずの人たちとさえも、緊張しないではいられない質なのだ。
彼らの小さな島での過酷な生活のことや、私がここにやって来た理由など、しばらく話をした。私はなれない言葉に苦戦したけれど、たいした障害にはならなかった。生活は楽ではないのは明らかのようだったけれど、一方で確かに自然とともに生きているという実感がしっかり伝わってきた。コーヒーと地元産だというウィスキーを数杯味わった後、遅くならないうちにと思って、お礼を言って引き上げることにした。そうしないと、居心地が良くて、ずっと座ったままになりかねない気がしたのだった。
帰り際、ドアのところまで送ってくれた父親が、まだしばらく滞在しているならパブへ連れて行く、と言ってくれた。なんでも、この小さな村にはパブが数軒あって、そこが村人たちの集う場所になっているということらしかった。私は、ヨーロッパの人たちのプライバシーとコミュニケーションのバランス感覚にはいつも驚かされる。我が国においては、たいていどちらかに偏るし、偏り方はプライバシーの方に大きく振れるようなのだ。
外に出ると、空は、満天の星だった。今まで、どこでも見たこともないような星空、たくさんの星々が静かに、白く輝いていた。文字通り、初めて見るものだった。
ゆっくりとホテルの方へ向かう途中、私はしばし空を眺めては、「幸せ」というのはいったいなんだろうと思い、そして、腑に落ちたような気がしたのだ。
それから、あの穴のあいた小石のことを思い出した。穴があいた小石は、釣りの時の重りにするのには極めて好都合だ。やがて、不意に、天の配剤、天の恵みという言葉が思い浮かんだのだった。
*
それにしても……、と思い出すたびに考えざるを得ないことがある。彼らはなぜ、住み続けているのか。あの荒涼とした景色と過酷な自然の中で暮らしていくのは、決してたやすいことではないはずだ。望めば、うんと豊かになるわけではないかもしれないが、もっと安全で安心できる場所に移り住むことができたはずなのに。実際、そうした人々もいる。それなのに、なぜ踏みとどまるのだろうか。その島では、神々が妖精となって人々を守っているというのだが、彼らは日々そのことを感じ取りながら暮らしているのだろうか。
*
短いあとがき
特別企画の第4弾。一応、これで終了。短い間に、いささか粗製乱造(⁉︎)の気味がありましたが、ま練習ですから。それに、反響はもとより、反応さえ皆無なのは、相変わらずですし。まあ、いったい何をしているのだろう、と自問することもなくはありませんけど。
この島だったか、あるいは同じルーツを持つ別の地域のことだったか、そこでは、「最も大きな誇り、それは倒れないことではない。倒れるたびに立ち上がる、それが誇りなのだ」、と言うようですから。
2024.02.29
読んでくれて、どうもありがとう。
おわりにお願い:ご意見と感想をいただけたなら助かります。
4週連続特別企画増刊号・第3弾 FANTASY 8 「「幸福」の情景」
まえがき
先日のブログでもちょっと触れたように、雪の日の電車で見たときに思いついたことをもとに、書きました。何しろ短い時間だったので、最初の部分はその時のブログを援用したところがあります。おまけに短い。すぐ読めます。
「幸福」の情景
私は、今でも時々思い出すことがある。彼女と彼を初めて見たときのこと、私の住む街で何度か見かけたこと。そして、そのあとのことも……。
その日は、赤坂で、遅ればせながらの新年会だった。それなのに、あろうことか当日は大雪の警報が出ていた。もう昔のことだ。たいていのことは、忘れてしまった。
家を出る頃には、もうちらつき始めていて、赤坂見附駅についた時には、すっかり本降りの様子で、さらに滑りやすくなっていた。ただ、路上の車や人通りはうんとすくなく、お店もガラガラのようだったのは、雪だけのせいじゃないかもしれない。経済関係者たちはいよいよデフレ脱却と浮かれている向きもあったようだけれど、あんまりそういう気はしなかった。
雪は、その降る様や積もったときの景色は美しいが、その後が厄介だ。歩こうとすると、足を取られたり滑ったりする。しかも人が歩いた後は、真っ白だったものが泥やゴミの黒が混じって、いっぺんに汚らしくなる。おまけに、翌日の朝は凍って、いっそう滑りやすくなっていることが多い。雪の多い場所に暮らす人は、雪かきや雪下ろし等々、さぞ大変なのに違いない(僕などはきっと、生き延びることさえできにそうにもない)。
その帰りのこと。久しぶりの会食、久しぶりの東京、久しぶりの雪でいっときの非日常の時間を楽しんだ後は、みぞれ混じりの雨の中をようやく地下鉄の駅にたどりつき、改札を抜けてエスカレータを降りて行くと、すぐ目の前にすらりと伸びた脚が現れた。綺麗な足だ。しばし見とれた。
その上の丸いお尻を包んでいるのはぴったりとした小さな布。ショートパンツでもなくキュロットでもなく、ごくごく短いスカートだった。ちょっとびっくりして、そっと目をあげると、金髪の外国人女性だった。どちらかというと素朴な感じのする顔立ちだった。背が高いのはいうまでもないけれど、その足のなんと長いことか。丸いお尻とその上の細い腰が、まるで私の顔の高さにあるようで、驚いた。ついでに言うと、その隣に立っていた男性は、彼女よりももっと高かったが。
ようやく来た電車に乗り込むと、乗客はずいぶん少なかった。立っている人はほとんどいないくらいで、車内を見渡すことができた。ほとんどの乗客が、スマートフォンに見入っている。時代遅れになったことを自覚しないわけにはいかない。そうでなければ寝ているか、だ(こちらは、昔も今も変わらないようだ)。ドアが閉まろうというとき、半ば閉まりかけたときに、スーツ姿の恰幅のいい男が駆け込んできた。まあ、こういう事態だから、次の電車はいつ来るかわからない。ようやく間に合ったとばかりに、あたりを見回し空いてる席を見つけて座ると、さして長くもない足を目一杯広げたのだった。足元はと見ると、立派そうな革製のスニーカー。やっぱりね、と思った。
向かいの席には若いカップルの姿があった。まだ10代のように見える女の子は目を閉じており、それよりも少し年上のように見える男の子が伸ばした腕をしっかり両方の手のひらで握りしめている。一方、隣では小さな男の子が若い母親にもたれるようにして眠っている。いずれも安心しきっているようだ。しばらくして目を開けた女の子は、今度は、男の子の腕を抱きしめるように抱えこんだ。微笑ましくて、なんとなく温かな気持ちになった。
車両が地上に出ると、窓が白くなって外は全く見えないが、乗客はさらに少なくなった。間隔調整はなおも頻繁に行われ、速度も遅くなる。これらの状況をその都度知らせるアナウンスが面白かった。うんと若い女性のようだったけれど、随分さっぱりした言い方で好ましかった。いつも耳にする妙に慣れたような、慇懃な調子がないのだ。ただ、「……して、申し訳ありません」という時も同じような調子で、全く申し訳ない感じがしないのがおかしかった(それは、彼女が意図したことだったかどうか)。
顔を上げると向かいの席には、まだあの若いカップルが座ったままだった。どこまで行くのだろう。私の降りる駅は、そろそろ近づいてきた。傘を忘れないようにしなくては、と言い聞かせて立ち上がった。すると、向かいのカップルも、立ち上がったのだった。そして、同じ駅で降りた。彼らは相変わらず手を繋いでいた。改札を出ると、私は左へ、彼らは右へ歩いて行った、やっぱり手を握りしめたままだった。
その日は、電車も遅延や運休が相次いだ。慣れてないせいか、ほんの少し積もるくらいの雪でも、影響するのだ(しかも、相互乗り入れが進んだせいで、影響が大きい。便利さは、それだけを手に入れようとしてもうまくいかないようだ)。いざ走り出しても、前を行く電車との間隔調整が頻繁に行われた。駅を降りてからも、シャーベット状の雪の上を歩くと、危うくころびそうになるのをようやく踏ん張るのだった(幸い、一度も尻餅をつくことはなかった)。その脇を、何人かの若い女性が追い抜いていった。おかげで、無傷で生還はしたものの、赤坂見附から家にたどり着くまで、通常の倍ほども時間がかかってしまった。
翌日は、もう雪は止んでいたが、家の前庭には薄く雪が積もっており、民家の屋根も白くなっていたが美しかった。でも、これにつられて外出などしてはいけない。そう思い定めて、その日は昼はイングリッシュブレックファースト(⁈)にして、ビールを片手に雪景色を楽しむようにしようと決めたのだった。もはや昼酒を楽しんだとしても、幸か不幸か、誰も文句を言わない。大した害もないだろう。しばらくして、外に目をやると、珍しく小鳥が何羽も電線に止まっていた。彼らも、久しぶりの雪景色を楽しんでいたのかもしれない。
*
その雪の日のことはすっかり忘れていたが、ある時に思い出した。スーパーマーケットで買い物をしていたら、どこかで見たような若いカップルを見かけたのだった。同じように女は、男の手をしっかり握り締めていた。ああ、あの時の……。
それからも、時々見かけることがあった。そして、ふっつりと見かけなくなった。まあ、不思議なことでもなんでもない。そんなに大きな街ではないが、住んでいる人はたくさんいるし、スーパーだっていくつかある。個人商店だってあるし、コンビニはなおさらだ。出くわさないことは、不思議でもなんでもない。むしろ、見かけたことが珍しいことだったのだろう。
*
あれからどれほどの時が経ったものか。ずいぶん長い時間のような気がするけれど、案外短いのかもしれないが。また、あのカップルを見かけたのだ。
スーパーに車を停めて、近くの図書館に行こうとして歩いていたら、出くわした。これまでと同じように女は男の手をしっかり握り締めていたが、もう一方の手には赤ん坊を乗せたベビーカーのハンドルを握っていた。反対側には、男の手がやっぱりハンドルを握っていた。ああ、1年も経てば、若いカップルには赤ちゃんが生まれたとしてもおかしくないのだ。なんだか、心の中にほの温かいものが灯るような気がした。お幸せに、とそっと呟いた。それから、図書館で本を返した。
*
そしてまた、時が経ったある日のこと。
冬の寒い日が続いた後の、たまたま温かい日のこと。気晴らしにと思って、ドライブに出かけることにした。それにしても、この辺りの冬はいい天気のことが多い、しかもたいてい文字どおりの快晴だ。私が育った地方の、どんよりとした雲に覆われて寒々しい眺めとは大違いだ。それでも、風はさすがにまだ冷たかったので、幌は下ろしたままにした。
途中で、広い駐車場の向こうに、ガラス張りの大きな窓のあるドライブインが目に入った。ここで、何か軽く食べることにしよう。散歩中には、何か食べたくなる。足じゃなくて、車で歩いてでも、だ。美味しいものを食べて、お腹が満たされると、いくらかでも気分が良くなる。今度はお弁当を持って出かけることにしてみようか。ささやかなピクニックのようで、いいかもしれない。幸い器はいくつか残っている。そんなことを考えながら車から出ると、冷たい風が吹き付けた。いくら暖冬だと言い、日差しは温かいと言っても、まだ冬なのだ。早く店に入ろうと、歩を早めた。
「いらっしゃいませ」
というウエートレスの声に迎えられて入ると、もう昼時を過ぎていたせいか、ガラガラで客はほとんどいないようだった。
「どうぞこちらへ」
白いシャツの上にブルーのエプロンをかけたウエートレスに導かれて、席に着いた。
「何になさいますか。もうお決まりですか」
「ごめんなさい、も少し待ってくれませんか」
顔を上げると、ウエートレスは髪を頭の上にまとめていた。どこかで見た気がした。でも、思い出せない。気になったが、まさか、訊くわけにはいかない。
「どこかで、お会いしましたか?」
気味が悪いと思われるのがせいぜいだ。
それから不意に、思い出した、ような気がした。ずいぶん前に電車の中で会い、そのあとで街でも見かけた女性ではないか。へえ、こんな所で働いているのか。ちょっと疲れているようにも見えるけれど、元気で働いていてよかった。夫もあの赤ん坊も元気にしているだろうか。きっと仲睦まじく暮らしているのに違いない。もしかしたら、妹が生まれたりしているのかも(弟かもしれないが)。
なぜだかそんなことを思って、ひとり微笑んだ。食事を済ませて、店を出ると車に乗り込んだ。エンジンをかけると、幌をあげようと思った。なんとなく、気分がよかったのだ。そして、冷たい風を受けながら、住み慣れた街に戻った。気持ちは温かいままだった。
その時に何を食べたのだったかは、よく覚えていないが、サンドイッチ、だったかもしれない。そうそう、表面だけをこんがりと焼いた3枚ではなく、2枚のパンの間にハムとチキン、それにレタスときゅうり、そしてマヨネーズを挟んだだけの少し簡略化したクラブハウス・サンドだった。そんなに悪くない味だった。一緒に頼んだノンアルコール・ビールはうまくはなかったけれど(なぜなのだろうね。登場してから、ずいぶん経つし、その間技術も進んだろうに)。
*
それからまた、時が過ぎた。
日曜の朝、散歩の途中にあった公園で休むことにした。ベンチに腰掛けてあたりを見ていると、3人連れの親子を見かけた。こちらに向かって歩いてくる。あ、どこかで見たことがある。父親の方を見ると、やっぱりそうだった。あの雪の日、電車で見かけたカップルの男の子に違いなかった(もはや、立派な大人の男のようだった)。よちよち歩きの男の子は、あの時の赤ん坊に違いない。思わず、またニンマリとした。ああ、少し大きくなったんだな。時の経つのは早い。うかうかしていると、あっという間だ。
人は歳をとるが
悪いことばかりじゃない
不意に楽しい思い出に出会うことがあり
素敵なことだ
そうしたことがたまにでもあれば
生きていける
生き続けることができる
前へと進むエネルギーを手に入れることができるのだ
嬉しい気分になって、もう一度連れ立って歩く3人を見た。すぐ近くまでやってきた。見たことのある顔に、見たことがない顔が混じっているような気がした。
さらに、彼らが楽しそうに話しながら、近づく。やっぱり、何かが違っているようだった。で、もう一度、目を凝らして見直した。
あ、女の顔が違う。よく似てはいるが、あのとき見た顔とは違っていた。もう少し若いようだった。
彼らは周りを気にすることなく、なんの屈託もないように笑いながら、私の前を通り過ぎて行った。相変わらず、まさに「幸福」という言葉がぴったりのようだった。
*
時々、ドライブインのウエートレスのことを思い出す。あの3人の、幸せを絵に描いたような家族とすれ違った時のことも。
そのあとで私は、自身のこれまでのことに思いを巡らせるのだ。それが、とりもなおさず、私の人生だ(もし、そう呼べるとしてのことだが)。そして、私は決まってモーツァルトのレコードを取り出す。ターンテーブルの上に乗せ、そっと針を落とすのだ。それから、気持ちがどこかへ沈んでいくのを感じる。しばらくその感情に身を任せた後は、音楽に集中する。と、不意に現実に引き戻される時がある。そして、声に出さずに呟くのだ。
今こそがさよならを告げるべきとき
その思いが楽しいものであれ
あるいは苦しいものであれ
さらには願いに
それが甘いものであれ
苦いものであれ
さよならだけが
人生 なのだから
*
今度はやや短い、あとがき
反応も反響もないのは、相変わらずですが、まあ練習ということも同じ。ということで、また掲載することにしました、4週連続企画特別増刊号第3弾。ブログに書いた、あの雪の日に見たことをもとにしたもの。前書きにも書いたように、一部を流用しながら(まあ、練習ですから)。
今度は、ちょっとアニエス・ヴァルダふう、かも……(?)。
予告:次週は、いよいよ最終週。
2024.02.22
読んでくれて、どうもありがとう。
おわりにお願い:ご意見と感想をいただけたなら助かります。
4週連続特別企画増刊号・第2弾 FANTASY 7 「2度鳴る電話」
2度鳴る電話
私は、電話が苦手だ。かけるのはもちろん、受けることもだ。できることなら避けたい、と思う。だから、メールでも済ませることのできる場合は、たいていメールの方を選ぶ(と言って、メールが好きなわけじゃないけれど)。でも、夫は私に輪をかけて電話が嫌いだ。というより、憎んでいると言ってもいいくらいかもしれない。たぶん、出るまで相手の状況が全くわからないことが、気分を重くするのだ。
*
ある朝、電話が鳴った。夫はいつものように、
「出なくていいよ」
と、言う。まあたいていのものは、そうしたものに違いないのだけれど。中には大事な電話もあるかもしれない。いずれにしても、かかってきたものは仕方がない。出ることにした。
「あなたの実家からかもしれないわよ」
と言いながら。ソファから立とうとしたら、すぐに切れてしまった。ああ、やっぱり間違い電話だったんだ、と思った。
「ほらね。そうしたものさ」
夫が、わかっただろう、と言わんばかりに呟いた。
別のある日の午後に、電話が鳴った。夫はいなかった。出ようとして受話器の方へ歩いて行ったら、やっぱりすぐに切れた。こうしたことが、不規則に何日か続いた。
また別のある日、電話が鳴った。今度はお昼近くだった。ソファに座って、新聞を見ていた夫に声をかけた。
「出てみなさいよ」
台所から、私は声をかけた。
「君のお母さんからかもしれないよ」
夫が応じた。電話に出たくないのだ。出たら、まあふつうに受け答えできるようなのに。すると、電話の呼び出し音がやんだ。
「母はもう、電話をかけることはできないわ」
今度は、リビングの方まで出て行って、言った。
「ああ。そうだった」
夫は、こともなげに言う。
私の母は今、ここからはるか遠く離れた小さな町の施設で過ごしている。若いうちから年の離れた父親の介護のために、何年も病院で寝泊まりしていたこともあってのことだろう、骨粗鬆となり、やがて腰の上の骨を骨折してぐずぐずの状態になった部分をコルセットで固め、長距離を移動することができなくなっていた。それでも、ずっと携帯電話で話すことができていた。それが、コロナ感染症の流行後は、面会がままならなくなり、私や妹でさえも部屋に入ることも叶わなくなってしまった。そして、さらに足を骨折した。しかも、2度も。
それ以来、自分で電話を取ることができなくなった。もちろん、かけることはできない。さらに悪いことに、電話で話すことにすっかり関心をなくしてしまったようなのだ。以前は、電話で話していると、同じ話を繰り返すことが多かったけれど、なかなか切ろうとしなかった。それが今では、施設のスタッフに取ってもらっても、少し話すと、
「ありがとう。みなさんによろしくね」
と言って、すぐに切ってしまう。
夫は不在がちだ。実家の両親の世話をするためだ。私は、そのことはあまり気にしていない、というか気にならない。
夫の義父は年の割には元気で、よく飲み、よく食べる。自分のことは、たいてい自分でできる。パソコンも携帯電話も、使いこなしている。電話嫌いの夫よりも、よほど上手かもしれない。ただ、家の中のこと、家事のうちでも調理や掃除は全くできない。というか、ほとんどやらない。全く関心がないようなのだ。
一方、義母は手すりを伝いながらようやく歩くことができるくらい。それも、短い距離だ。以前は、街に出かけるのが好きだった。おしゃれをして、買い物や食事に出かけることが楽しみだった。それはいまでも変わらないけれど、もはやなかなかままならない。それに、記憶力のこともある。この二つが、コロナ禍以降急速に進んだ。でも、私を見ると、にっこり笑うときがある。邪気のない童女のような笑顔だ。いっしょに食事をしていると、何かと世話を焼きたがる。ただ、それが全くのマイペース、周囲の動きとは関係なしなのだ。何か言われても、おかまい無し。義父は、昔主婦として取り仕切っていた時のことを思い出してのことだろうと言うのだが、そのことを夫に指摘されると、一瞬無表情になり、それから、私の方を見ると、目を大きく開けてニンマリとしてみせる。
それで、夫はほぼ実家の方にいることが多くなった。フリーランスのカメラマンだ(だった、と言う方が適切かもしれない。もう半分リタイヤしたようなものだ)。だから、時間は自由になるのだ。私は、会社勤めだけれど、職種の関係で在宅ワークが認められているので、平日に外に出るのはむづかしいものの、やっぱり家にいることが多い。
例の電話は、いろいろな時間にかかってくる。そして、取ろうとしたらすぐに切れる。そうしたことが続くうちに、気づくことがあった。呼び出し音は、きっかり2回で切れるのだ。これはふつうの、よくある間違い電話じゃない。
また、電話が鳴った。
「切れる前に出てちょうだい」
「君が出ればいいだろう」
夫がそういう間に、また切れた。やっぱり2回だ。
「ほら、また2回よ」
「だから、さっさと出ればいいじゃないか?」
「いやよ」
「どうしてさ?」
「だって、きみがわるいもの」
「出てみなきゃわからないよ」
「だったら、あなたが出なさいよ」
「知ってるだろ。電話は苦手なんだよ」
時々、そんなやりとりを繰り返すことが続いた。
「ほら、まただわ。きっとあの電話よ、出てみてよ」
「そんなに気になるなら、君が出ればいいだろ?」
「だから、言ったでしょう」
今度は、つい咎めるような口調になった。すると、夫は、読んでいた新聞をソファに放ると、無言のまま2階の自分の部屋に行ってしまった。
自分が、なんだかすごく惨めな気がした。夫がいなくなった場所に目をやると、読みさしの新聞や雑誌が乱雑に積み上げられていた。
「ねえ。これなんとかしなさいよ!」
私は、たまらず声を荒げて、叫んだのだった。
「ねえ、ねえってば!降りて来なさいよ!」
何度か言ううちに、夫がようやく降りて来た。
「どうしたのさ?」
いかにも面倒、というような言い方だった。
「見てごらんなさいよ」
「えっ?」
「えっ、じゃないでしょ」
「だから、どうしたって…」
「なんで片付けられないの」
「ああ、そのことか」
「そうよ。いったい、何度言えばわかるのよ」
「ああ、悪かったよ」
「じゃあ、片付けなさいよ」
「あとでちゃんとやるよ」
「今すぐに!」
夫は、無言のまま、くるりと背を向けると、そのまま出て行った。
*
妻とちょっとした諍いがあったせいで気分がむしゃくしゃして、行く先も決めずに車で出てきた。車を走らせている間、先ほどのことが思い返されて、気分はささくれ立つばかりるばかりで、いっこうに収まらなかった。
それでもそのまま走り続けると、道路沿いに1軒、店らしきものが見えた。カフェだろうか、それともレストランか。
広い駐車場に車を向けると、ガラス張りの大きな窓の、瀟洒な建物が目に入った。ここで、何か軽く食べることにしよう。お腹が満たされると、気分も落ち着くだろう。ともかく、ざわついた気持ちをなだめる必要があった。
「いらっしゃいませ」
というウエートレスのあかるい声に迎えられて入ると、中はそれほど広くはなかった。ゆっくりとあたりを眺めると、けっこうお客が入っていたが、奥の席が空いているようだった。
「どうぞこちらへ」
白いシャツの上にブルーのエプロンをかけたウエートレスに導かれて、席に着いた。
「何になさいますか?」
「あ、はい。も少し待ってくれませんか?」
改めてみると、そのウエートレスは髪をポニーテールに纏めて、その上から青いバンダナを巻いていた。
「はい。わかりました。それでは、お決まりになりましたら、声をかけてくださいね」
そして、席から離れていった。
メニューを手にしたものの、さほどお腹が減っているわけじゃなかった。それでも何か選ばなくてはいけないので、いちおうは見たものの、これはというものはなかった。ランチメニューと大書きされたメニューには、オムライスの写真が載っていた。オムライスか、久しぶりだと思って、これに決めかけたけれど、そこには今やすっかり定番となったようなチキンライスの上にオムレツを乗せたものだった。他には見当たらなかった。これを発明した伊丹十三は敬愛するけれど、オムライスはやっぱり少し焦げ目のついた薄い卵で巻かれた昔風のものが好ましい。ソースは、ただのケチャップよりはもう一手間かかったものが好きだけれど、ホワイトソース風のものは御免被りたい。
ないとなれば、なおさら食べたい気がした。そんなわけで、もう一つ、別のメニューがあったので開いていくと、平たいスパニッシュオムレツ風のものが目についた。フリッタータ(イタリアン・オムレツ)とある。あとで足した、手書きのかっこ書きがおかしかった。ちょっと気分がほぐれたような気がした。よし、これにしよう。それからサラダと飲み物があれればいい。
「お願いします」
僕は、声をかけた。
「お決まりですか」
例のウエートレスがやってきた。
「ええ。これとこれとノンアルコールの白ワインをください」
「承知いたしました」
と言うと、注文した料理を繰り返した。
運ばれてきたフリッタータは、見慣れたスペイン風のトルティーヤとは違って、片面焼きで表面はとろりとした黄味が残っているようだった。さっそく、取り掛かることにした。冷めたら美味しくない。この頃はこうした洋風の食べ物であっても、たいていのものは箸で食べる。その方が断然楽だし、口に触る時の感触もいい。でも、なければ仕方がないし、わざわざ頼むほどでもない。ナイフとフォークで切り分けて、食べた。シンプルなサラダも、たまねぎがたっぷり入ったドレッシングがうまかった。
食べ終わると、泡立つようだった気持ちも、少し落ち着いた。妻の気持ちも、わかるような気がした。
「もう、おすみですか。それじゃあ、お皿を下げますね」
ウエートレスがやってきて、言った。
「ええ。お願いします」
「お飲み物はいいですか?」
「ありがとう。けっこうです」
「承知しました」
「ところで、フリッタータは片面焼きなんですね?」
「ええ。シェフの好みのようです。両面焼きの方が良かったですか?」
「いやいや。そういうわけじゃないけれど」
「もし両面焼きの方が良ければ、今度はどうぞおっしゃってくださいね」
「ああ。どうもありがとう。ごちそうさまでした」
店を出ると深呼吸をして、車に乗り込み、キーを挿してひねった。
でも、なんの音もしない。うんともすんとも言わず、なんの音も立てず、全く反応しなかった。エンジンがかからないのだ。そういえば、以前から不調だった。アイドリング中にエンジンの回転数が不安定な時が時々あったし、走行中でも、急に回転数が落ちることがあったことを思い出した。何しろ、古い車なのだ。それで仕方がないから、JAFに来てもらうことにした。それから、一瞬躊躇したが、妻に電話をした。
妻は、すぐに出た。
「……」
「もしもし。どちら様でしょうか」
事務的で不安げな声だった。
「もしもし、僕だけど」
「ああ、あなたなのね」
低く、抑揚のない声で言った。
「ああ。さっきは悪かったよ」
「……」
「もしもし。さっきはごめん」
「ええ。私も」
「この頃は、気持ちが落ち着かないんだよ」
「そうね」
「ああ」
「とにかく、できるだけ早く戻って来てちょうだい」
「それがね、……」
「どうしたの。もう怒っていないわ」
少し落ち着いたようだった。
「ああ。でも戻れないんだよ」
「えっ。何かあったの?」
「エンジンがかからないんだ」
「えっ、それは大変だわ」
「ちょっと不調だったからね」
「大丈夫?」
「今、JAFを待っているとこなんだよ」
「へえ、そうなのね」
「ああ」
「とにかく待ってるわ」
少し、ハリのある声に戻ったようだった。
「うん」
少しホッとして、電話を切った。
仕方がないので、また店に戻ることにした。もうお客の姿はほとんどない。今度はJAF
の車を見逃さないよう外がよく見えるように、窓際の席に座ると、例のウエートレスがやってきて、不思議そうな顔をして見た。
「ああ。エンジンがかからないんだ」
「あら!それは大変。大丈夫ですか?」
「ああ。JAFを呼んだから、来るまで待たせてもらいたいんだけど、ここでいいかな」
「はい。ええ、どうぞ。大変でしたね」
「それじゃあ、コーヒーをもらおうかな」
「かしこまりました」
「コーヒーのおかわりはいかがですか」
「ありがとう」
「コーヒーをお持ちしましょうか」
「頼みます」
「おかわりは?」
「いや、もうけっこう。どうもありがとう」
なぜ、イラついてばかりなのか?この頃は、特にひどくなってきたようだ。なぜ、読みさしのものをそのままにする?何杯もコーヒーを飲んでいるあいだ中、自問自答した。
たぶん、いつの間にか、ストレスが溜まっているんだ。ずっと実家の両親の側にいて、時々世話をする。両親も、仕方がないとはいえ、楽しげな様子の時はほとんどない。特に負担がかかることもしていない代わりに、どこにも出かけることがない。仕事もしていない。それらが、いつのまにか不満となり、次第にたまっていたのが、爆発することなく、少しずつ放出されていたのだろう。そして、ある時に噴火した。そんな気がしたのだった。
それから数時間ほど待っていたら、JAFの車が見えた。ようやく来てくれた。
回転数が安定しなかったことを含めて、これまでの経緯を説明した。いろいろとみてくれたのだけれど、結論は、
「ええっt、ガス欠ですね」
「(えっ……)」
ガソリンを補給し、タブレット端末を見ながら作業を説明してくれた。そして言った。
「ここにサインをお願いします」
僕がサインをすると、彼は「気をつけてくださいね」と声をかけると、何事もなかったかのように、来た道を引き返していった。
やれやれ。なんとも情けない気持ちになった。それから、気を取り直して、また妻に電話をかけた。
「もしもし。あら、大丈夫だった?」
もうすっかり、元に戻っているようだった。
「ああ」
こちらは、すっかり力をなくしてしまっていた。
「どうだったの?」
「実は、えーっと……」
「どうしたの?」
「うーん、……」
「だから、何があったの?」
「ガス欠だった」
「えっ⁉︎」
妻が笑い出し、そして、二人して大笑いした。
それで気分一新とはいかないけれど、ともあれガス欠は解消した。車は、動くようになった。妻も笑った。今のところは、何も問題はなくなったような気がした。それから、来た時よりもゆっくりと車を走らせ、自分の住む街へ戻った。
家に着いた時はもう暗くなっていたが、電気は消えていた。どうしたのだろう。はやる気持ちを抑え込もうと深呼吸をして家の中に入った。リビングルームの電気をつけると、妻がうつ伏せになっていた。きっと疲れたのだ。その下からは、何やらメモのようなものがのぞいていた。毛布をかけると、そのままにしておいた。
それから2階へ上がると、キース・ジャレットのCDをかけた。まず、「スティル・ライブ」。彼がまだ元気だった頃のものだ。この時は、前ヘ前へと進むエネルギーに満ちてる。1枚目が終わると、今度は、病を得て束の間立ち直った時に自宅で録音されたという、「メロディ・アット・ナイト・ウィズ・ユー」を。こちらは音の一つ一つが慈しむかのように鳴らされ、バラバラになる寸前にかろうじて踏みとどまっているかのようだ。
人は歳をとるのだ
病気もする
昔のままではいられない
寂しいことだ
いや 寂しくはない
受け入れて 成熟していけばいいことだ
そうかも知れない
ただ 人は変われるものなのか
*
それから、もうあの電話はかかってこなくなった。どういうわけか、ピタリと止んだのだ。
小競り合いは相変わらずだけれど、少なくとも、あの電話をめぐっての争いはなくなった。
*
ふたたび平穏な時間が訪れて、時々、私は母のことを思う。
この街から遠く離れた小さな室で ひっそり眠る
もはやひとりでは 歩くこともできなくなってしまった
灰色の細胞には 記憶も長くは留まらなくなってしまった
あなたは いったい 何を抱えて眠っているのだろう
もしかしたら 寂しさに耐えて
孤独であることを 閉じ込めようとしたのだろうか
それまでの記憶を 手放そうとして
現在を諦めたのかもしれない ような気がした
電話をかけることが できなくなり
取ることさえも 叶わなくなってしまった
それでも不意に思い出して ボタンを押したり
それから不安になり 切るのだろうか
あるいはまた 電話を目にして なにか不思議なものを見た気がして
適当にボタンを押したのだろうか
*
それにしても……。
あの電話は、いったい、誰からのものだったのだろう。
誰が、何のために、何回もかけてきたのだろう。
しかも、呼び出し音はきっかり2回鳴るだけで切れた。
それとも、白昼夢のようなものだったのだろうか。
それから少し落ち着いて、冷静さを取り戻すと、いったい、私は何をしているのだろう、
と思ったりする。
*
ちょっと長めのあとがき
相変わらず反応も反響もありませんが、まあ練習だし。と思って、第2弾を掲載することにしました。ちょっと今までとは違った試みだし、もう少し推敲するために、順番を変えようかとも思ったのですが。まあ、どうせ同じことだし、勢いを大事にしようと思い定めたのでした(また、書き直せばいいことだ)。
ハッピーエンド症候群から少しだけでも逃れるべく、ちょっと変わった味をと思って、カーヴァーのものを思い出したのでしたが……。
それにしても、世の中には才人がたくさんいるものですねえ。朝刊の下の欄、本の宣伝を眺めていると、知らないアイドルグループの人かと思うような人が、小説や絵を描いて評判を集める。出版もされる。単なる余技ではなく、立派に世間に通用する仕事のようだ。まあ、多才な人というのは昔からいましたね。例えば音楽に限らず美術論も相撲論も書いた人がいたし、文学から政治まで縦横無尽に論じるほか、歌い継がれる童謡の歌詞も書いた。そのほかにも、何人かのイラストレーターたちは、その枠に収まらず、様々な分野で活躍した。そして無知であることを自覚して、本物となることの重要さを身をもって教えたあの才人も。すごいですねえ。羨ましいなあ。せめて小才でもと思ったりもするけれど、ま、できることをやり続けるしかありませんね。
捨てる神あれば拾う神あり、とはいかないものかとも思った。けれど、すぐに忘れることにしました。なぜなら、その理由は、(もちろん、自身の能力ということもありますが)それより何より今の世界の状況を見たなら、明らかのようですから。
2024.02.15
読んでくれて、どうもありがとう。
おわりにお願い:ご意見と感想をいただけたなら助かります。
臨時増刊号 FANTASY 6 海辺のランチ
まえがき
最初は、練習のためにスタインベックの「朝めし」をもとに自分だったらこうするということで書いてみようと思った(いわゆる翻案。いや、というよりも訳し直しか)。絵本もうまくいかないようだし。でも、開高の本を読んでいたら、「書きたいことを書きたいときに書きたいように書く」のがよろしいとあったので、なるほどと思い、方針を変更して、ひとまず出来上がったのがこれなのですが。
海辺のランチ
さて、いつのことだったか。今となってはもう、よくは思い出せないが、そろそろ遠出のドライブは無理だろうと思って、最後のよすがに小さな岬まで行ってみようと思い立った。広がる海を、うんと近くで見たかったのだ。で、日は少しずつ長くなっているとはいうもののまだ冬の、たまにほんの少しだけ春が顔を見せるような頃のある晴れた日の朝、出かけることにした。
出発したのは、まだ日が昇り切らず山の端あたりがオレンジ色に染まる頃だったが、途中でゆっくりしたせいもあって、岬に着いたのはもう昼に近かった。近所に、食堂らしきものは見当たらない。それどころか、人家さえも見えない。まだ温かいとまではいかず、時折吹いてくる風は冷たかった。いそれでも、遠くまで広がる海、たっぷりの水の景色を満喫した。海面は濃い青緑色で、おだやかで、春の陽の光を受けてきらめいていた。草の上に腰を下ろして、目の前の光景を見つめていると、飽きることがなかった。それでも、風が吹き始めると少し冷たかった。ちょうどおなかもすいてきたので、そろそろ引き上げることにしようと思った。
帰りは、来た道と違った、さらに海沿いの道を通ることにした。少し細くて、しかも曲がりくねっているようだったけれど、まあ昼間のことだし、対向車も少なそうだ。ゆっくり行けば、問題はないだろう。それに、来た時の道沿いには、ここからしばらくは食堂もなかったようだった。まあ、これはこの道も同じことだろうけれど。窓を開け放ち、時折海に目をやりながら走った。風は少し肌寒かったが、むしろ気持ちが引き締まるようで心地よかった。ただ、いよいよおなかが減ってきたのには参った。
遠くの方に、煙が立ち上っているのが目に入った。ああ、あの辺りには、何かあるかもしれない。悪くても、聞いてみることくらいはできるだろう。それで、その煙に導かれるように、急ぐような気分で走らせたのだった。煙が少しばかり先に見えるところまで行くと、路肩に車を寄せて、エンジンを切った。
煙の元は、バーベキューか何かの火のようだった。車を降りると、肉の焼けた匂いが、かすかに鼻腔を刺激した。香ばしく、甘い香り。思わず、目を閉じて吸い込んだ。と、ぐーっとおなかがなった。
キャンプかピクニックかをしていたのだろうか。こんな時期にも、と驚いたが、人影はどこにも見当たらなかった。
しばらく眺めていると、一人の女性が現れ、近寄って来た。まだ女の子と呼びたいくらいの歳だ。ぴったりと体に沿ったニットのセーターと重ねたカーディガンの下に、若い女性らしい柔らかな曲線が見て取れた。艶やかで、長い髪を後ろで縛っていた。家の近所では見ることのない、まだ若いにも関わらずどこか洗練された感じがする女の子だった(今時の若者は皆、こうしたものかもしれない)。ただ、食事の時間は、すでにもう終わっているようだった。
「やあ」
声をかけると、その女の子も、
「こんにちは」
と、見かけによらず気さくに応じ、そして訊いてきた。
「どうしたの?」
「どこか食べるところを知らないかい?」
「そうねえ。もう1時間半ほども行かなきゃダメかも」
「うーむ」
「おなか、空いてるの?」
「まあね」
同時に、またぐーとおなかが鳴った。
「ふーん」
「ちょっとぼんやりしすぎた。久しぶりに、海を見ていたんだ」
「あら残念。でも、かわいい車ね。色もシックだわ」
「ああ、持ち主同様、だいぶくたびれているけどね。気に入っているんだよ。塗り替えたんだ」
「へえ。そうなのね。元は何色?」
「赤だった。若気の至りさ」
「ふーん。赤もいいけど、グレイの方が上品な感じがして、好きだわ。あ、ごめんさい。おなか減っているのよね。ちょっと見てくるわ」
そう言うと、彼女は身を翻した。
しばらくして戻って来ると、彼女はこう言ったのだ。
「パンとハムのサンドイッチならできそうだけど。残念ながら、野菜はほとんどなくなっていたわ」
僕は嬉しくなって、思わず訊いた。
「え?なにか食べられるの?」
「ええ。できるのは、たぶんサンドイッチくらいね」
「ありがたい。助かるよ」
「それに、コーヒーもあるわよ」
「いいね。ぜひ、お願いできたらありがたい」
「ええ。それでは、こちらにどうぞ。ついていらっしゃいな」
それで、やさしい言葉に甘えることにした。ついて行った先には、バーベキュー用のスタンドの残り火が目に入り、肉の焦げた強い匂いが鼻をついた。それから改めてあたりを見渡すと、女の子よりも少し年上らしい男が二人と同じように若い女性が一人、車のこちら側で待っていた。いずれ劣らず都会の若者らしい洗練された様子だったけれど、不思議なものを見るような目で、こちらを見ていた。
「やあ、どうした?」
若い男のうちの一人が訊いた。
「おじいさんが一人、飢えかけている」
女の子が答える。
「そうなのかい?」
「ああ、悪いね」、
「何も食べてないのかい?」
男が、ぶっきらぼうに訊いた。
「いや、朝早くにコーヒーとトーストを一枚だけ」
「それきり?」
「ああ。ちょっと急いでいたものだからね」
「ふん。そりゃ大変だ」
「もうあんまり残ってないけど。まあ残りものでよければ、どうぞ」
男のうちの一人が、保冷庫を開けながら、言った。
「おじいさん、ラッキーだったね。ハムが少々残っていたよ。あ、レタスも隠れている。それから、バゲットもたぶんまだ3分の1本ほどあったはずだ」
「ああ、それはありがたい」
「じゃあ、カスクートね」
「そうだね」
それから、男はバゲットを軽く炙り、手際よくおなかを裂くと、そこにレタスとハムを挟んだところに、マスタードとマヨネーズを合わせて乗せた。
「さあ、できたよ。どうぞ、召し上がれ」
「ありがとう。お、うまい」
「でしょう?」
「彼はシェフなのよ」
「まだ、見習いのようなものだけどね」
恥ずかしながら、あっという間に平らげた。
「ああ、おいしかった」
心の底から、そう言った。
「それは何より。よかった」
彼らが声を揃えて、笑った。
「コーヒーは、僕が淹れることにしようか」
「そうね。ここも、プロに任せるのがいいわね」
二人の女がまた、声を揃えた。
「そうなのかい?」
「まあね。僕らは、お店がご近所同士なのさ」
あいかわらず、ぶっきらぼうな口調のままだ。
「ふーん。そうなんだ」
「久しぶりにみんなの休みが揃ったので、のんびりしようとやってきたんだよ」
取り繕うところのない口の利き方が、むしろ親密な気がして、心地よかった。
「へえ。羨ましいね」
「そうかい。まあ、悪くはないよ」
「どうも、ごちそうさま。ほんとにおいしかった。ありがとう。すっかりお世話になったね」
「いえいえ。どういたしまして。喜んでもらえて、嬉しいよ」
それから少しばかり話をした後、遅くならないうちに、と思った。
「じゃあ、そろそろ行くよ。どうもありがとう。本当に助かった」
「それはよかった」
「僕の街に来たら、ぜひ寄ってください」
「ああ。そうしますよ」
「会えてよかった」
「楽しかったわ」
「面白い体験だった」
「とっても」
彼らは口々に言った。
「じゃあ、またね。どうもありがとう」
私は、名残惜しかったけれど、もういちど別れを言うと車に戻り、エンジンをかけ、アクセルに足を乗せかけた。
すると、最初の女の子が追いかけて来た。
「これをどうぞ」
と言って、ペットボトルの水とちいさな紙片を差し出してくれた。
「どうもありがとう。至れり尽くせりで、私はついているね」
「また、私たちの街に来たら、寄ってみてね。お店の名前と住所が書いてあるわ」
「ああ、ぜひそうしよう」
「ほんとに、かわいい車だわ。インテリアもウッドパネルだし。あ、ちょっと大変かも。燃料計が」
「あ。どうしよう」
「ガソリンスタンドは、ずっと先のはずよ」
「大丈夫かな」
以前、JAFに来てもらった時にガス欠が原因だったことを思い出した。
「うーん。まいったな」
それから女の子は、後ろを振り向くと、大きな声で言った。
「みんな、来てちょうだい」
「どうした?」
「ガソリンが尽きかけているかも。燃料計が0を下回っているの」
「そりゃ大変だ」
「ガソリンスタンドまでは、持たないかもな」
「そうね」
もう一人の女の子が、心配そうに言う。
「うーん。どうしたものだろう?」
「僕らの車はどう?まだたっぷりあったはずだけど?」
「ちょっと見てくる」
「どうだった?」
「ほとんど満タン」
「よかった」
「ところで、あなたの車のガソリンは?」
「ほとんど、空」
「じゃなくて」
「ああ、ごめん。ハイオク、だった」
「そうなのね」
「まいったな」
「どうしたの?」
「僕らのは、レギュラーなんだよ」
「そうか」
それから、彼らは色々と考えてくれた。結局、ガソリンスタンドに来てもらおうということになった。
「でも、電話番号は?」
「調べればわかるよ」
「うん。そうよね」
「ああ」
「よかった」
皆が、わがことのように喜んでくれた。
それから、ガソリンが運ばれてくるまで、私たちは太陽が少しずつ海に近づくにつれてその表情を変えていく、穏やかに光る海を眺めながら話をした。遠くの方には、光を反射してきらめくものが見えた。
「やっぱり、海はいいね」
「うん、時々見たくなる」
「いや、毎日見たいよ」
「ああ」
「見ることができたら、素敵だわ」
「たっぷりの水を見ると、なぜかほっとした気分になるんだ」
「そろそろ行くよ。暗くなってしまう前にね」
「そうね」
「じゃあね」
「気をつけてね」
「またね」
「どうもありがとう」
そうして、私たちは今度こそ別れた。車に戻ってドアを開け、運転席に座るとキーを差し込み、ひねった。そして、もう一度、ありがとう、さよならと言った。それは、エンジンの音に紛れて、彼らには聞こえなかったかもしれないけれど。ギアを1速に入れ、アクセルを踏むと、バックミラーに手を振る4人の姿が写ったが、やがてそれは小さくなり、すぐに見えなくなった。
それから私は、少しずつ茜色を濃くしていく空と海を時折見遣りながら、自身の迂闊さに呆れたものの、思い切って出かけてきて良かった、と束の間の幸運な経験のことをしみじみ思い返したのだ。
今ではもう遠くまで車を運転することもできそうにないが、この時のことを思い出すと、決まって胸にこみ上げるものがあり、それまでの気持ちがどうであれ、きっとほの温かくなるのを感じるのだ。
あとがき
先の開高の本というのは、「完本白いページ」だったのですが、「書く」の項目に「自分が何もしていないときは手当たり次第に乱読するが、何か書く気にかかっているときは他の本は読まないように、目にふれないようにしたくなる」とあった。
読めば、「おれはだめだ。なにもかも書かれてしまっている。おれの這いこむ余地がない」と思えてくるから、というわけです。ならば、書いた後に、参照しようと思ったのでしたが(まあ、「朝めし」が元、というのには変わりがありませんけど)。
で、いちおう出来上がったものを読み返してみると、やっぱり筋を変えずに、翻訳に徹する気持ちで、表現の仕方だけを練習するつもりで書く方がよかったかもという気もしますね(うーむ)。まあ、せっかく書いたから掲載することにして(貧乏性)、これから色々と手を入れてみようかな(まあ、練習ということには変わりがないだろう)。
お気付きの点は、なんでも、お知らせください(自分では気づかないことが多いし、何よりいけないことに、何度か推敲するうちに急に飽きてしまうのです)。
2024.02.01
読んでくれて、どうもありがとう。
おわりにお願い:ご意見と感想をいただけたなら助かります。
クリスマス特別増刊号 FANTASY 5 プチとクリスマスのおはなし
今年もいよいよ終わりの月。いい年だったという人もそうではなかった人も、皆同じです。12月といえば、クリスマス。クリスマスといえば、楽しみなのがプレゼント。でも、何もあげるものがありませんから、クリスマスのお話を書き上げることにしました。これをさしあげようと思うのですが……。と言っても、ささやかなものですから、いわばそれぞれの人にとっての本当のクリスマスプレゼントの前座、露払い、プレ・クリスマスプレゼントのようなものです。
クリスマスらしいお話を、というつもり。積もり積もったお話というわけではありませんけれど。自分の技量のことは脇に置き、おまけに脇目も振らずにというわけでもありませんが、即席でこしらえたものです。ですから、悪い人も意地悪な人も出てこない、悪いことも悲しい出来事も起きないお話です。でも、たぶん、早起きは出てきたかも。約束はできかねますが。それもこれも、最終的には、できあがるまでの出来心次第。
あの映画に倣って、5週前からの連載開始しようと思いましたが、1週前にいっぺんに(何と言っても前座ですから)。
プチとクリスマスのおはなし

「それじゃ行ってくるよ」
プチが、おばあさんに言います。またもや、なんだかウキウキしているよう。それまで降り続いていた雪混じりの雨も、今朝はもうすっかり上がったよう。家の外もなかも、お日さまのあかるい日差しがたっぷり。
「気をつけて行っておいで。今度こそ遅くならないようにね」
おばあさんが、やんわりと釘をさします。
「はい」
プチは、また言われちゃったと思いながら、言われても仕方がないこともわかっていたので、素直に答えました(何しろ、これまで何回か遅くなって心配をかけたことがあったのですから)。
「でも、慌てるんじゃないよ」
おばあさんは、プチのことを誰よりも大事に思っているのです。
「うん。わかった」
今度は、プチも元気よく、返事をします。
家を出たプチは、街へ急ぎます。家にマッチはあったかな?今日は、クリスマスイブ。クリスマスの準備をするための買い物に、出かけるのです
買うものはといえば、もう決まっています。きれいな炎の出るローソクを立てた小さなデコレーションケーキと、おばあさんへのプレゼント。晩ごはんは、とびっきりの海のご馳走をアオが届けてくれることになっています。イカもあるといいかも。あるかな。タラもあったら、きっと満足。
クリスマスツリー用のもみの木は、山に生えているものを使うから、買わなくてもいいのです。

問題は、おばあさんへのプレゼント。何にしよう?何がいいのだろう?プチは、このことをずっと考えながら歩いています。実は、これが難題で、もう何日も前から考えているのでしたが、なかなか決まらないのです。渡したときに、「なんだい」といわれるのはこまるので。その一方で、プチは、サンタさんは何をくれるのかなと、楽しみにしているのです。
そんなふうに考え事をしながら、ぼんやりと歩いていたものですから、プチは川のそばに積もっていた落ち葉の上で、つるりと足を滑らせ、転んでしまいました。地面の上で湿った落ち葉がたぶん、凍っていたのです。あっという間もなく体がはんぶん地面に着いたかと思ったら、たちまちプチは川の中へ、するりと一直線。落ちてしまったのでした。しまったと思っても、後の祭り。

いつもの浅瀬でも、このところ降り続いていた雪や雨で増水した上に、川底がつるりと滑って、なかなか立ち上がることができません。流されてゆくばかりです。はじめは、早く着けそうだと喜んでいたのですが、川のところどころに顔を出している大きな石にぶつかりそうになって、ヒヤリとします。水がかかると、顔がひんやり。そのうちに、体もひんやりしてきました。
なんとかよけると、ふーっと吐き出した息も、たちまち白くなります。プチも立ち上がれません。水もとても冷たいのです(もう、すっかり冬ですからね)。すると運よく、岸の大きな木から張り出した枝が目に入りました。プチはすかさず、えいやと飛びつきます。枝は大きくしなりましたが、大成功。なんとか無事に川から抜け出すことができました。

「ああーっ、助かった」
安心したのもつかの間、凍りつくような水をたっぷり含んだ体が冷えてきたのです。雲一つ無い快晴だというのに、冷たさがいや増すと、プチは思わずああ嫌と顔をしかめて、苦悶の表情、泣きそうになったくらい。プチは、2度、3度ぶるっと体を震わせると、また歩き始めました。と、向こうに、何か光るものが見えます。近づいてみると、それはお日様の光を浴びてピカピカ光っている大きな石で、さわると温かい。お日さまの熱をたっぷりと吸い込んで、貯め込んでいたのですね。そこで、プチは体を横にして、冷えた体を温めました。
濡れた体も乾いてあったまったプチは、すっかり元気になり、またふたたび街を目指して歩き始めました。マタタビでも目にしたよう。今度は、足元によおく注意しながら。ああ、滑らない足袋を履いてくればよかった、と思っても、これまた後の祭り(もしかして、このお話も股旅物か)。

ようやく街に着くと、あちらこちらでクリスマスの音楽が鳴っていました。お店の人が何人か、がなっています。プチは、クリスマスがきたことを嬉しく思いながら、わくわくしながらお店を見て歩きます。といっても、小さな街ですから、そんなにたくさんのお店があるというわけじゃありません。雑貨屋さん、手芸屋さん、魚屋さん、お肉屋さん、八百屋さん、お料理屋さん、お菓子屋を兼ねたパン屋さんなどがあるだけです。それから、小さいけれど本屋さんも文房具屋さんも、ちゃんとあります。プチは、あちこちを何度も行ったり来たりして、まだ迷っています(おばあさんへのプレゼントのことですよ)。
「きれいな色の毛糸はどうだろう?おばあさんは、編み物が好きだし……。毛糸玉を何色か。あ、僕は、手玉に取られている?」
「メガネが落ちないための、紐はどうかな?おばあさんは、いつも私の読書用のメガネはどこって言っているし、探す手間も時間もたいへんかも……」
「お魚は?アオが持ってきてくれるから、いらないか。イカはなくてもいいか?」
「お肉は?だしがきいたあたたかいシチューにするとおいしそう……。でもプレゼントだしなあ。うーむ」
考えは堂々巡りするばかり。
「果物は?りんごとかみかんとか、色とりどりでいいかも。でも、山の鳥たちに取られたらかなわない……。僕は、おばさんにはかなわない」

「お菓子もいいかな?ああ、だめ、ケーキがあるしなあ。でも、きれいなキャンディは、長持ちするぞ、おばあさんの長持の中に入れておけばいいかも」
「それとも、本にしようかな?おばあさんは、読書が好きだしな……。でも、小さな字を読むのは嫌だし、と言っていたしなあ。なら、絵とか写真の本は?本を選ぶのは、ほんとにむづかしい」
「あ、厚い表紙のノートもいいかも。おばあさんは、いつも日記をつけたり、スケッチを描いたりしているものね。そしたら、ペンもいる?あ、ニッキの匂いがしてきたぞ。ああ、お腹すいたあ」
と、まあこんな具合。それまでのテンポの良さもどこへやら、天保の飢饉は1883年から1887年まで3年間も続いた。このままじゃ溶けた雪の上でじゃ行き倒れになるかも。それじゃあ残念。じゃあ、何か食べなくちゃあね。じゃないと、このジャーニーもおしまいになってしまいそう。
「うーん、どうしようかなあ。何がいいのかなあ?」
プチは、まだ迷っています。どれもよさそうな気がするし、決めかけると今度は何かが足りない気がしてきて、いつまでも決まらないのです。おまけにプチの頭の中は、クリスマスイブの晩ごはんやサンタさんのことも気になって……、もうぐちゃぐちゃ、なんだかわからなくなってしまったようでした。
「困ったぞ、困ったぞう。ゾウさんはいないけど、ほんとに困ったぞう」
思わず口に出した時、道路の脇に小さな看板が置いてあるのが見えました。近づいてみると「新しいお店ができました。海のそば(でも、蕎麦はありません)」とありました。
そういえば、新しくお店ができたということを聞いていたのを思い出して、そこへ行ってみることにしました。そのお店は、少しだけはなれたところにあったのです。プチは初めてで、慣れてはいないのですけれど。街の商店街には、空いているところがなかったせいですね。

それは、海沿いの道に面したところにありました。道路に面した方には薄茶色の綿のテントが張ってあって、テーブルと椅子が出してありました。お客は、小さなぬいぐるみのクマがストローでジュースを飲んでいるだけで、ほかには誰もいませんでしたけれど。
「あれ。新しいお店というのは、カフェか何かなのかな?」
プチは、ちょっとがっかりした(コーヒーやお茶を飲むところなら、街中にもありましたからね)。それでもせっかく来たのだからと、ちゃっちゃっとお店の入り口のところまで行ってみることにしました(ミルクなら飲んでもいいかな)。

入り口の脇には大きなショウウインドウがあり、そこには色とりどりのセーターやコートなどのすてきな洋服を着たマネキンたちがいて、おばあさんと同じうすい茶のセーターの上に淡いピンクのショールを巻いたものもいました。
「なんて綺麗な色だろう」
「おばあさんに合うかな?いや、きっと似合うよね。うん」
「でも、いったい、いくらくらいするんだろうか?高いのだろうか。きっとクラクラするほど高いに違いない、か」
「買えるかな?やっぱり足りないかな?足りないだろうなあ?やっぱり帰るかなあ」
プチは、頭の中でずっと、一人で質問して自分で答えることを、何度も何度も繰り返していました。

そんなふうに、どうしようか、迷いに迷ってショウウィンドウの前に立っていたのですが、考えているうちに頭の中はシチューのように煮えている気がしましたし、そのうちに外はすっかり寒くなってきたことに気づきました。まるで、冷蔵庫のよう。雲が広がって(出るときは、雲の影ひとつ無い快晴だったというのに)寒さが増すと、プチは思わず顔をしかめて、苦悶の表情を浮かべます。海の方から、冷たい風が吹いてきたようなのでした。時折、激しく吹き付けることもありました。プチの体は、自然にぶるっと震えたくらい。思わず、涙も溢れたくらい。
「寒くなってきたぞ。さあ、早く決めないといけないぞ」
そう自分に言い聞かせるのですが、なかなか決心がつかないのでした。プチは、値踏みのことも忘れて、足踏みを始めました。でも、効果はあんまりありませんようでしたね。

するとその時、ドアが開いて、お店の中から女の人が出て来ました。頭に巻いたスカーフから長くて綺麗な髪がのぞいています(まるで、しっぽみたい)。
「ああ、またおこられるのかな」
プチは、身を固くしました。少し前に、川向こうの大きな街に出かけた時に、お魚屋さんのお兄さんに手ひどく追い払われたことを思い出したのでした。
「ほら、そんなところに立っていないで!」
女の人が、プチに言いました。
「(ああ、やっぱり)ごめんなさい」
プチの毛はもうすっかり乾いていましたけれど、まだ毛並みは乱れたままだったので、邪魔にされても仕方がないかと思ったのです(じゃあまあ、これでと、お暇すべきなのか?)。
「いったい、どうしたっていうの?」
女の人が、今度はやさしく訊きました。
「(あれっ?そういうのはぜんぜん予想していなかった)ちょっと……」
プチは、ばつが悪そうに口ごもります。
「外は寒いでしょう?この時間になると、冷たい風が吹くのよ。しようがないのよ。さ、どうぞ、中へお入りなさいな」
スカーフを尼僧のように巻いた女の人は、いっぺんにそう言いながら、ドアをはんぶん開けて、招き入れてくれました。マネキンたちも、たぶん。
「ありがとうございます」
プチはそう言うと、するりとお店の中に入りました。なんといっても、本当に寒かったのです。

「ああ、あったかい」
店の中のあたためられた空気に触れて、プチは心の底からほっとして、思わず口にしました(そりゃあ、嬉しいよね。君もこんな経験をしたことがあったかい?)。
それから、ようやく落ち着いて店内のそこかしこを見回すと、中にもいろいろな洋服が飾られていました。素敵な置物はあったけど、お着物はないようでした。
「ああ、なんて綺麗な服なんだろう。いいなあ」
「ようこそ、私の店へ。あなたは、今日のお客の第1号よ」
「えっ。(ところで、イチゴのジュースはあるのかな。好きなんだけれど。クマは何を飲んでいたんだろ?)」

しばらくして、女の人は、温かいミルクの入ったカップを運んできてくました。カップからは、湯気が立ちのぼっています。プチからはすっかり、物憂げな表情が消えました。
「さあ、どうぞ」
「あ、ありがとうございます」
「寒かったでしょう?いったい、どうしたの?」
「ええ」
「ああ、ごめんなさい。さ、どうぞお飲みなさいな。もしかして、お腹も空いてる?でも、鯨の尾の身はないけどね、あったまるわ。遠慮することはないわ」
「ありがとうございます」
と言いながら、プチはなかなか口をつけようとしません(少し前に、眠り薬の入った紅茶を飲まされたことがあったことでしたしね)。
「あら、大丈夫よ。ただのミルクだもの。そんなに熱くないはずよ」
「はい(ただだよね?お金の余裕はないはず)」
プチは、カップにそっと口を近づけて、ミルクを一口飲みました。ねこ舌にも熱すぎないちょうどいい温度でした。
「ああ、おいしい!(石井くんに出会った時は、「お、いしい!」)
「それで、どうして店の前にずっと立っていたの?こんなに寒くなったというのに」
「あのショールが綺麗だなって思って」
「そうね。確かに綺麗だわね。でもね、あなたにはどうかしらね?」
「ええ。(そんなこと言われても、おいらは知らね)」
「そう。わかっていたのね。それならいいわ。わかっていて、よかったわ」
女の人はそう言うと、次の答えを待っているのか、プチをずっと見つめています。
「おばあさんへのプレゼントをさがしていたんです」
プチはそう言うと、年をとって、ずっと病気がちでベッドの上にいることの多いおばあさんのことを話しました。おばあさんに素敵なプレゼントを見つけて、元気づけようとしていることも忘れませんでした。それから、山の上の家でずっと二人で暮らしていることも、です。
「そう、ならピッタリね」
「はい。でも(ここは奈良じゃないし、お金もない)……」
「うん?それなら何か気に入らないことがあるの?何も遠慮することはないわ。言っておしまいなさいよ」
「いえ。えーっと、ずいぶん高そうだし……(そうだとしたら、もうおしまいだし)」
プチは、恐る恐る言いました。
「うーん。たしかに、安くはないわね」
女の人がまた、こともなげにあっさりといいました。
「そうなんですね。だから、僕に買えるかなあって……」
はんぶんは自信なさげ、もうはんぶんは投げやりな気持ちで言います。
「ふーん、なるほど。そういうことね」
「いくらくらいするんですか?もし買えるのなら、足りない分は、あとで持ってきます……」
プチは、思い切って訊きました。
「ふーん。あなたは、いくら持っているの?」
プチは、テーブルの上にお小遣いを貯めて用意したお金を並べてみせました。

「あら、まあ大丈夫みたいね」
「えっ?(あらま!)」
プチは、狐につままれたような気になりました。
「ちょうど、大幅値下げをするところだったのよ」
「ほんとうに」
「きれいな色で好きなんだけれど、大人が巻くのにはちょっと小さかったのね」
「いいんですか?」
「もちろんよ。それに、なんと言っても、クリスマスだもの」
それを聞いて、プチはびっくりしましたが、すっかり嬉しくなりました。
女の人は、プチのところにショールを持ってくると、うす紙でくるみ、さらに紙で包んで箱に詰め、赤いリボンをかけて、それを綺麗な袋に入れると、もう一度緑のリボンをかけて持たせてくれました。
「はい、どうぞ。お待たせしたわね」
「ありがとうございます」
「でも、これはとっておきなさい。クリスマスの夜には、とっておきのケーキもあったほうがうれしいでしょ?」
そう言って、机の上のお金の大部分をプチの方に押しやりました。
「はい、とっても。ありがとうございます(何回目のありがとうでしょうね?)。でも、ほんとうにいいんですか?」
「もちろんだわ。でもね……」
「でも?」
「ひとつだけ条件があるの」
「はい(やっぱりね……)」
プチは、諦めなければならないのかと思って、顔を曇らせました(お店の外は、元から曇っていましたけど)。
「今度来たときには、ぜひおばあさんが巻いてみたときの感想を聞かせてね」
女の人は、そう言ったのです。ただ、それだけ。
「ええ、もちろん」
プチは、ホッとして元気な声で答えました。
「じゃあ、お行きなさい。さあ、早く持って行って、おばあさんを喜ばせてあげてちょうだい」
「はい」
「その前に、わすれずにケーキも買うのよ」
「はーい」
プチは、すっかり嬉しくなって、景気のいい返事もそこそこに、店を飛び出しました。

それから、おばあさんの待つ山の家へと走り始めました。なんと言って、おばあさんのプレゼントを手に入れることができたのですから。でも、しばらく走り続けているうちに、ケーキのことを思い出し、
「あ、いけない!」
と口に出して、くるりと向きを変えると、今度は一目散にケーキを売っているパン屋さんを目指して走り出しました(おかげで、足はもうぱんぱん)。危機一髪。危うく、ケーキを買うのを忘れるところだったのでした。
「ああ、やれやれ」
パン屋さんに着きましたが、今宵の月はまだのよう。でも、ショーウインドウの中を見ても、今度は迷いませんでした(ケーキのことですよ)。クリスマス用のケーキは、大きさが違うだけで、形は一緒だったのです。2人分の大きさのものを買うと、今度こそおばあさんの待つ山の家へと全速力で走り始めました。
と、まもなく、プチは何か軽いものにぶつかり、よろけてしまいました。

「また⁉︎」
プチは、ケーキとショールの入った袋のことを気にしながら起き上がると、痩せこけたおじいさんが、ぜえぜえと息を吐きながら、両手と膝をついていました。おまけにとても寒そうにしていて、震えているのがわかりました。
「だいじょうぶ?」
プチが心配して声をかけましたが、おじいさんは、
「うーん」
というだけで、とても辛そうです。
「さむくない?」
「うーっ、寒い」
おじいさんは、ガタガタ震えていて、止めることができないようでした。それから、ごほんと咳をしました。マフラーの1本も巻いていないのですからね。
「よっぽど寒いんだね?だって、こんなに薄い服じゃあね」
プチは、急いで緑のリボンをほどき、赤のリボンもほどくと、買ったばかりのショールをおじいさんにかけてあげました。
「これでどう?」
「ああ」
「少しはあたたかくなった?体温も高くなった?」
「ああ」
「ああよかった」

それから、プチは、おじいさんを家まで送っていきました。その家も、やっぱり着ていたものと同じくらいにみすぼらしくて、あちこちから隙間風が吹き込んでいました。それで、プチはショールを着せたままにし、ケーキもはんぶんほど分けてあげることにしました(ついでに手についた分と少し。何と言っても、クリスマスなのですから)。
「ありがとう」
おじいさんはプチの手を握ると、そう言いました。
「いいんです」
「ありがとう。このショールは?いいのかい?」
おじいいさんは、ショールの方に手をやります。
「いいんですってば。でもね、病気にならないよう、気をつけてね」
「ああ。ありがとう」
また言いました。ありがとうならミミズはハタチ、蛇は二十五で嫁に行く。だったら、ねこは幾つだろ?僕は嫁には行けない、来てもらわなくっちゃいけないほうだけど。
「じゃあ、行きますね。家で、おばあさんが待っているんです」
プチが済まなさそうに言うと、おじいさんに
「ああ。早くお行き。ありがとうね」
とうとうと言われて、とうとう去ることに。
「本当に、気をつけてね」
もう一度プチが言います。
またまた、遅れることになってしまったプチ。ショールとケーキのことを思うと、さすがに気が重くなって(荷物は軽くなっていましたが)、しばらくは、とぼとぼとあるくことしかできませんでした(あたりには、「飛び出す鹿に注意」の看板しかありませんでしたが)。
それでも、おばあさんのことをしかと思い出だすと、早く帰らなければという気持ちが湧いてきました(なんだか、前にも同じようなことがあった気がしますけど)。
それで、また全速力で走り始めたのでした。ずっと全速力で駆け続けました(プチはこねこでしたが、山で鍛えていますからね)。プチは、寒さに耐えて走ります。こういうことが、このところ絶えることがありませんが。

「ただいまあ」
家に着くと、プチはおばあさんのところへ走り寄りながら、精一杯の大きな声で言いました。
「おかえり。それにしても、お前は懲りない子だねえ」
おばあさんは、安心したような、呆れたような顔をして言いました。
「ごめんなさい(でも、おばあさんのお顔は、ああきれい」
「本当に困った子だよ。でも、無事に帰ってきてよかったよ。少し遅れたって、かまいやしないさ(もう、釜も使えやしないし)」
「……」
「いったい、どうしたというんだい?」
「ごめんなさい」
プチはしょんぼり。さっきの元気はどこへやら、やっぱり小さな声であやまるばかりです。
「何があったんだい?」
「うん」
「話してごらんよ」
おばあさんが、促します。
「うん」
プチは、生返事をするばかりで、煮えきらない。なかなか言い出すことができません。
「さあ」
「あのね、ケーキがね……、はんぶんになっちゃったんだ」
「なーんだ。そんなこと?なにか悪いことがあったのかと、心配したじゃないか」
おばあさんは、やっと安心したようでした。
「ごめんなさい」
「そんなことなら、なんでもないよ。遠くまで行ったんだから、お腹もすくってもんさ。お前が食べたいだけ、食べればいいさ」
おばあさんは、プチが帰り道で我慢できなくなって、食べてしまったと思ったようでした。
「おまけに、プレゼントがないんだよ(今晩の食事どきは前途多難。それもしかたがないけど。カマンベールはあるのかな?)。ごめんなさい」
「それも全然気にしないよ。でも、いったい何があったというんだい?」
おばあさんは、プチが貯めたお金を持ってプレゼントを買いに行ったことを知っていましたから、心配になったんですね。
プチは街へ行ってからのことを話しました。お店の女の人がお婆さんへのプレゼント用にうんと安く分けてくれたショールのこと、それを寒そうにして凍えていたおじいさんにあげたこと、ケーキもはんぶん置いてきたことを含めて、ぜんぶ話しました(といっても、森の中で滑って川に落ちてしぶきをあげた上に、あやうく流されそうになったことはしっかり省きましたけれど)。

それはいいことをしたねえ」
おばあさんは怒るどころか、それより何より、嬉しそうに言ったのでした。
「えっ?」
「お前のその優しい気持ちが、プレゼントがないより、何より嬉しいよ」
おばあさんはプチを手招きすると、力の限り抱きしめたのでした。
「悲しくないの?プレゼントがなくてもほんとに平気?」
「もちろんさ。いいに決まってる」
おばあさんはもう一度、プチをせいいっぱいの力で抱きしめました。
「それじゃあ、食事にしないかい?アオが持ってきてくれた飛び切りの魚があるよ。もう切り身になっているよ」
「うん」
それから二人は、アオのとびきりのお魚をなかよく切り分けて食べたあとは、はんぶんよりも少なくなった上につぶれかけたケーキを食べました(ケーキは、ほとんどをプチが食べたのですけどね)。たっぷりのご馳走というわけにはいかなかったのですが、いつも以上に美味しかったのは、いうまでもありません。
それからすっかり食べ終わると、今度は二人でクリスマスツリーの飾り付けをしました(もちろん、おばあさんがやり方を教え、指示を出して、相談しながらプチが飾り付けをしたのですが)。プチは、ことしはなんだか特にうれしい気持ちになったようでした。
飾り付けがすむと、二人はやすむことにしました。
「おやすみなさい」
「ああ、ゆっくりお休み。疲れただろう?あしたはクリスマスだよ」
「うん。ぐっすり寝ます」

翌朝、ぐっすり眠ったプチ(なんといっても、いろいろなことがあって、疲れていたのです)が目を覚ますと、クリスマスツリーが冬のお日さまの光を受けて、キラキラと輝いていました。家の中にもあかるい光が満ちていました。それからプチは、その下に赤と緑のリボンがかけられた箱がふたつあるのを見つけました。

いったい何だろうと思いながら、プチは大急ぎでふたつの箱を抱えると、おばあさんのところへ行きました。
「もう、起きた?」
プチは、今朝起きた不思議なことを伝えようと、声をかけました。
「おはよう、プチ。よく眠れたかい?」
「はい。おはようございます」
「おや、それは何だい?」
おばあさんが訊きました。
「うん。起きたらね、ツリーの下にあったんだ」
「何だろうねえ?」
また、訊きます。
「何だろう?」
プチもわからずに、言いました。
「プチとプチのおばあさんへ、とあるね」
「ああ、そうだね」
「開けてみるかい?」
「うん」
「開けるかい?」
「うん」
「じゃあ、開けてごらんよ」

プチが、急いで開けると、赤のリボンが結ばれていた方の箱には、あのおじいさんにあげたはずのショールが入っていました(もちろん、ちゃんと洗ってあって、アイロンもかかっているようでした。新品同様。いやもしかしたら新品なのかも)。それに、手紙も入っていました。
「おやまあ、なんて綺麗な色だろう。おまけに暖かそうだねえ」
「羽織ってみてよ」
「えっ?」
「いいから、早く羽織ってみせて」
プチがせかせます。
「いいのかねえ?」
「早くてっば」
「じゃあ。どうだい、似合っているかい?」
おばあさんは、嬉しそうです。ほんとうに気に入ったんですね。木にはいっていなくて、紙の箱に入っていたんですけどね。
「うん。とっても、おばあさんに合っているよ」
プチがそう言うと、
「そうかい。これは、お前が選んだのかい?」
と、また訊きました。
「うん。そうだよ(運んだのは、運送屋さんかもしれないけど)」
「あったかいねえ。うれしいねえ。買いに行った甲斐があったかい?」
「あったさ」
「ああ。よかったねえ」
それからおばあさんは、また、
「あったかいねえ。うれしいねえ」
と、なんども繰り返しました。

もう一つの、緑のリボンがかけられていた方の箱には、素敵な色のニットの帽子が入っていました。プチが、前から欲しかったものでした。こちらにも、手紙が入っていました。
送り主は、どうやらあのみすぼらしい格好をして、寒さに震えていたおじいさんのようでした。おじいさんは、ほんとうは山のふもとの街の町長で、クリスマスの町の人たちの様子を見るために変装して出かけたのですが、すぐにプチとぶつかってしまったのでした(それにしても、たいそうお芝居上手ですね。プチも体操が上手ですけど)。そして、女の人の手紙も入っていました。プチは、なんとなく町長の娘さんのような気がしました(ただの直感でしたけれど)。
「よかったねえ」
おばあさんが、嬉しそうに言います。
「うん」
「お前が、困っていた人に親切にしたせいだね」
「そうかな?」
と言いながら、プチも悪い気はしないみたいでした。
「でも、何かをしてもらうために、親切にするんじゃないよ」
おばあさんは、今度はまっすぐプチの顔を見て、真剣な顔をして言ったのでした。
「うん」
「わかったかい?」
「うん。わかったよ」
プチが答えます。
「なら、よかった(ずっと昔に行ったことのある、奈良も良かったわ)」
そう言うと、にっこりして、思い出したように訊きました。
「ねえプチ。ところで、もう一つ箱はなかったかい?」
「えっ、どこに?」
プチは思わず、訊き返しました。
「もちろん、お前の枕元さ」

プチは、急いで自分の部屋に走り出しました。それからしばらくして、細長い箱を抱えて戻ってきました。

「あったよ。起きた時は気づかなかったのは、どうしてだろう?」
プチは、とっても不思議そう。こんなことは、そうそうあるものじゃない。
「それより…。さ、開けてごらんよ」

「あっ、レッグウォーマーだ。ちゃんと4本あるよ」
「ああ、お前がずっと欲しかったものだね?どうだい、気に入ったかい?」
「うん。とっても」
それは、プチの好みを知り尽くしたサンタさんからの贈り物でした。
「よかったねえ」
「うん!」
そんなことがあって、プチとおばあさんは、ふたりで暮らすようになってからいちばんのクリスマスを過ごすことができたのでした。
プチは、洋服屋の女の人と約束した通り、早くおばあさんが喜んでくれたこと、そして不思議なプレゼントが届いたことを伝えなければ、とおもいました。

今日は街のお店はお休みなので(何と言っても、昨日はクリスマス・イブでしたから、どこの店も忙しかったのです)、明日一番で、さっそくあのお店にいくつもりです(今度こそは遅れないようにしよう、と思っているようですね)。それに、ようやく見つけた野の花を摘んで花束にする準備も、もう済ませたようですよ。
おしまい
みなさんに、素敵なプレゼントが届きますように。
読んでくれて、どうもありがとう。
おわりにお願い:ご意見と感想をいただけたならうれしいです。
急募!ダメ出しボランティア

今年も「プチと山高帽の紳士のおはなし」を加筆修正して、昨年はかすりもしなかった「絵本大賞」に応募しようと思います。
そこで、原稿を読んで、ダメ出しをお願いできる人を探しています。何しろ急に思いついたことなので、時間もないし、そんなに暇のある人もいないとは思いますが、ダメで元々のつもりで募集します。もしやってもいいという方がいたら、上のバナーかここをクリックしてお知らせください。折り返しワード仕様の原稿をお送りします。
内容:以下のようなことをはじめとして、なんでも気づいたことを気軽にお知らせいただければ
大いに助かります。
① このところがわかりにくい。
② こういう場面を足す方が良い。
③ ここに挿し絵があればいい。
④ 挿し絵の描き方。
⑤ 誤字脱字等の指摘。
⑥ その他、何でも。
期限:10月8日。
提出期限が、10月10日なので、可能な限り早い方が助かります。
どうぞよろしくお願いします。
日曜特別増刊号 FANTASY 4 プチと山高帽の紳士のおはなし
プチと山高帽の紳士のおはなし
はじめに
今回のおはなしは、こないだのおはなしの続きからです。もしかしたら、あのあとプチが間に合ったかどうか心配した人があるかもしれませんからね。でも、もうすっかり忘れているかもしれません(何と言っても、人は忘れやすいものですからね)。
1

また遅れてしまいそうになって、あせっていたプチに、隣に停めた車の中から声をかける人がおりました。
「もしもし、ずいぶんとお急ぎのようですな?」
びっくりしたプチは、思わず答えました。
「ええ、はい」
それを聞いて、その人はまた訊いてきます。
「どこまで行かれるのかな?」
「あの山の上の方までなんです」
「じゃあ、私の車に乗って行きませんかな?」
まだ若そうな見かけとはちがって、ずいぶん古めかしい言い方でしたが、親切にもその人は、そう申し出てくれたのです。
「えっ?」

プチがおどろいて返事につまっていると、車の中から男の人が出てきました。山高帽をかぶり、手には杖を持ったその人は、きちんとした身なりをしていました。ちょっとばかりぽっちゃりした体つきで、いかにも気さくな紳士のようでした。そして、もう一度やわらかな調子で、こう言ったのです。
「私が、送って差し上げましょう」
プチも、そのいかにも親切な紳士らしいようすを見て安心したせいで、思わずまた
「いいんですか?」
と、訊き返したのです。
「ええ。もちろん。それにしても、先ほどの宙返りはお見事でしたなあ!」
山高帽を被った紳士は、あらためてプチの顔をながめながら、言いました。
「いえいえ、急いでいたので、つまづいてしまったのです」
プチは、てれながら、こたえました。恥ずかしかったけれど、ちょっとうれしくなったのですね。
「いやあ、見事なものでしたよ」
「そんなことはありませんよ。ふだんなら、つまづいたりしないもの」
プチは、こんどは少しムキになって言いました。もっとうまくできるもんといいたかったのでしょうか(やっぱり、まだ仔どもっぽいところがあるんですね)。
「ええ、そうでしょうとも。さ、どうぞ、お乗りくださいな」
山高帽の紳士は、さらにプチの気持ちをよくさせようと、やさしい口調でさそいます。
「ほんとうに?」
「もちろんですとも。遠慮はご無用ですぞ。さあ、どうぞ、どうぞ」
山高帽の紳士人はドアをあけて、促しました。
「それでは、よろしくおねがいします」
プチは礼儀正しく言うと、すばやく乗り込みました。疲れていましたし、それになんといったっておばあさんをそれ以上待たせたくなかったのです。
「さっ、まいりましょう」
山高帽の紳士は、そう言うやいなや、車を急発進させました。
「はい」
プチが返事をするまもなく、車はあっという間にスピードを上げていきます。
「すごいなあ!」
プチは思わず声に出しました。
「ところで、お住まいはどちらでしたかな?」
「あの山の上の方なんですが……」
「そうでした、そうでした。それじゃあ、いそぐことにいたしましょう」
「あ。でも道は途中までしかないんです……」
「そうですか。それじゃあ、とにかく行けるところまでごいっしょいたしますよ」
「ほんとうに?」
「もちろんですとも」
「お願いします。おくれそうなんです。いや、もうておくれているかも……」
プチは、小さな声で言いました。
「じゃあ、いきますよ」
山高帽の紳士はにやりと笑うと、さらにスピードを上げました。許されるスピードギリギリかもしれません。超えてなければいいのですが(誰も見ている人はいないのですが)。
「はい。よろしくお願いします」
「いやあ、ほんとうに見事な見ものでしたな。あれなら何回でも見たくなりますなあ」
山高帽の紳士は、またプチを褒めて言いました。プチは、すっかりいい気持ちになってきたようでした。褒められて悪い気はしませんものね、とくにプチのようなまだ小さなこどもにとっては。
まもなく、おばあさんの待っている家の近くまでやってきました。スピードを出して走ってきた車は、キーッという音を立てると、急停車しました。車はここまで。これ以上は進むことができません。
「着きましたぞ。どうやら、ここまででのようですな」
「どうもありがとう」
「いえいえ。どういたしまして」
「おかげでとっても助かりました」
「なんのなんの。気になさることはありませんぞ。困ったときはおたがいさまですからな」
なんだかずいぶんもったいぶった言い方も、プチは気になんかしませんでした。というより、気がつかなかったという方がいいかもしれません(きっと、ようやく帰ってこれたことに安心したのでしょうね)。
「はい、ほんとうにありがとうございました」
「間に合いそうですかな」
「さあ。それは、どうかな……」
「それじゃ、いそいでお行きなさい」
「ええ。でも、ちゃんとお礼をしなくちゃいけません」
「とんでもない、気になさらないでよろしいよ」
「ありがとうございます」
「また、どこかで会いたいものですな。あの見事な宙返りを見たいものですから」
「ええ。ぜひ」
いかにも紳士らしい男の人に親切にも助けてもらったプチは、嬉しい気持ちでいっぱいになって、走り出しました。おばあさんお待っているうちはすぐそこです。
2

窓から明かりが見えていました。急いでつくと、思い切りドアを開けて、大きな声で叫びました。
「ただいまあ」
「おやおや」
出てきたのは、アオでした。
「アオ!待っていてくれたんだね」
プチは、思わず大きな声で言うと、アオのところへ走り寄りました。
「ああ。もちろんさ」
「遅くなってごめんなさい」
「いいさ。それより、おばあさんが待っているよ」
アオは、プチの肩に手をやりながら、やさしく言いました。
「うん」
「ただいま」
プチは、大きな声で言うと、おばあさんところへ駆け寄りました。
「おかえり、プチ。無事に帰ってきたんだね。よかった」
「うん、ごめんなさい。もうごはんは食べた?」
今度は、小さな声で訊きました。
「これからだよ」
「えっ?」
「アオがつくってくれたんだけどね。お前が帰ってくるのをもう少し待とうと思ってさ」
「……」
「どうしたのさ。おかしいねえ」
「ごめんなさい」
もういちど、プチはおばあさんのほうを見てあやまりました。
そこへ、アオがお皿を持って、入ってきました。
「お待たせしました」
「いつもすまないねえ」
「ありがとう」
「どういたしまして。さ、召し上がれ。プチもお腹すいただろう?」
「うん」
その夜のばんごはんは、いつにもましてのご馳走のように感じました。美味しかったことは、いうまでもありません。
食べているあいだ中、もちろん、口の中に食べ物が入っている時は別ですけれど、プチは新しい街で見たことや新しい友だちのこと、それから街に戻ってきてから、車で送ってくれた山高帽の紳士のことを話し続けました。
「間に合わないと思って、諦めようとしたり、また走ったりしているときに、ちょうど車が通りかかったんだよ」
「うん」
「僕のそばに止まると、中から山高帽とステッキを持った、とっても素敵な服を着た男の人が降りてきたんだよ」
「そうかい」
「でもね、僕は油断しないようにしなくちゃ、と思ったんだ。悪い人だったら困るからね」
「そうだよ。気をつけなくちゃいけないよ」
「でも、その人はとても礼儀正しくて、優しかったんだ」
「うん」
「僕が何をしているのか聞いて、約束の時間に遅れそうだということを知ると、車で送りましょう、と言ってくれたんだ」
「そうなんだ」
「僕が走っている途中で宙返りしたのも見ていて、とても上手だったと褒めてくれたんだよ」
「ふーん。で、お前は上手だったのかい?」
「うん。くるりと回って、転ばずにふわりと着地したんだ」
得意げに言ったのでしたが、でも、なぜ宙返りをして見せたのかは、黙っていました(だって、やっぱり恥ずかしかったんですね)。おばあさんも、アオもなぜってたずねることはしませんでした(これは、どうしたことでしょうね?)。
それからも、ずっとプチは話を続けました。おばあさんとアオは、やさしい顔で聞いていました。途中で口にしたことといえば、「そう」、「よかったね」くらいでしたが、最後に、「知らない人について行っちゃダメだよ」と言うことは忘れませんでした(実は、悪いことが起きなかったからいいようなものの、とても心配だったのです)。
「ちゃんとお礼をしてないから、しなくちゃね」
「親切にしてもらった時にはね」
「うん。だから、あの山高帽の男の人にもね」
「うん。でも、それはできないかもしれないね」
「そうかなあ」
やがて、遅い時間になると、アオも帰って行きました。
3
そのあと、しばらくの間は、プチはその親切な山高帽の紳士のことを熱心に話していましたが、日が過ぎるにつれて、いつの間にか、忘れてしまったようでした。毎日の新しい体験や遊びの方が、なんと言っても楽しいですからね。それで、おばあさんも少し安心しました。プチはまだ子どもでしたから、騙されて辛い思いをしないようにと、心配していたのです。
ある時、プチがおばあさんのところに駆け込んでくるなり、言いました。
「ねえ、ねえ。今日とってもいいものを見たんだよ」
「おやおや、どうしたんだい?」
「あのね、うっ…」
プチは、勢い込んだせいで、うまく喋ることができませんでした。
「ねえ、プチ。ちゃんと聞くから、ゆっくり話してごらんなさいな」
「うん」
プチは大きく息を吸い込み、吐き出すと、ゆっくり話し始めました。

「あの男の人がいたんだよ」
「男の人って誰のことだい?」
「ほら、こないだ話したでしょう。おそくなった夜に、僕を送ってくれた山高帽の人」
「ああ。その人がどうしたんだい」
「だから、その人がね、町外れのところにいたんだよ」
「へえ。で、お礼をいうことはできたのかい?」
「いいや」
プチは残念そうに言いました。
「どうしてさ?」
「また、誰かを車で送って行くところのようだったんだよ」
「へえ」
「声をかけようとしたら、やっぱりすごいスピードで走って行った」
「おや、それは残念だったねえ」
「うん。でも、また会えるかもしれないね?」
「ああ。そうだね」
おばあさんは、ちょっと心配になりましたが、プチをがっかりさせないように返事をしました。
「やっぱり、とっても親切な人だったんだなあ」
プチは、すっかりあの山高帽の紳士のとりこになったようでした。
そのあとでも、同じようなことが何回か続いたので、おばあさんは、心配になって、アオに相談しなくてはと思いました。
4
「ねえ。明日のお昼にちょっと出かけてきていい?」
プチが、弾んだ声で、おばあさんに言いました。
「どこへ行くんだい?」
「少し先まで行って見たいんだ。でも大丈夫。夕ごはんの前にはちゃんと帰ってくるよ」
「いいけどね。でも、遅くなっちゃダメだよ」
「うん。今度は遅くならないよ。約束するよ」
「そうかい。ならいいよ」
おばあさんは、あの山高帽の紳士のことをうっかり忘れてしまっていたのです。
「うん、よかった」
翌日、お昼ごはんを済ませたプチは、
「行ってきます」
と大きな声で言うと、いそいそと出かけて行きました。
「行っといで。気をつけるんだよ」
「うん」「遅くならないようにね」
「わかっているよ」

プチが急いで山を降りると、道の所に車が止まっていて、そこにはあの山高帽の紳士が立っていました。
「おじさーん」
プチは待ちきれずに声をかけました。
「やあ、プチ。よくきたね」
「よろしくおねがいします」
「楽しみにしてもらっていいですぞ」
「はい」
「それでは、行くとしますかな」
5
プチは、つい何日か前に、ここで山高帽の紳士、こないだプチが遅れそうになった時に親切にしてくれた男の人と出会ったのでした。

「大きな川はいいですねえ」
プチは、こないだ渡った川のことを話していました。
「そうですな。でもね、もっといいものがありますぞ。湖は見たことがありますかな?」
山高帽の紳士が、尋ねました。
「みずうみ?」
「そう。湖は、もっといいですよ」
「へえ。どんなところ?」
「とっても広くて、水がたくさんあってね、でも、海とは違って、しょっぱくはないんです」
「へえ」
「わたしの夏用の小屋もありますぞ」
「そうなんだ」
「そうそう。あなたの友だちになれそうな動物たちもおりますぞ」
「へえ!」
プチは、いよいよ行ってみたい気持ちを抑えることができないようでした。
「興味はありますかな?」
「うん!はい」
とうとうプチは、がまんできずに言いました。
「どうです、行ってみますかな?」
「はい。でも遠いですか?」
プチは、こないだのことを思い出したのでした。
「そうですなあ。ちょっとばかり時間がかかるかもしれませんなあ」
「そうですか」
「どうかしましたかな?」
「ちょっと」
「そんなに見たいというわけじゃないんですな?」
山高帽の紳士は、わざと焦らすように言いました。
「いえ。そうじゃないんです」
プチは、あわてて答えました。
「どうしました」
「実は、家におばあさんがいて……」
「それじゃあ、アオが来てくれる時にしますかな?」
「はい」
「いや、せっかくですから、ちょっと見るだけでも行ってもいいですぞ」
「はい。でも……」
「だいじょうぶ。お昼ごはんのあとに出かければ、夕ごはんまでには戻れます。わたしがちゃんと、送りますからな」
「はい」
「そうしませんかな?もう、道もわかっていますからな。心配はいりませんぞ」
「ええ」
「あしたのお昼過ぎに、ここであいましょう」
「はい」
つい、プチはそうこたえのでした。こんなことがあったので、プチはあの紳士と湖を見に出かけることになったのです。
6
よく日、プチは連れて行ってもらうことにしました(おばあさんにはないしょでした)。いくつかの街の中を通り抜け、上がったり下がったりする道を過ぎると、やがて広いところに出ました。その向こうには何やらキラキラ光っています。
もう少し進むと、山高帽の紳士は車を止めて、
「さあ、ここからは歩きましょう。湖はもうすぐですぞ」

どんどん歩くと、やがてあの川よりももっと穏やかで、たくさんの水のある場所につきました。
「どうです?」
「すごい」
「お気に召されたかな?」
「ええ。こんなに静かで、たくさんの水は見たことがありません」
「そうですか。それはよかった。それじゃあ、戻ることにしますかな?」
「えっ。もうですか?」
「ええ。また、くればよろしい。今日は、遅れないように帰ることにいたしましょう」
「はい」
「今度は、私の小屋にもお招きいたしましょう。お友だちもいますぞ」
プチと山高帽の紳士は、来た道を引き返しました。今度は、まだ陽のある時間までに、山の上に着くことができました。おばあさんに心配をかけることも、ありませんでした。プチは、ほっとしました(あの山高帽の紳士が戻りましょうと言ってくれなかったら、きっと遅くなったのに違いないと思ったのです)。
「ありがとうございました」
「湖はどうでしたかな?」
「とっても楽しかった」
「それは良かった。それじゃあ、日曜のお昼にいつものところでお待ちしておりますぞ」
「はい。ありがとうございます!」
というと、プチはおばあさんの待つ家に向かって、走り出しました。
家に帰って、おばあさんと夕ごはんを食べている時も、今日のこと、初めて見た湖のことの話しはしませんでした。おばあさんに心配をかけたくなかったのです。いや、ほんとうは、止められたら嫌だなあと思ったせいかもしれませんが。
7

それからというもの、プチのウキウキしている様子は誰にもあきらかで、おばあさんも思わず、
「プチや、お前は、いったいどうしたっていうんだい?」
と訊くのですが、その度にプチは、
「えっ?なんのこと?なに言ってんのさ」
と、とぼけるのです。きっと知られたくないのですね。
「へえ、そうなんだね。でもね、私のことは心配することはないよ。好きなところへ行っていいんだよ」
「どこにもいかないよ」
そう言うのですが、プチの気持ちは半分以上、初めてちょっとだけ見た大きな湖のことでいっぱいでした。プチはそのことを抑えて、おばあさんのことを考えようとしましたが、それはなかなかむづかしいことでした(しっかりしているとはいっても、プチはまだ仔どもの猫でしたからね)。
プチは、アオが来てくれることになっている日曜日が、待ちどおしくてたまりませんでした。
8
やがて、その日がやって来ました。
アオの姿が見えると、すぐにプチは走り出しました。
「やあ、アオ。こんにちは」
「やあ、プチ。ずいぶん待っていたようだね?」
アオが尋ねます。
「うん。今日は、ちょっと遠くまで出かけようと思ってさ」
プチは、急ぎたい気持ちを抑えようとして言ったつもりでしたのですが、……。
「ふーん。でも、こないだのように遅くならないようにね」
アオは、そんなプチの気持ちがわかって、やさしく諭すように言います。
「うん」
「おばあさんに、あんまりしんぱいをかけないようにしなくちゃね」
もう一度、念を押します。
「ちゃんと、わかってるよ」
プチも、こんどはアオをしっかり見て、言いました。
「それならいいんだ」
「じゃあね。行って来るよ。おばあさんのことをよろしくね」
「ああ」
アオがそう言った時には、プチはもう下の方をめざして、一目散に走り出していたのでした。

「やれやれ。どうしたっていうんだろう?」
アオは不思議に思いながら、おばあさんのところへ急ぎ足で歩いて行きました。アオも、おばあさんとお話しするのが、まちきれないほどに大好きだったのです。
9
プチがいつもの場所の近くまできて、下の方を見ると、もうあの山高帽の紳士と車が止まっていました。プチは、全速力で降りて行きました。
「こんにちは。お待たせしました」
「やあ、プチ。ずいぶん早くにお着きになりましたな」
「はい。いそいできたんです」
「ふーん。よほど楽しみにしていたのですかな?」
「ええ」
「それじゃあ、さっそく出発することにしましょう。遅くなるといけませんからな」
「はい、おねがいします」
「さあ、行くとするか」
男の人は、ニヤリとすると、それまでとは違った口調で言いました。しかし、プチは、そのことには全く気が付きませんでした。
プチは一度見たことがある景色でしたので、前の時よりも早く進んでいるような感じました。その途中で、山高帽の紳士は、道沿いの大きな駐車場の中に車を入れました。
「食事の材料を買っていくことにいたしましょう」
「え。はい」
広い駐車場の向こうには、大きなお店があります。おじさんは入り口の近くに車を止めた後、
「ここで、待っていてもらえますかな。買ったら、すぐに戻りますので」
と言って、山高帽の紳士は店の方に歩いて行きました。窓は少しだけ開いていました。
「ええ。はい」
プチは退屈になって、少し空いた窓から外を眺めることにしました。見たことのないような大きなお店の駐車場で、あたりを見回していると、窓をたたく音と呼びかける声がしたような気がしたのです。振り向いてみると、新しく友達になったばかりのポチのようでした。

「やあ、プチ!」
「やあ、ポチ!ここで何をしているんだい?」
「ちょっと仲間のところに寄ったのさ。きみこそ、いったいどうしてここに?」
「湖を見に連れて行ってもらうところなのさ」
「へえ。よかったね」
「うん。実は2回目なんだ」
「ふうん。湖はいいよね」
「君は見たことがあるんだね」
「ああ。大きくて、たっぷりの水が静かにしている。いいなあ」
「うん。そうだね」
「じゃあまたね。楽しんでね」
お店から山高帽の紳士が出てきました。
「あ、あのおじさんが来た」
「えっ」
「あの人だよ。黒い帽子をかぶった、ちょっとぽっちゃりした男の人だよ」
山高帽の紳士が、すぐ近くまでやってきていました。
「あの人かい。君を湖に連れて行ってくれるって人は?」
ポチは、少し声を小さくして訊きました。
「ああ。とても見た目どおりのいい人だよ」
「そう?じゃあ、またね」
なぜだかわかりませんが、ポチはそういうと、すぐに駆け出したのでした。
「あれ?どうしたっていうんだろ?」
走って家に着いたポチは、すぐにこのことを妹のハナとおじいさんに伝え、三人で作戦を練ることにしたのでした。
「お待たせしましたな。たくさん買ってきましたぞ」
山高帽の紳士はそう言うと、ドアを閉めて、また車を走らせました。
「急ぐとしますかな。遅れるといけませんからな」
「はい」
「とびっきりのお昼ごはんを食べさせますぞ」
「うれしいな」
プチは、お昼ごはんのことを聞いて、ますます楽しみになりました。
やがて、車は湖のそばに平らなところに着きました。駐車場の脇にはいくつかの倉庫もありました。
「さ、参りましょう」
10
「さあ、着きましたよ。どうぞ、お入りなさい」
と言って、ドアを開けてくれました。
「はい」
プチが中に入ると、そこは大きな部屋で、大きなテーブルと台所がひと続きになっていました。
「わあ、ひろいなあ!」
「そうですか?」
「ええ。はじめてみました」
「そうでしたか?」
その時、ドアの向こうから何やら音がした気がしました。
「あれ、なんか聞こえませんでしたか?」
「ああ、あれね。あれは君のお友だちの声ですな」
「そうですか」
「ちょっと行って、連れてきましょうかな。会ってみたいですかな?」
「ええ。もちろん!」
「少しだけお待ちなさい」
と言うと、ドアを開けて中に入って行きました。それから動物たちのちいさな声と山高帽の紳士が何か言う声が聞こえましたが、何を入っているのかはわかりません。

しばらくすると、山高帽の紳士がとってもちいさな犬を抱えて、戻ってきました。
「待たせたね。これは、ひなといいますぞ」
「こんにちは、ひな。ぼくはプチ。よろしくね」
「こんにちは」
ひなは、体と同じように小さな声で言いました。
「それじゃ、この子を戻して、食事の準備をすることにしようか」
「はい。何かお手伝いしましょうか?」
「いや。そこに座っていてくれればいいよ」
なんだか、いつものあのもったいぶったような昔の人のような口調とは違います。
「さあ、どうぞ。お食べなさい」
「はい。あの子は?」
「あの子たちのことは、気にしないでけっこう」
「そうですか?」
「さ、食べなさい」
すすめられるままに、プチはお皿に手を伸ばし、口に入れました。
「とってもおいしいです」
「そう……?」
山高帽の紳士が言う声が遠くなって、プチはなんだか急に眠くなったような気がしました。まもなく、すっかり眠り込んでしまったのでした。
11
そのころ、ポチたちは途中で仲間たちのところへ寄りながら、プチのいる小屋を目指していました。大きな道路の交差点に集まりました。そして、目の前に大きなトラックが止まった時に、後ろの荷台に飛び移ったのです。
いっぽう、おばあさんからはなしを聞いたアオもだまってはいませんでした。すぐに街に引き返し、仲間の猫に会うと、すぐにプチが乗った車のゆくへを突き止めるよう、言いました。その中には、あちらこちらの街で悪さをしたあとにアオやプチたちと戦って、やがて改心した猫たちもいました。彼らは、いろいろな街のことを知っていました。
「プチはだいじょうぶかな?」
「ああ。すぐに売られるわけじゃない」
「そうなの?」
「芸を覚えさせたあとに、売るんだ……」
古くさい口調の山高帽の紳士は、街で見つけたまだ小さくてかわいい動物たちを騙して小屋に連れて行き、芸を仕込んだあとに、売りさばくことを商売としていたのです。少し前に、ポチの仲間がその餌食になりかけたことがあったのでした(そのときは、ポチの機転で助かったのですが)。
小屋の中では、あの山高帽の紳士がすっかり眠ってしまったプチを抱えて、食堂の隣の部屋に運んだところでした。部屋にはたくさんの檻があって、そのいくつかの中には小さな猫や犬や、ウサギなどが入れられておりました。
男の人はプチを、檻の中に入れると扉を閉めて、鍵をかけるとまたニヤリと笑いました。
山高帽の紳士は、ミルクのたっぷり入った紅茶を淹れることにしました。
一仕事終えて、すっかりくつろいだ気分だったのです。
「あの仔ねこは、ほんの少し教えるだけでよさそうだ」
とつぶやくと、紅茶を一口飲みました。
「うまいなあ。やっぱりうまくいった後の紅茶が一番だ」
また独り言を言いました。
とその時、小屋の外が何やら騒がしくなりました。男の人は、水鳥たちが戻ってきたのかと思いました。
「まあ、気にすることはない。うまく行った後だし、少々うるさくたって、かまうことはないさ」
もう一度、椅子に深々と座りなおすと、紅茶を口いっぱいに含みました。
そのときのことでした。
たくさんの犬や猫たちが、いっせいに駆け込んできたのです。おどろいた山高帽の紳士は紅茶を膝の上にこぼしてしまいました。
「あちっ!」
ズボンに着いたしみはきっと取れないことでしょうね。でも、山高帽の紳士にとっては、履けなくなったって、もう困ることはないかもしれません。
犬たちが一斉に山高帽の紳士に飛びかかり、服を食いちぎり、ついでに耳や鼻もかじりました。手も足も、外に出ているところは全部。山高帽の紳士は(この時はもう山高帽はありませんでしたが)、必死で手足を振り回し、ようやく振りほどくと、それでも噛みついてくる犬たちから逃れようと、急いで外に出ました。犬たちは逃すものかと、追いかけます。山高帽の紳士は、やっとの思いで湖のところまでたどり着くと、飛び込みました。そして、やがて見えなくなりました。
一方、アオたちは、檻の中からプチやひなたちを出してやりました。プチは助け出された後、喜ぶよりもしょんぼりしているようでした。たぶん、騙されて皆に迷惑をかけたことを、恥じて悔やんでいたのでしょうね。
そんなプチを見て、アオは声をかけました。
「プチ、見てごらん。湖がキラキラ光っているよ。とってもきれいだね」
「うん」
「こんなに綺麗なら、僕もまた見たいな」
「ごめんなさい」
プチは自然に口にしました。
「ああ。気をつけなくちゃあね」
アオは、叱ることもせず、そう言いました。
「うん」
プチは、心の底からホッとして、にっこりしたのでした。
「こんなに綺麗なら、誰だって見たくなるさ」
「そう?」
「そうだよ」
「怒っていない?」
「ああ」
「僕が騙されて、心配をかけるようなことをしたのに?」
「はじめは腹を立てたさ。おばあさんもとても心配してたからね」
「うん。ごめんなさい」
「ああ。でも、僕だって騙されたかも、と思いなおしたんだ」
「そう?」
「そうさ」
プチは思わず飛び上がって、アオに抱きついたのでした。アオも、しっかりと受け止めて、抱きしめました。
一方、アオたちは、檻の中からプチやひなたちを出してやりました。
それから、プチやポチ、青とその仲間たちは湖のそばで、しばらく過ごしました。
やがて、トラックがやってくるたびに、来た時と同じように、荷台に乗り移って、それぞれの住む街へ帰って行きました。

プチも、もちろんおばあさんの待つ家に帰りました。そして、おばあさんといっしょに、アオが置いていてくれた夕ごはんを食べながら、得意げに話したのでした。もちろん、檻の中に入れられたことはしっかり省きましたけど(これは、おばあさんに余計な心配をかけたくないということもあるでしょうけど、きっとそれよりも、失敗を知られたくないせいでしょうね)。
ところで、あのちいさな仔犬のひなは、おじいさんのところで、ポチとハナといっしょに暮らすようになったそうです。
ひとまず、おしまい。
読んでくれて、どうもありがとう。
おわりにお願い:ご意見と感想をいただけたなら助かります。参考にして完成させたいと思います。よろしくお願いします。
日曜特別増刊号 FANTASY 3 仔ねこのプチのもうひとつの冒険のおはなし 第5回
5
はなれていくまちは、たくさんのいろとりどりのあかりがともっていて、
プチは、そのけしきをあらためてとてもきれいだとおもいました(それに、なんといっても、あたらしいともだちもできたことですし)。
それでも、あんまりすみたいという気にはならないようでした。

やがて、ふねがプチのすむまちにちかづいてくると、
あかりのかずこそすくなかったのですが、
やっぱり、きれいだなあ、とかんしんしたのでした。
ふねがつくと、まだしっかりとまらないうちに、
プチはぜんそくりょくでかけおりて、
りくちをめがけてとびだしました。
さらに走っていると、やがてひもほとんどしずんで、
あたりくらくなり、
ほとんどたかさもかたちもちがわないたてものがシルエットになり、
まどにはすこしずつあかりがともりはじめました。
なんてきれいなんだろう。
しばらく見つめながら、
プチはちょっとこわいような気もちになりました。
プチがふだんくらす山のなかとはあまりにもちがって、
まるでべつのせかいにまぎれこんだかのような気がしたのでした。
プチは、よるのまちをよくみたことがなかったのです。

あ、いけない。
プチは、またいそいではしりだしました。
すっかりくらくなってしまうまえに、もどらなくちゃ。
おばあさんの夕ごはんのときまでには、つかなくっちゃ。
やくそくしたんだもの。
こんどこそはまもるんだ。
だけど、あたりはますますくらくなり、
おまけに、ちょっと風もでてきたようでした。
「ああ、またか。まにあわないかもしれないな……。
ゆっくりしすぎちゃったのかな」
「さあ、いそいでかえろう」

プチは、山のほうをめざして、
まどのあかりも少なくなってくらいなかを、
また、いちもくさんにはしりはじめました。
「はやくもどらなくっちゃ」
さいわい、車も、人どおりもないので、
だれともぶつからずにすすみます。
それからすぐのことでした。

「あっ」
プチは、またまたちゅうにまったのです。
きょうはなんと3どめでした。
どうやら、ほどうのじめんからかおをだした、
木のねっこにつまづいたようでした。
でも、こんどはくるりとからだをまるめてかいてんすると、
ひらりとちゃくちしました。
「ああ、またか」
プチはため息をつくと、こんどこそまにあわないかもしれない……、
とあきらめかけたのでしたが。

それから、顔をなんどかよこにふると、
プチは、またいちもくさんにはしりはじめました。
プチはしらないまちで、
しゅっぱつのまえにおばあさんがしんぱいしていたように、
やっぱり、
はじめてみるものにむちゅうになりすぎてしまったのかもしれませんね。
さあ、プチが、なんとかまにあうことができればいいのですけれど。
おしまい(このあとのことは、またいつか)
日曜特別増刊号 FANTASY 3 仔ねこのプチのもうひとつの冒険のおはなし 第4回
いたいなあ、いったいどうしたことだろう。
とおもってあたりを見まわすと、
すこしはなれたところに、おなじようによこたわっているものが、
見えました。

おそるおそるちかづいてみると、仔いぬのようでした。
おなじくらいのとしのようです。
さらにのぞきこむと、仔いぬはゆっくりと顔を上げ、
「うーっ」とほえました。
「だいじょうぶ?」
と、プチがききます。
「うん。ああ」
仔いぬがちいさな声でこたえました。
「ほんとうに?
「うん。まあ。なんともないよ」
そういって、仔いぬはバツがわるそうに、ちいさくニッコリしました。
「そうかい。よかった」
プチはいうと、またききました。
「どうして、そんなにいそいでいたんだい?」
「港に、おじいさんをむかえに行くところさ」
「へえ。あ、僕もいそがなくちゃいけない」

と、ギーッという音が聞こえました。
はね橋が上がり始めたのでした。おおきな船がとおるようです。
あわててプチと仔犬は走りだしました。
「きみは、どうしてさ。なぜ急ぐんだい?」
こんどは、仔いぬがききます。
「おばあさんが待っているんだ」
「へえ。港でかい?」
「いいや。川の向こうさ」
「じゃあ港まで急ごう。船が着くから、それに乗っていけばいいよ」
「うん。じゃあ、急ごう」
ならんではしっていた仔ねこのプチと仔いぬは、さらにスピードを上げました。
ようやく港へ着くと、ちょうど船が着いたところでした。
「ああよかった。まにあった」
「うん。よかったね」

と、仔いぬが、きゅうにはしりだしました。
海のほうをみると、おじいさんがゆっくりおりてきたのでした。
ヒゲをはやした、
おおきくて立派なおじいさんでした。
足取りもしっかりしているようでした。
プチははしってかれらのほうにちかづくと、
「よかったね。じゃあ、またあおう」
と、いうと身をひるがえして、ふねにはしりこみました。
ぶじにふねにのりこんだプチが、
はなれかけていたきしのほうを見ると、
仔いぬとおじいさんが手をふっているのがみえました。
プチもまけずに手をふり、おおきなこえで、
「またねぇっ」
とさけびました。
そこに、もう一ぴきの仔いぬがはしってきていました。

そして、とおくからおんなの子のこえで
「ありがとう」
というこえが聞こえたような気がしました。
首に赤いリボンをまいた、もう1ぴきの仔いぬのこえのようでした。

プチもおもいきり両手をふって、
もういちど、せいいっぱいおおきなこえで、
「またねぇっ」
とさけびました。
続きます。
日曜特別増刊号 FANTASY 3 仔ねこのプチのもうひとつの冒険のおはなし 第3回

でも、だいじょうぶ。
仔ねこはまるでコップの中のミルクのように体がやわらかくて、
ぶつかってもへいきなのでした。
ちいさな船は、プチにとって親しみのある匂いがしました。
そう、魚のにおいです。プチがおちたさきの船はちいさなつり船だったのです。
ああ、よかった。
プチは、ふーっとおおきなためいきをはきだしました。
むこうがわに目をやると、
見しらぬ街の景色が目にとびこんできました。
いままで見たことのないような、高くて、しかくなたてものが
たちならんでました。
ああ、あの街に行ってみたい。
でも、どうやって……。
4

でも、すこしずつ街が近づいてきたようでした。
あれ⁉︎やがて船は、さん橋に着きました。どうやら、つり船の
はっちゃく所についたようでした。
プチはおもいきっりとびおりると、いちもくさんにはしりだしました。
街にはたくさんのたてものがあり、その中にはお店があり、
道路には、テントやら屋台やらが出ていたり、
楽器をひきながらうたっている人がいたりして、
大勢の人で賑わっていました。

プチは、はじめて見るけしきに、すっかり見いっていました。
「たのしいなあ。はじめて見るものばかりだ」
と、だれかがぶつかって、あやまることもせずに
とおりすぎていきました。
やれやれとおもっていたら、こんどはおみせのなかからでてきた人から、
「しっ、あっちへいきな。そんなとこにいられたら、じゃまなんだよ」


しかたなく、とぼとぼとあるきはじめると、
なにやら赤いものが目に入ったのです。すてきにきれいな色です。
首にまくリボンのようでした。
しめた。
これをじぶんがまいたらにあうかな。いやおばあさんのほうがよろこぶかも。
もってかえってやろう。おばあさんはどうおもうだろうな。
ちょっとワクワクしました。
するとなんだか、声がきこえたような気がしたのです。
「プチ、ねえ、プチ」
おばあさんの声のようでした。そしておもったのです。
「ああ、いけない。ごめんなさい」
5
「こまっている子がいるかもしれないね。さがさなくっちゃ」
さっそく、あるきはじめました。すこしいったところで、
とおくのほうに目をやると、むこうのほうからとぼとぼと、
あたりをみわたしながら、ゆっくりと歩いてくる仔いぬがみえました。
もしかしたら、そうおもったプチははしりだしました。
「なにかさがしているの?」
「ええ」
「おとしたのかい」
「赤いリボンがないの」
 プチと仔犬
プチと仔犬
「あっ」
プチは、いそいでつつみのなかから赤いリボンをとりだしました。
「きみがさがしているのは、これ?」
「ええ。どうしてそれを?」
「とちゅうでひろったんだ」
「かえしてくれる?だいじなものなの」
「もちろんさ。どうしたのさ」
「おじいさんにもらったの。だからとてもだいじなの」
「そうなんだ。はいどうぞ」
「ありがとう」

いつのまにか、あたりはもうくらくなりかけていました。
おっといけない。またおそくなってしまう。
プチはあせりはじめました。
「じゃあね」
「はい。ありがとうございました」
仔いぬのこえはきこえたのですが、その時はもういそいで
はしりはじめていたのです。

そして橋のうえにたつと、
うえからながめるゆうぐれどきのおおきなどうろは、
赤、黄、白のあかりがとぶようにながれさって、とてもきれいでした。
そのむこうのそらも、茜いろにそまっています。
プチはおもわずたちどまって、じっとながめていました。
なんといってもはじて見るけしきだったのです。

「なんだかなあ」
みながいそいでいて、ゆっくりすることがなく、やさしいきもちを
わすれているような気がしたのです。
プチは、だんだんじぶんの街がこいしくなってきました。
さあ、はやくかえろうとおもって、はしりはじめました。

すると、まもなく、プチは、またちゅうにまったのです。
続きます。
日曜特別増刊号 FANTASY 3 仔ねこのプチのもうひとつの冒険のおはなし 第2回
2

やくそくどおりアオが、いつものようにつつみをかかえて
プチのところにやってきました。
「やあ、まってたかい」
「うん、いつもありがとう」
「よし、じゃあ、おばあさんのところにいこう」
「うん」
「ところで、こんどはどこへいくつもりなんだい?」
「となりの街だよ。こないだとははんたいがわのとってもおおきな橋の
むこうの街のほうさ」
「へえ」

さっそくおばあさんのところにいって、いいました
「おばあさん、じゃあいってくるよ」
「ああ、たのしんでおいで。でも、気をつけるんだよ」
「えっ?」
「あら、こないだのことはわすれたのかい」
「あ、そうだった。気をつけるよ」
「じゃあ、いっといで。うんとたのしんでおいで」
おばあさんはプチが出かけることができるようになって、
うれしいのです。こうしたことができるようにと、
ときどきアオがそばにいてくれるようになったことを、
ほんとうにありがたくおもっています。
アオも、おばあさんとおしゃべりをするのが、
たのしみになっています。
いろいろなはなしをきくのがゆかいだし、
ほんとうのかぞくのような気がしているのです。

「おべんとうはもったかい?」
「うん」
「じゃあ、いっといで。楽しんでくるといいよ」
「ありがとう」
「でも、くらくなる前に帰ってくるんだよ」
アオが念をおすようにいいました。
「ああ。わかっているよ」
プチもへんじをしました。
ほんとうにわかっていれば、いいのですけれど。
プチは、おもしろいものを見つけると、むちゅうになって、
時間のことを忘れてしまうことがあるのです。
え、きみもそうなの?
でも、気をつけてくださいね。
「いってきます」
まえを向いたままいうと、プチは早あしで歩きはじめました。頭のなかは、
これからはじまる冒険のことでいっぱいなのだね。

3
よくはれたあおい空には太陽がまだのぼりはじめたばかりで、
葉っぱのあいだをぬけてくるひかりにてらされた小川の水が、
キラキラと光っている。岩もうすい金いろにかがやいている。

「なんてきれいなんだろう」
ずっと見てきたはずだなのに、いままで、いそぎすぎて、
わからなかったことに気づいて、息をとめるようにして
見入ったのでした。
見なれた森を抜け、街をぬけてさらにすすむと、
プチはおおきな川のところに出ました。すこし向こうには
おおきな橋もあります。
プチは、いままでこんなにおおきな川を見たことがありませんでした。
よし、むこうまでいってみよう。
りっぱでおおきな橋のところまで来ると、
川がもっとよく見えるようになりました。
ときどき人をのせたおおきな船や小舟がのんびりとゆきかいます。

「ああ!」
プチはすっかりかんしんして、見いりました。もっと見ようとおもって、歩道をすすんで、さらに欄干にとびのって顔を出しました。
とその時、走り去る人がぶつかってきたのでした。どうしてだか、
その人は、プチの町にはめずらしくいそいでいたようなのです。
たまらずプチは、あっというまに欄干のそとにほうりだされたのでした。みるみるうちに、水面が近づき、おおきな船のうしろ姿が見えました。
「わあっ!」

そのあとすぐに、ドンと何かにぶつかる音がして、衝撃を感じたプチはおもわずそっと後ろを振り返ったのでしたが……。
続きます。
月曜特別増刊号 FANTASY 3 仔ねこのプチのもうひとつの冒険のおはなし 第1回

仔ねこのプチのもうひとつの冒険のおはなし

きみは、仔ねこは好き?

「うん。好きだよ」
といってくれたならうれしいのですが。
じつはね、また仔ねこのプチのおはなしをしようとおもっているのです。
1
仔ねこのプチは、ときどきひとりで、
すこしとおくのほうまで出かけるようになりました。
でも、いっしょにくらすおばあさんがいるので、
いつもっていうわけじゃありません。
年のはなれたおにいさんのようなアオが、
おばあさんといっしょにいてくれるときだけです。

これまでとちがった場所にいけば、
いままでみたこともしたこともないことに出あいます。
いつもというわけじゃありません。
だから、よけいにプチはたのしみにしています。
きょうが、その日。
もうそろそろ、アオがやってくるころです。

続きます。
日曜特別増刊号 FANTASY 3の予告と、少しだけ
予告の前に、少しだけ。
手仕事(と言うほどのことはしませんが)は、まあ好きなほうだと思う。メモは頻繁につくるし、いったん書いた文章に手を入れる*ことは苦にならないどころか、始終やっている。というのは、何もマメな性格ということじゃなくて(確かに、ヒマではありますが)、そうしないとできない。文章であれなんであれ、2桁の数字2つだけのごく簡単な計算だって、目に見えるようにしないと何もできないのです。他にも、スタンプを使って手帳を自作したり、ブログのための写真の加工(ごく簡単なものですけど)も、厭じゃない。

だから、しばらく前からまた取り組むようになった小さな物語につける絵も、いちおう自分で描く。と言っても、それは簡単な線画で、ラフにさっと仕上げる文字通りの素描。正確に細かいところまで描いたものではない。と言うか、ていねいに描こうとしても描けないのだ(上手か下手かということについては、いうまでもなく論外のこと)。
細かな作業に取り組んで、これを続けることが苦手。要するに、ていねいな手仕事、辛抱を必要とすることができない(ちょっと致命的なような気がするけれど**、できないものは仕方がない)。まあ、やれる範囲でやるしかない。年取ったら、完璧をめざすよりも、まずは実践や完成が大事なことになるようなのです(何しろ、若い人と違って、時間がありません)。
話の大筋は比較的早くできた(何と言っても短い)。出来ばえについては、あんまり気にしないようにしようと思います。でも、やっぱり根気のいる長いものは、なかなか……。そして、いざ絵を描こうとすると、ていねいに……と思ってはみるものの、先にも書いたように、どうしてもささっと走り描きしたような、極めて大雑把なものになってしまうのだ。このままでは、また、完成しないまま放置することになりかねない。

先日の夕日通信に届いたお便りの中には、プチとアオが一目でわかるとよいともあったのですが、なるほどと思い、おおいに惹かれるものの、残念ながら手に余ります(うーむ)。
そんなことで、いよいよ、明日、6月26日(月曜)から連載開始です。
しかし、箴言めいたことを書くのは柄じゃないし、まして独自性のあるものというのはとても無理。おまけに、ハラハラ、ドキドキするような大きな事件も起きない。さて、これで、読み進めてもらうことができるものかどうか(ちょっと不安。で、予防線を。ま、ボケ防止のためが第1ですが……)。
こんなことを書きつけていたら、ちょっと恥ずかしくなった。いい歳をして、一人ではしゃいでいるような気がしてきた(でも、ご覧の通り、結局は掲載しました)。なんと言っても、あるものは使うというのがモットーなのだから。端材だって、何かに使えないかと思うし、取っておいたりするのです(結局は、これが元凶かも)。
* この場合、削ることよりも付け加えることが多くなる傾向にあるので、いじくりまわして、余計なことを書き加えるだけのことも少なからずありそうです(自戒)。
** ただ、住宅の計画には案外いいかも。人の生活や嗜好は変わるから、あんまりきっちり作り込み過ぎてしまうと、家に従わなければならなくなる。強度等安全性に関わる事柄は別にして、計画は基本を押さえたなら、あとは少し抜けているくらいの方がいい気がします。
日曜特別増刊号 FANTASY 2 こねこのプチのちいさな冒険 一挙掲載

こねこのプチのちいさな冒険
きみには好きなどうぶつはいるのかな。
「いるよ」
といってくれたならいいのだけれど。なんといっても好きなどうぶつがい
るっていうのはうれしいし、まい日がたのしくなりますね。
でも、きみはなにがいちばん好きなのでしょうね。
うさぎでしょうか。いぬでしょうか。それとも、おにわにやってくるこ
とり?ことりを見たら追いかけずにはいられない、こねこはどうでしょう?
好きだったらいいのだけれど。もしそうじゃなかったら、このおはなしを
読んで好きになってくれるとうれしいのですが。


こねこの名まえは、プチ。茶色と白のまじった色の、すばしこいねこで
す。おばあさんと山のほうでくらしています。
このためずっと、とおくへ行ったことはありませんでした。なんといっ
ても、年をとるにつれてからだが、だんだんよわってきたおばあさんのお
せわをしなければならなかったのですから。
でも、あるときに知りあったアオというともだちがいます。こちらはす
こし青みがかったような灰色の毛なみがとてもうつくしいねこです。アオ
は、プチにとっては年のはなれたおにいさんのようなものでもあります。
プチと同じまちですが、海べにすんでいます。
ある朝のこと、いつものようにアオがプチのところにやってきました。
なにやらつつみをかかえています。きっとおさかなでしょうね。アオはこ
うやって、プチとおばあさんとこころにおさかなをとどけてくれるのです。
少しまえのことですが、プチとアオはわるさをするねこたちにたいし、い
っしょにちからをあわせてたちむかったことがあってなかよしになったの
です。

「いつもありがとう」
「いいんだよ。ぼくたちのところでは、さかながたくさんとれるからね」
「うん」
「ところで、プチ。きみはこのまちを出て、とおくへ行ったことはあるか
い?」
「いいや。ないよ」
「行ってみたいとおもったことはないかい?」
「もちろんあるよ!」
「行ってみたくないかい?」
「うん。でもね」
こうこたえたプチは、ちょっとさびしそうでした。
「おばあさんのお世話のことだね?」
「ぼくがいなくちゃいけないんだよ」
「うん。つらくはないのかい?」
「ぼくは、おばあさんのことが大好きなんだ」
「でも、だいじょうぶ。きょうはぼくが、おばあさんのそばについている
よ」
「ほんとうに?」
プチは、うれしそうでしたが、まだ信じられないようです。
「ああ」
「いいの?」
アオを見あげて、ききました。
「じゃあ、おばあさんのところに行って、はなしをしよう」
「うん」

さっそくおばあさんのところに行ってはなしをすると、おばあさんもと
てもよろこんで、
「ぜひ、行ってらっしゃいな。でも気をつけるんだよ」
といったのでした。おばあさんも、まだちいさいのにじぶんのせわをして
くれるプチのことが、ずっと気がかりだったのです。
「ぼくがいなくてもだいじょうぶ?」
「だいじょうぶさ。アオもいてくれるといってくれているしね」
それで、プチはさっそく出かけることにしたのでした。もちろん、アオ
がよういしてきてくれたおさかなを、おべんとうに持っていくのもわすれ
ませんでした。ちゃんとつつんで、首にかけました。
「どこに行ってもいいけど、となりまちの海のどうくつだけはダメだよ」
アオがねんをおすようにいいました。
「えっ、どうしてさ?」
海のどうくつときいて、いっそうきょうみを持ったプチはいそいできき
かえました。
「おおきなどうくつのなかには、おおきなおおきなさかながいるんだ。ぼ
くたちでも、とてもかなわない。おぼれさせられたなかまもいるんだよ」
「ああ、わかったよ」
「くれぐれも気をつけるんだよ」
「うん、気をつけるよ」
プチはそういいながら、もうこころはとおくへ行っていたようでした。
「じゃあ、たのしんでおいで」

歩きはじめたプチは、はじめは木々、ついで街なかをとおりぬけ、そして
海べを行きすぎます。これらはプチにとっても見なれたけしきでした。
さらにすすむとしだいにちがったけしきが、目のまえにあらわれだしま
した。プチははしって浜べにおりて、どんどんすすんでいきました。
すると、おおきな波やちゅうくらいの波、そしてちいさな波がおしよせ
てきます。おおきな波がきたときに、プチはずぶぬれになってしまいまし
た。
なんて気持ちがいいんだろう。プチはとちゅうで見かけたちいさなさか
なをつついたりしました。おどろいたさかなはあわててにげだします。プ
チも追いかけます。こうしてますますたのしくなったプチは、じかんのた
つのもすっかりわすれたようでした。アオのいっていたことも!

いっぽう、アオとおばあさんはすっかりうちとけて、たくさんはなしを
しました。プチのことについてもいっぱいはなしをしました。
プチがおかあさんとおとうさんをなくしたときのはなしもききました。
それで、アオはいままで知らなかったプチのことがだんだんわかってきた
のでしたが、このはなしはまたいつかすることにしましょう。

プチがどんどんすすむと、やがてぽっかりと大きく口をあけたどうくつ
のようなものが見えてきました。穴のしたはひかりをはんしゃして青くひ
かっています。
プチは、ちかくでまた小ざかながはねるのを見て、おもわずとびこむと、
こんどはつかまえることができた。プチはあたらしいけいけんがたのしく
てたまらず、すっかり熱中するようになりました。そうしているうちに、
どうくつのほうにどんどん近づいて行きました。

そのとき、すこしさきのほうでなにかがキラリとひかったようでした。
と、おもったら、なにかが飛びはね、おおきなおとがして、あたりにし
ぶきが上がり、ぜんしんに水をかぶってびしょぬれになったプチはもう、
なにも見えなくなったのです。

プチがようやく目をあけることのできたときには、おおきなさかながこ
ちらへむかってくるのが見えました。あわててにげるプチ。あっとおもっ
たら、きゅうに足がとどかないことに気づいた。いそぐあまり、浜べのほ
うではなくて、海のほうにすすんでしまったようでした。おまけにとおあ
さの浜べがきゅうにふかくなっていたのです。

おおきなさかなは、ぎょろりと目をひらいて、ながい舌を出してプチを
つかまえようとします。プチはもがきながら、ひっしで手足をうごかしま
した。そのときに、しっぽのほうがぬるりとした気がしました。うしろを
ちらりと見ると、おおきなさかなのかおがせまっています。長くてあかい
したでペロリとなめられたようでした。さらに、なにか首がグイッとひっ
ぱられた気がしました。

それでも、プチはこんどこそひっしで浜べのほうにむかってにげだして、
すな浜にあいたおおきな穴にとびこんだ。

ああこわかった。たすかった。プチは、フーッとおおきな息をはきだし
て、あんしんしたのでした。それもつかのま、下のほうからなにかにさわ
られたような気がしたのです。

おおきなハサミのようでした。プチがはじめて見る生きものでした。カ
ニですね。
プチは、またまたおおいそぎでにげだしました。そのときに、背中がか
るくなっているような気がしたのですけれど、気にしてなどいられません。
ようやくしずかなばしょにたどりついたプチは、きゅうにおなかがへっ
ていることに気づきました。アオがよういしてくれたおべんとうのことを
おもい出して、ホッとして首に手をやったのでした。
あれっ。ない。

なんかいも手をまわしてたしかめたのですが、やっぱりありません。
ああ、あのおおきなさかなに追いかけられたときにとられたんだ。ちか
づかなければよかった。でも、こうかいしても、もとにはもどりやしませ
ん。

しかたなく、プチはトボトボあるきはじめました。そのとき、すぐそば
でおおきななにかがはねるおとがした。おどろいて、そちらのほうを見る
と、またあのおおきなさかながはねていました。にっこりとわらったよう
でした。もしかしたら、ただあそびたかっただけだったのかもしれません
ね。
それでも、プチは、またまたおおいそぎではしって、にげだしました。

それからどのくらいたったのか。はしりつづけたプチは、もうはしれな
いとかんねんして立ちどまってしまいました。
すると、うすぐらいなかで目こらすと、みなれた海べのすがたが見えた
のでした。そして、アオのなかまたちもいた。どうやら、プチをさがしに
きてくれたようでした。
すっかりあんしんしたプチは、きゅうに気がぬけてしまい、ばったりと
たおれてしまいました。気をうしなってしまったのです。
やがてプチが目をさますと、そこは山のなかのおばさんとくらすうちで
した。アオのなかまたちがはこんできてくれたのです。そこにはもちろん、
アオもいました。

アオがやさしく声をかけました。
「やあ」
プチは下をむいて、ちいさな声でこたえます。
「おかえり」
「ごめんなさい」
「なあに?」
「いいつけを守らなくて、ごめんなさい」
「まあ、しかたがないさ。はじめて見たら、だれだってこうふんするもの
だよ」
「ごめんなさい」
もういちど、あやまりました。
「あたたかなミルクでものんだらおちつくよ」
「うん」
アオがはこんできてくれたミルクをのむと、プチはあたたかなベッドに
もぐりこんで、すぐに目をとじてねむってしまったのでした。
それを見とどけたアオは、なかまたちとおばあさんのところに行って、
いっしょにおさかなをたべたのでした。
それからどのくらいたったのでしょうか。

もういちど目をさましたプチは、それを少しはなれたところのおふとんの
なかからながめながら、すっかりあんしんして、こんどこそはふかいねむ
りについたのでした。
おしまい
読んでくれて、どうもありがとう。
感想やお便り等をこちらから。ご遠慮なくぜひどうぞ。
お願い
今回は、5才程度の子供も読めるようにしようと思って、つくりました。
と言いながら、5才の子供の実態はまったくわからないのです。
なにより、自分で書いたものが果たして他の人にとって面白いものになっているのか、そうではないのか、さっぱり見当がつきません。
ひらがなと漢字の使い分けなんかも同様です(今回はふりがなは省いてあります)。
そこで、大急ぎで掲載して、皆さんの感想やご意見を待つことにしました。どんなことでもいいので、感想をお知らせいただければ助かります。
ぜひ、よろしくお願いします。
FANTASY 1 海のそばの猫、山にすむ猫 8
12

ある穏やかに晴れた日の午後に、またアオがやってきました。朝早くにお魚を届けてくれたばかりだったので、今日はもう2回やってきたことになります。
「やあ、どう…」
と挨拶をしようとするまもなく、アオが、
「ちょっとこまったことになりました」
ちょっとどころかほんとうに困ったようにいったのです。だいたい、アオはいままで弱音を吐くことはありませんでした。だから、ほんとうににっちもさっちもいかない気がしていたのでしょうね。いつもはピンとしている長いしっぽもだらんとしているようです。それで、いそいで聞きました。
「どうしたのさ?なにがあった?」
「ぼくたちがつかまえた猫たちのことをおぼえているでしょう?」
「ああ、もちろん。わすれたりはしないさ」
といったあと、なにか悪いことが起こったのかと思って、すぐに続けて聞いたのです。
「あの猫たちがどうしたって?」
「そろそろ外に出してくれないか、というのです」
とアオが答えた。
「で、どうしたのさ」
「実は、意見が分かれているのです」
「そうなんだ、それは困ったことになったね。ところで、きみはどう思っているの?」
「ぼくは、正直にいうと、出してあげたいのです」
「ふーん。どうして?」
「時々おりをのぞいてみるのですが、あの猫たちもほんとうはなかよくしたいと思っているようなのです」
「ふーん。きみはそれを信じるのかい?」
そういいながら、アオの寛容さに感心しました(ぼくは、そうすることがいいことがわかっていても、そんなに寛大になれない時があるのです)
「ええ、まあ。でも、反対する猫たちは、出せばまた悪さをするに決まっているというのです」
「うーむ。それもむりもないかもしれないな。だって、あれだけ悪さをしたのだからね?」
「そうですね。だからぼくも、反対する気持ちもわからないわけじゃないんです。実際のところどうなるのかは、やってみなければ、わからないですからね」
そういって、アオは顔をゆがめた。いつもはキラキラと光っている目もくもっているようでした。そして、意を決したようにいったのです。
「ねえ。一体どうすればいいと思いますか?」
アオが、ぼくに意見を求めることはあんまりなかったから、正直にいうなら、ちょっとおどろいた。
「でも、きみが信じていることを、もう一度ていねいに、反対派のみなさんたちに説明したらどうだろう?」
「そうですね。そうするしかなさそうですね?」
アオはそういったあと、
「ありがとう。それではまた」
と大きな声でいうと、いつもよりも素早い足取りで帰って行きました。
13
そのつぎの朝、ぼくはいつも以上に早起きをして、アオが魚を持ってきてくれるのを待ちました。
「やあ、おはよう」
「きのうはありがとうございました。おかげでたいへん助かりました」
といったあとに、こう訊いたのでした(だって、こうしてぼくが待ちかまえていることはいっとう最初の時だけで、ほかにはなかったのですから)。
「でも、今日はどうかしたんですか?」
「今日は天気もいいことだし、あんまり寒くもないから、たまにはいっしょに山の方へ行くのもいいかなという気がしたのさ」
「ああ、なるほどね。それはいいですね」
「プチもいっしょに朝ごはんを食べたら楽しいだろうな、と思ったんだよ」
「そうですね。それはいい。ぜひそうしましょう」
「ありがとう。でもきみは仕事はだいじょうぶなのかい?」
「だいじょうぶ。ぼくがしばらくのいなくたって、もう困ることはありませんよ。みんなしっかりしていますもの」
そういって見上げた瞳は元のように輝いていました。どうやら、きのうの話がうまくいきはじめているようでした。
「そうだね。じゃあ、いっしょに行ってもらうことにしよう」
それから、うちの中に入ってもう用意してあったおべんとうを三つとってきました(実は、ぼくは、アオがなんといおうとも、ぜひいっしょに行ってもらうつもりだったのです)。

それから、ふたりならんで歩きはじめたのです。もうすでにいったとおり、天気はよかったし、とおり道のそばのあちらこちらに咲いている花や草もとてもきれいだったのです。野の花や草はあんまりほめられることはないし、はなやかでもおおきくもないけれど、よく見るととてもきれいですから、みなさんもこんど歩くときは、ぜひよく見るようにするといいと思います。そうやって歩いているうちに、山のふもとまでやってきました。
そこでぼくは、
「プチがあらわれたら、自然にふるまうよう、くれぐれもおねがいするよ」
と念を押しました。
「ええ、もちろん。でもどうしてそんなことをいうのですか?」
それで、ぼくはこのところのプチの行動について教えました。
「ふーん。でも、かわいいですね。しっかりしているように見えても、やっぱりまだ子どもらしいところがのこっているんですね」
「そうなんだ。だから、よろしくね」
「ええ。もちろん」
そして、こう続けていったのです。
「プチはぼくにとっても、年のはなれた弟みたいなものですからね」
それを聞いて、ぼくはすっかり安心したのでした。
そうしていると、すこし先の枝がちょっと揺れたような気がしました。ほら、やっぱりね。
「あれ?今日はどうしたのですか?」
ぼくたちを見たプチが訊きました。
「やあ。あんまり天気がよかったからね。ところで、きみこそどうしたんだい?」
「おばあさんの朝ごはんをすませたあとに、まだ早いからちょっとお散歩に出たんだよ」
「ふーん。ところで、きみはもう朝ごはんはすんだのかい?」
「いいえ。実をいうと、おばあさんの朝ごはんは早いのですが、ぼくはまだなんだ」
よくわかります。年をとると、朝がとても早くなるのです(その分、夜も早くなります。ん、逆でしょうか)。
「じゃあ、いっしょに食べるかい?」
「ええ、もちろん。でも、どうしよう?三人ぶんの朝ごはんなんてどこにもないよ」
「だいじょうぶ。ここにおべんとうが3つあるし、アオがいつものように用意してくれた魚もあるさ」

それからぼくたちは、川べりの陽だまりを見つけるとそこにすわって、おべんとうをひろげたのです。
すると、プチが大きな声をあげた。で、僕も思わず聞きました。
「どうしたのさ?」
「これはなんですか?とってもきれいだ」
そこには焼いた鮭やら卵焼きやらブロッコリやらがいろどりよくならんでいたのですが、プチはいままでおべんとうを見たことがなかったのだね。
「これはおべんとうといってね、外に出かけるときに持っていくんだよ」
といって、作り方についても教えました。
それからしばらくのあいだ、おべんとうを食べながら話をしましたが、楽しかったな。アオとぼくのおべんとうばこはすっかりからになっていたのですが、プチのおべんとうばこはそうではありませんでした。まだたくさん残っていました。
「もうおなかいっぱいになったのかい?」
「ええ。ぼくはもうおなかいっぱいだし、おばあさんにもね、食べさせてあげたいなと思って」
「ああ。そうするといいね。またおなかがすいたら、アオのお魚を食べるといいよ」
「ええ。ありがとう」
そういうと、プチはおべんとうばこをかかえて走って行きました。たぶん、プチは自分だけのためじゃなく、おばあさんのためにうけとって、ほとんどを食べないでのこしたのだね。
しょうじきにいえば、ほんとうは、あのおりの中に閉じ込められていた猫たちがその後どうなったか訊きたかったのだけれど、おべんとうの時間が楽しくて、そのことをすっかりわすれていたのです。いったい、どうなったのでしょうね。

さて、皆さんは、どう思うのでしょう。
(おしまい)
FANTASY 1 海のそばの猫、山にすむ猫 7
10
ぼくはあいかわらず山へ散歩に出かける毎日です。アオは約束どおり魚を持ってきてくれるけれど、会うことはあんまりありません(残念ですが、きっといろいろと忙しいのにちがいないのです。新しい猫たちとのつきあいも増えたことだしね)。それでも、ぼくたちは時々、窓辺で話をします。

こないだは、音楽のはなしをしたな。でもまずは、天気のはなしからです。
「今日は、いい天気だねえ」
「ええ。朝もやをとおり抜けてきた太陽)の光はかくべつでしたよ。ちょっと幻想的だったな」
「そうだね。ぼくも早起きしたよ」
だいたい、年を取ると遅くまで寝ていることがむづかしいのです。もう、残された時間がすくないせいでしょうか。
さて、その日の音楽のはなしのことですが、猫たちはぼくたちのようにレコードやCD、インターネットで聴いたりする習慣はないようです。それには理由があるのですが、みなさんはなんだと思いますか。アオは、ぼくたちと同じ音楽も聴くようになったようでしたが、それでも大きな音で聴いたり、イヤフォンで聴くことはぜったいにないそうです。
「ところで、昨日は何か聴いた?」
「ええ。バッハのゴールドベルクを」
「それはまた、どうして?」
「朝が早いので、よく眠れるようにと思ったんです」
「なるほどね。ぼくは、シューベルトを聴いたよ。他にはどんなものを聴くの?」
「やっぱりバッハ、モーツァルトかな」
「どうして?」
「聴くがわの気持ちをじゃましないところでしょうか」
「やっぱりね」
「でも、私たちの暮らしている場所のまわりにある自然の音、海の音や雨の音、風の音なんかがいちばんかな」
それはぼくたちがわすれかけているとてもだいじなことのような気がするのですが、みなさんはなんの音、どんな音楽が好きなのでしょうね。
しばらくそんな話をした後に、アオが突然いいだしました。
「私たちのところへはなかなか招待できずに、ごめんなさい」
「どうもありがとう。きみたちが暇になったらね」
ぼくは一刻も早くもう一度訪れたくてたまりませんでしたけれど、アオたちが忙しくしているのを知っていたから、そういったのですが……。
11
いっぽうその代わりに、プチとは時々川辺の陽だまりでおしゃべりをします。ぼくがいつものように川べりをとおると、ぐうぜんあったようにして、あいさつをしてくるようになったのです(たぶん、てれくさいのと、ほんとうはさびしがりやだということを知られたくないのだね)。
「やあ」
ぼくもたまたま見かけたのでというように、声をかけるのです。
「こんにちは」
プチも、そっけなく答えます。
「元気かい?」
「うん。いつもありがとう」
近頃は、こんなふうに礼をいうようになったのです。
「会議はどうだい?たいへんじゃないのかい?」
「まあ、うまくいっているよ」
「それはよかった」
「アオがうまくやってくれているからね」
「そうなんだ」
「ああ。それに知らないことを、いろいろと教えてくれるんだ」
プチがそういった時、ぼくはすっかり安心したのでした。プチは小さいながらも、山の猫の代表(こんどは正真正銘の)として忙しいようなのだけれど、なんといっても若(わか)いし、まだ子どものようなところもあるのです。そんな年頃で、おおきな責任を負わされるのはたいへんなことなのですからね。実は、ちょっと心配していたのです。
「ふーん。アオとなかよくなったんだね」
「うん。そうだよ」
この時のプチはほんとうに子どもらしかったな。アオのことをすっかり気に入ったようすで、尊敬できる、すこし年のはなれたお兄さんができたように思ってよろこんでいるようなのです。
「これからも、いろいろと教わることができたらいいね」
「うん」
こんなに素直なプチを見たのははじめてのことでしたが、きっとずっと肩にのしかかっていた責任をわかちあうことができて、緊張が解けたのだね。

そんなふうにして、プチとぼくはすこしずつ仲良くなっていった。ぼくには子どもがいませんから、プチが友だちというよりも子どもみたいな気がしてくることがあります。ほんとうなら孫というところなのかもしれませんが、子どもをとばして孫というわけにはいきません。プチの方もおとうさんとおかあさんが早くになくなったために、おばあさんに育てられたようなので、そんなふうに感じたのかもしれません。
それから、川面をスクリーンにして映画を見たりしました。プチは冒険ものやファンタジーがすきですね。あの『トムとジェリー』も気に入っているみたいです(猫はたいていネズミにやられるのにね、なぜでしょうね)。それで、しばらく見ないと、
「ねえ。あれ見ない?」
といってさいそくしてくるのです。やっぱり、何といってもプチはまだ子どもの猫なのだね。
「あれってなにさ?」
ぼくは気づかないふりをして、聞き返します。すると、
「あれだよ。わからないの?」
とむきになっていうのです。この時のプチはあきれたなあというような顔をしながらも、ちょっと得意げなのです。そういう時のプチをみなさんにも見せてあげたいと思うのですが、彼らと会うのにはちょっとしたコツがいるし、今はなにかとあたらしいことがおおくてけっこういそがしそうですからね。もうしばらくのあいだ想像しながら、待っておいてくださいね。とにかくも、こういうときにはぼくは、
「わからないな」
といって、焦らすのです。ちょっとばかりいじわるのようですけれど。こうすると、プチが子どもらしくなるのですから、やめるわけにはいきません(でも正直にいっておくと、残念なのですが、時々ほんとうの意地悪になることがあるのです。みなさんはどうですか)。そうやってすこしばかり焦らしたあとに、
「そうだ、あれ見ようか」
ときくのです。するとプチも、
「えっ?あれってなんのこと?」
と負けずにいうのです。
こんなふうに質問したりされたりをしばらく続けるのですが、たいていはプチの方が根負けして、きっというのです。
「ねえ、『トムとジェリー』を見ようよ」
「うん、そうしよう」
この時はもう、あっというまに決まります。こうなるともう、プチは気どっていたりすることはできません(なんといったって、子どもなのですから)。たまにはこうしなければ、あたまがパンクしてしまうのに違いないのです。
(続きます)
FANTASY 1 海のそばの猫、山にすむ猫 6
08
町がうるさくなったのは、それからしばらくしてからのことでした。どうやら町の外から猫の一団がやってきたらしいのです。以前に見たプチを取り囲んでいた猫たちは、そのなかまだったようでした。そうして、もとからいたあのアオのいる集団との争いが始まったというわけです。この戦いはすぐに決着がつきました。外からの猫の一団は力自慢で戦いにあけくれていたようでした。一方、アオたちは、戦うことになれていなかったし、争うことが得意じゃなかったのです。このため、アオたちはあっというまに追いやられてしまったのでした。
それでも、アオを中心とした猫の一団はあの海があるので、食べるものには困ることはありませんでしたけれど、ただ町の中をのんびり歩いたり、塀の上の陽を浴びながら寝そべることができなくなってしまったのです。わがもの顔でそこら中を歩き回る新顔の猫たちを見て、町の人たちもはじめは顔をしかめて見るだけでした。しかし外来の集団は次第に、平気で庭の中に入ってきたり、時には住まいの中まで侵入して食べ物を持っていくようになったのです。
さらに悪いことには、これに乗じて、ほかの猫もやってきたのです。おまけに、たとえ追い払ったとしても、彼らはすぐに戻ってきてしまうのです。これには町の人たちもほとほと困りはててしまいました。どうしたら、町を荒しまわる猫たちがいなくなって静かになり、もとのおだやかな生活が取り戻せるのだろうか……。
いい案が浮かばないまま、ぼくはいつものように散歩に出かけて、お魚を届けた後、山道を下って帰るときに、小川のそばの石に腰かけて「どうすれば、いいのかなあ」とつぶやいたのでした(あの時は、ほんとうに、なすすべがなかったのです)。
それから何日かたったある日、どうしたことなのか、プチとその仲間の猫たちがあらわれて、新参(しんざん)の猫軍と戦うことになったのです。数は少なかったけれど、なんといっても山でくらしている猫たちですから、変幻自在に動くことができるのです。
09

こうして、町の中は、色とりどりの毛並みの猫たちが入り乱れて戦う戦場となりました。やがてそのうちに、すこしずつ様子が変わってきたようでした。新参の猫たちは散りじりになって戦っているようでした。
というのも、山の猫たちの戦いぶりは、こちらと思えばまたあちらから仕掛けるというぐあいで、外からきた猫たちはやがてつかれてしまい、どこに向かっていけばいいかわからなくなり、一匹ずつがバラバラに行動するようになってしまうのです。ただ、それでも多勢に無勢なので、なかなか決着はつきません。
そのうちに、アオたちの一団もうわさを聞きつけて、町の中にふたたび出てきました(だいたい彼らは、おだやかに暮らすことを好み、戦うことをしたくなかったのです)。そして、アオとプチの仲間が協力して戦うことになりました。そレからは、形勢は一挙に動きました。プチたちが外からの猫たちを追い回して、一匹ずつバラバラにしたところを、アオとプチの連合軍が取り囲んでつかまえてしまったのです。
こうして、外からの猫たちは全員がとらえられてしまいました。この猫たちをどうするのか、町の人たちも興味津津で見ていました。中には、「一匹のこらず袋に詰めて、海の中に放り込んでしまえ」という人もいました。実際、猫たちの中にも同じ考えを持つものもいたようでした(プチの仲間の猫はその代表でした)。そうしないと、また同じことが起きると考えたせいでした。みなさんはどうですか。
このため、外からの侵入してきた猫たちは、まだがんじょうなおりの中に閉じ込められたままです。
ともあれ、こうして町はもとの静かな姿に戻ったのでした。
(続きます)
FANTASY 1 海のそばの猫、山にすむ猫 5
06

ある時、近所からすこし足をのばして歩いていると、近くで猫の高い声やうなり声が聞こえました。何匹かが争っているようでした。何かと思い、それで音のする方に歩いていくと、すっかりのびた草の向こうで見なれない3匹ほどの茶色の猫がブチの猫を取り囲んで、大声で威嚇していました。ブチの猫も、負けじと低い唸り声をあげながらなんとか睨み返しているようでした。
「やあ。きみたち、一体どうしたんだい?」。
3匹の猫は散歩でこんなふうにすこし遠くまで来た時に、たまに見かけたような気がしたのですが。一方のブチの方は、どうやらこないだ代表して来たとうそをついた、あの仔猫のようでした。よく見ると、ブチの方はいたる所の毛が抜けており、しっぽの先はかじられたようになっていました。
おどろいたぼくは、あわてて
「もしもし、どうかしましたか?」
ともう一度、声をかけました。
「知らない人は、だまっててくれないか」
「そうだ、そうだ」
「だまってればいいんだ」
3匹の猫は、口々におおきな声でいいました。
「でもね、そうもいかないようなんだ」
ぼくは、引き下がらずに、いいました。
「どうしてなのさ、わからないな」
「そのちいさな猫は、知りあいなんだ」
「知りあいといわれてもね、こいつを許すわけにはいかないね」
「なにか悪いことでもしたのかい」
「したもなにもない。こいつはおいらたちの食べものをぬすんだのさ」
「それはいけないね」
「ああ、そうさ」
「でも、ここはぼくに免じてゆるしてくれないか。食べものの分(ぶん)は弁償するから」
そういったら、3匹の猫はようやくブチの猫を解放してくれました。
「どうして助けたりしたんだ?」
ブチの猫は、吐き捨てるようにいいました。
「だって、いじめられているところを見たら、だまっているわけにはいかないさ」
「ふん。よけいなことを」
「だって、あのままじゃ、きみはコテンパンにのされていたかもしれないよ」
「ひとりでも、大丈夫だったさ」
「そうなのかい?」
「ああ。そうさ」
ブチの猫はあくまでいいはります。これじゃ堂々巡りだと思ったぼくは、
「そりゃ、悪かったね」
といったあとで、訊いたのです。
「ねえ、きみはあの時、どうして代表だといったんだい?」
「あんたには関係ないことだろう?」
「そうでもないよ。ぼくだって町の住民のひとりなんだからね」
それからはしばらくのあいだ、沈黙が続きました。それでも、ぼくはがまんして、じっと待ちました。
「そうでもいわなきゃ、いうことを聞いてくれないからさ」
「どういうこと?」
「食べるものがなかったんだよ。もういいだろう?」
そういうと、ブチの猫は振り返ることなく、尻尾を立てて一目散に走り去って行きました。
07

あるとき、また例の青みがかった灰色の美しい猫がやってきました(そうそう、呼びやすいように名前をつけることにしましょう。アオではどうでしょう。ついでに、ちいさな猫はプチ)。そこで、ためしにきいてみることにしたのですが、アオのはなしによると、山のほうはちいさな川しかないため、もともと魚がすくなかったのに、嵐のためにもっと取れなくなった。山の方でくらす猫は少なかったようですが、その中には年おいたおばあさんの猫もいるそうだということでした。それで、がてんがいきました。
「ねえ、お願いがあるのだけれど」
ぼくはいいました。
「ええ。なんでしょう?」
「すこし魚をわけてもらえないだろうか」
「えっ。また足りなくなったのですか」
「そうじゃないんだ」
「じゃあ、なんのために?」
「あのブチの猫のことだよ。プチと名前をつけた」
「ああ」
「ところできみの名前はなんていうんだい?アオと呼ばせてもらおうと思ったのだけれど」
「いいひびきですね。気に入りました。いいですよ。で、どうしたのですか」
これもあとでわかったことですが、どうやら猫たちの間では人間のような名前がないらしいのです。
「ブチの仔猫、つまりプチってことだけれど、は、おばあさんを助けるために嘘をついたと思うんだ。たぶん、わるい子じゃないと思う」
「だから?」
「うん。だから、たすけてやりたい。それで、きみたちの力をかしてほしいのさ」
ぼくはそういい、そのための条件(じょうけん)を話し合った。アオはお礼なんか気にしなくていいですよといったのだけれど、甘えるばかりというわけにはいかないので、魚一匹につきクリームたっぷりのスコーン一つということで折りあうことができました(どうでもいいことかもしれませんが、スコーンにしたのは、その色からして、アオがスコットランドと関係ありそうだという気がしたからなのです)。
それからは、毎日アオたちがとどけてくれたお魚をあのプチのいる山まで持っていくことになったのです。すこし遠くなったのですが、あたらしい散歩コースにしたので、ぜんぜん苦にはなりませんでした。だって天気のいい日に、うつくしい木々のあいだを歩いていると、木もれ日や野の草や花を見るのもたのしかったのです。ただ、雨の日はちょっといやだったな。ぬれてつめたくなるし、ベタベタとまとわりついたりもする。ずぶぬれになったぼくを見かねたのか、ある時アオが、雨の日は私たちが届けましょうといってくれたのです(ぼくは、すなおにあまえることにしました)。
届けるときには、プチに気(け)どられないように、すこし川下の方におくようにしました(猫たちにはそれぞれにプライドがあって、ぼくのように甘えるのがむづかしいようなのです。プチもまだうんと若いけれど、すでにちゃんと誇りを持っているようです)。
(続きます)
FANTASY 1 海のそばの猫、山にすむ猫 4
05

そんなことがあってからしばらくたって、ようやく町が落ち着きを取り戻した午後に、ぼんやりと窓の外を眺めていると、一匹の猫がやってくるのが見えました。
「こんにちは。誰かいませんか」
と、おおきな声で呼ぶのがきこえました。
すると、近所の誰かが出てきて、いいました。
「やあ、猫さん。こんにちは。こないだはありがとう。おかげで、みなおおだすかりでしたよ」
で、ぼくも窓をあけて顔を出したのです。えっ、ヒトのことばを話せる猫がいたのか(だって、僕はこないだは猫語で話したばかりだったのですから)。すると、見た覚(おぼ)えのない小さなからだのブチの猫がいました。
「どういたしまして。それはよかった。お役に立てて何よりでした」
とブチの猫はにこやかにいって、それから顔を曇らせて、ちょっといいにくいのですがと前置きして、こう続けたのでした。
「今日は代表してきたのですが、こないだはわたしたちも、ちょっとした損害があったのですよ」
「それはたいへんでしたね。でも、あんなにおおしけだったのですからね」
「それで、こんどはすこしばかり助けてもらいたいのです。まことににもうしわけないのですが、2日に1度は魚を届けてもらえればありがたいのですがね」
と伝えたのでした(たぶん、魚をつかまえるのは得意なはずだけれど、なまけものの猫なのかもしれませんね)。
近所の人はちょっとおどろいた様子で、すこしだまってから、こういいました。
「わかりました。みなさんと相談してから、すぐにお返事します」
「また近いうちにおうかがいしますから、その時に返事をお聞きします」
そして、さらに続けて、
「そうしてもらわないと、今度またおおしけが続いても、
助(たす)けることができないかもしれませんよ」
と、おだやかに脅したのでした。
町の人たちはすぐにあつまって相談した(当然、ぼくも参加しましたよ)のですが、そうなってはこまるから(何といっても、すでにいちど経験したばかりだったのですから)、いやもおうもなかったのです。このため、しぶしぶながらも、
「それでけっこうです」
と答えたのでした。
また、ふたたび、例の壁を通り抜けた猫がやってきたのは、それからまもなくしてからのことでした。あんまりたくさんのことは話してくれませんでしたが、じつは、ブチの猫は代表者でもなんでもなかったということがわかりました(それを伝えるときは、ちょっとさびしそうでした)。
さらにその後、何匹かの猫が悪だくみをしたといううわさが聞こえてきましたが、さてどうしたのか、なにがあったのでしょうね。
(続きます)
FANTASY 1 海のそばの猫、山にすむ猫 3
04

それからしばらくたったころに、このあたりでおおきな災害が起きたのです。町には暴風雨が吹き荒れ、道路には水があふれて、何本かの木も倒れてしまいました。僕は、外が荒れていても、家の中から外を眺めているかぎりは、守られている気がしてうれしい気分になります。しかし、今度ばかりは、そうも言っていられません。海もおおしけがつづきました。だから当然ですが、魚はとれません。近頃は、こうした異常気象がひんぱんに起きるようになってしまっているのです。
そうした日がしばらく続き、近所の人たちが、力がつくたべもの、とりわけおいしいお魚がこいしくなったころに、ぼくもつい…、
「お魚が食べたいな」とつぶやいたのです。
でもね、とうぜんむりな願いなのです。だって、おおしけがまだずっと続いていたのですから。
翌日、眠いまま起き出して、新聞を取りに外に出ると(こんな天気でも、ちゃんと新聞をとどけてくれる人がいるのですね。会ったこともないし、これからもないかもしれませんが、ほんとうにありがたいです)、そこに何か見なれないものがおいてあった。
「なんだろう?」
ふしぎに思って、よそのうちはどうだろうと思って眺めてみると、同じようなものがどこのうちの前にもあるようでした。
「へんだな。おかしなことがあるものだな」

ちょっといぶかりながら、もう一度よくみてみると、にもつの上に手紙らしきものが載っていました。おもてには、「みなさんへ」と「猫たちより」の文字が見えました。それで、おもいきってさっそくあけてみると、それはこないだの猫さんたちからのものでした。そこには、こんなことが書いてありました。
みなさんへ
おはようございます。
いかがおすごしですか。海があれてたいへんですね。
私たちは、全然気にしませんが。
ということで、すこしですが、おすそ分けです。
どうぞお召し上がりくださいね。
いつもやさしいみなさんへの心ばかりのものです。
きんじょの猫より
海のそばの猫たちからの贈り物だったのです。そういえば、町の中でもゆっくりと歩いていたり、塀の上でからだをのばしている猫をときどき見かけていたことを思い出しました。きっと近所の人たちは、かわいがっていたにちがいない。みな、猫のことが好きだったのですね。
それで、近所のみなが久しぶりのお魚にありつけたというわけ。当然ですが、とってもおいしかったな。おかげで、全員が元気をとりもどすことができたのです。
ところで、きみたちはお魚は好きですか(もし食べず嫌いだとしたら、もったいない)。あの猫たちのことはどうでしょうね。
ぼくは、またあの入り口の向こうで会いたいものだと願っていますが、まあきっと、そのうちに会えるでしょう。また会ったら、そのときのことをおしらせすることにしましょう。
でもどうやって、猫たちは魚をつかまえたのだろう、と疑問に思った人もいるかもしれませんね。気になって眠れなくなる人がいたらいけないので、そういう人たちのためにそっとお知らせしておきましょう。あとで知ったのですが、彼らの目の前の海は、私たちの海とは違って、いつもないでいるようだし、おまけにあの猫のみなさんたちはみながすばらしい漁の技術の持ち主だということでした。
(続きます)
FANTASY 1 海のそばの猫、山にすむ猫 2

03
ようやく落ち着いて、よく見ると、他にも何匹かの毛色や尻尾の長さが違った、それぞれに美しい猫たちがいました。
「ねえ、みなさんはどうやってここを見つけたの?」
なんといったって気になりすることなんてできません。で、少々無作法だとは思いましたが、思い切って訊いたのでした。
「ん、そんなにむづかしくないでしょ?」
そばにいた猫が、あたりまえのようにいいます。
「えっ?」
ぼくは、そういうものかと思って、それ以上たずねることはしませんでした。ぼくたちだって、あんまりあたりまえすぎることをあらためて訊かれると、こたえられないことがあります(まあ、いばれることではないのですが)。
それで、あらためてまわりを眺めたのでしたが、ほかの猫たちは、お行儀よくテーブルについておしゃべりをしながら、お魚を食べていたのでした。みんながくつろいでいるようでした。ここはいつでもお魚がつかまえられる、秘密の場所なのかもしれません。
そう思いあたったぼくは、またまた驚きました。こんな場所で、しかもテーブルで食事をしているなんて!。おどろいたままぼんやりと眺めていたら、今度は一匹の輝くような黒い色をした猫がやってきて、
「あなたもおひとついかが?」
といってくれたのでした。
「ありがとう。でも、遠慮しておくことにします」
ぼくはていねいに断りました(ほんとうは、とてもおなかがすいていたのですが)。
「えっ。どうして?」
黒い猫はわけがわからないという感じで、たずねたのでした。
「だって、みなさんたちの食べるものをとったら、わるいでしょう?」
「そんなことないですよ。心配しなくても大丈夫」
「でも…、やっぱりねえ」
「ほら、見てごらんなさい。何が見えますか?」
「ああ、海ですね。きれいですねえ」
「そうでしょう。だから、いつでもつかまえられるのですよ」
「あ、なるほどね…」
ぼくはそういうものかと感心して、うなづきました。
「もしかして、なまのお魚が苦手なの?」
「ええ、まあ…。食べられなくはないですけれど…」
猫さんたちには内緒にしていたのだけれど、白状すれば、なまのお魚は苦手なのです。
「なーんだ、やっぱりね。大丈夫、それなら焼くことだってできますよ。お望みなら、煮ることだって」
「へえ?」
「ほら、よく見てくださいな。七輪があるでしょう?」
七輪の中では、炭がまっかに燃えていたのです。やっぱり猫さんたちは魚が大好物だけあって、いちばんおいしい食べ方を知っているのだね。
「あ、ほんとうですね。でも、やっぱりねえ…」
ちょっと、いや相当に心惹かれたのですが、ぼくが食べると猫さんたちの何倍も食べそうな気がしたのです(この時は、自分が小さくなっていたことをすっかり忘れていたのです)。
「心配しないで。どうぞ、遠慮なく召しあがってくださいな」

というわけで、ぼくはお皿の上にきれいに盛りつけられたお魚をごちそうになったのでした。
「ああ、おいしかった。どうもごちそうさまでした」
「それはよかった」
「すっかり遅くまでおじゃましてしまいました」
ぼくは、そろそろ帰らなくちゃと思い、いいました。楽しくおしゃべりをしながら食べていたら、いつのまにかずいぶん時間がたっていたようなのです。
「いえいえ、どういたしまして。また来てくださいな」
それから、ぼくはとんでもなく大事なことに気づいたのでした。
「どうやって帰ったらいいのだろう?」
道はおぼえていないし、だいいち壁には扉もついてなかったぞ。それに、自分が猫さんたちと同じくらいに小さくなってしまっていたことを思い出したのです。
これはまずいことになったぞ。どうしよう。無事に町に戻れるだろうか。うんと時間がかかるんじゃないか。だいいち戻れたって、こんなに小さい体じゃ、町の人だって気づかないかもしれない。そうなったらどうしようなどとと思ったりして、不安になったのです。
すると、最初のあの青みがかった灰色の猫がやってきて、またまた声をかけてくれたのでした。
「だいじょうぶ、ちゃんと出口まで案内しますよ。体も元どおりになりますから、心配しないで」
猫たちは、人の気持ちもわかるようでした。きっと相手のことをよおく見ていて、思いやるのでしょうね。
それで、穴のところのところまで案内してもらい、ぼくはぶじにもとの場所に戻ることができた、というわけなのでした。
そして、一緒に坂道の入り口のところまで来ると、体もすっかり元の大きさに戻っていることに気づいたのです(この時ばかりは、ほんとうにほっとしたな)。
「どうもありがとう。すっかりお世話になりました。今度はぼくが、ごちそうしなくちゃいけません」
「いえいえ、どうぞご心配なく」
「さようなら」
「ごきげんよう。それでは、また」
そういうと、きれいな色の猫ははじめのときのように、すばやくきびすを返して帰っていったのですが、やっぱりあっというまに見えなくなってしまいました。
それで、ぼくはときどき家の裏にそっとミルクの入ったびん(だって、魚はいくらでもありそうでしたから)をおいておくのですが、いつのまにかなくなって、ちゃんと洗われてきれいになった、からのびんが戻っているのです。きっと、あの猫さんたちが飲んでくれているのだね。そのたびにぼくは、あの坂道の向こうでのことを思い出しながら、うれしい気持ちになるのです。
(続きます)
FANTASY 1 海のそばの猫、山にすむ猫 1
海のそばの猫、山にすむ猫

01
しばらくのあいだ、あたりがなにかとうるさかった時が、あったのです。
「そうですね」という人もいるかもしれないけれど、たぶんぼくがいうのとはちょっと違うような気がします。だって、ぼくがいうのは猫たちの争う声なのですから。なにしろ朝も昼もないのです。みんなが寝静まるような夜だって止むことがなかったのです。どうやら町に集まった大小の集団が入り乱れての戦いが勃発していたようだったのです。海の猫軍団、山の猫軍団、外からの猫軍団にその他の猫軍など。ちょっと迷惑。町の人はみな、ほとほと困っていたのです。今までは、こんなことはなかったのに。
ところで、みなさんは散歩はしますか。ぼくはこのところ、カメラを持ってよく散歩をします。気になるものを目にするとすぐに写真を撮ります。最近は、草花がお気に入り。ゆっくり歩いていると、忙しくしていた時には気づかなかったことに気づくようになるのです。
02
すこし前のことですが、うちの近くのマンションのそばをゆっくりと歩いていると(なんといったって散歩ですし、雲ひとつない青い空が広がっているような、すばらしくいい天気だったのですから。少々寒くたって気にしません)、通路のようなものが3つあるのに気づいた。今までも何回も見ているはずなのに、ぼんやりしている証拠ですね(やれやれ)。一つはすぐ先が行ど止まり、もう一つはずっと向こうまで続いていた。そして最後の一つはちょうどその中間、行き止まりだけれど、向こうの壁の一部はあいていてどうやら坂になっていて、駐車場に続いているようでした。
と、その時そのぽっかりとあいた口に何かが飛び込む姿が見えたのです。ちょっと光っているようだった。初めはぼんやりと見ていたのですが、すぐに猛烈に気になってきた。あれは何、猫のようにも見えたけれど…。どこからきたんだろう。それより何より、いったいどこへいったんだろう。
それで、悪いとは思ったのですが(なんといってもよその家なのですから)、ちょっと近づいてみようとして歩いていったのです。別に変わったところはないようでした。よく町の中のビルで見るのと同じ、地下の駐車場に続くスロープのようだったのです。しかし、猫(?)のすがたももうありませんでした。よおく目をこらして見たのですが(坂の先は暗くなっていたのです)、やっぱりどこにもいないようでしたし、他のなにも見えなかった。
あきらめてもう戻ることにしようとした、ちょうどその時、また、目の前をものすごい勢いで走るものが見えました。それはぼくの目の前で、ピタリと止まったのです。おどろいたな。いったいなんだろう。なんだと思いますか。もう、気づいた人もいるにちがいないのですが、そのとおり。先ほどぽっかりとあいた口に勢いよく飛び込んでいった正体不明のもの、やっぱり猫だったのです。すこし青みがかったような灰色の毛並みがとても美しい猫です。

それで、なかば呆然として猫を見つめていたら(びっくりしていましたし、なんといったってとても美しかったのです)、その猫がちょっとだけ首を振ったような気がしたのです(猫の方だっておどろいたのかもしれません)。
ついでにそっというと、ぼくは猫や犬とはあんがいすぐになかよくなることができるし、実は、その気になればすこしだけことばもわかるのです(ほかのもの、とくに人とはなかなかそうはいきません。ちょっと残念ですが、これは昔から変わりません)。ただ、あんまり話(はな)しかけたりすることはありません(だって、他の人が見たら変に思うでしょう)。
そこでもう一度しげしげと眺めていると、猫もやっぱりもう一度首を穴の方に傾けた。ちょっと誘うようなしぐさに見えた。それから、いちもくさんに駆け出したのです。それで、ぼくも遅れてはならじと走り始めました(ちょっとヨタヨタしましたけれど)。いつまで走っても、駐車場には行き着きません。どうやら、ふつうの駐車場に続く道とは違っていたようでした。おまけに、ぼくは猫とおんなじくらいに小さくなったような気がした。
そうやってようやくの思いで後に続いていくと、猫はピタリと走るのをやめて、じっと壁の方を見ていました。ノックするわけでもなく、ただじっと見つめているだけです。すると、壁の一部にいつのまにか穴があらわれて、猫はそこに入っていきました。ぼくは、立ったまま見ていたのですが、しばらくしてから座り込んでその穴にぐっと顔を近づけたのでした。
と、あっという間に吸い込まれて、スキーで勢いよく蛇行しながら滑っているときのように(ほんとうはボブスレーのようなというほうがいいと思うのですが、残念ながらボブスレーの経験はないのです)、ずっとぐるぐる目が回るような気がしていた。そしてようやく出口まで達すると、目の前には岩にかこまれたたいらな場所があって、その先にはおだやかな海が広がっていたのです。
でも、それにしても、猫はどうやってこんな場所を見つけることができたのでしょうね。のんびりしているように見えますけれど、あんがいすばしっこいところがあるようなのですね。
(続きます)

 HOME
HOME Nice Spaces II
Nice Spaces II Fantasy
Fantasy Yuuhi Tsuushin III
Yuuhi Tsuushin III Profile
Profile Link
Link
